「小論文で時間が足りなかった」「時間内に書けなかった」という経験はありませんか?
多くの受験生が直面するこの問題は、正しい対策で解決できます。
本記事では、効率的な時間配分と執筆のコツを紹介し、「小論文で落ちた」という結果を避けるための具体的な方法を解説します。
自分のペースを知り、適切な準備をすることで、制限時間内に質の高い小論文を書き上げる力が身につきます。
今回学ぶこと
小論文が時間内に書けなかった人の特徴

小論文を時間内に書けない人の特徴には、いくつかの共通点があります。
制限時間内に完成させるための対策を立てるためにも、まずは自分がどのようなタイプかを理解しましょう。
自分の書く時間を把握していない
小論文で時間が足りなくなる大きな原因の一つは、自分がどれくらいの速さで文字を書けるかを把握していないことです。
文字を書くスピードは人それぞれ違います。早い人もいれば遅い人もいますが、重要なのは自分のペースを知ることです。
そして書く文字数の合格ラインを把握しておきましょう。文字数だけの合格ライン確実は指定文字数の9割、最低でも8割以上です。
指定文字数が800字ならば9割の720字以上800字以下が合格確実で、8割の640字以上が合格ラインということになります。
その上で自分が800字を書くのに何分かかるのか、事前に把握していないと適切な時間配分ができません。
模範解答を書き写す際の時間も参考にはなりますが、問題を把握して自分で書くときに時間を計る方が正確な書く時間になります。
これは書く練習をしていくと早くなりますが、まずは今の自分の書く時間を把握しましょう。
そしてある程度練習が進んでから、もう一度書く時間を把握します。自分が上達してきたことが実感できるでしょうし、実際の試験での時間配分の参考になります。
いきなり書き始めてしまう
急いで書き上げなければという焦りから、多くの受験生がメモや構想を省略していきなり解答用紙に書き始めてしまいます。これは時間を無駄にする最大の原因です。
計画なしに書き始めると、途中で何を書いたらいいか分からなくなり、考え込んだり書いては消したりを繰り返すことになります。
小論文を効率よく書くためには、必ずアウトラインを書く時間を設けましょう。
60分の試験なら5~10分程度をアウトライン作成に使っても決して無駄ではありません。
むしろ、最初にしっかりとした「設計図」を作ることで、清書がスムーズに進み、全体として時間の短縮につながります。
考えを整理し、論の流れを組み立てておくことが、スムーズな執筆の鍵となります。

オリジナルの構成で書いてしまう
小論文が時間内に終わらない人には、独自の構成で書こうとする傾向があります。
「序論・本論・結論」という基本的な三部構成を無視して、自分なりの展開で書き進めようとすると、論理の一貫性が失われ、何を言いたいのか分からない文章になりがちです。
結果として文章の整合性を保つために余計な時間がかかり、制限時間内に書き終えられません。
小論文では独創性よりも、まずは基本的な構成を守ることが大切です。
「序論で主張を述べ、本論で根拠を展開し、結論でまとめる」という流れを徹底すれば、論理的な文章がスムーズに書けるようになります。
型を意識することで、書くべき内容が明確になり、時間内に小論文を完成させられるのです。
書く知識が足りない
小論文でペンが止まる最大の原因の一つは、書くための材料が足りないことです。
いくら書き方のテクニックを身につけても、そもそも自分の意見や根拠となる知識がなければ、文章は進みません。
特に「賛成か反対か」までは書けても、その理由が思いつかないというケースが多いです。
この問題を解決するには、日頃からのインプットが欠かせません。
志望学部に関連するニュースや時事問題に触れ、自分の意見をまとめる習慣をつけましょう。高校生向けの新聞や専門誌を活用するのも効果的です。
毎日少しずつでも情報収集を続けることで、小論文で使える知識や考えが蓄積され、スムーズに書けるようになります。
知識の引き出しを増やすことが、時間内に書き上げるための重要な土台となります。
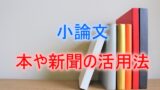

小論文の書く時間が足りなかった

小論文試験で最も多い失敗が「時間が足りなかった」というものです。
どれだけ優れた内容や構成を考えていても、制限時間内に書き終えなければ評価には結びつきません。
時間配分をきちんと行い、制限時間内に完成させるためのポイントを押さえていきましょう。
3つのパートに分けて時間配分をする
小論文を時間内に書き上げるためには、作業を明確に3つのパートに分けて時間配分することが重要です。
具体的には「アウトライン作成」「本文作成」「見直し」という3段階です。多くの受験生は序論・本論・結論という内容で時間を区切りがちですが、それでは効率的に書けません。
まずアウトライン作成の時間を必ず設けましょう。ここで全体の構想を練り、主張とその根拠を整理します。
次に清書の時間では、アウトラインをもとに実際に解答用紙に文章を書いていきます。
そして最後に見直しの時間を確保して、誤字脱字や論理の飛躍がないかチェックします。この3段階をしっかり意識することで、焦らず計画的に小論文を完成させることができるのです。
小論文の書く3段階
本文作成の時間を把握する
自分が文章を書くのにどれくらいの時間がかかるのかを正確に把握することは、時間内に小論文を完成させる上で非常に重要です。
多くの受験生は自分の文字を書くスピードを把握していないため、時間配分が適切にできずに焦ってしまいます。
実際に模範解答を原稿用紙に書き写す練習をしてみましょう。
例えば400字を書くのに何分かかるかを計測します。実際の試験では思考しながら書くため、この時間の倍以上はかかると見て良いでしょう。
この自己診断によって、「800字の小論文なら本文作成に何分必要か」が分かり、メモ作成と見直しの時間も適切に配分できるようになります。
自分の書くペースを知ることは、時間内に小論文を完成させる第一歩です。
時間配分の例
小論文の時間配分は試験の文字数と制限時間によって調整する必要があります。
例として、60分の試験時間で800字を書くのであれば、アウトライン作成に5~10分、本文作成に40~50分、見直しに5~10分という配分が目安になります。
時間配分の例
| 文字数/制限時間 | アウトライン作成 | 本文作成 | 見直し | 課題文を読む時間 |
|---|---|---|---|---|
| 600字/50分 | 5~10分 | 30~40分 | 5~10分 | – |
| 800字/60分 | 5~10分 | 40~50分 | 5~10分 | – |
| 1000字/90分 | 5~10分 | 70~80分 | 5~10分 | – |
| 課題文付きで1000字/90分 | 5~10分 | 60~70分 | 5~10分 | 10分 |
重要なのは、どの段階でも時間を意識することです。
特にアウトライン作成では思考が広がりがちですが、時間を決めて集中的に行うことで効率が上がります。
また、本文作成の途中でも段落ごとに誤字・脱字や表現の見直し、そして進捗と残り時間を確認し、ペース配分を調整しましょう。
最後に見直しの時間は必ず確保すること。この段階で細かい修正はできないので、全体として文章が整っているか確認しましょう。
この時間配分を意識して練習を重ねることで、本番でも焦らず小論文を書き上げることができます。
「小論文で落ちた」を避ける

小論文の評価は合否を分ける重要な要素になることがあります。
しかし、どのような小論文が評価され、どのような小論文が評価されないのか、その基準を知ることで効果的に対策することができます。
ここでは小論文での失敗を避けるための重要なポイントを解説します。
小論文だけで落ちることはない
小論文の結果だけで合否が決まることはほとんどありません。多くの大学や企業では他の教科や面接なども評価対象となります。
小論文が直接合否の決め手になるのは、試験科目が小論文だけであったり他の要素がほぼ同等の場合です。
ただし、明らかに課題から外れた内容や支離滅裂な文章を書いた場合は、不合格の理由になる可能性が高まります。
反対に、基本的な構成や字数制限を守り、筋の通った文章を書くことができれば、小論文が致命的な弱点になることは避けられるのです。
実際には、多くの受験生は調査書の内容や総合的な評価で大まかな合否の方向性が決まっています。
とはいえ、小論文も試験として課されている以上、合否の影響は決して小さくありません。
小論文は、他の教科や面接と合わせて「この受験生は合格にしよう」と思わせる追加ポイントとなり得る要素です。
配点や合否のデータを調べておく
志望校選びの段階で、小論文がどの程度重視されているのかを事前に調査することが重要です。
公式には発表されていないことが多いですが、大手予備校や塾などが過去の傾向をもとにデータを分析していることがあります。
こうした情報を入手することで、限られた時間の中でどの対策に力を入れるべきかの判断材料になります。
例えば、推薦入試では面接よりも小論文の配点が高い傾向にあるため、小論文対策により多くの時間を割く必要があるでしょう。
また、過去の出題傾向や評価基準なども可能な限り調べておくことが大切です。
どのような論点が求められているのか、どの程度の専門知識が必要とされるのかを知ることで、的を射た対策が可能になります。
そして就職試験の場合は、データが公開されているわけではないものの、小論文の内容をもとに面接で質問されたりするなど、かなり重要な要素だと認識しておきましょう。
昇進試験の小論文の場合、書いた内容が直接昇進先の役職業務に結びつくため、手抜きはできません。
こうした下調べは時間の効率的な使い方につながり、本番での焦りを軽減する効果もあります。
試験本番で自信がない、あるいは試験後手応えがなかったとしても、評価基準に沿って書けていれば合格の可能性があるので諦めないでください。
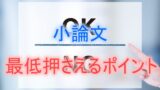
小論文の評価の分かれ目
合格する小論文と不合格になる小論文の差は明確です。
合格する小論文を書ける受験生は難関校でも推薦入試で合格する可能性が高く、逆に不合格になる小論文しか書けない受験生は、どの大学を受けても小論文に関しては合格しにくい傾向があります。
評価を分ける最大の要素は「根拠の明確さ」です。
不合格になりやすい小論文は「何を主張するか」に焦点を当て過ぎており、その意見を支える根拠や理由が不明確です。
一方、合格する小論文は「なぜそう考えるのか」という理由や根拠を論理的に展開しています。
また、志望学部・学科の基礎的な専門知識を盛り込むことも重要です。例えば、経済学部志望なら経済学の基本概念や時事問題への見解を示すことで、学習意欲の高さをアピールできます。
入門書レベルでも良いので専門分野の知識を身につけ、それを小論文に適切に活用できれば、評価者に好印象を与えることができるでしょう。
これは就職試験や昇進試験の小論文でも、同じことが言えると認識しておいてください。
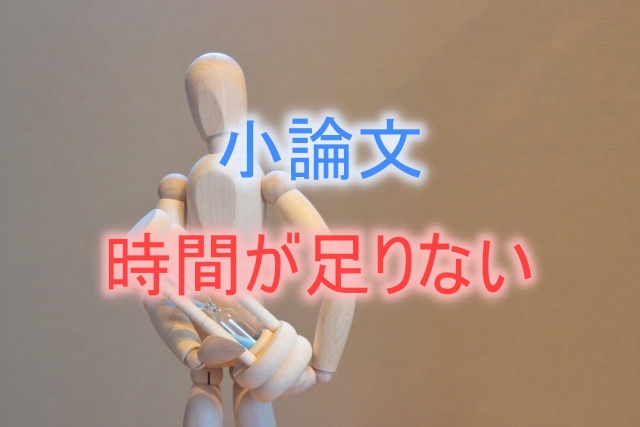
-500x336.png)



コメント