小論文の練習を始めたいけれど、どんなノートを使えばいいか、どの練習用紙を選べばいいか分からない高校生の皆さん。安心してください。
効果的な小論文ノートの作り方から、書きやすい練習用紙の選び方、さらにネタ集めの習慣まで、実践的な方法を分かりやすく解説します。
適切なツールと練習方法を身につけて、どんなテーマが出題されても自信を持って取り組める小論文力を身につけましょう。
関連記事
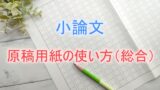
小論文の練習ノート

小論文を効果的に練習するためには、適切なツールを選ぶことが大切です。
練習用ノートの選び方から、無料で使える原稿用紙のダウンロード方法、さらに縦書きと横書きの使い分けまで、実践的な情報をお伝えします。
小論文の練習にオススメのノート
小論文の練習には、文字数を把握しやすく、添削がしやすいノートを選ぶことが効果的です。
特におすすめなのは「漢字罫200字ノート」で、縦20マス×横10マスの構成により、一目で文字数を確認できます。
このノートの最大の特徴は、各マスの右側に細長いスペースがあることです。このスペースを活用すれば、文章を書いた上からコメントや修正点を書き込むことができ、添削も受けやすくなります。
マスのサイズが1.1センチと大きめなので、文字を書いた後でも十分なスペースがあります。セミB5サイズで30枚綴りのため、最大12,000文字の練習が可能で、継続的な練習に最適です。
原稿用紙のダウンロード
自宅で気軽に小論文の練習をしたい場合は、インターネットから無料でダウンロードできる原稿用紙を活用しましょう。
多くのサイトでは400字詰め原稿用紙をPDF形式で提供しており、印刷してすぐに使用できます。記名欄の有無や、A4・B5サイズの選択も可能です。
また、オンラインで文字を入力すると自動的に原稿用紙形式で表示される「原稿用紙エディタ」も便利なツールです。
リアルタイムで文字数を確認でき、印刷も可能なため、手軽に練習を始められます。無料で利用できるサイトが多数あるため、自分の使いやすいレイアウトを見つけて活用しましょう。
スマートフォンでも利用できるサービスもあるので、場所を選ばずに練習できます。
縦書き・横書き両方に慣れておく
小論文の入試では、大学や学部によって縦書きと横書きの両方が出題されるため、事前に両方の書き方に慣れておくことが重要です。
文学部では縦書きが多い傾向にありますが、理系学部や社会科学系では横書きが主流となっています。
縦書きの場合は漢数字(一、二、三)を使用し、横書きの場合はアラビア数字(1、2、3)を使用するなど、それぞれ異なるルールがあります。
また、句読点の位置や改行の仕方も微妙に異なるため、普段から両方の形式で練習しておくことで、本番でも迷わず対応できます。
志望校に事前に確認を取り、どちらの形式が出題されるかを把握しておくことも大切です。
両方の形式に慣れておけば、どちらが出題されても自信を持って取り組めます。
近年は横書きが主流となりつつありますが、受験年度によって縦書き・横書きの形式が変わる場合もあるので、本番で慌てないためにもタテ・ヨコ両方の形式に慣れておくのが望ましいですね。
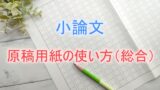
手書きで書く
デジタル化が進み手書きの機会が減っている近年でも、小論文の練習では手書きによる執筆を重視すべきです。試験では手書きで書くからです。
手書きの練習を通じて、普段パソコンで入力している際には気づかない漢字の書き間違いや、思い出せない漢字を発見できます。
また、手書きの場合は文字を書く速度がタイピングより遅いため、一文一文をより慎重に考える習慣が身につきます。これにより、論理的な文章構成を意識する能力も向上します。
手書きでの練習を重ねることで、文字の美しさや読みやすさも改善され、採点者に良い印象を与えることができます。
入試本番では800~1000字という文章を手書きで書く必要があるため、手の疲れに慣れておくことも重要です。
PCで書くことと手書きで書くこととは、全く別物と考えた方がいいですね。
ネタ帳としての小論文ノートの作り方

小論文の合格には、日頃からテーマに関する知識と自分の意見を蓄積することが欠かせません。
ネタ帳を活用した効果的な準備方法と、実践的な作成手順を詳しく解説します。
ネタ帳として1冊ノートを用意する
ネタ帳作成の第一歩は、適切なノートを選ぶことです。
持ち運びやすく、書きやすいノートを用意しましょう。特にルーズリーフ式のノートがおすすめです。ページの差し替えができるため、テーマごとに整理し直すことや、新しい情報を追加することが簡単になります。
また、関連するテーマをまとめて並べ替えることで、論理的な思考を整理する訓練にもなります。
小型の手帳タイプなら、電車の中でニュースを見た時や学校の休み時間にも、すぐにメモを取ることができます。いつでも記録できる環境を整えることで、日常的に情報収集と意見整理を行う習慣が身につきます。
継続的な記録が小論文試験での「何を書けばいいかわからない」という不安を解消してくれるのです。
私も高校生の時にこんなノートを作ったことがなかったので、作り方を教えてくれる人がいれば小論文で合格点を取れたのかなと思いますね。
小論文の基本や対策のおさらい
小論文を書いていくとつい忘れがちな基本や対策について、以下で改めて確認しておきましょう。



ネタ帳ノートの作成手順
効果的なネタ帳を作るには、体系的なカテゴリー分けが不可欠です。
まず、志望校の過去問分析から「出題テーマと傾向」「対策」を整理し、これらを軸に6~7個のカテゴリーを設定しましょう。
「新聞やニュースのネタ」では時事問題を、「本のネタ」では読書から得た知識を記録します。
「自分の経験」には部活動やボランティア活動などの体験を、「公的なデータ」には政府の白書や統計情報を整理しておきます。
「模試や添削の結果」では自分の弱点と改善点を記録し、継続的な成長を促進します。
特に「新聞やニュースのネタ」「本のネタ」カテゴリーに情報を書き込む際は、出典(例:朝日新聞2025年6月10日付 朝刊15面)と日付を明記し、200字程度の要約を付けることで、後から見返しやすくなります。
この分類により、試験で特定のテーマが出題された際に、関連する情報を素早く思い出せるようになります。
ネタ帳ノートのカテゴリー例
| 志望校の過去問分析
出題テーマと傾向
|
意見の書き方
ネタ帳での意見形成は段階的に行うことが効果的です。
まず、志望校の過去問傾向を参考に、関連するテーマを新聞や本から選びます。
テーマ選定の理由も簡潔に記録しておくと、後の振り返りで思考プロセスを確認できます。
次に、選んだテーマについて、新聞やニュース、本などから書く内容を探し「新聞やニュースのネタ」「本のネタ」に記録します。
記録の際は、テーマと出典を明記し、プリントアウト可能なものは貼り付け、それ以外は出典(例:朝日新聞2025年6月10日付 朝刊15面)と内容の要約を200字程度で書きます。
そして数字などのデータの裏付けが必要になる場合は政府の白書や統計データ、その他公的なデータで裏付けとなる事実を収集し、「公的なデータ」カテゴリーに整理します。
最後に、自分の意見を記録します。最初は1~2行でも構いませんが、慣れてきたら序論・本論・結論の構成で書きましょう。
反対意見も想定し、それに対する反論も考えることで、より説得力のある論述力が身につきます。
ネタ帳ノートからの意見の書き方
|
本格的な小論文の練習用紙

小論文の練習では、書きやすい環境を整えることが上達の近道です。適切な練習用紙を選び、効果的な練習方法を身につけましょう。
本格的な小論文の練習にオススメな用紙
小論文の練習には、コクヨの原稿用紙「ケ-75N」が最適です。
この用紙はA4サイズの横書き仕様で、20×20の400字詰めマス目が設けられています。罫線が緑色で目に優しく、長時間の練習でも疲れにくいのが特徴です。
市販の原稿用紙の中でも文字の書きやすさに定評があり、ペンの滑りが良く、文字がきれいに書けます。
50枚入りで価格も手頃なため、繰り返し練習するのに経済的です。
また、A4サイズなので一般的な大学入試の小論文用紙に近い感覚で練習できるのも大きなメリットです。
実際の試験では手書きで解答することが多いため、普段から手書きに慣れておくことで本番でのミスを防げます。
定期的な自己添削と振り返りを行う
小論文の実力向上には、書きっぱなしではなく定期的な自己添削が不可欠です。練習後は必ず自分の文章を客観的に見直し、改善点を見つけましょう。
具体的には、論理構成が明確か、根拠が適切に示されているか、文章表現が自然かなどをチェックします。
また、時間を置いてから読み返すことで、書いた直後には気づかなかった問題点を発見できます。
添削した内容は練習ノートに記録し、同じミスを繰り返さないよう意識しましょう。
さらに、模範解答や他の人の文章と比較することで、自分の文章の特徴や改善すべき点が明確になります。この習慣を続けることで、論理的思考力と文章表現力が着実に向上します。
もちろん自己添削の前後で学校の先生など、信頼できる大人の添削も必ず受けましょう。

ネタ集めの習慣を作っておく
小論文では幅広いテーマに対応できる知識と視点が求められるため、日頃からネタ集めの習慣を身につけることが重要です。
取材記者になったつもりで「なぜ?」「どうして?」「それはどういうこと?」という疑問を持って情報収集すると、モチベーションが上がります。
新聞記事やニュース、書籍から気になった情報を練習ノートに整理しましょう。
その際、単なる事実の記録だけでなく、自分なりの考えや疑問点も併せて記録することが大切です。
また、異なる立場からの意見や反対意見も調べておくと、多角的な視点で論じられるようになります。
社会問題、科学技術、環境問題など、入試でよく出題される分野を意識してネタを収集すると効率的です。
この習慣により、どんなテーマが出題されても自信を持って取り組めるようになります。
高校生ならできるだけ早い時期から上記の準備を行い練習をし、特に高校3年生の人は遅くとも夏休み前後から以上の準備と練習を行うと嫌でも小論文の書くレベルは上達し、推薦入試も含め試験本番までに余裕をもって合格圏内に到達できる小論文が書けるようになるはずです。
正しい練習と労力は自分を裏切らないので、ぜひ今から一つ一つ準備と練習を進めてみてください。

-500x336.png)

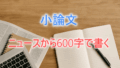
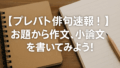
コメント