昇進試験で小論文を課される場合は、意外と多いですよね。
「どう書き始めればいいの?」「評価ポイントはどこ?」といった疑問を抱えている方も少なくありません。
「そもそも昇進先の自分の役割が分からないし、対策のしようがない」という社会人の人が多いのではないでしょうか。
しかし準備不足だと「職場における私の役割と課題」というよく出るテーマに対して、グダグダの出来になってしまいます。
本記事では、昇格試験における課題・テーマの読み取り方をはじめ、小論文の効果的な書き方や、評価される書き出しの例文を詳しく解説します。
今回学ぶこと
関連記事

昇進試験での小論文の書き方

社会人として迎える昇進試験では、小論文が重要な評価ポイントとなります。
多くの企業が筆記試験を導入しており、あなたの思考力や表現力が試されます。ここでは、小論文試験の基本から評価のポイントまで、段階的に解説していきます。
小論文が実施される企業
昇進・昇格試験において小論文試験を導入している企業は非常に多く、特に従業員1,000人以上の企業では約8割が採用しています。
小論文試験は、応募者の論理的思考力や問題解決能力を測る重要なツールとして位置づけられています。
業種を問わず、製造業、サービス業、金融業など幅広い業界で実施されており、特に中間管理職以上の昇進には欠かせない試験となっています。
役職が上がるほど、文書による意思伝達能力が重視される傾向にあるため、この試験の重要性も増していきます。
試験形式
昇進試験における小論文試験は主に3つの形式で実施されます。
最も一般的なのは「集合型試験」で、受験者全員が一つの会場に集まり、その場でテーマが発表され60〜90分程度で800〜1,200字の小論文を書き上げます。
次に「提出型試験」では、事前にテーマが通知され、期日までに論文を作成・提出する形式です。こちらは時間的余裕がある反面、面接でその内容について深く質問されることが多いため注意が必要です。
最近増えているのが「Web型試験」で、オンライン上で時間制限内に小論文を作成する方式です。いずれの形式でも、与えられたテーマに対して論理的かつ具体的な記述が求められます。
| 試験形式 | 特徴 | 実施方法 | メリット・デメリット |
|---|---|---|---|
| 集合型試験 | 最も一般的な形式 | 受験者全員が一会場に集まり、その場でテーマが発表される | ・制限時間:60〜90分程度 ・字数:800〜1,200字 |
| 提出型試験 | 事前準備型 | テーマが事前に通知され、期日までに論文を提出 | ・メリット:時間的余裕がある ・デメリット:面接で内容について深く質問される |
| Web型試験 | 近年増加傾向 | オンライン上で時間制限内に小論文を作成 | ・場所を選ばず受験可能 ・PCでの文章作成スキルも問われる |
いずれの形式でも、与えられたテーマに対して論理的かつ具体的な記述が求められます。
> 小論文・完全ロードマップ解説の《無料メルマガ登録はコチラ》から
頻出テーマ
昇格試験の小論文で頻出するテーマは大きく2つに分類できます。
1つ目は「現状の問題点とその改善策」を問うもので、自社や自部門の課題を分析し、具体的な解決策を提案するものです。
2つ目は「役職者としての役割や心構え」に関するもので、上位職に就く際の意識や行動指針を問われます。
上記から、よく出るテーマとして「職場における私の役割や課題」があります。
これはあなたが「昇進先の役職リーダーとしてふさわしいのか?」という問いを言い換えたものであり、職場の現状と課題をふまえて、どのように課題を解決していくのかという役割が問われています。
直接このような問いでなくても、求められることはあまり変わらないので、日頃から職場や昇進先の現状と課題、昇進した自分ならどのような方法で課題を解決するのかを箇条書きでもよいので、ノートや手帳を用意して書き出しておくとよいでしょう。
そして昇進をするということは、雇われ側で自分の成果を求めるのではなく、「チームで成果を出す・課題を解決する」という会社側での組織の動かし方という視点が必要になります。
つまり昇進先の職場におけるイチ経営者になるということです。
いまいちピンとこない人は、直属の上司や昇進先の上司に「(係長・課長・部長)に求められる役割は何だと思われますか?」と聞いてみてもよいでしょう。
そして同僚や先輩・後輩に「自社や職場の課題や問題点」などを直接聞いてみることもいいかもしれません。
これらをメモしておき、考えると自分だけでは思いつかない視点が見えてくるはずです。
| 頻出テーマ | 内容 | 求められる記述 |
|---|---|---|
| 現状の問題点とその改善策 | 自社や自部門の課題を分析し、具体的な解決策を提案するもの | ・現状分析 ・問題点の特定 ・具体的な改善策 |
| 役職者としての役割や心構え | 上位職に就く際の意識や行動指針を問われるもの | ・役職者としての視点 ・マネジメント方針 ・リーダーシップの発揮方法 |
【頻出キーワード】
「マネジメント」「リーダーシップ」「生産性向上」「部下育成」「コミュニケーション」「テレワーク」「ワークライフバランス」「SDGs」など
そして日頃からこうした観点で業務を振り返る習慣をつけておくと、試験本番でもスムーズに考えをまとめることができるでしょう。
評価基準
昇格試験の小論文では、文章力だけでなく思考力や問題解決能力が総合的に評価されます。
具体的には次の3つの能力が重点的にチェックされます。
1つ目は「問題を把握する力」で、テーマの本質を正確に理解し、現状分析と原因究明ができているかが問われます。
2つ目は「論理を構築する力」です。主張とその根拠が明確で、筋道立てて説明できているかがポイントとなります。
3つ目は「自ら考え抜く力」で、自分自身の経験や知見に基づいた独自の視点が示されているかが評価されます。
評価者は、あなたが上位職に就いた際に直面する様々な課題に対して、どのように思考し解決策を導き出すかを見極めようとしています。
昇進試験の小論文にも対応!
《高評価を得る【小論文の書き方講座】を実施中!》
無料メルマガ内でのプレゼント↓↓↓
> 小論文・完全ロードマップ解説の《無料メルマガ登録はコチラ》から
小論文の基本構成は同じ
昇格試験の小論文も、基本的な構成は他の論文と同様です。
「序論・本論・結論」の3部構成が基本となり、
これはPREP法(Point-Reason-Example-Point)と呼ばれる構成法に通じるものです。
序論では結論(主張)を先に示し、テーマに対する自分の立場を明確にします。
本論では、その主張の理由と具体例を展開します。
この部分で自身の経験や具体的なデータを用いると説得力が増します。
そして結論では、再度主張を繰り返しつつ、さらに一歩踏み込んだ提言や展望を述べると効果的です。
| 構成 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 序論 | 結論(主張)を先に示す | テーマに対する自分の立場を明確にする |
| 本論 | 主張の理由と具体例を展開 | 自身の経験や具体的なデータを用いると説得力が増す |
| 結論 | 再度主張を繰り返す | さらに一歩踏み込んだ提言や展望を述べると効果的 |
この基本構成を守ることで、読み手に伝わりやすく論理的な文章になります。どのようなテーマが出題されても、この構成に当てはめて考えることで、スムーズに論文を組み立てることができるでしょう。
昇格試験での論文書き出し(例文)

昇格試験の論文では、書き出しが評価を大きく左右します。
効果的な導入部は読み手の関心を引き、論文全体の方向性を示す重要な役割を担います。以下に、様々なテーマに適用できる書き出しの例文をご紹介します。
例文1
↓ ↓ ↓ 小論文試験に必須の一冊 ↓ ↓ ↓
小論文の基本から、試験を想定した
実践練習まで、この一冊で身に付きます!
この一冊で小論文のお悩みすべて解決!
\ Amazonで400冊突破!/
例文2
例文3
書き出しのポイント
効果的な論文の書き出しには、社会情勢や業界動向から説き起こし、自社の課題へと焦点を絞るアプローチが有効です。
まず、大きな環境変化や潮流を示すことで、論文の背景と重要性を示します。
次に、その変化が自社にどのような影響をもたらしているかを述べ、自部門や自身の業務と関連付けることで当事者意識を示します。
そして、問題意識を明確に表明した上で、論文の目的と構成を簡潔に予告します。これにより採点者は論文全体の見通しを得られ、論理展開が理解しやすくなります。
また、具体的な数字や事例を盛り込むことで説得力が増します。最後に、論文を通じて何を提言したいのかを明確にすることで、読み手の関心を引き付ける効果も期待できるでしょう。
「です・ます」「だ・である」のどっちが良い?
昇進試験での小論文の語尾をどちらにするかは、明確にルールがあるわけではありません。
ただ、どちらでもよいのであれば「だ・である」調をおすすめします。
論理的に自分の考えを示すときの基本ですし、「です・ます」調よりも無駄な文字数を削減できるからです。
いずれにせよ、一度選んだ文体は論文全体で一貫させることが重要です。混在させると論文の統一感が損なわれ、印象が悪くなります。
また、どちらの文体を選ぶにせよ、簡潔で明瞭な文章を心がけ、冗長な表現や回りくどい言い回しは避けるべきです。
読み手の立場に立った、わかりやすい論文作成を心がけましょう。
昇格試験・論文の課題と例文(解答例)

昇格試験における論文作成は、自身の思考力や問題解決能力を示す重要な機会です。
効果的な論文を書くためには、事前準備から実際の執筆まで、段階的なアプローチが必要です。以下では、昇格試験論文の作成プロセスとともに、具体的な解答例を紹介します。
日頃から自社の課題などを把握する
昇格試験の論文で高評価を得るためには、普段から自社の課題や動向を把握しておくことが重要です。
日常業務の中で、自部門における問題点や全社的な経営課題に目を向け、メモを残す習慣をつけましょう。
朝礼や全体会議、社内報などから情報を収集し、業界ニュースや経済動向も定期的にチェックすることで、論文で取り上げる価値のある課題が見えてきます。
特に、上司との1on1ミーティングや同僚との雑談も貴重な情報源となります。
これらの情報を整理しておくことで、試験当日に具体的な事例や数字を交えた説得力のある論文を書くことができ、評価者に「現場を理解している」という印象を与えることができるでしょう。
↓ ↓ ↓ 小論文対策に必須の一冊 ↓ ↓ ↓
小論文の基本から、試験を想定した
実践練習まで、この一冊で身に付きます!
この一冊で小論文のお悩みすべて解決!
\ Amazonで400冊突破!/
まず問題文を読んで内容を把握する
昇格試験の論文に取り組む際は、まず問題文をよく読み、出題意図を正確に理解することが必須です。
特に「役割」や「課題」などのキーワードがある場合、それらの定義を混同しないよう注意しましょう。
例えば、「職場における私の役割と課題」という問題では、「役割」は職務上求められる責任や期待を、「課題」はその役割を果たすために克服すべき具体的なタスクを指します。
また、昇格対象の職位(係長、課長など)を念頭に置き、現在の立場ではなく、昇格後の視点で論じる必要があります。
問題文に記載された文字数制限も必ず確認し、時間配分を意識しながら準備を進めましょう。
問題文の読み違えは、どんなに内容が優れていても評価を下げる要因となるため、最初の数分で確実に理解することが重要です。
書くテーマと論点を決める
昇格試験論文において、テーマと論点の設定は合否を分ける重要なポイントです。
与えられた課題に対して、自分の強みや経験を活かせるテーマを選び、2〜3つの主要論点に絞ることで論文の骨格が明確になります。
例えば「職場における私の役割と課題」という課題なら、「部門目標の達成」と「部下の育成」を役割として設定し、それぞれに対応する課題を具体的に示すとわかりやすくなります。
論点を選ぶ際は、会社の経営方針や部門の目標と整合性があり、かつ自分の実務経験に基づいた説得力のある内容を心がけましょう。
また、独自の視点や問題意識を示すことで、評価者に「この人ならではの考え」を印象づけることができます。
抽象的な美辞麗句ではなく、具体的な事例や数値を含む論点を設定して実現性のある答えが高評価につながります。
アウトラインを書いて解答を書く
効率的に論文を作成するには、本格的な執筆前にアウトラインを作成することが不可欠です。
まず、双括型(結論 → 理由 → 具体例 → まとめ)の構成を基本に、各パートの大枠を決めましょう。
アウトラインには、結論(10%)、理由(40%)、具体例(40%)、まとめ(10%)の割合を目安に、要点を箇条書きで記入します。
この段階で使いたい重要なキーワードや事例もメモしておくと良いでしょう。
例えば「職場における私の役割と課題」なら、役割の定義から始め、自分が考える役割を明示し、その役割から導き出される課題を論理的に説明する流れを計画します。
アウトラインの作成は試験時間全体の5分程度に収め、残りの時間で実際の執筆に集中することが大切です。
文章化する際は、パラグラフごとに「主題文→説明→具体例→小括」の流れを意識し、全体の一貫性を保ちながら書き進めましょう。
解答例1
問題:あなたの職場における働き方改革の課題と解決策
【解答例】
働き方改革の本質は、単なる労働時間の短縮ではなく、業務効率の向上と従業員のワークライフバランス実現の両立にある。当社営業部門における働き方改革の課題は、①デジタルツール活用不足による業務非効率、②成果主義への移行過程での評価基準の曖昧さ、③多様な働き方を支える組織文化の未熟さ、の3点だと考える。
これらの課題に対する解決策として、まず①については、顧客情報管理システムとモバイル端末の連携強化を図り、外出先からでもリアルタイムで情報共有できる環境を整備する。当部門では年間3,000件以上の顧客データを扱うが、現状ではその入力・更新作業に多くの時間を費やしている。新システム導入により、この作業時間を40%削減し、顧客との直接対話時間を増やすことが可能となる。
②の評価基準については、従来の「営業訪問件数」や「勤務時間」といった量的指標から、「顧客満足度」や「問題解決率」といった質的指標へと重点をシフトする。具体的には、四半期ごとに顧客へのアンケート調査を実施し、その結果を評価に反映させる仕組みを構築する。これにより、必ずしも長時間働かなくても高い成果を上げる社員が正当に評価される土壌が醸成される。
③の組織文化の醸成については、部門内で「働き方改革推進チーム」を発足させ、様々な立場の意見を集約しながら改革を推進する。特に、育児や介護と仕事の両立を図る社員の体験を共有する場を設け、多様なライフスタイルへの理解を深める取り組みを実施する。
これらの施策を通じて、生産性向上と従業員満足度の双方を高める真の働き方改革を実現し、持続可能な組織成長につなげていきたい。
解答例2
問題:デジタル技術を活用した業務効率化について
【解答例】
デジタル技術を活用した業務効率化は、単なるコスト削減だけでなく、社員の創造的な業務への集中と顧客満足度向上を両立させる重要な経営課題である。現在、製造部門では図面管理や検査記録の紙ベース処理が多く、月間約150時間が書類作成・検索に費やされている状況だ。
業務効率化のためには、まず情報のデジタル化と一元管理が不可欠である。設計図面や検査データをクラウド上で管理し、必要な情報へのアクセス時間を短縮する。具体的には、タブレット端末を生産現場に導入し、リアルタイムでデータ入力・参照ができる環境を整備する。これにより、従来30分かかっていた過去図面の検索が5分以内で完了するようになり、年間約1,000時間の工数削減が見込める。
次に、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用し、定型業務の自動化を進める。特に月次の品質レポート作成や在庫確認などの反復作業は、RPAに置き換えることで人的ミスを減らしながら処理時間を80%削減できる。これにより生まれた時間を、品質改善や新製品開発といった付加価値の高い業務に振り向けることが可能となる。
さらに、IoTセンサーを製造設備に取り付け、稼働状況や異常の予兆を常時監視するシステムを構築する。これにより、従来の定期点検から予防保全へと移行し、突発的な設備故障による生産停止リスクを最小化する。実際に類似システムを導入した他部門では、設備停止時間が年間40時間から15時間に減少した実績がある。
以上の施策を通じて、デジタル技術を効果的に活用することで、業務効率の大幅な向上と社員の働きがいを両立させ、持続的な競争力強化に貢献していきたい。
以上、解答例は昇進先の役職の立場としての取り組みを省いているため、かなり文字数が少ないですが、あなたの昇進先での役職であれば、どのように取り組むかも考えて参考にしてみてください。
小論文の対策は、下の無料メルマガでも実施中↓↓↓
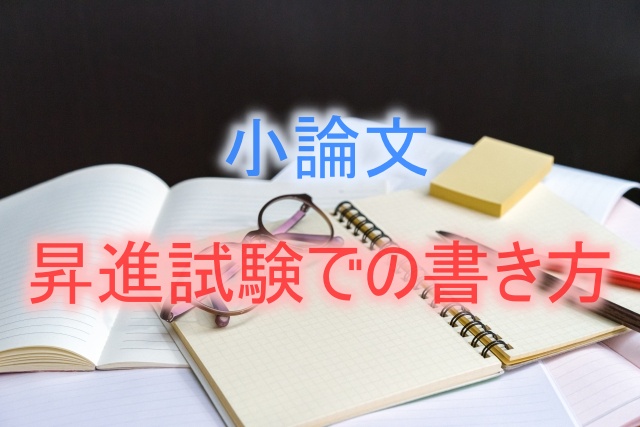
-500x336.png)

-500x336.png)




コメント