「小論文の具体例が思いつかない…」と悩んでいませんか?
小論文で説得力のある文章を書くためには適切な具体例が不可欠ですが、多くの受験生が具体例の書き方やネタ探しに苦労しています。
本記事では、小論文の具体例を効果的に書くポイントと、具体例が思いつかないときの実践的な対処法を解説します。
問題文の正確な理解から始まり、自分の経験を活かす方法、日常からのネタの集め方まで、あなたの小論文を飛躍的に向上させる具体的なアプローチをご紹介。
小論文の具体例で悩む受験生が、説得力と独自性を兼ね備えた小論文を書けるようになるためのヒントが満載です。
今回学ぶこと
関連記事
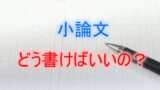
小論文の具体例の書き方

小論文で説得力のある文章を書くには、適切な具体例が不可欠です。しかし、多くの受験生が「どんな具体例を挙げれば良いのか」「どう書けば効果的か」と悩んでいます。
ここでは、小論文における具体例の効果的な書き方のポイントを解説します。
| ポイント | 概要 | 具体的な方法 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 問題を理解する | 問題の主旨を正確に把握することが出発点 | ・問題文に線を引く
・重要な箇所を囲む ・「何について論じるのか」を明確化 |
・的外れな具体例を避ける
・迷ったら問題に立ち返る |
| 問題の条件を理解する | 出題者からの指示・条件を遵守する | ・「具体例を挙げて説明」などの指示を確認
・字数制限の把握 ・構成についての指示の確認 |
・条件無視は大幅減点
・具体例は全体の3割程度が理想 |
| 理由から意見を考える | 理由を明確にすることで適切な具体例が浮かぶ | ・「なぜそう考えるのか」を掘り下げる
・自分の経験や社会問題から具体例を探す ・理由と具体例の整合性を確認 |
・意見が明確でないと具体例も曖昧になる
・読み手に「なるほど」と思わせる具体例を選ぶ |
問題を理解する
小論文の具体例を書く際、まず問題の主旨を正確に理解することが出発点です。
問題文に線を引く、重要なところは文言を囲んだり印をつけ「何について論じるのか」「どのような視点が求められているのか」を明確にしましょう。
例えば、環境問題について論じる場合、単なる現状説明ではなく、原因や解決策についての考察が求められていることがあります。
問題の核心をつかめていないと、いくら良い具体例を挙げても的外れになってしまいます。具体例選びに迷ったときは、一度立ち止まって問題に立ち返ることで、自分の意見と整合性のある事例を選べるようになります。
問題の主旨を捉えることは、説得力のある具体例を導き出す第一歩です。
問題の条件を理解する
小論文では問題文に示された条件を必ず守らなければなりません。
「具体例を挙げて説明しなさい」「賛成・反対の立場を明確にしなさい」など、出題者からの指示は無視できません。条件を見落として書き進めると、いくら内容が優れていても大幅な減点対象となります。
また、字数制限や構成についての指示も重要です。
制限字数内で効果的に具体例を組み込むには、事前に割り当てを考えておくと良いでしょう。
特に具体例は文章全体の3割程度に収めるのが理想的です。条件を把握した上で計画的に文章を組み立てることで、求められた形式で自分の考えを効果的に伝えられる具体例になります。
理由から意見を考える
具体例と意見がうまくつながらない原因の多くは、自分の意見が明確に固まっていないことにあります。
まず「なぜそう考えるのか」という理由を掘り下げましょう。
理由が明確になれば、それを補強する具体例も自然と浮かびます。
例えば、「教育におけるICT活用は重要だ」という意見があるなら、「学習の個別最適化が可能になる」という理由に対して、「ある学校での学力向上事例」という具体例が生まれます。
また、自分の経験や社会問題、歴史的事象など、さまざまな分野から具体例を探すことで説得力が増します。理由と具体例の整合性を確認しながら、読み手に「なるほど」と思わせる具体例を選ぶことが、小論文の説得力を高める鍵となります。
小論文で具体例が思いつかないときは

小論文で具体例が思いつかず行き詰まることは誰にでもあります。「立派な例を書かなければ」と思いすぎて筆が止まってしまうことも。
具体例に悩む受験生のために、効果的なネタの集め方から発想法まで、実践的なアプローチを紹介します。
| 対処法 | ポイント | 具体的なアプローチ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 自分の主張は一般論でもOK | 奇抜さより説得力を重視する | ・一般的な意見でも理由や根拠で差別化
・「なぜそう思うのか」を自分の言葉で説明 ・思考の深さや論理性を意識する |
・筆が進みやすくなる
・論理的一貫性が生まれる ・採点者に伝わる説得力のある文章になる |
| 知っていることに置き換える | 問題を自分の知識や経験に関連付ける | ・身近な体験に置き換える
・抽象的テーマを具体的に言い換える ・ニュースや授業の知識を活用する |
・具体例が見つけやすくなる
・独自性のある内容になる ・説得力が増す |
| 問題の内容を掘り下げる | 多角的視点から問題を検討する | ・出題の背景や意図を考える
・キーワードから連想を広げる ・時間軸(過去/現在/未来)で考える |
・新たな視点が生まれる
・論点が明確になる ・幅広い具体例が見つかる |
| 自分の体験や知識を掘り下げる | 経験から学びを導き出す | ・「そこから何を学んだか」まで考える
・日常の出来事を深掘りする ・体験を「自分ごと」として消化する |
・独自性のある文章になる
・説得力が高まる ・小論文に個性が生まれる |
自分の主張は一般論でもOK
小論文で独自性を出そうとするあまり、奇抜な主張を考えようとして行き詰まることがあります。
しかし、入試小論文では珍しいアイデアよりも説得力のある根拠が重視されます。自分の主張自体は一般的な意見でも構いません。
例えば、「教育にICTを導入すべき」という主張は多くの人が書きそうなテーマですが、なぜそう考えるのかの理由や具体例で差別化できます。
大切なのは「なぜそう思うのか」を自分の言葉で論理的に説明できることです。
採点者は奇抜さではなく、思考の深さや論理性を評価しています。一般論でも、自分ならではの視点や根拠を加えることで、説得力のある小論文に仕上げられるのです。
塾や予備校、書店の参考書の影響で、つい奇抜なアイデアを思いつかないといけないという間違いをしがちですが、小論文は広告のキャッチコピーではないので、勘違いをしないようにしましょう。
問題の内容に沿って、自分が知っていることに置き換える
小論文の問題が自分と関係ないと感じて具体例が思いつかない場合は、問題の内容を自分の知っている事柄に置き換えてみましょう。
例えば、医療問題について書く場合、自分や家族の病院体験を思い出してみる。環境問題なら、学校での環境活動や地域の取り組みに置き換えられます。
抽象的なテーマでも「要するにどういうことか」と問いかけ、自分の言葉で言い換えることで具体例は見つかりやすくなります。
また、新聞やニュースから得た知識も活用できます。ポイントは広く浅くではなく、少ない例でも深く掘り下げること。
問題の本質を自分の知識や経験に照らし合わせることで、独自性のある具体例を見つけることができます。
問題の内容を掘り下げる
具体例が思いつかない時は、問題自体を多角的に掘り下げてみましょう。
まず「なぜこの問題が出題されたのか」「この問題の背景には何があるのか」と考えてみることで、新たな視点が生まれます。
例えば「SNSの利点と問題点」という題材なら、利便性、コミュニケーション、情報拡散、プライバシー、依存性など様々な側面から検討できます。
また、問題に関連するキーワードをいくつか挙げ、それぞれについて連想ゲームのように関連事項を広げていく方法も効果的です。時間軸で考えることも大切で、過去の類似事例や将来の展望に目を向けると具体例の幅が広がります。
もっとも試験時間があるので、やみくもにブレインストーミングを行うのではなく、キーワードを絞り、論点を2つくらいに絞って考えていきましょう。
このように問題の本質を深く理解することで、説得力のある具体例を見つける糸口になるります。
自分の体験や知識を掘り下げる
小論文で最も説得力があるのは、自分自身の体験から導き出された具体例です。
「こんな経験をした」だけでなく、「そこから何を学んだのか」「どう考えが変わったのか」まで掘り下げることで、独自性のある文章になります。
例えば、ボランティア活動の経験があれば、そこで感じた社会問題や自分の価値観の変化を具体例として活用できます。
日常の些細な出来事でも、それを「なぜ○○なのか?」「他の事例は?」などと少し深堀りするだけでも立派な具体例になります。
また、読書や授業で得た知識も自分なりに解釈することで活きた具体例になります。
ポイントは、体験や知識を「自分ごと」として消化し、自分の言葉で表現すること。
たとえ体験してなくとも、「自分ならどうするだろうか?」と考えることで問題を「自分ごと」として消化できます。
そして他の受験生と同じ体験でも、そこからの学びは一人ひとり違います。その違いこそが、小論文に個性を与える重要な要素といえます。
物事を自分ごととして考えると、小論文に限らずけっこう面白いこともあるので、こういった考え方はかなりオススメですよ。
小論文の具体例のネタ集め

小論文を書く際に説得力を高めるポイントは、自分の意見を裏付ける具体例をいかに効果的に提示できるかです。
日常生活の中で意識的にネタを集めることで、独自性のある説得力の高い小論文を書くことができます。以下、効果的なネタ集めの方法をご紹介します。
小論文の具体例のネタ集め
小論文で独自性を発揮するには、他の受験生と差別化できる具体例が不可欠です。
新聞やニュースサイトから得た情報、専門書籍の内容、統計データなどを活用することで、論述に説得力が生まれます。
日頃から志望学部に関連する話題に注目し、気になる情報はメモやスクラップにまとめておくと良いでしょう。
ただし、情報をそのまま引用するのではなく、その情報から自分が考えたことや感じたことを付け加えることが重要です。
情報の収集と同時に、それに対する自分の考えを整理する習慣をつけることで、入試本番でもスムーズに文章を組み立てられるようになります。
新聞や書籍、Webから集める
信頼性の高い情報源から具体例を集めることは、小論文の質を高める効果的な方法です。
新聞は見出しを流し読みして志望学部に関連する情報をチェックし、気になる記事はスクラップしておくと便利です。
インターネットの活用では、「〇〇とは」と検索して基本概念を押さえたり、省庁などの公的機関のウェブサイトから最新の政策や統計データを入手したりすると良いでしょう。
書籍からは体系的な知識を得られますが、すべてを暗記する必要はなく、ポイントを理解して自分の言葉で説明できるようにしておくことが大切です。
これらの情報源から得た知識は、具体例として活用するだけでなく、自分なりの視点で解釈し、意見の根拠として組み立てられるようにしておきましょう。
赤本の「傾向と対策」から集める
志望校の過去問を分析することは、効率的なネタ集めの一つです。赤本の「傾向と対策」ページには、その大学が重視する論点や頻出テーマが掲載されていることが多く、これを参考にすることで的を絞った準備ができます。
「傾向と対策」には参考書籍が掲載されている場合があるので、それらを読んでみましょう。
そして過去に出題された問題を実際に解いてみると、どのような具体例が評価されやすいのかが見えてきます。
また、志望学部に関連する時事問題や専門的なトピックが出題される傾向があれば、それに関する情報を優先的に集めることも有効です。
過去問の模範解答や解説を読むことで、論理展開の方法や具体例の挙げ方についても学べます。志望校が求める小論文のスタイルを把握した上で、それに合わせたネタを集めることで、より効果的な対策となります。
実体験を活用する
自分自身の経験は、他の受験生にはない独自性のある具体例になります。
部活動での体験、ボランティア活動、家族との会話、旅行先での気づきなど、日常生活のあらゆる場面が小論文のネタになり得ます。
例えば、環境問題について論じる際に地域の清掃活動に参加した経験を挙げたり、医療問題について書く際に家族の入院体験から感じたことを述べたりすることで、説得力のある文章になります。
もちろん実体験を挙げるときでも、問題に沿って挙げるべきか止めるべきかを考えましょう。
また実体験を活用する際は、単なるエピソード紹介に終わらせず、そこから得た気づきや考えを深め、問題との関連性を明確にすることが大切です。
自分にしか書けない体験談と、客観的な資料や情報を組み合わせることで、独自性と説得力を兼ね備えた小論文を作成できるようになります。
今回の考えた方は、小論文を書くということ限らず、社会のあらゆる問題を考えることに役立ち、思考の幅が何倍にも広がるので、ぜひ活用してみてください。

-500x336.png)

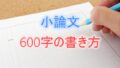
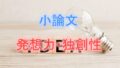
コメント