小論文で国際系のテーマを探している受験生の皆さん、悩んでいませんか?
トランプ政権の保護主義政策とその行き詰まりは、まさに今の国際情勢を読み解く絶好の小論文テーマです。
なぜトランプが保護主義を推進するのか、その背後にある経済的・感情的要因から、関税政策の限界、ドル安誘導や日米同盟の見直しまで、多角的な視点で論じられます。
本記事では、国際系小論文で重要な「自分の考え」を持つための視点を、トランプ政策を例に解説。
あなたの小論文が採点者の心をつかむ国際系ネタをお届けします。
関連記事

小論文の国際系ネタ

国際学部や外国語学部の受験を考えている人にとって、小論文対策は非常に重要です。
これらの学部では、グローバルな視点や多文化理解、国際問題に関する知識と思考力が問われます。
以下では、国際系小論文の対象学部、頻出テーマ、対策について解説します。
主な対象学部
国際系の小論文が課される主な対象は、国際関係学部、国際学部、外国語学部、グローバル学部などです。これらの学部では、世界の多様な文化や言語、国際社会の課題について深く学ぶことができます。
国際学部・外国語学部の小論文では、特に言語と文化の関係性についての出題が多く見られます。例えば「日本において公用語を英語とするメリットとデメリット」などのテーマが出題されることがあります。
また、これらの学部を志望する場合、グローバルな視点は必須です。世界における日本の立ち位置や役割について考察することも重要になります。
各大学の特色によって出題傾向は異なりますが、文化交流や国際協力、グローバルビジネスなど、幅広い領域について思考力と表現力が求められるのが特徴です。国際系学部の小論文では、論理的思考力とともに、多角的な視点から物事を捉える力が評価されます。
ただ対象外の学部でも小論文の問題として出されることがあるので、受験生のみなさんが要チェックしておきましょう
頻出テーマ
国際系小論文では、現代のグローバル社会における様々な課題がテーマとして出題されます。以下が特に頻出するテーマです
【多文化共生と異文化理解】
多様な文化や価値観が共存する社会における課題や可能性について論じる問題が多く出題されます。日本社会における外国人との共生や、ダイバーシティ&インクルージョンについての考察が求められます。
【グローバリゼーションの功罪】
経済のグローバル化がもたらした恩恵と問題点について考察する問題です。貧富の格差拡大や環境問題なども関連して出題されることがあります。
【言語と文化の多様性】
英語の世界共通語化と各国の言語文化保護のバランスについての問題です。EU諸国の言語政策や英語帝国主義についての知識も役立ちます。
【国際的IT企業と国家主権】
GAFAMなどの巨大IT企業が国家の枠を超えて影響力を持つことの意義と課題について考察します。個人のプライバシー保護と経済発展のバランスも論点になります。
【環境問題と国際協力】
気候変動問題や持続可能な開発目標(SDGs)に関する国際的な取り組みについての問題です。日本の環境政策と世界標準との比較も重要な視点です。
【感染症対策と国際協調】
COVID-19パンデミックを契機に、各国の感染症対策の違いや国際協力の重要性についての出題が増えています。文化や政治体制による対応の違いも考察すべき点です。
これらのテーマに関して、世界と日本を比較する視点や、歴史的背景を踏まえた考察が求められることが多いです。単なる知識の羅列ではなく、多角的な視点からの分析と自分の意見の論理的展開が評価されます。
対策
国際系小論文で高評価を得るためには、日頃からの情報収集と思考トレーニングが不可欠です。以下に効果的な対策を紹介します:
情報収集と知識の吸収
- 新聞・ニュースの活用: 日本の新聞だけでなく、海外メディア(BBCやCNNなど)も定期的にチェックし、グローバルな視点を養いましょう。
- 時事用語集の活用: 「日経キーワード」などを活用して、国際関係の重要キーワードを理解しておきましょう。
- 専門書の読み込み: 『異文化コミュニケーション学』(鳥飼玖美子)などの国際系のテーマを扱った新書や専門書を読み、知識と思考を深めましょう。
小論文作成のテクニック
- 資料の正確な読み解き: 課題文や統計資料を正確に理解し、要点を整理する練習をしましょう。
- 設問の意図把握: 何が問われているのかを正確に理解し、指示通りに解答することが重要です。
実践的トレーニング
- 過去問演習: 志望大学の過去問を入手し、実際に時間を計って解答する練習をしましょう。
- 構成メモの活用: 本番前に構成メモを作る習慣をつけ、論理的な展開を意識しましょう。
- 添削指導: 書いた答案を先生や信頼できる人に読んでもらい、客観的なフィードバックを得ることも大切です。
論述のポイント
- 多角的視点: 一方的な意見ではなく、異なる立場や視点も考慮した論述を心がけましょう。
- 具体例の提示: 抽象的な議論だけでなく、具体的な事例や自分の経験を交えると説得力が増します。
- バランスの取れた主張: 極端な意見より、多様な価値観を尊重する姿勢が評価されます。
- 解決策の提案: 問題点の指摘だけでなく、現実的な解決策まで踏み込んで論じると良いでしょう。
国際系の小論文では、グローバルな視点と日本の立場を両方考慮しながら、論理的かつ説得力のある文章を書くことが求められます。日頃から国際問題に関心を持ち、自分なりの考えをまとめる習慣をつけることが、合格への近道となるでしょう。
採点者から見ても、普段から国際問題に関心を持って考えてきた人とそうでない人は、小論文を書かせるとすぐに分かります。
知識を増やすと同時に、通り一遍の暗記してきた知識ではなく、持っている知識で多角的に考えて書くという意識を持って練習をしましょう。
トランプが保護主義を進めるのはなぜ?

現在進行形のテーマとして、関税政策を主とするトランプ大統領の保護主義について見ていきます。
この保護主義政策には、経済的・政治的な様々な背景があります。関税を武器にした貿易戦略は単なる経済政策ではなく、国内支持層への訴求や国際交渉のテコとしての側面も持ち合わせています。
以下では、その主な理由と背景について詳しく見ていきましょう。
関税が国内産業を復活させるとの考え
トランプ政権が保護主義政策を進める最大の理由は、関税によって外国製品の価格を引き上げ、アメリカ国内産業の競争力を回復させられるという信念にあります。
外国からの安価な輸入品に対して高い関税を課すことで、その価格優位性を相殺し、国内企業の製品がより魅力的になるという論理です。
とりわけ中国や日本、ドイツなどからの工業製品輸入によって職を失ったと感じる製造業従事者の支持を獲得しています。
この考え方は、グローバル化によって国内の工場が閉鎖され、製造業の雇用が失われた「ラストベルト」と呼ばれる地域の有権者に強く響いています。
関税政策が短期的には国内産業を保護する効果がある一方、経済学の「比較優位説」に基づく自由貿易の恩恵を犠牲にするというトレードオフも存在するのです。
そして関税はアメリカに輸出している外国が支払うわけではなく、アメリカ国内の輸入業者が支払うため、その製品価格に転嫁され、アメリカ国内の消費者が支払うため自国の国民に負担を強いる政策といえます。
感情的な側面もある
トランプの保護主義には強い感情的要素が絡んでいます。
「アメリカ・ファースト」のスローガンに象徴されるように、グローバル化によって不利益を被ったと感じるアメリカ人の不満や怒りに訴える側面があります。
多くの支持者にとって、安価な外国製品の流入は単なる経済問題ではなく、アメリカの威信や自尊心に関わる問題として捉えられています。
自由貿易協定が「不公平な取引」としてレッテルを貼られ、アメリカが世界に「搾取されている」という感情的なナラティブが形成されています。
このような感情に基づく政策は、冷静な経済分析よりも強力な政治的訴求力を持ちます。
実際、保護主義政策が経済的に最適でないとしても、「アメリカを再び偉大に」という感情的なメッセージと結びつけることで、広範な支持を集めることに成功しているのです。
パッケージ・ディールという側面
トランプの関税政策には、単なる保護主義的措置を超えた戦略的な側面があります。
ディール(取引き)を交渉の主体に据えるトランプ氏は、高い関税を最初に提示することで、相手国からより有利な条件を引き出すテコとして活用しています。
これは「パッケージ・ディール」と呼ばれる交渉手法の一環であり、関税という強力なカードを切ることで、貿易赤字の是正や市場アクセスの改善、知的財産権の保護強化など、他の分野での譲歩を引き出そうとしているのです。
実際、USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)の交渉では、関税の脅しを背景に旧NAFTAを自国に有利な条件で再交渉することに成功しました。
トランプ政権にとって関税は目的ではなく手段であり、最終的には二国間の「より公平な」貿易協定を結ぶことを目指している可能性が高いといえるでしょう。
小論文のテーマとして、どう考えるか
トランプの保護主義政策を小論文のテーマとして考察する場合、多角的な分析が必要です。
まず、グローバル化の恩恵と代償を客観的に評価することが重要です。
自由貿易は経済全体としては効率的ですが、その利益と損失は社会の中で均等に分配されているとは限りません。
そのため、単に「保護主義は悪、自由貿易は善」という二項対立で論じるのではなく、どのような政策が持続可能で公平な国際経済秩序を構築できるかを検討すべきでしょう。
また、アメリカのような資源大国と日本のような資源に乏しい国では、保護主義の影響が大きく異なる点にも注目すべきです。
さらに、保護主義政策の短期的効果と長期的影響を区別し、政治的人気と経済的合理性のバランスについても論じる必要があります。
結局のところ、保護主義か自由貿易かという二択ではなく、公正なルールに基づいた持続可能な国際経済システムをどう構築するかが本質的な問いなのです。
いま日本では主要な輸出産業である自動車に追加関税が課されて、その追加関税の撤廃を巡ってアメリカと交渉をしていますが、難航しています。
今までならば、このような時はアメリカ産農産物の関税を引き下げ輸入自由化を行うなど、競争力の弱い日本の農業を犠牲にするという措置で譲歩してきましたが、今夏の参議院選挙に向けて、政府与党はこれ以上農家の票を失うことは避けたいために対応に苦慮しています。
これは個人的な考えですが、日本もパッケージ・ディールを行えばよいと考えています。
ただ自動車の関税を下げてくれと言っても、それだけではさらなる譲歩をせまられるばかりでしょう。
そこで日本も、「どうしても輸出自動車の一律関税を元に戻さないのであれば、やむを得ずアメリカからの輸入農産物に対する関税ゼロや優遇措置を撤廃して、全てのアメリカ産農産物に高い関税をかけざるを得ない」とアメリカが困るような政策を提示することです。
「トランプ政権以前の状態まで戻せば、アメリカ産農産物に対する高関税政策は撤廃する」と持ち掛けます。
対中国のように関税の引き上げ合いの応報になるかもしれませんが、あるところまでいくとアメリカにとっても相当の経済的な打撃になるので、アメリカ側も譲歩せざるを得なくなるでしょう。
世界最大の石油産出国であり、自国の食料自給率が100パーセントを超えるアメリカは、形の上では貿易抜きでやっていける数少ない国かもしれませんが、現代のテクノロジーであるApple iPhoneのようなスマートフォン一つとっても、その製造を外国に依存しているため、保護貿易の継続はアメリカ国民に最も打撃のある措置といえるかもしれません。
小論文のテーマ「トランプ政策の行き詰まり」

トランプ政権の政策展開は単なる関税政策にとどまらず、ドル安政策や同盟国との安全保障関係の見直しなど、多層的な戦略を持っています。
仮に一つの政策が行き詰まっても次の手段へと移行する可能性があり、特に日本のような同盟国はその影響を強く受ける立場にあります。
以下では、トランプ政策の行き詰まりとその先の展開について考察します。
関税政策は行き詰まるとの見方
トランプ政権が掲げる高関税政策は、長期的には持続困難との見方が強まっています。
関税引き上げは輸入品価格の上昇を通じてアメリカ国内のインフレを加速させ、消費者負担を増大させるためです。
また、対象国からの報復関税により、農産物をはじめとする米国製品の輸出が打撃を受ける懸念もあります。
実際に第一次トランプ政権時の対中関税戦争では、米国農家への悪影響が顕著となり、巨額の補助金で対応せざるを得ませんでした。
さらに、世界貿易機関(WTO)のルールとの整合性問題や、グローバルサプライチェーンの複雑化により、関税だけで貿易赤字を是正することには限界があります。
それでもトランプ政権は国内支持層への配慮から関税政策を掲げ続けるでしょうが、その効果は徐々に薄れていくと予想されています。
次はドル高の是正か
関税政策の限界が見えてくると、トランプ政権は「第2の矢」としてドル安政策へと舵を切る可能性が高まります。
トランプ大統領は従来から「ドル高は米国製造業の国際競争力を損なう」と主張しており、為替操作を批判してきました。
ドル安政策が本格化すれば、財務省や連邦準備制度理事会(FRB)への圧力を強め、利下げ要求や為替介入の可能性も出てくるでしょう。
特に注目すべきは、かつてのプラザ合意のような国際的な通貨調整の枠組みを模索する動きです。
ただし、現在の国際金融市場は1980年代とは大きく異なり、中国という新たな経済大国の存在や、各国の政策協調の困難さから、単純なドル安誘導は期待通りの効果をもたらさない可能性があります。
それでも国内産業保護という政治的目標のため、ドル安政策は推進されていくでしょう。
円安圧力の人質としての日米同盟見直し
日本は対米安全保障上の依存度が高いため、トランプ政権の政策展開において特に脆弱な立場にあります。
円安が続く日本に対して、トランプ政権は二国間通貨合意を迫り、円高誘導を要求してくる可能性があります。
この際に「人質」として機能するのが日米安全保障条約です。安全保障面での「応分の負担」を要求する中で、為替政策への協力を同時に求めてくる展開は十分に考えられます。
日本は世界最大級の米国債保有国であることを交渉カードとして活用できますが、トランプ政権はこれを単に「最も安全で流動性の高い金融商品を日本に提供している」と解釈する可能性もあります。
日本政府は円安修正とドル安政策への協力要請、そして安全保障負担増加の要求が同時に押し寄せる事態に備えた包括的な外交戦略を構築する必要があるでしょう。
そこで安全保障の分野で在日米軍の日本からの引き上げすらトランプ大統領が持ち出しかねないというと与党政治家や主要な論客者まで、まるで日本だけが困るようなものの言いようします。
したがってそうならないように、日本側が譲歩すべきだという言説です。
たしかに現時点で在日米軍が引き上げられれば日本は困ります。ただし安全保障上の点で在日米軍の引き上げで一番困るのはアメリカだという点が抜けています。
世界戦略の一環としての在日米軍基地の存在の大きさや中国やロシアに対するアメリカ本土の安全保障にも大きな寄与をしており、在日米軍基地の喪失によって在韓米軍基地やグアムまで後退することになり、日本以上にアメリカにとっての安全保障上の大きな損失、脅威の増大につながるでしょう。
また在日米軍基地の存在は、日本と中国が接近しすぎることにくさびを打つという側面もあります。
日中の仲が悪すぎても困るが、仲良くしすぎてもアメリカにとっては東アジアでの影響力の低下を招くので、自国の安全保障上困るということです。
これらのことをきちんと理解して、あるいはトランプ政権に理解させて、変に譲歩をするのではなく、むしろ「東アジアで最大の基地設備を提供してやっているのだから、半分くらいはアメリカが費用を負担しろ!」と言えなければ、きちんとした交渉はできず譲歩に譲歩を重ねるしかありません。
受験生のみなさんはどう考えるでしょうか。
直接問われることはないが、自分の考えを持っておく
トランプ政権の政策展開と日本への影響について、一般市民が直接政策決定に関与することはありませんし、まして小論文の問題として直接問われませんが、国際経済の仕組みと自国の立場を理解しておくことは極めて重要です。
米国の保護主義的政策は短期的には自国産業を守るように見えますが、長期的には世界経済全体の縮小を招き、結局は米国自身の繁栄も損なう恐れがあります。
一方で、日本が過度に円安に依存した輸出主導型成長から脱却し、内需拡大や生産性向上による持続可能な経済成長を目指すべきという視点も重要です。
国際政治経済の変動に一喜一憂するのではなく、どのような環境変化にも対応できる経済構造への転換が求められています。
第二次世界大戦後に築かれてきた国際体制や価値観が揺らぐ中で、問題解決を模索する小論文の問題としても間接的には格好のテーマと言えるでしょう。

-500x336.png)

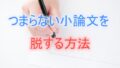

コメント