「最近のニュースから600字で小論文を書きなさい」という課題が出されて、何から手をつけていいか分からない高校生の皆さん。安心してください。
最近のニュースで600字の小論文を書くさいのテーマ選定から、最近のニュースをもちいた小論文の書き出し方まで、効果的な取り組み方を分かりやすく解説します。
ニュース選びのコツ、社会問題の読み取り方、論理的な構成の作り方を身につけて、高評価を得られる小論文を書けるようになりましょう。
関連記事


最近のニュースから600字で小論文を書く

小論文を書く際は、単にニュースを要約するのではなく、そのニュースから見えてくる社会問題について自分の考えを述べることが重要です。
600字という限られた文字数の中で、効果的に自分の主張を伝えるためのポイントを詳しく解説します。
新聞、ネット記事から興味を持った記事を選ぶ
記事選びは小論文の成否を左右する重要な要素です。
まず、自分が興味を持っている分野の記事を選ぶことで、より深い考察ができるでしょう。
AI技術、環境問題、働き方改革など、普段から関心のある分野であれば、背景知識も豊富で説得力のある論述が可能です。
一方で、普段は興味がない分野のニュースを選ぶことも効果的な練習方法です。
国際情勢や経済問題など、馴染みのない分野について調べ、考察する過程で、多角的な視点を身につけることができます。
これは実際の入試で予想外のテーマが出題された際に、冷静に対応する力を養うことにもつながります。
重要なのは、選んだ記事が社会性を持っているかどうかです。
個人の成功談や芸能ニュースでも、その背景に社会問題が隠れていることがあります。表面的な出来事だけでなく、そこから読み取れる社会の課題を見つけることが、良い小論文を書く第一歩となります。
はじめは「面倒くさ!」と思いますが、こういう練習がのちにある小論文の試験の時に効果を発揮しますよ。
社会問題の読み取り方
ニュースから社会問題を読み取るには、体系的な思考が必要です。
まず「何が問題なのか?」を明確にしましょう。
例えば、高齢者の交通事故のニュースであれば、問題は「高齢者の運転能力低下」「公共交通機関の不足」「免許返納制度の不備」など複数考えられます。
次に「なぜ問題なのか?」を考察します。
高齢者の交通事故が問題となる理由は、被害者の増加、社会不安の拡大、高齢者の移動手段の制限などが挙げられます。この段階で、問題の本質を理解することができます。
「背景には何があるのか?」では、問題の根本原因を探ります。
少子高齢化の進行、地方の過疎化、公共交通政策の遅れなど、様々な要因が絡み合っていることが見えてきます。
最後に「その問題が社会全体にどんな影響があるのか?」を考えることで、問題の重要性と緊急性を理解できます。
これらの視点を箇条書きで整理することで、論点が明確になり、説得力のある小論文を書く準備が整います。
分からないことがあれば
小論文を書く過程で分からないことに遭遇するのは当然のことです。
その際は「調べる → 考える → 人に聞く→ 考える」という順序で知識を深めていきましょう。
まず、インターネットや新聞、書籍を活用して基本的な情報を収集します。
専門用語の意味、統計データ、専門家の意見などを調べることで、書く土台を固めることができます。調べた内容について自分なりに考察し、疑問点や不明な点を整理します。
次に、先生、家族、友人などに質問し、異なる視点や意見を聞きます。
他者の考えを聞くことで、自分の視野が広がり、より多角的な論述が可能になります。ただし、人に聞いた内容をそのまま使うのではなく、再度自分で考えることが重要です。
この「調べる → 考える → 人に聞く → 考える」のサイクルを繰り返すことで、表面的な知識だけでなく、深い理解に基づいた小論文を書くことができます。
知識を得る過程そのものが、思考力を鍛える貴重な機会となります。
最近のニュースから小論文を書く意味
最近のニュースを題材にした小論文の練習には、実践的な意味があります。
実際の入試では、出題される小論文の多くが、現在進行形の社会問題やニュースで話題となった問題の背景から作られています。
AI技術の発展、環境問題、働き方改革など、現在社会で議論されている問題が、そのまま入試問題として出題されることも珍しくありません。
普段からニュースに触れ、それについて考える習慣を身につけることで、入試本番で初めて見るテーマでも、冷静に対応できる力が身につきます。
また、複数の視点から問題を捉え、自分の意見を論理的に構築する能力も養われます。
さらに、ニュースを通じて社会問題に関心を持つことで、将来社会人として必要な判断力や思考力も身につきます。
小論文の練習は、単なる入試対策ではなく、社会の一員として必要な力を育てる重要な学習活動なのです。
日々のニュースに目を向け、それについて考える習慣こそが、質の高い小論文を書く最も確実な方法と言えるでしょう。
小論文の試験も要は、普段からの練習の慣れなので、こういう練習をしていた人とそうでない人では差が出るのは当然ですよね。
最近のニュースから小論文を書くポイント
最近のニュースから小論文を書く課題には、以下のような意味があります。
1. 社会への関心を高める
日々のニュースに関心を持つことで、社会の動きを理解し、自分も社会の一員であることを自覚できます。
2. 批判的思考力を育む
ニュースをただ受け取るのではなく、批判的に分析し、自分の意見を形成する力が身につきます。
3. 論理的表現力を向上させる
限られた字数の中で、論理的に自分の考えを表現する技術を習得できます。
4. 多面的な視点を養う
一つの問題について、様々な立場から考える習慣が身につきます。
コツとポイント
- 感情的な表現は避け、客観的な視点で書く
- 「思う」より「考える」を多用する
- 具体例や数字を入れて説得力を高める
- 最後は前向きな提案で締めくくる
小論文は「正解」があるわけではありません。
重要なのは、自分の考えを論理的に表現することです。最初は難しく感じるかもしれませんが、練習を重ねることで必ず上達します。
今日のニュースから、早速一つテーマを選んで挑戦してみましょう。
最近のニュースから小論文のテーマを選ぶ

小論文のテーマ選びは、書く内容の質を大きく左右します。
テーマが決まっている場合と決まっていない場合では、アプローチ方法が異なります。どちらの場合でも、効果的な選び方を理解しておくことが重要です。
テーマが決まっている場合
学校の課題で「環境問題について」「AI技術について」など、あらかじめテーマが指定されている場合は、そのテーマに関連するニュースを探すことから始めましょう。
環境問題であれば、気候変動、脱炭素社会、再生可能エネルギー、プラスチック問題など、幅広い視点から関連ニュースを収集します。
重要なのは、テーマの範囲内で最も書きやすく、かつ説得力のある論述ができそうなニュースを選ぶことです。
例えば、AI技術のテーマなら、ChatGPTの教育現場での活用、自動運転技術の進歩、AI による雇用への影響など、具体的な事例が豊富にあるニュースを選びましょう。
また、テーマが決まっている場合でも、そのテーマに対する自分なりの切り口を見つけることが大切です。
同じ環境問題でも、技術的解決策に焦点を当てるか、ライフスタイルの変化に注目するかで、論述の方向性は大きく変わります。テーマの範囲内で、自分が最も関心を持てる角度からニュースを選ぶことで、より深い考察が可能になります。
テーマが決まっていない場合
テーマが自由に選べる場合は、まず自分の興味・関心のある分野から始めてみましょう。
スポーツ、音楽、ゲーム、ファッションなど、どんな分野でも社会問題につながる可能性があります。好きな分野から入ることで、書くことへの抵抗感が減り、自然と深い考察ができるでしょう。
一方で、あえて普段興味のない分野に挑戦することも有効な練習方法です。政治、経済、国際問題など、馴染みのない分野について調べ、考察する過程で、多角的な視点を身につけることができます。
これは実際の入試で予想外のテーマが出題された際の対応力向上にもつながります。
「何に興味があるか分からない」という人は、新聞やネットニュースのカテゴリーから選んでみましょう。「社会」「経済」「国際」「科学技術」「スポーツ」「芸能」など、各カテゴリーを眺めて、少しでも気になる記事を見つけることから始めます。
芸能ニュースでも、「誰々が不倫した」など単なるゴシップではなく、パワハラやセクハラなど社会性のある問題を扱った記事なら、立派な小論文のテーマになります。
> 小論文・完全ロードマップ解説の《無料メルマガ登録はコチラ》から
考え方
選んだニュースについて、体系的に考察することが重要です。
まず「何が問題なのか?」を明確にしましょう。表面的な出来事だけでなく、その背景にある本質的な問題を見つけることが大切です。
次に「なぜ問題なのか?」を考え、問題の重要性や緊急性を理解します。
「その背景は何か?」では、問題の根本原因を探ります。
歴史的経緯、社会構造、制度の問題など、様々な要因が絡み合っていることが多いはずです。
「社会にどんな影響があるか?」では、その問題が放置された場合の将来への影響を考察します。
さらに「そこから言えること」では、個別の問題から見えてくる普遍的な課題や教訓を抽出します。「自分はどう考えるか」で自分の立場を明確にし、「なぜそう考えるのか」で根拠を整理します。
これらの要素を箇条書きで書き出すことで、論点が整理され、説得力のある小論文の骨格が完成します。
実際に書くとき
小論文を書く際は、選んだ問題に関連する自分の知識や経験を積極的に活用しましょう。
学校で学んだことや読書で得た知識、日常生活での体験など、幅広い視点から問題を捉えることで、オリジナリティのある論述が可能になります。
例えば、働き方改革の問題を取り上げる場合、両親の働き方を観察した経験や、アルバイトでの体験などを織り交ぜることで、説得力が増します。
ただし、個人的な体験だけで終わらせず、それを社会全体の問題として捉え直すことが重要です。
また、異なる立場の人々の視点も考慮しましょう。
問題の当事者、関係者、専門家など、様々な立場から問題を見ることで、多面的な論述が可能になります。
自分の主張だけでなく、反対意見にも言及し、それに対する反論を述べることで、より説得力のある小論文になります。
そして自分がその当事者なら「どうなるのか?」ということも考えてよいでしょう。
最終的には、問題の解決策や今後の展望についても言及できれば高評価を狙えますし、実際の小論文を書く本格的な練習になります。
私が高校生のとき、「最近のニュースを小論文で書いてみよう!」という宿題自体がなく、もし当時あったら「え~、面倒なんですけど」と思ったでしょうが、今から考えると自分の思考力を鍛えるために、こういう宿題があった方がよかったですね。
こういう宿題で、小論文の考え方や書く手順を学んでいれば、大学入試の小論文もきちんと書けたと思うので、今この記事を読んでいる皆さんにはぜひ考える力を鍛えてもらいたいと思います。
最初は面倒ですが、慣れてしまえばそんなに難しいことではなく、むしろ物事を考えるのが楽しくなりますよ。
最近のニュースでの小論文の書き出し例

ここでは、実際の時事問題を題材にした書き出しパターンと600字で書いた答案例を紹介します。実際に書く参考にしてみてください。
書き出し3例
1. 選挙とSNS(問題提起から始める)
近年の選挙では、SNSを活用した情報発信が当たり前となっている。特に若者の政治参加を促進する手段として期待される一方で、誤情報の拡散や感情的な議論が横行する問題も浮上している。SNSが選挙に与える影響を考えると、情報の真偽を見極める力がこれまで以上に重要になっていると感じる。
そこで私は、SNSを政治参加の入り口として活用しつつ、情報リテラシーの向上が不可欠だと考える。
2. 生活保護費減額は違法との最高裁判決(分析から始める)
2013年から実施された生活保護費の減額措置について、最高裁判所は2025年6月に「違法」との統一判断を示した。この判決の背景には、過去に芸能人の親族による生活保護受給が批判を浴び、政権が公約として掲げた制度見直しがあった。
しかし、憲法25条が保障する生存権の観点から、最高裁は行政の判断に問題があったと結論づけた。この判決は、社会保障制度の根本的な意味を改めて問い直すものだと考える。
3. 政治家の失言(具体例から始める)
米価高騰の中、「コメを買ったことがない、支援者がくれるから家の食品庫には売るほどある」という元農相の発言や、「運がいいことに、能登で地震があった」と災害を政治的に利用するような発言が相次いでいる。確かに発言の一部が切り取られて報道されることもあるが、言葉にはその人の日常的な思考や価値観が表れる。
特に国民の代表として選ばれた議員の発言は、その人の国民や社会に対する基本的な姿勢を示している。私は、政治家には言葉の重みを自覚し、国民の立場に立った発言を心がけてほしいと考える。一方で災害の被災者や社会的弱者などを含めて国民の立場に立つという姿勢のある候補者かどうかを、選挙を通じて私たち有権者は今いちど見極める必要があるとも考える。
600字答案例(生活保護費の減額は違法との最高裁判決)
(ニュースを見て問題提起)
2013年から実施された生活保護費の減額措置について、最高裁判所は2025年6月に「違法」との統一判断を示した。この判決は、社会保障制度の在り方を根本的に問い直すものであり、私たちは改めて「生存権」の意味を考える必要がある。
(社会的な背景)
この減額措置の背景には、一部芸能人の親族による生活保護受給問題があった。世間の批判を受けて、当時野党であった自民党は生活保護費の適正化を公約に掲げ、政権復帰すると実際に生活保護費の減額を実施した。しかし、最高裁は厚生労働大臣の判断に「誤りがあり、違法だった」と指摘し、減額処分を取り消した。
(実際の裁判で下された判決の分析)
この判決から見えてくるのは、社会保障制度が政治的な思惑に左右されてはならないという原則である。確かに制度の悪用は許されないが、それを理由に本当に支援が必要な人々の権利を制限することは、憲法25条の生存権に反する。社会保障は国民の最低限の生活を保障するセーフティネットであり、感情的な議論ではなく、客観的なデータに基づいて運営されるべきだ。
(自分の考え)
また、この問題は私たち国民の意識にも関わっている。「生活保護を受けることは恥ずかしいこと」という生活保護に対する偏見や差別意識が、制度の適切な運用を妨げている面もある。支援が必要な人が適切に制度を利用できる社会こそが、真の福祉国家と言えるのではないだろうか。(548字)
小論文の対策は、以下の無料メルマガでも実施中↓↓↓
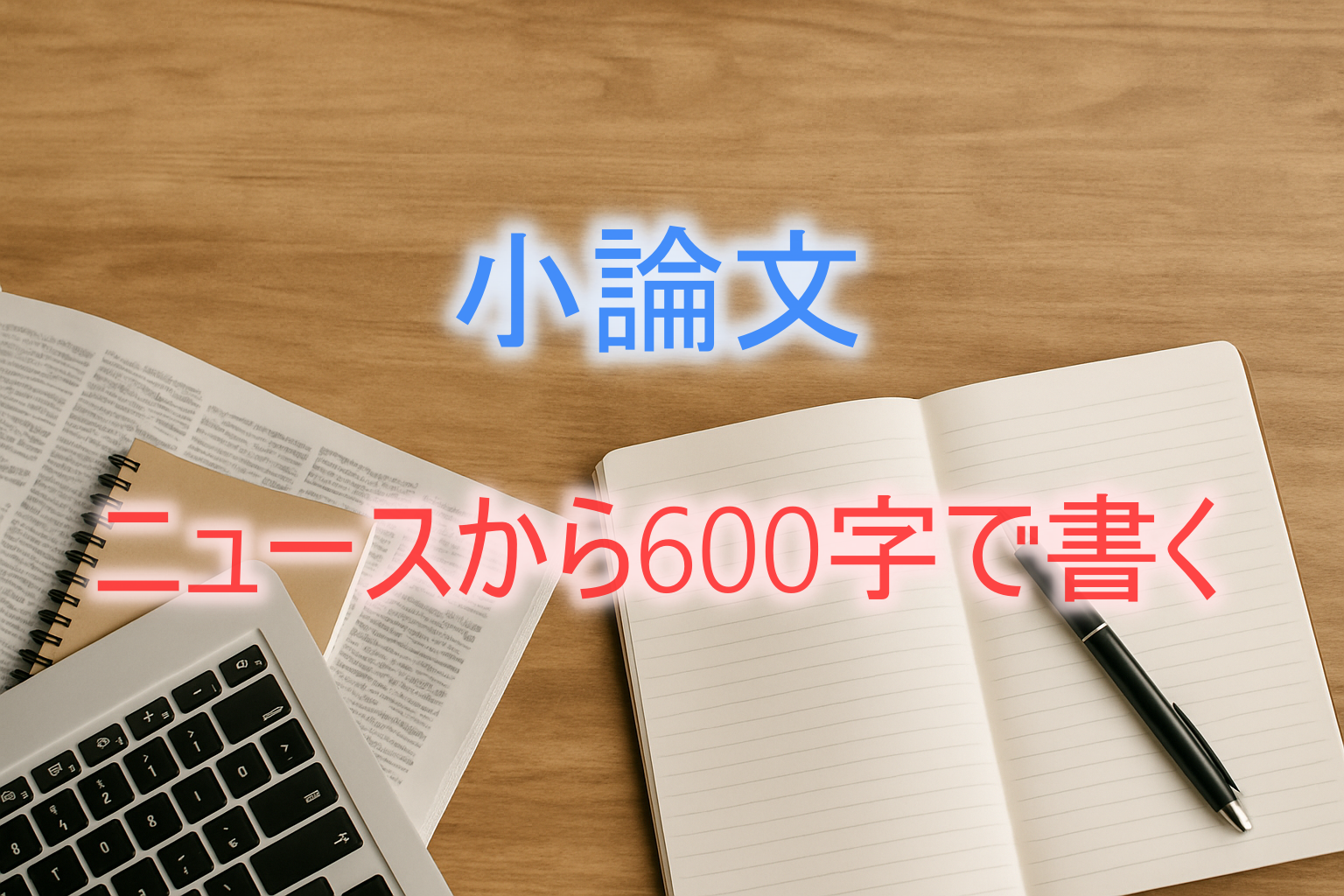
-500x336.png)


-500x336.png)
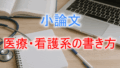
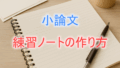
コメント