「小論文でやらかした!」
受験生からの悲鳴が聞こえるときがあります。
ただ、これは小論文のよくあるミスを押さえておけば、大丈夫です。
また「小論文でやらかしたけど、合格した!」という例もあるので、もしやらかしてしまったという人がいたら諦めないでください。
もし不合格だとしても、よくあるミスを押さえて、次の試験に活かしましょう。
今回学ぶこと
関連記事


小論文でやらかした

「小論文でやらかした」というのは何が原因なのかといえば、正しい基本が身についておらず、正しい方法で練習をしていないからです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
正しい基本を身に付けていないから
小論文でやらかさないために、まずは正しい小論文の基本をおさらいしておきましょう。
以下をご覧ください。


やらしてしまうというのは、普段はきちんとできているんだけど、試験本番にそれができなかったというトーンで言われますが、本当は基本が身についていないから必然的にやらかしてしまいます。
あるいは、きちんと身に付けず曖昧な理解なままだと、その「試験本番でやらかす」確率が高くなります。
正しい方法で練習していないから
書き方も上の基本と同じく、正しい方法で練習を重ねないと本番でミスをしてしまう可能性が高まります。
練習の方法は、以下でご覧ください。

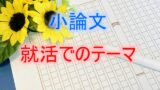
「自分の言いたいことが定まらない」ということが無いように、最初に作ったアウトラインの通りに文章を書いていき、結論で内容を追加して文章の方向性が変わってしまうことのないようにしましょう。
あれもこれも書いて、自分の意見を詰め込みすぎることを避けるためにも原稿用紙に書き始める前に、アウトラインを作っていきます。
小論文のよくあるミス6選

受験生が小論文でよくやりがちなミスを6つ挙げました。反対にこれらのミスを防げば合格に近づくということなので、しっかり見ていきましょう。
① 問題の指示に答えていない
これは不合格につながる致命的なミスです。
出題者側が聞いていることに答えていないわけですから当然です。
そこで「問題の指示に答えるなんて当たり前じゃん!」と思うでしょうが、多くの受験生ができていません。
例えば「〇〇について賛成か反対かを理由を添えて答えなさい」と聞かれているのに、「私は(賛成・反対関係なく)~と考える」と書く。
「あなたはなぜ本県の教員を志望しているのか、本県の教職員の課題を踏まえて答えなさい」と聞かれているのに、延々と自分の志望理由を答えて、その県の教職員全体の課題を踏まえていないなど。
聞かれたことは全部答えるのが小論文の基本なので、聞かれたことに1か所でも答えていないのは、致命的だと覚えておきましょう。
チェックリスト
② 原稿用紙の使い方が正しくない
これは形式的なミスですが、かなり気にする採点者の人もいます。
もちろん複数の採点者の平均から最終的な評価が出るので、ひとりの人の評価が悪いからといって、即不合格になるわけではありませんが、見た目でも文章に対する印象に影響するので、原稿用紙は正しく使いましょう。
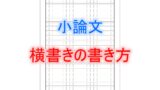
上は横書きの原稿用紙の使い方ですが、縦書きは原稿用紙を右に90度回転させたものが使い方です。
いずれ縦書きの原稿用紙の使い方も書きますが、横書きとの違いは数字の使い方で、縦書きの場合、数字は漢数字を使います。
数字の使い方以外は、縦書き横書きどちらも共通の書き方で通用します。
チェックリスト
③ 誤字・脱字
これも一見形式的なことに見えますが、自分が書きたかったことと別の意味に解釈されかねないので、誤字・脱字には気をつけましょう。
単純な漢字表記のミスや言葉の使い方のミスなど、一つ一つの減点は小さなものですが、積み重なると合否に影響するので、これら誤字・脱字のミスはしない、あるいはできるだけ減らすように心がけましょう。
チェックリスト
④ 言葉の使い方が正しくない
これも細かいところですが、言葉の使い方が正しくないと別の意味に解釈されたり、文章全体の印象も悪くなります。
しかし、最近は新聞でもこういった誤りの文章を平気で載せることがあるので、言葉づかいがきちんとしていると、それだけで採点者から「ほぉー、言葉づかいがきちんとできてるじゃん!」と好印象を持たれるかもしれません。
チェックリスト
⑤ 話し言葉になっている
これも文章に対する印象が悪くなります。
書き言葉で書きましょう。
親しみのある文章を書きたい人もいるかもしれませんが、小論文に親しみはいらないので、以下のように書き言葉で文章を書いていきます。
チェックリスト
⑥ 語尾が「だ・である」調に統一されていない
小論文は基本的に語尾は「だ・である」調で書き、最後まで統一します。
文章の途中で「です・ます」調にならないようにしましょう。
チェックリスト
「小論文をやらかしたけど、合格した」という仕組み

「小論文をやらかしてしまったけど、何か合格した」という話は時々聞きますが、なぜ合格したのか以下でその仕組みをおさらいしておきましょう。
小論文が書き終わらなかったけど合格した
小論文が書き終わらなかったけど、合格したという仕組みは以下の記事で解説しています。
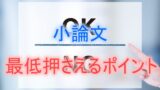
「やらかした」と思っても、採点基準を知っておく
「小論文でやらかした」と思っても、採点基準を知っておけばパニックにならずに済むので、以下の解説をご覧ください。
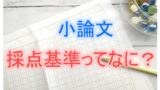
「これで絶対合格だ!」「不合格だ!」ということではないのですが、少なくとも基準にはなるので、試験後合格ならば、今度は就職試験や昇進試験の小論文などでやらかさないように活かしましょう。
もし不合格ならば、2次試験や別の志望校、または志望先企業の小論文の試験に活かして、自分の失敗を決して無駄にしないようにしましょう。
練習で書いたら、以下のチェックリストで見直してみる
☑ 原稿用紙のタテ書きは漢数字(一、二)、横書きはアラビア数(1、2)
☑ 誤字・脱字はないか
☑ 言葉の使い方は正しいか
☑ 書き言葉になっているか
☑ 語尾は「だ・である」調に統一されているか

-500x336.png)

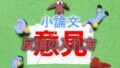

コメント