歴史のテーマで、小論文をどう書いてよいか悩む受験生必見!
今回の「関口宏の一番新しい近現代史」(1883年~1886年)に合わせて、鹿鳴館の舞踏会外交やアフリカ分割のコンゴ問題など、歴史の転換点を深く読み解きます。
「なぜそうなったのか」という問いかけを中心に、単なる暗記ではなく因果関係で歴史を捉える思考法を解説。
国内と国際情勢の繋がりを理解することで、説得力ある小論文が書けるようになります。歴史の本質に迫るヒントが満載です!
関連記事

関口宏の一番新しい近現代史を小論文で見る

関口宏の一番新しい近現代史(1883年~1886年)を通して、日本の近現代史を小論文の視点で考察します。
単なる史実の羅列ではなく、歴史の転換点における因果関係や国際情勢の中での日本の立ち位置を理解することが、近代日本史の本質です。
ここでは特に注目すべき3つの視点から分析していきます。
近代世界史の中の日本
日本の近代化は世界史の大きな潮流の中で位置づけることで初めて本質が見えてきます。
明治維新は単なる国内改革ではなく、当時の西欧列強による世界分割という国際情勢への対応でした。
江戸時代の独自的な発展から、明治以降は西洋を追いかける道を選んだ日本。その結果、西欧化と近代化の同義語化が進み、アジアの一員でありながら西洋に追いつき追い越せという矛盾した立場に置かれました。
特に日清・日露戦争での勝利は、アジアにおける日本の特異な立場を確立させましたが、同時に帝国主義への道を進める契機となりました。
小論文では「なぜ日本は西洋化の道を選んだのか」「アジアの中の日本という立場はどのように変化したか」といった問いかけが重要です。
歴史の因果関係を国際情勢と関連付けて考察することで、説得力のある小論文を構築できるでしょう。
英傑による構築から、システム化していく維新体制
明治維新は坂本龍馬や西郷隆盛といった英傑たちの活躍で語られることが多いですが、小論文では個人の活躍から社会システムへの転換という視点が重要です。
維新直後の近代国家形成は、確かに志を持った英傑たちによって推進されましたが、やがて軍隊・警察・教育・官僚制度などの「システム」によって支えられる国家へと変貌していきました。
この「人からシステムへ」という転換は、西欧の近代国家を模倣した結果であり、日本社会の根本的な変化を意味します。
小論文では、このシステム化がもたらした功罪、特に国民国家としての統一感獲得と個人の自由の制限という二面性について掘り下げると良いでしょう。
憲法制定や議会開設といった制度面だけでなく、「家」制度の再編や国民意識の形成といった社会的変化も、システム化の過程で生じた現象です。
歴史を単なる出来事の連続ではなく、社会構造の変化として捉える視点が小論文には不可欠です。
世界と国内での因果関係を見る
小論文で歴史を論じる際には、国内事象と国際情勢の相互作用について考察することが重要です。
例えば、鹿鳴館に象徴される西洋文化の導入は単なる文化的憧れではなく、不平等条約改正という外交目標を達成するための国策でした。
また、アフリカ分割という国際的な植民地争奪戦は、日本の朝鮮半島や台湾への進出と時期的に重なり、世界的な帝国主義の潮流と日本の行動には強い相関関係があります。
小論文では「なぜその時期にその事象が起きたのか」という問いを立て、国内要因と国際要因の両面から考察することで説得力が増します。
特に産業革命と軍事力の関係、資源獲得と植民地政策の連動性など、経済と政治の相互関係を論じることで、歴史の必然性と偶然性を浮き彫りにできるでしょう。
関口宏の番組が示す「日本の意志とは何だったのか」という問いは、こうした複合的な因果関係の中に答えを見出す試みと言えます。
歴史は暗記ではなく、因果関係の流れで理解することで深い学びになりますし、記憶に定着しやすくなります。そして面白さを感じるようにもなります。
この考え方は、受験なら他の記述問題にも応用できますよ。
鹿鳴館での舞踏会はなぜ行われたか、その目的は?

鹿鳴館は明治期日本の西洋化政策を象徴する建築物で、条約改正を目指した外交戦略の一環として建設されました。
ここでは当時の鹿鳴館外交について、単なる西洋の模倣と批判される側面だけでなく、その歴史的意義と背景について多角的に考察していきます。
西洋の猿真似と揶揄された舞踏会
鹿鳴館での舞踏会は、当時「西洋の猿真似」と揶揄されることが少なくありませんでした。
1883年に完成した鹿鳴館では、上流階級の日本人がフロックコートやドレスを身にまとい、ワルツやポルカを踊る姿が見られました。
特に福沢諭吉のような開明的知識人からも「表面的な模倣に過ぎない」と批判されたのは、その形式だけを取り入れる姿勢への懸念があったためです。
外国人からも「ぎこちない模倣」と揶揄される場面が多く、舞踏会で食事のマナーを間違える日本人貴族の姿は、西洋文化の本質を理解せずに形だけを取り入れる危うさを示していました。
そもそも伊藤博文ら推進者たちも、鹿鳴館文化を日本の伝統と調和させようという意図よりも、西洋列強に「文明国」としての日本をアピールすることに主眼を置いていたのです。
このような表層的な西洋化は、その後の日本の近代化過程において、常に内在する問題となっていきました。
必ずしも猿真似だけとは言えない面もある
ただし、鹿鳴館外交を単なる「猿真似」と断じるのは一面的すぎるでしょう。
明治政府にとって不平等条約改正は国家的急務であり、鹿鳴館はその外交戦略として綿密に計画されたものでした。
イギリス船籍の貨物船が和歌山県の紀州沖で座礁沈没した際、日本人乗客が救助されず全員死亡したことでイギリス人船長の責任が問われたものの、領事裁判によって不問に付された「ノルマントン号事件」によって、日本人は不平等条約の弊害を痛感することになったのです。
井上馨外務卿は「日本の文明化」を列強に示すことで条約改正交渉を有利に進めようと考え、その象徴として鹿鳴館を機能させようとしました。
実際、来日した外国使節を招いた舞踏会は、彼らの日本観を変える効果を部分的に持つことになります。
また、日本の上流階級女性が社交場に出ることで、「女性の地位が低い東洋の遅れた国」というイメージを払拭する狙いもありました。
さらに、鹿鳴館での交流は、単なる模倣を超えて西洋外交の作法や国際関係の構築方法を実践的に学ぶ場として機能していました。
しかし、井上馨による条約改正がなかなか進まず、世論は彼の外交を弱腰だと批判するようになりました。
そして、井上は1887年に辞任に追い込まれ、これで鹿鳴館の時代が終わってしまったのです。完成からわずか4年でした。
ただし、鹿鳴館の建物自体は華族会館として利用され、その後は日本徴兵保険会社となり1940年の解体まで使用されています。
皮肉なことに、表面的模倣と批判されながらも、この経験が後の日本の国際舞台での活躍の基盤を形成したという側面は見逃せません。
また内閣制度を導入して、1885年に初代内閣総理大臣に伊藤博文が就任し、ようやく国の形ができていく中で、まだ大日本国憲法の発布(1889年)や国会開設(1890年)がなされていないのが少し驚きですよね。
この時期、まだまだ日本の国家制度を形づくる途上だったことが分かります。
近代文明の本質を理解するチャンスだった
鹿鳴館外交は、本来であれば近代化の本質そのものを理解する絶好の機会だったと言えます。
舞踏会やテーブルマナーといった形式の背後には、個人の尊厳や男女平等思想、契約概念に基づく人間関係など、西洋近代が育んできた価値観が存在していました。
しかし多くの場合、日本の指導者層はそうした本質よりも表面的な作法の習得に力を注ぎ、形式と内容の乖離を生じさせてしまいました。
例えば、男女が対等に踊る社交ダンスの背景には西洋の男女観があったにもかかわらず、その思想的背景への理解は置き去りにされがちでした。
この時期に西洋の制度や文化の単なる模倣ではなく、その根底にある思想や価値観まで深く理解していれば、その後の日本の近代化はより健全な発展を遂げた可能性があります。
そして近代文明=西洋文明ではないという本質的な理解が未だになされていないことにも表れています。
たしかに近代化は西洋で興りましたが、西洋が近代化していく基盤となった羅針盤・火薬・活版印刷の三大発明は中国での出来事であり、算用数字や「マンガン」などの科学用語はアラビア文化に起因します。
つまり、中世までの世界各地の遺産や業績を体系化したものが近代文明であり、それは西洋の業績ではありましたが、西洋文明ではありませんでした。
もしこのとき西洋文化から、ここまで近代の本質を学べていたら、もっと日本に合わせた近代化が実現できていたでしょう。
残念ながら、その理解は今も日本では進んでおらず、「エビデンス」や「サステナブル」など日本語で言えることにわざとカタカナ語を持ってくるような猿真似的な現象が続いています。
鹿鳴館時代は、近代日本が西洋や近代との向き合い方を誤った象徴的な出来事として、現代にも重要な示唆を与えているのです。
ベルリン会議、アフリカ分割の原則、今に残るコンゴ問題
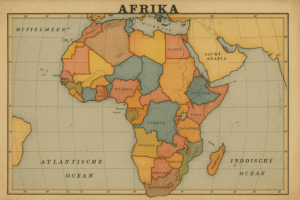
19世紀後半に行われたアフリカ分割は、欧州列強による植民地獲得競争の集大成でした。特にコンゴ地域をめぐる問題は、その後の現地社会に深い傷跡を残しています。
ここでは、アフリカ分割の実態とコンゴ問題の歴史的背景から現代への影響を考察します。
植民地獲得は早い者勝ち
近代初期まで超大国であった清の力が弱まる中、ヨーロッパは東南アジアに進出し、太平洋地域でも本格的な領有が進むなど、欧米によって世界の領土を分け合う状況になっていきました。
その中でもアフリカ分割は、19世紀後半に欧州列強が文字通り「早い者勝ち」でアフリカ大陸を分け合った歴史的事象です。
1880年代以前、欧州諸国のアフリカ支配は主に沿岸部に限られていましたが、産業革命による工業化で原料と市場を求める動きが加速しました。
特に転機となったのは、ベルギー国王レオポルド2世による「コンゴ自由国」の設立宣言でした。
彼は「文明化」や「奴隷貿易撲滅」という名目を掲げつつ、実際には個人的な富の獲得を目指していました。
イギリスやフランスもこの動きに対抗し、次々と内陸部への進出を本格化させます。各国は探検家や冒険家を派遣し、現地首長と「条約」を結ばせて自国の勢力圏を拡大していきました。
こうした無秩序な領土獲得競争は、欧州諸国間の摩擦を生み出し、最終的には「分割ルール」を定めるベルリン会議へと発展していったのです。
当事者抜きでの国際会議
1884年から1885年にかけて開催されたベルリン会議は、アフリカの運命を決定づけた歴史的会議でしたが、そこにアフリカ人自身の代表は一人も参加していませんでした。
ビスマルクが議長を務めたこの会議では、欧州列強がアフリカ分割のルールを制定し、互いの植民地獲得を認め合うという、現地住民を完全に無視した話し合いが行われたのです。
もっとも、欧米の植民地になって嬉しいという現地住民の人はいないですし、そもそも自分の住む土地が欧米の植民地になること自体にも反対でしょうから、現地住民を完全に無視しなければできない会議ですよね。
この会議では、特に「実効支配の原則」が採択され、単に領有権を主張するだけでなく、実際に統治機構を置いた国に領有権が認められることになりました。
これにより植民地化競争は一層激しくなり、列強は内陸部へと急速に勢力を拡大していきました。
コンゴについては、ベルギー国王レオポルド2世の個人所有という異例の形態が国際的に承認され、「コンゴ自由国」として統治されることになりました。
こうした当事者不在の国際決定は、現地の民族集団や文化的境界線を無視した恣意的な国境線の設定につながり、現代アフリカの紛争の遠因となっているのです。
現代のウクライナでの戦争やパレスチナ問題でも、肝心の侵略を受けている人たちを無視したような国際合意が行われようとしているのと似ていますよね。
今に残るコンゴ紛争の遠因
現代のコンゴ民主共和国で続く紛争は、植民地時代に形成された社会構造に深く根ざしています。
レオポルド2世の統治下では、天然ゴムの採取をめぐって前例のない残虐行為が行われ、約1000万人ともいわれる犠牲者を出しました。
また統治手法として、少数派の氏族(クラン)を支配層に仕立て上げ、武器を与えて他の民族を抑圧させる「分割統治」が行われました。
この手法が民族間の亀裂と敵対感情を生み出し、独立後も続く対立の種をまきました。
1960年の独立後も、コンゴは度重なる内戦や紛争に苦しみ、特に1990年代からの「アフリカ大戦」では540万人以上が犠牲になりました。
コンゴの地下に眠るレアメタルなどの豊富な資源は、現在も約130もの武装勢力の資金源となっており、こうした「紛争鉱物」は私たちが日常使用するスマートフォンやパソコンの部品として間接的に世界経済とつながっています。
植民地時代に形成された社会構造と資源の呪いが、現代の紛争を長期化させているのです。
「なぜ?」「どうして?」と考える
小論文にかかわらず歴史では、「なぜそうなったのか?」という問いを立てることが重要です。
アフリカ分割について考える際も、単に「欧州列強が分割した」という事実だけでなく、その背景にある産業革命、ナショナリズムの高揚、社会ダーウィニズムの影響などを多角的に分析する必要があります。
例えば「なぜ19世紀後半に急速に分割が進んだのか」という問いに対しては、蒸気船の発達による内陸部へのアクセス向上、キニーネによるマラリア対策の進展、機関銃の発明による軍事的優位性など、技術的要因からも説明できます。
また「なぜ列強はコンゴに特別な関心を示したのか」という問いからは、象牙や天然ゴム、鉱物資源などの経済的価値と、コンゴ川流域の戦略的重要性が浮かび上がります。
こうした「なぜ」の連鎖を追求することで、単なる暗記から脱却し、歴史的事象の因果関係を理解する思考力が養われます。
とくに小論文や社会科の記述問題では、このような問いを軸に論理的な考察を展開することが高評価につながるでしょう。

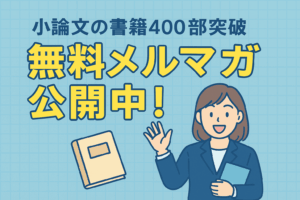


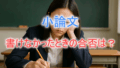
コメント