「小論文って反論入れなきゃダメですか?」という質問をよく受けます。
たしかに反論の重要性って、イマイチよく分かりませんよね。
しかし、この反論というのは、小論文ではとても重要です。
ただ、必ず反論を入れるべきということではなく、文章に応じて入れるということです。
「じゃあ、どうやって書くの?」という具体的な書き方をもとに見ていきましょう。
今回学ぶこと

小論文に反論は必要なの?

「そもそも小論文って反論を挙げる必要があるの?」と思っている人もいるでしょう。
絶対ではありませんが、説得力を必要とする小論文では挙げた方が良いです。そのメリットを小論文の基本構成などから見ていきましょう。
小論文の構成基本
まず小論文の基本構成は、序論・本論・結論ですね。
小論文の基本構成については、こちらをご覧ください。

小論文では文章を書く作業が重要だと思われがちですが、実は構成を決める作業が一番重要で、反論を入れる場合、この構成のどこに入れるかによって小論文の完成度が決まります。
反論はどこに入れる?
小論文の構成で、反論をどこに入れるのかといえば、本論に入れます。
序論
↓
本論(ココに入れる)
↓
結論
序論でいきなり入れるのは、唐突すぎて自分の主張が弱くなり、また結論に入れてしまうと取ってつけた印象となるので、本論に反論を入れて自分の主張と反対意見とのバランスを取ります。
例:SNSの実名制導入の賛否について、あなたの意見を述べなさい。
【序論】
私はSNSの実名制導入には反対である。それは適切な批判や書き込みだとしても気軽に自分の意見を表明しづらくなるからだ。
【本論】
たしかに実名制を導入すれば、デマ情報を流したり誹謗中傷をする人物が特定されることで、それらの投稿が無くなる方向に向かうかもしれない。(ココが反論)
しかし、実名であろうとデマ情報を流したり誹謗中傷を行う人物は現に存在し、その炎上から視聴数などを稼ごうとする動きには通用しない。また適切な意見表明の投稿でも、実名だと学校や職場など知られたくない人に自分の投稿を知られることで、SNSの利用を控えてしまう恐れもある。
【結論】
SNSというのは、ルールを守れば誰もが気軽に投稿できるという利点が持ち味である。根拠のないデマ情報や誹謗中傷などの投稿は表示されない、また投稿者には警告を出し、従わないまたは改善が見られない場合は、アカウントの利用停止を行い、同じSNS内では別のアカウントも作れなくなるなど対応措置をとって、匿名で誰もが気軽に投稿できるような利用を継続するべきである。
上の例の場合、賛成・反対どちらが正解ということはありませんが、本論の中に反論を入れることで文章全体のバランスが取れ、より説得力が増していきます。
反論を入れるメリット・デメリット
小論文に反論を入れるメリットは、以下の通りです。
【メリット】
・対立意見や異なる意見も踏まえているというアピールになる
・一方的な文章にならない
・文章の客観性が保証され、説得力が増す
一方、反論を入れるデメリットも少なからずあります。
【デメリット】
・文章がまわりくどくなる
・余計な文字数を割いてしまう
・反論が適切でない場合、文章全体の説得力をかえって下げてしまう
みなさんも「これはイイ商品ですよ!メリットばかりです!」と言われると怪しいと思うでしょうし、変に「これはこういう欠点があって、こっちにも欠点があって」と言われても「う~ん、買うのはやめよう」と思いますよね。
やみくもに反論を入れればよいということではなく、入れない場合も含めて「適切に反論を入れる」ということを意識しておきましょう。
小論文の反論なし場合

小論文では文章の客観性(誰が見ても、そうだよねと思える性質)を持たせるために反論を入れる重要性について見てきましたが、あえて「反論を入れない」という場合もあります。
どういうことか下で見ていきましょう。
「反論は絶対に入れる」というわけではない
先ほども言いましたが、反論というのは絶対に入れるわけではありません。
あくまで入れた方が良いというのであって、文章によっては入れてしまうとまわりくどくなったり、かえって説得力が低下してしまうこともあります。
とくに指定文字数が300~600字の間であれば、コンパクトに文章をまとめる必要があるので、あえて反論は書かない場合もあります。
強い説得力があるのならば、反論は入れなくてもよい
自分の主張の根拠をいくつか挙げて、そこに反論を入れなくても強い説得力があるのであれば反論は入れなくてもかまいません。
先ほども言ったように指定文字数が少ない場合は、とくに反論を入れないで文章をまとめることも必要になってきます。
例題
日本ではひとり親が働いている世帯の方が,ひとり親が働いていない世帯より貧困率は高くなっています。(1)なぜこの様な現象が日本で生じるのか,(2)改善のためにはどの様な施策を講ずるべきかを,資料1から資料4を参考にしながら,合わせて600字以内で述べなさい。
【解答例】
日本で、ひとり親が働いている世帯の方が、ひとり親が働いていない世帯より貧困率が高くなる要因は、まず資料1より考察すると、働くひとり親、特に母親が働いている場合、生活保護の額を下回る賃金しか得られていない場合が多く、その結果、働いていないひとり親の世帯より貧困率が高くなる傾向にある。次に資料2より、依然として男女間の賃金格差が大きいことも挙げられる。
また資料3より、格差を生み出す要因となる勤続年数についても男女間で差がある。そして資料4より、これらの問題を是正するはずの再分配効果は、OECD 21カ国中で極めて低い水準にあり、働くひとり親、特に母親のひとり親世帯が貧困に陥る要因が整っているといえる。
この現状を改善するために、残業など長時間労働の是正と同一労働・同一賃金により男女間の賃金格差是正の実施が必要である。また法律で定められた育児休業の完全実施を企業に促す。これらを積極的に進める企業に、国として公的補助や税負担の一部を免除する仕組みを作り、労働環境全体の改善を企業に促していく。さらに、税の再分配効果を上げるために、高額所得者の所得税や法人税の税率を引き上げ、低所得世帯ほど負担になる消費税を引き下げることが考えられる。その上で、貧困世帯への減免措置や児童手当の充実も図ることで、公的移転や税による再分配効果を高めていく必要がある。
(569字)
資料から読み取ったことの分析とそれを踏まえて改善策を書くもので、「でも、これはどうなんだ!」という反論は踏まえていますが、直接の反論は入れていません。
また資料分析があるので、自分の意見は実質300~400字というコンパクトさでまとめる必要があり、反論は入れていませんが説得力は確保されています。
反論の書き方

これまで反論のメリット・デメリットや反論を入れない場合について見てきました。
ここでは実際の反論の書き方、入れ方について見ていきます。
反論に使えるフレーズ
まず反論に使えるフレーズというものを確認しておきましょう。
・~と言われている(指摘がある・意見がある)しかし
・というのはもっともである~しかし
・~はもっともである~ただ
反論の入れ方
反論の入れ方は、詳しくは以下の記事で紹介していますのでご覧ください。
反論を書く注意点

上の内容でもいくつかあげましたが、反論を書く際の注意点について詳しく見ていきましょう。
やみくもに反論しない
小論文では、とにかく反論を入れればよいということではないので気をつけてください。
とくに資料分析型や課題文型などで、指定文字数が短い場合はなおさら反論を入れない方が良い場合があります。
ただし、「この問題形式だから」「指定文字数が短いから」必ず反論を入れないということではなく、何を論点にするか文章構成をどうするのかによっても決まるので、やはり練習を重ねて、反論を入れる・入れないの感覚をつかんでいきましょう。
論点が異なる反論はダメ
反論を入れて、これは一番やってはいけないケースです。
論点からズレた反論を入れてしまうと文章の軸がブレてしまい説得力を大幅に低下させるので気をつけましょう。
賛成の立場で文章を展開するとして、メディアリテラシーを学ぶという論点を設定したとします。
反論
たしかに、親の経済状況でスマホを持ってくることができない子供もいる。
インターネットやSNSの使い方も含めたメディアリテラシーを学ぶことが論点なので、親の経済状況でそもそもスマホを持つ持てないは、論点がズレています。
この場合は以下のような反論を挙げると文章の一貫性が出てきます。
反論
たしかに、わざわざ家庭から持ってこなくとも、予備も含め授業で生徒が使用する数のスマホを、あらかじめ学校で用意すればよいという意見もある。
このように、論点を設定したら同じ論点での反論を挙げて説得力を高めましょう。
乗り越えられない反論は入れない
反論は乗り越えてこそ説得力がある
出所:https://shindohaiku.com/shoronbun-hanron/
まさにその通りです。
反論に沈黙してしまう、あるいは反論を上回らない論理は説得力に欠けてしまいます。
したがって、反論は自分が対応できる範囲のものを挙げましょう。
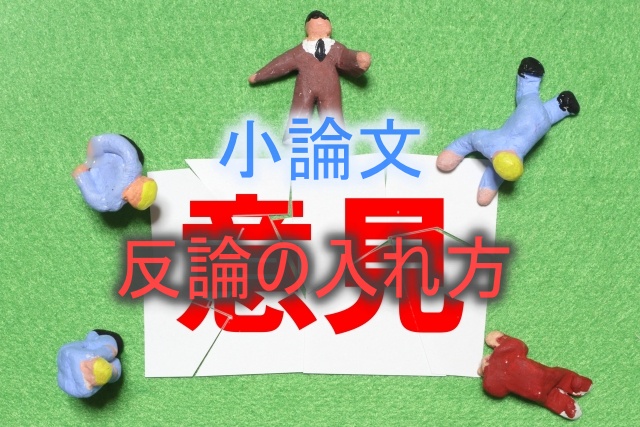
-500x336.png)

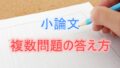

コメント