小論文のまとめ(結論)の書き方に頭を抱えていませんか?
多くの受験生が「どう締めくくればいいのか分からない」と悩んでいます。
でも大丈夫です。小論文のまとめ方には明確なコツがあり、例文を参考にすれば誰でも説得力のある結論が書けるようになります。
本記事では、高校生のための小論文の結論の書き方を、書き出しから構成まで具体的に解説します。
対象は高校生ですが、基本は変わらないので、就職試験を控える大学生や昇進試験を控える社会人の人にも充分使える内容です。
「簡潔さ」と「主張の明確さ」を意識した小論文のまとめ方を身につけて、受験を突破しましょう!
今回学ぶこと
関連記事

小論文「まとめ」の書き出し

小論文のまとめ、つまり結論の書き出しは、マニュアルにしたがって書けば難しいことはありません。以下で書き方を覚えましょう。
書き始めはどう書くか?
結論の書き始めは、まず自分の立場や主張を改めて明確に表明することが重要です。詳しくは以下をご覧ください。
書いてはいけないこと
結論に「書いてはいけないこと」は、主観的な宣言や字数稼ぎの冗長な記述です。詳しくは以下をご覧ください。
書く際のポイント
結論を書く際のポイントは、過不足なく要点をまとめ、冗長な表現を省いて50字程度で核心を伝えましょう。詳しくは以下をご覧ください。
小論文のまとめ方の例文(良い例と悪い例)

実際に小論文のまとめの良い例文と悪い例文を見てみましょう。例文のどこが良くてどこが悪いのか、見比べながら実際の書く参考にしてみてください。
良い例文
以上の理由から、高齢化社会における地域コミュニティの再構築は不可欠である。個人の努力だけでなく、行政と住民の協働によって実現する持続可能な社会こそが、私たちの目指すべき未来の姿だ。
このように、教育におけるデジタル技術の活用は、学びの多様性を広げる可能性を秘めている。しかし、その本質は人間同士の対話と探究を補完するものであり、決して置き換えるものではないと考える。
よって、環境問題の解決には、法整備や企業の取り組みだけでは不十分である。一人ひとりの生活習慣の見直しと、それを支える社会システムの構築が同時に進められてこそ、真の持続可能性が実現するのである。
悪い例文
したがって環境問題は難しい。法律や会社の取り組みもあるし、温暖化対策や持続可能な社会に向けて、私たちも何かしないといけないかもしれない。
以上、異文化理解は大事だと思う。世界は広く、また文化や習慣の違いからお互いを理解し合う気持ちと努力が必要である。
よって、先に述べた問題はとても複雑であり、解決策はあるかもしれないが、そう容易にいかないだろう。
小論文の結論の書き方(高校生レベル)

ここでは大学入試を控える高校生のレベルから結論の書き方を見ていきます。
基本は高校生レベルなのですが、就職試験の小論文を書く大学生、昇進試験を控える社会人にも充分当てはまる基本の書き方なので、ぜひ最後までご覧ください。
「まとめ」の書く考え方
結論を書く「考え方」については、以下をご覧ください。

「わかりやすく簡潔に」を心がける
小論文を書く際、つい専門用語や略語などの言い回しに頼りがちですが、本当に伝わる文章は分かりやすく簡潔に書かれています。
専門用語や複雑な構文は、内容が優れていても読み手の理解を妨げます。
大切なのは、「一文に一つの内容」が原則です。一つの文には一つの内容だけを盛り込みましょう。長文は短く区切り、接続詞を効果的に使えば論理の流れが明確になります。

また、具体例を入れることで抽象的な議論が分かりやすくなります。「環境問題」より「プラスチックごみによる海洋汚染」と書く方が読み手のイメージを喚起します。
結論を先に示し、それを支える根拠を順に説明する構成も効果的です。
自分の答案を自分が採点者のつもりで読んでみて分かりやすいか、そこから何を伝えたいのかを常に意識しながら書くことで、伝わる小論文が書けるようになるでしょう。
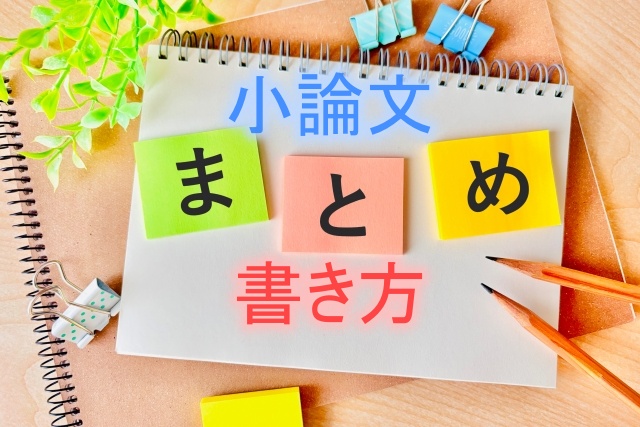
-500x336.png)



コメント