小論文と作文の違いがわからず、「どうやって小論文を書けばいいの?」と悩んでいませんか。
小論文と作文の違いは「気持ち」を書くか「意見」を書くかの違いです。
小論文の考え方や構成、ルールを理解することで、誰でも論理的で説得力のある文章が書けるようになります。
本記事では、小論文と作文の根本的な違いから、効果的な小論文の考え方、基本的な構成パターン、原稿用紙の使い方まで体系的に解説します。
ここで改めて小論文の基本について確認しておきましょう。
関連記事

小論文と作文の違い

小論文と作文は、どちらも「文章を書く」という点では同じですが、実際には全く異なる性質を持っています。この違いを理解することで、それぞれの文章に適した書き方ができるようになります。
ここでは、両者の根本的な違いについて詳しく見ていきましょう。
「気持ち」を書くか、「意見」を書くかの違い
小論文と作文の最も重要な違いは、何を表現するかにあります。
作文では自分の感情や体験を中心に「気持ち」を表現するのに対し、小論文では客観的な視点から組み立てた「意見」「考え」を述べることが求められます。
作文では「楽しかった」「悲しかった」「感動した」といった感情的な表現が重視され、読み手に共感してもらうことが目的となります。
一方、小論文では個人の感情よりも、根拠(なぜそう考えるのかの理由)に基づいた主張を展開し、読み手を説得することが目標です。
この違いを理解せずに、作文の書き方で小論文を書いてしまうと、感情的すぎる文章になってしまい、評価が下がる可能性があります。
小論文と作文の違いについては以下も参照。
根拠があって意見が成り立つ
小論文において最も重要なのは、自分の意見に説得力のある根拠を示すことです。
単に「私はこう思います」と述べるだけでは不十分で、なぜそう考えるのかを順序だてて説明する必要があります。
根拠とは、自分の意見を支える材料のことです。例えば、統計データ、専門家の見解、歴史的事実、実験結果などが挙げられます。これらの根拠を適切に組み合わせることで、読み手が納得できる説得力のある文章が完成します。
作文では個人の体験や感想が中心となるため、客観的な根拠はそれほど重視されません。
しかし小論文では、主観的な感想だけでなく、誰もが認める客観的な事実に基づいて議論を進めることが不可欠です。
このような論理的な構成こそが、小論文の特徴と言えるでしょう。
事実と感情を分ける
小論文を書く際には、客観的な事実と主観的な感情を明確に区別することが重要です。
事実とは、統計データ、研究結果、専門家の意見、新聞や学術書からの引用など、誰が見ても同じ内容として認識できる客観的な情報を指します。
感情は個人の内面的な反応であり、人によって異なるものです。
「嬉しい」「悲しい」「興味深い」といった表現は感情に該当します。
小論文では、まず客観的な事実を提示し、その後に自分の分析や意見を述べるという順序が基本となります。
この書き方は、問題の聞き方や書く型によって結論から述べる場合もあります。
ただ事実と意見、感情の区別ができていないと説得力のない文章になってしまうことは、いずれの書き方でも共通します。
例えば「環境問題は深刻だと感じます」ではなく、「CO2排出量が過去10年間で20%増加しており、環境問題は深刻化している」と事実を示してから自分の見解を述べることで、より説得力のある小論文が書けるのです。
ここまで小論文について説教臭く説明してきましたが、小論文は作文と違って文才が必要ないので、適切な方法で練習することで高校生以上の人であれば誰でも書けるようになるので安心してください。
小論文の考え方

小論文を効果的に書くためには、正しい思考プロセスを身につけることが不可欠です。
感情に任せて書き始めるのではなく、戦略的にアプローチすることで説得力のある文章を構築できます。ここでは、小論文を書く上で重要な思考の流れを解説します。
まず結論から考える
小論文を書く際は、最初に結論を決めることが成功の鍵となります。多くの人は問題文を読んで思いつくままに書き始めますが、これでは論理的な一貫性を保つことが困難になってしまいます。
結論を先に設定することで、文章全体の方向性が定まり、ブレのない主張を展開できるようになります。
例えば「私は環境保護のために個人の行動変容が最も重要だと考える」という結論を決めれば、この主張を支える根拠や具体例を集めて組み立てればよいのです。
制限時間が限られた試験においては、効率的な文章作成が求められます。結論から逆算して論理を組み立てることで、迷うことなくスムーズに執筆を進めることができ、説得力のある文章に仕上がります。
結論の考え方は以下を参照。

結論を補強する理由や事実を挙げる
結論が決まったら、次にその主張を支える根拠を集める作業に取り組みます。説得力のある小論文には、客観的で信頼性の高い情報が不可欠だからです。
根拠として活用できるのは、統計データ、学術研究の結果、専門家の見解、歴史的事例などです。
例えば環境問題について論じる場合、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書によると」といった具体的な情報源を示すことで、主張の信頼性が大幅に向上します。
また、身近な事例や社会現象も有効な根拠となり得ます。
ただし、個人的な体験談だけでは説得力に欠けるため、必ず客観的なデータや事実と組み合わせて使用することが重要です。
根拠の質と量が、小論文の評価を左右する重要な要素となるのです。
試験本番では調べる時間はないので、練習のときから自分の考えの根拠となる事実やデータの収集が重要となってきます。
予想される反論を考える
優れた小論文を書くためには、自分の主張に対する反論を予想し、それに対する反駁を用意しておくことが重要です。
これにより、論証の穴を埋め、より説得力の高い文章を作ることができます。
反論を考える際は、「しかし」「一方で」「確かに〜だが」といった表現を使って、異なる視点からの意見を紹介します。
例えば「確かに個人の努力だけでは限界があるという指摘もある」と認めた上で、「しかし、個人の意識変化が社会全体の変革につながる」と再反論することで、議論に深みが生まれます。
反論を想定することは、自分の主張を客観視する機会にもなります。一方的な主張よりも、多角的な視点を示した文章の方が、読み手にとって説得力があり、高い評価を得やすくなるでしょう。
自分が知っている事実や経験を考えてみる
小論文のテーマが与えられたら、そのテーマに関連する自分の知識や経験を整理することから始めましょう。この作業により、論文の材料となる情報を効率的に収集できます。
社会問題であれば、ニュースで見聞きした情報、学校で学んだ内容、読書で得た知識などを思い出してみます。
また、自分自身や周囲の人々の体験談も、適切に使えば有効な材料となるでしょう。
ただし、個人的な経験だけに頼らず、必ず客観的な事実と組み合わせることが大切です。
この段階では、関連する情報をできるだけ多く洗い出すことがポイントです。後で選別すればよいので、まずは幅広く材料を集めることに集中しましょう。
豊富な材料があることで、説得力のある論理構成を組み立てやすくなります。
小論文の構成

小論文は決まった構成パターンに従って書くことで、読み手にとって分かりやすく説得力のある文章になります。
構成を理解し適切に活用することは、小論文成功の基盤となる重要なスキルです。基本的な構成要素と実践的な書き方を身につけましょう。
序論・本論・結論
小論文は「序論・本論・結論」の3部構成で書くのが基本です。作文でよく使われる起承転結とは異なり、より論理的で明確な構成となっています。
序論では問題提起や自分の主張を明確に示します。「私は○○だと考える」「○○という問題がある」といった形で、文章全体の方向性を読み手に伝えるのが目的です。
本論では序論で示した主張を支える具体例、根拠、データなどを詳しく展開し、論理的な裏付けを提供します。
結論では序論で述べた主張を再確認し、文章全体をまとめます。新しい論点を持ち出すのではなく、本論で展開した内容を踏まえて、最終的な見解を明確に示すことが重要です。
この3段階の流れを意識することで、筋の通った分かりやすい小論文が書けるようになります。
結論から主張 → 理由 → 具体例を考える
効果的な小論文を書くためには、まず結論となる自分の主張を決めてから、それを支える理由と具体例を逆算して考える方法が有効です。この手順により、論理的な一貫性を保った文章を構築できます。
最初に「私は○○だと考える」という明確な結論を設定し、次に「なぜそう考えるのか」という理由を複数挙げます。
理由が決まったら、それぞれを裏付ける具体例やデータを選定していきます。
例えば「個人の環境意識向上が重要だ」という結論なら、「教育効果が高い」「継続的な変化をもたらす」といった理由を考え、それぞれに統計データや事例を組み合わせます。
この逆算思考により、文章の途中で論点がぶれることなく、首尾一貫した説得力のある小論文を作成できます。制限時間内での効率的な執筆にも大きく役立つでしょう。
書く基本構成
小論文には複数の基本的な構成パターンがあり、問題の内容や求められる解答形式に応じて使い分けることが重要です。代表的なパターンを理解し、状況に応じて選択できるようになりましょう。
「結論先行型」は序論で自分の主張を明示し、本論でその根拠を展開、結論で再度主張をまとめる構成です。自分の立場がはっきりしている場合に適しています。
「問題提起型」は序論で社会問題や課題を提示し、本論で分析・検討を行い、結論で自分の見解を示す構成で、複雑な問題について考察する際に効果的です。
また、反対意見に配慮した「両論併記型」では、異なる立場を紹介してから自分の主張を展開することで、より説得力を高められます。
どの構成を選ぶかは問題文の指示や字数制限を考慮して決めましょう。基本パターンを身につけることで、どのような課題にも対応できる柔軟性が身につきます。
小論文のルール

小論文を書く際には、採点者に好印象を与え、減点を避けるための基本的なルールがあります。
言葉遣いや表記方法、受験での注意点を正しく理解することで、内容面だけでなく形式面でも評価される小論文が書けるようになります。
小論文のルール
小論文では「だ・である」調で統一し、主語が一人称の場合は性別に関係なく「私」を使用します。
意見を述べる際は「~と思う」のような曖昧な表現ではなく、「~と考える」「~である」と言い切ることが重要です。人物名は敬称略で構いません。
書き言葉を徹底し、話し言葉は避けましょう。「なので」は「したがって」、「あと」は「また」、「私的には」は「私は」のように言い換えます。
「い抜き言葉」「ら抜き言葉」も不適切で、「してる」は「している」、「食べれる」は「食べられる」と正しく表記する必要があります。
省略語やカタカナ語の多用も控えます。「ネット」は「インターネット」、「バイト」は「アルバイト」と正式名称で書きますが、「コンビニ」のように広く一般的に知られている場合は使用可能です。
原稿用紙の使い方
原稿用紙の向きは、横に長い長方形なら縦書き、縦に長い長方形なら横書きです。
本文は1マス空けて書き始め、段落を変える際も同様に1マス空けます。句読点や記号は1マスとして数え、行頭には置けません。
数字の表記は書字方向によって異なり、縦書きでは漢数字(一、二)、横書きでは算用数字(1、2)を使用します。
横書きの場合、数字は1マスに2字まで書くことができます。促音「っ」や拗音「ゃ、ゅ、ょ」は1マスに1文字で書きます。
行頭に句読点や閉じかっこを置くことは減点対象となるため、前行末に入れるか、閉じかっこと句点を同じマスに書く工夫が必要です。
これらの基本ルールを守ることで、採点者から形式面でも高い評価を得られます。
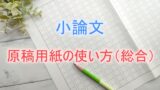
本記事で説明してきたことは「小論文の基本中の基本」なので、書く練習で自分の中に染み込ませて合格できる小論文を書いていきましょう。
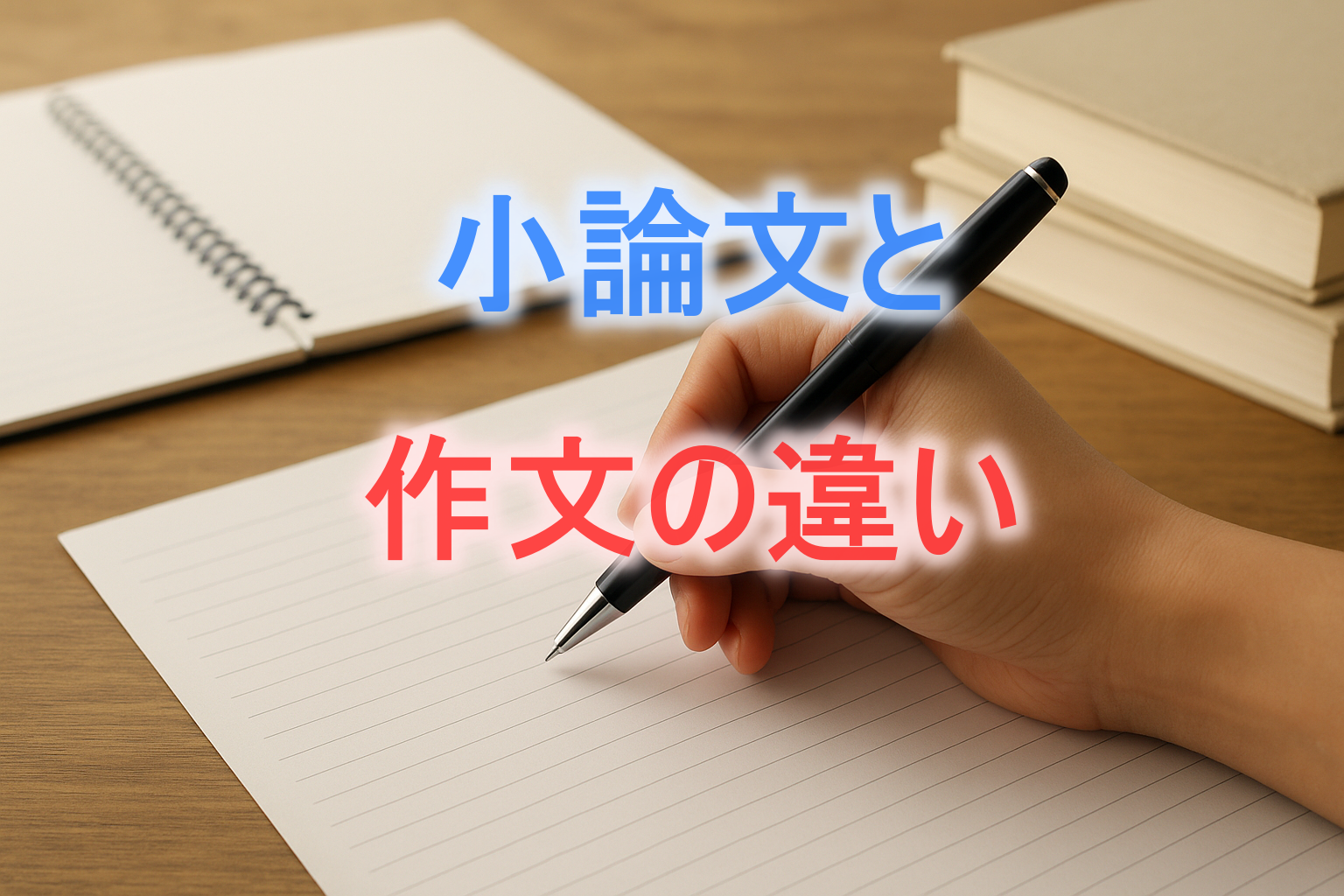
-500x336.png)

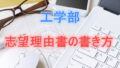

コメント