「総合型選抜の小論文対策って何から始めればいいの?」「書き方がわからなくて不安」そんな悩みを抱えていませんか?
実は、総合型選抜の小論文には明確な書き方のコツと対策方法があり、適切な準備期間を確保すれば必ず合格レベルに到達できます。
本記事では、総合型選抜小論文の書き方から効果的な対策をいつから始めるべきか、さらに実際の例文を使った具体的な練習方法まで、あなたが「書けない」から「書ける」に変わる小論文の攻略法を詳しく解説しています。
関連記事
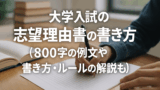
総合型選抜での小論文の書き方

総合型選抜では小論文が重要な評価要素となります。採点者の視点を理解し、適切な知識を身につけ、継続的な練習を積むことが合格への近道です。
また、近年のトレンドテーマを把握しておくことで、本番での対応力も向上するでしょう。
総合選抜型の小論文とは
総合型選抜の小論文は、受験生の論理的思考力と表現力を測る重要な試験です。
作文が感情や体験を中心に書くものに対し、小論文は明確な立場を示し、根拠を挙げて論理的に主張を展開する文章です。
大学が小論文試験を課す理由は、入学後に必要な学術的な文章作成能力を事前に確認するためです。
大学では研究論文やレポート作成が日常的に求められ、これらに必要な基礎的な論理構成力を小論文で判断しています。
また、社会問題に対する関心度や知識の深さ、多角的な思考ができるかも評価されます。
総合型選抜では特に、受験生の人物像や将来への意欲を総合的に判断したいため、小論文を通じて思考プロセスや価値観を見極めようとします。そのため単なる知識の暗記ではなく、自分なりの見解を論理的に表現する能力が重要視されるのです。
小論文の基本
総合型選抜での小論文の書く練習をする前に、今いちど小論文の基本について以下でおさらいをしておきましょう。



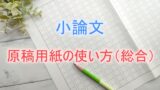
採点者を意識する
小論文では採点者との明確なコミュニケーションを意識することが不可欠です。採点者は論理的構成力、問題に対する適切な応答、文章表現力の3つの観点から評価を行っています。
まず論理的構成力では、主張と根拠の関係が明確で、話の筋道が通っているかを確認されます。
次に問題に対する適切な応答では、設問の意図を正しく理解し、求められている内容に的確に答えているかが重要です。
単に自分の意見を述べるだけでなく、問われていることに対してピンポイントで解答する姿勢が求められます。
文章表現力については、読み手にとって分かりやすい文章構成になっているか、適切な語彙選択ができているかが評価されます。
採点者は限られた時間で多くの答案を読むため、簡潔で明瞭な表現を心がけることが高評価につながります。採点者に「この受験生は論理的思考ができ、分かりやすい文章が書ける」と印象づけることが合格への鍵となるでしょう。
私が総合選抜型の小論文の採点者でも、答案が何を言いたいのかがよくわかり、その理由付けもきちんとしているものは自然と合格点を与えたくなりますね。
反対に答案が何を言いたいのかよく分からず、その理由も曖昧なものは「ちょっと合格点は与えられないよ」となります。
したがって小論文を書くときは、採点者つまり読む人を意識して書くようにしましょう。
知識を仕入れる
小論文で説得力のある文章を書くには、幅広い社会問題への知識が欠かせません。日々のニュースや新聞記事を通じて、現代社会の課題や議論されている論点を把握することが重要です。
効果的な知識収集方法として、新聞の社説やコラム欄を定期的に読み、重要な記事は切り抜いてノートにまとめることをお勧めします。
その際、記事の内容だけでなく、自分なりの意見や疑問点も200文字程度で併記しておくと、後の小論文作成時に活用できます。
また、書籍やオンラインの信頼できる情報源からも、深い洞察を得ることができるでしょう。
知識収集では量より質を重視し、一つのテーマについて複数の視点から情報を集めることが大切です。
賛成・反対両方の立場からの意見を理解しておくことで、小論文でも多角的な議論が展開できます。志望する学部や学科に関連する専門知識も併せて習得しておくと、より深みのある論述が可能になります。
練習をする
小論文は繰り返し書くことで確実に上達する分野です。まずは基本的な型を身につけ、段階的にレベルアップを図ることが重要です。
初期段階では、新聞のコラムや社説を要約する練習から始めましょう。
300文字程度で記事の要旨をまとめ、続いて200文字程度で自分の意見を書く練習を重ねます。この作業により、文章構成力と論理的思考力を同時に鍛えることができます。
慣れてきたら、実際の過去問題を使って本格的な小論文を作成し、学校の先生や塾講師に添削を依頼しましょう。
効果的な練習方法として、問題分析から始める手法があります。
設問文を精読し、何を求められているかを明確にしてから執筆に取りかかることで、的確な回答ができるようになります。
また、優秀な小論文の模範解答を読み、構成や表現技法を学ぶことも上達への近道です。
トレンドのお題
近年の小論文では社会の変化を反映したトレンドテーマが頻出しており、これらへの対策が合格の鍵となります。
トレンドのお題
特に注目すべきは社会の「分断」問題で、格差拡大や世代間対立、価値観の多様化による社会の分裂状況について問われることが増えています。
「人権」については、多様性の尊重やマイノリティへの配慮、ジェンダー平等などが重要なテーマとなっています。
「持続可能性」では、環境問題だけでなく経済発展との両立や将来世代への責任が議論の中心です。
「Z世代」に関しては、デジタルネイティブ世代の特徴や価値観、社会参加のあり方が注目されています。
気候変動による「猛暑」は環境問題の具体例として出題され、適応策や緩和策について論じる機会が多くなっています。
地域経済では「老舗」の伝統継承と「新店舗」の革新性を対比させながら、地域活性化や経済発展について考察する問題が見られます。
これらのテーマについて日頃から情報収集し、多角的な視点から自分なりの見解を形成しておくことが重要です。
総合型選抜の小論文対策は、いつから?

総合型選抜の小論文対策は、いつから始めればいいの?と疑問に思っている人も多いでしょう。そこで総合型選抜の対策は、いつから始めればよいのかについて見ていきます。
早めに行う
高校1年生から小論文対策を始めることが最も理想的な選択といえます。
早期開始により学習時間に余裕が生まれ、基礎から応用まで段階的にスキルを積み上げることができるためです。
早期対策の最大のメリットは、評定平均の安定的な維持が可能になることです。
また小論文の学習を通じて論理的思考力や表現力が向上し、他教科のレポート作成や定期テストの記述問題でも高得点を獲得しやすくなります。
また、社会問題への関心が高まることで、現代社会や政治経済などの成績向上も期待できるでしょう。
さらに志望校変更が必要になった場合でも、早期から培った小論文スキルは他大学の入試でも活用できます。
幅広いテーマに対応できる基礎力があれば、短期間での軌道修正も可能です。
継続的な学習により自分の興味関心が明確化し、真に学びたい分野や将来の目標も見えてくるため、早期開始は合格への確実な道筋となります。
遅くとも高校3年に入った時点で始める
高校3年生になった時点で小論文対策を開始することは、総合型選抜成功の最低限のラインといえます。この時期から始めれば、受験までに約1年間の準備期間を確保でき、基礎から実践まで体系的に学習することが可能です。
3年生からの対策では、まず基本的な小論文の型を習得し、並行して時事問題の知識収集を行います。
春から夏にかけて基礎固めを行い、秋以降は志望校の過去問題を中心とした実践練習に移行するのが効果的なスケジュールです。
この期間があれば、添削を受けながら文章力を向上させ、苦手分野の克服も十分に可能でしょう。
ただし3年生からのスタートでは時間的制約があるため、効率的な学習計画が不可欠です。
毎日の新聞読解と週2〜3回の小論文執筆を継続し、月1回程度は模擬試験形式での練習を行うことが重要となります。
遅いスタートでも計画的に取り組めば、十分に合格レベルに到達することができます。
最低でも総合型選抜を受けることが決まった時点で始める
総合型選抜の受験を決めた時点で、直ちに小論文対策を開始することが絶対に必要です。「1〜2週間で小論文は書けるようになる」という情報を信じてはいけません。
実際には基礎的な文章構成力を身につけるには、それなりの時間と練習が必要です。私は小論文の指導では最低3か月という時間が必要だとみています。
総合型選抜試験の小論文は、一般入試の小論文よりもレベルが一段高いために本来なら最低でも半年くらいの時間は確保したいところです。
それに短期間の対策では、小論文の型を暗記することはできても、説得力のある内容を書く力は養えません。
社会問題に対する深い理解や多角的な視点は、継続的な学習によってのみ身につくものです。
また、自分の考えを論理的に整理し、限られた文字数で的確に表現するスキルは、繰り返し練習することで向上します。
直前期で時間がない場合でも最低3〜4か月の準備期間は確保したいところです。
この期間があれば、基本的な書き方を習得し、頻出テーマの知識を蓄積し、実際の過去問題で実践練習を積むことができます。
短期間での対策は合格の可能性を大幅に下げるリスクがあるため、受験を決めたその日から本格的な学習を開始することが成功への鍵となるでしょう。
総合型選抜の小論文の解答例文

効果的な小論文対策には、過去問の入手と出題傾向の分析、そして実際の例題を通じた実践練習が欠かせません。
志望校の特色を理解し、具体的な解答例を参考にすることで合格レベルの文章力を身につけられます。
まず過去問を入手しよう
志望校の過去問入手は小論文対策の最重要ステップです。
過去問の入手方法
- 大学のホームページを見る
- 進路指導室で探す
- 大学の入試課に問い合わせる
まずは大学の公式ホームページを確認し、入試情報のページで過去問題が公開されているかを調べましょう。多くの大学では過去3年分程度の問題を掲載しています。
ホームページで見つからない場合は、学校の進路指導教員に相談することをお勧めします。進路指導室には各大学から送られてきた過去問資料や入試要項が保管されていることが多く、すぐに入手できる可能性があります。
また、先輩の受験体験談や対策資料も併せて確認できるでしょう。
それでも入手困難な場合は、大学の入試課に直接問い合わせてみてください。電話やメールで丁寧に依頼すれば、過去問題や出題傾向に関する情報を提供してもらえることがあります。
一部の大学では、オープンキャンパスや進学説明会で配布することもあるため、これらのイベントにも積極的に参加しましょう。あくまで総合型選抜の小論文の過去問なので、一般入試の小論文の過去問と間違えないようにしましょう。
このように、過去問入手は合格への第一歩となる重要な作業です。
出題の傾向をつかむ
過去問分析では最低でも3年分のデータを収集し、出題パターンの変化や一貫性を把握することが重要です。単年度だけでは偶発的な要素が強く、真の傾向を見極めることができないためです。
分析時は出題形式、文字数制限、テーマ分野の3つの観点から傾向を整理しましょう。
出題形式では、設問型、テーマ型、課題文型、資料分析型のどれが多いかを確認します。
文字数制限は400字、600字、800字など大学ごとに特徴があり、制限時間との関係も重要な分析要素です。
テーマ分野については、教育問題、社会問題、環境問題、医療・福祉など、各学部の専門性に関連した傾向が見られることが多いでしょう。
また、設問の問い方にも注目してください。「あなたの考えを述べなさい」「メリット・デメリットを踏まえて論じなさい」「解決策を提案しなさい」など、求められる論述スタイルも大学によって異なります。
これらの傾向を把握することで、効率的な対策が可能になり、本番での対応力も大幅に向上するはずです。
例題と解答例
実際に総合型選抜の小論文で出題された問題から解答例を見ていきましょう。以下、実際に書く練習の参考にしてみてください。
例題1:あなたは富山県の地域医療にどのように関わりたいか、その目標を簡潔に述べたう上で、その目標に近づくために、あなたが受けたいと思う教育の理想像について、合計400字以内で述べよ。(富山大学 医学部医学科 設問2 2024年 総合型選抜、学校推薦型選抜)
【解答例】
私は富山県の中山間地域で総合診療医として働き、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる医療体制の構築に貢献したいと考えている。過疎化が進む地域では医師不足が深刻で、一人の医師が幅広い疾患に対応する能力が求められるからだ。
この目標を達成するため、私が受けたいと思う教育の理想像は三つの要素から成る。第一に、内科、外科、小児科、精神科など各分野の基礎知識を幅広く学べるカリキュラムだ。専門性を深めることも重要だが、地域医療では総合的な診断能力がより重要になってくる。第二に、実際の地域医療現場での長期実習である。教科書では学べない住民との信頼関係構築や、限られた医療資源の中での工夫を体験したいと考えている。第三に、予防医学や健康増進活動について学ぶ機会だ。治療だけでなく、地域住民の健康維持・向上に積極的に取り組める知識と技術を身につけたいと考えている。(376字)
【解答例】
母語で教育を受けることは、学習効果や文化的アイデンティティの形成において重要な意義を持つ一方で、グローバル社会における競争力の観点から課題も存在する。これらのメリット・デメリットを踏まえ、私は基礎教育段階では母語教育を重視し、段階的に多言語教育を導入するバランス型アプローチが最適だと考える。
母語教育の最大のメリットは、深い理解に基づく質の高い学習が可能になることである。子どもは母語で思考するため、複雑な概念も直感的に理解でき、創造的思考や批判的思考の発達が促進される。例えば、数学の論理的思考や国語の文学的感性は、母語という土台があってこそ十分に育まれる。また、母語教育は文化的アイデンティティの継承という重要な役割も果たす。言語は単なるコミュニケーション手段ではなく、その民族固有の価値観や世界観を内包しており、これらを次世代に伝える媒体として機能している。
しかし、母語以外の言語でしか教育を受けられない環境にも利点がある。早期から国際的な言語に触れることで、グローバル社会で活躍するための語学力と国際感覚が自然に身につく。特に英語などの国際共通語で教育を受けた場合、将来的な進学や就職の選択肢が大幅に広がる可能性がある。一方でデメリットも深刻である。非母語での学習は理解度の低下を招きやすく、特に抽象的概念の習得に支障をきたす恐れがある。また、母語の発達が不十分になることで、深い思考力や表現力の育成が阻害される可能性もある。
これらを総合的に考慮すると、初等教育段階では母語を中心とした教育により思考の基盤を固め、中等教育以降で段階的に多言語教育を拡充していく方法が理想的である。この取り組みにより、深い思考力と国際的な視野の両方を兼ね備えた人材を育成できると考える。(738字)
解説(AIによる評価)
評価:優秀(A評価相当)
優れている点:
- 明確な目標設定:「中山間地域での総合診療医」という具体的で現実的な目標を提示
- 地域課題の理解:過疎化と医師不足という富山県の実情を的確に把握
- 論理的構成:目標→理由→教育像の流れが明確で読みやすい
- 具体性のある教育像:3つの要素を具体的に提示し、それぞれの必要性を説明
- 字数配分:376字で適切にまとめており、簡潔性と充実度のバランスが良い
特に評価できる点:
- 「住民との信頼関係構築」「限られた医療資源での工夫」など、地域医療の本質を理解している
- 治療だけでなく予防医学にも言及し、包括的な視点を示している
改善の余地:
- より個人的な体験や動機があると説得力が増す
- 富山大学の教育プログラムとの関連性を示せるとさらに良い
評価:良好(B+評価相当)
優れている点:
- バランスの取れた分析:メリット・デメリットを公平に検討
- 明確な結論:段階的アプローチという建設的な提案を提示
- 具体例の活用:数学や国語の例で理解を促進
- 文章構成:序論・本論・結論の構造が整っている
- 字数管理:738字で適切に論述
優れた論点:
- 言語と文化的アイデンティティの関係性への深い理解
- 教育段階に応じた段階的アプローチの提案
- グローバル化と母語教育の両立という現代的課題への取り組み
改善点:
- 具体的事例の不足:実際の国や地域の事例があるとより説得力が増す
- 個人的見解の薄さ:一般論に留まり、筆者独自の体験や価値観が見えにくい
- 対立軸の設定:メリット・デメリットの対比がやや表面的
【総評】
両解答例とも、設問の要求を適切に満たし、論理的に構成された優良な解答です。例題1は医学部志望者として必要な地域医療への理解と具体的なビジョンを示しており、例題2は複雑な言語教育問題を多角的に分析しています。
大学入試の小論文において重要な「問題意識 → 分析 → 提案」の流れを両者とも踏襲しており、採点者に好印象を与える解答といえるでしょう。
上記はAIの評価ですが、練習で書いたら学校の先生など必ず信頼できる大人の添削を受けましょう。
総合型選抜の小論文の練習でも、最も重要なことは書いたら添削を受けるを繰り返して内容をブラッシュアップしていくことです。
この作業が、たとえ短期間の対策だとしても合格への可能性を高めます。
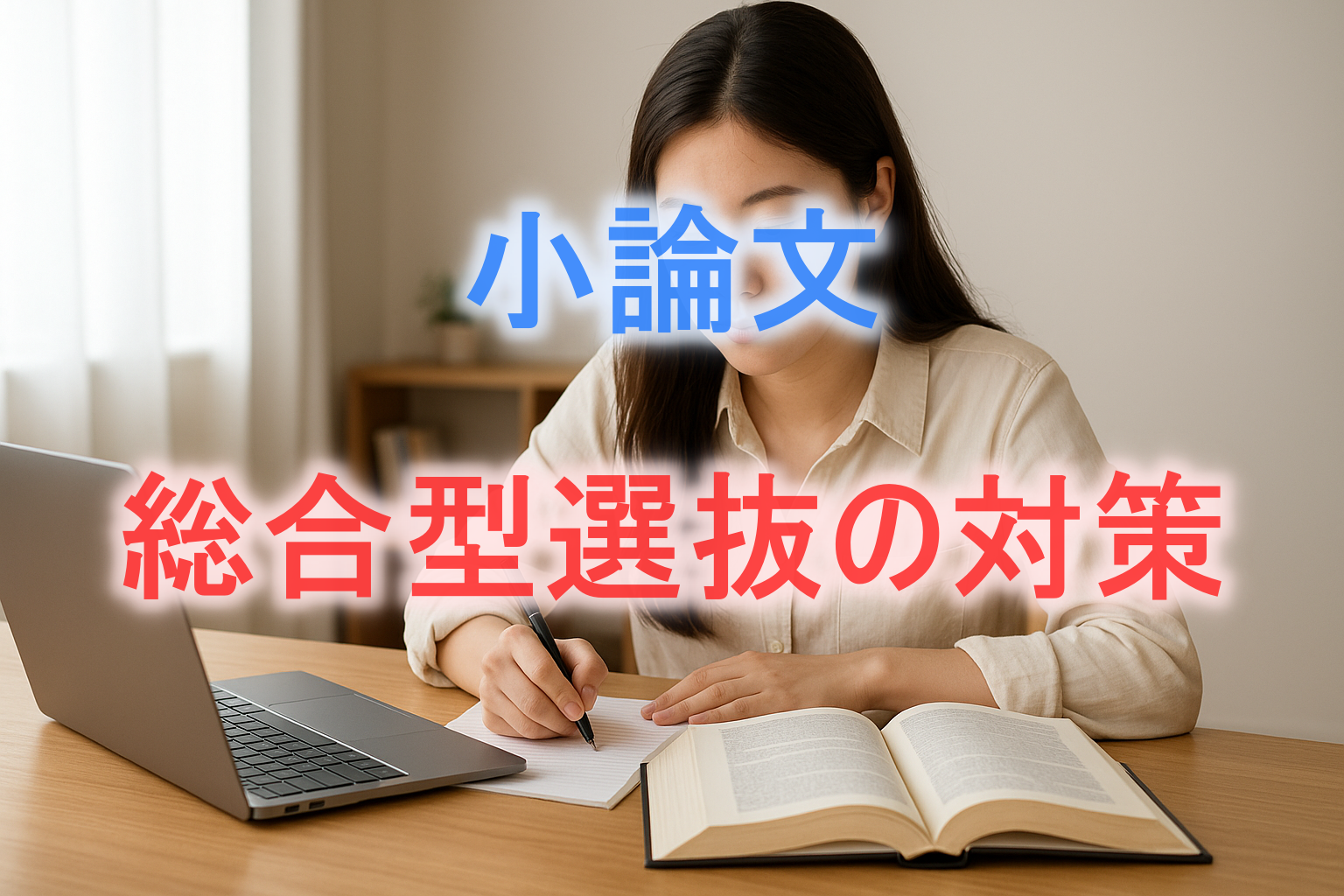
-500x336.png)

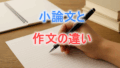
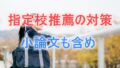
コメント