「資料型の小論文の書き方が分からない」「グラフや表をどう読み取ればいいか不安」そんな悩みを抱えていませんか?
資料型の小論文には明確な攻略法があり、資料を正確に読み取る手順を身につければ、説得力のある答案が書けるようになります。
重要なのは資料のテーマや種類を見極め、傾向と特徴から出題者の意図を汲み取ることで、それを論理的に展開する力が合格への鍵となります。
本記事では、資料型の小論文の基本から資料を読み解く4つのステップ、そして実際の例題と解答例まで、資料型小論文で高評価を得るための方法を詳しく解説しています。
関連記事
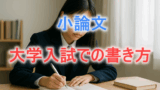
小論文の基本おさらい

設問型の小論文を書く前に、まずは小論文の基本を確認しておきましょう。
小論文と作文の違い、基本構成、そして論理的に書くためのポイントを理解することで、どんな形式の問題にも対応できる土台が築けます。
小論文の基本
まず小論文は、作文とは異なります。以下で小論文の基本について改めて確認しておきましょう。

書くルール
小論文の内容は良くても、書くルールを踏まえていないと減点され、最悪0点ということもあるので、以下で書くルールを確認しておきましょう。

原稿用紙の使い方
形式的なことですが、原稿用紙の使い方も小論文では採点対象になります。以下で原稿用紙の使い方についても改めて確認しておきましょう。
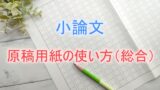
資料型の小論文の書き方

資料型の小論文を攻略するには、資料を正確に読み取り、そこから意図を汲み取る力が必要です。
ここでは、資料を読み解く基本的な手順を4つのステップで解説します。
① 資料の種類を見る
まず確認したいのが、資料がどの形式で提示されているかという点です。
棒グラフは複数の項目を比較する際に用いられ、円グラフは全体に対する各要素の割合を示します。
折れ線グラフは時間経過による変化を表し、表形式の数値統計は複数のデータを整理して見せる役割があります。
それぞれの資料形式には明確な目的があり、出題者はその特性を活かして情報を伝えようとしています。
資料の種類を見極めることで、「何を読み取るべきか」の方向性が見えてくるでしょう。
グラフの形式を理解すれば、データの読み取りがスムーズに進みます。
表:数値などを整理して、一目で分かるように表したもの
棒グラフ:項目ごとに数値を比較する
円グラフ:全体を100%としたときの各要素の割合
折れ線グラフ:時間経過による数値の変化
数値統計:複数のデータを数値で整理して見せる

② 資料が何を表しているのか読み取る
次に、提示された資料が何について説明しているのかを把握することです。
資料には必ず出題者が伝えたいメッセージが込められており、それを見逃すと的外れな解答になってしまいます。
焦って細かい数値に目を向ける前に、まず資料全体が扱っているテーマを確認しましょう。
たとえば「若者の投票率」なのか「地域別の人口推移」なのかによって、注目すべきポイントは大きく変わります。
まずこれを見誤ってしまうと見当違いの解答を書いてしまうことになるので、気を付けましょう。
資料のテーマを正しく理解することが、その後の分析や論述の土台となります。
③ 資料のタイトル、凡例、単位を見る
資料を正確に理解するために欠かせないのが、タイトル・凡例・単位の3点です。
タイトルからは資料全体のテーマが分かり、凡例(はんれい)はそのグラフや数値が何を意味するのかを説明しています。

また、単位を見落とすと数値の大きさを誤解する恐れがあります。たとえば「万人」なのか「人」なのか、「%」なのか「ポイント」なのかで解釈は大きく変わるでしょう。
試験本番では緊張から思い込みで読んでしまうことがあるため、必ずこれらの情報を丁寧に確認する習慣をつけてください。
正確な読み取りが、説得力のある小論文につながります。
これを焦らないように行うためには普段の練習が欠かせないので、過去問などから資料を読み取る練習を繰り返し行いましょう。
> 小論文・完全ロードマップ解説の《無料メルマガ登録はコチラ》から
④ 傾向と特徴を見て、資料から何が言えるか
資料には必ず出題者が気づいてほしいポイントが隠されています。全体の傾向としては増加傾向なのか減少傾向なのか、横ばいなのかをまず把握しましょう。
その上で、極端に高い数値や低い数値、急激な変化など特徴的な部分に着目します。
こうした例外的な箇所こそが、資料が伝えたいメッセージの核心です。
たとえば「全体は増加しているのに特定の年代だけ減少している」といった発見ができれば、それが論述の材料になります。
資料から読み取った傾向や特徴を、下のように資料に直接簡単にでもメモをしておくと、後の論述がスムーズに進むでしょう。


ちなみに、上の2つの資料からはアフリカ地域の「栄養不足人口の割合」の高さや内戦・紛争の多さ、また他地域に比べて人口増加率が高いことが分かります。
このように問題に複数の資料がある場合は、「これらの資料から2つの資料を選んで答えなさい」などの但し書きがない限り、問題で提示されたすべての資料を踏まえて答える必要があります。
あとは小論文の基本おさらいをもとに、以下のようにアウトラインを書いてから解答を書きましょう。
例題と解答例

実際の問題を通して、資料型小論文の書き方を具体的に学んでいきましょう。ここでは2つの例題を用意し、それぞれの解答例を示します。
例題1
【問題】 以下の資料は、2020年から2024年における日本の年代別スマートフォン平均利用時間(1日あたり)を示したものである。この資料から読み取れることを述べた上で、若年層の利用時間が長い理由とその影響について、あなたの考えを800字以内で述べなさい。

(解答例)
資料から、年代が若いほどスマートフォンの利用時間が長く、10代が最も多い240分、60代以上が最も少ない60分と、年齢による明確な差が見られる。特に10代と20代は1日3時間以上利用しており、30代以降と比較して大きな開きがあることが分かる。若年層の利用時間が長い理由として、第一にSNSやゲームなど若者向けコンテンツの充実が挙げられる。動画配信サービスやメッセージアプリは若年層の生活に深く浸透しており、友人との交流や情報収集の主要な手段となっている。第二に、デジタルネイティブ世代である若者は幼少期からスマートフォンに親しんでおり、操作に抵抗感がない。一方、高齢層は従来の電話や対面でのコミュニケーションを好む傾向があり、利用時間が短くなっていると考えられる。
しかし、若年層の長時間利用には懸念すべき影響もある。まず健康面では、長時間の画面注視による視力低下や睡眠不足が問題となる。夜遅くまでスマートフォンを使用することで生活リズムが乱れ、学業や日常生活に支障をきたす恐れがある。また、対面でのコミュニケーション能力の低下も指摘されている。画面越しのやり取りに慣れすぎると、実際の会話で相手の表情を読み取ったり、適切に意思を伝えたりする力が育ちにくくなる可能性がある。
一方で、スマートフォンは学習ツールとしても有効である。オンライン講座や学習アプリを活用すれば、効率的に知識を習得できる。また、世界中の情報に瞬時にアクセスできることは、視野を広げる上で大きな利点だ。
重要なのは、スマートフォンを適切に活用することである。若年層が利用時間を自己管理し、健康や人間関係に悪影響が出ないように注意できる環境が不可欠だ。学校では、デジタル機器との健全な付き合い方を教育し各家庭で実践できるプログラムが必要である。スマートフォンの利便性を享受しながら、バランスの取れた生活を送ることが求められる。(789字)
↓ ↓ ↓ 小論文試験に必須の一冊 ↓ ↓ ↓
小論文の基本から、試験を想定した
実践練習まで、この一冊で身に付きます!
この一冊で小論文のお悩みすべて解決!
\ Amazonで400冊突破!/
例題2
【問題】 以下の資料は、それぞれ2024年における都道府県別の公共図書館数と、2015年から2024年までの日本全国における年間平均読書冊数の推移を示したものである。この2つの資料から読み取れることを述べた上で、読書習慣を促進するために必要な取り組みについて、あなたの考えを800字以内で述べなさい。


(解答例)
資料1から、公共図書館数は東京都が450館と最も多く、大阪府380館、愛知県320館と続き、人口の多い都市部に図書館が集中していることが分かる。一方、資料2からは、年間平均読書冊数が2015年の12.3冊から2024年には8.5冊へと約3割減少し、右肩下がりの傾向が見られる。この2つの資料を比較すると、図書館という読書環境が整備されているにもかかわらず、読書冊数は減少し続けているという矛盾が浮かび上がる。つまり、図書館の数を増やすだけでは読書習慣の促進には不十分であり、別の要因が影響している。
読書冊数減少の背景には、スマートフォンやSNSの普及がある。現代人は空き時間を動画視聴やゲームに費やすことが多く、読書に時間を割く機会が減っている。特に若年層においてこの傾向は顕著であり、活字離れが深刻化している。読書習慣を促進するためには、まず図書館の利便性を高める必要がある。開館時間の延長や休日開館の拡充により、働く人々も利用しやすい環境を整えるべきだ。さらに、電子書籍の貸し出しサービスを充実させれば、いつでもどこでも読書ができるようになる。オンライン予約や自動貸出機の導入など、デジタル技術を活用した利便性の向上も効果的である。
次に、読書への関心を喚起する取り組みが重要だ。学校では読書感想文コンクールやビブリオバトル(知的書評合戦)など、本を楽しむイベントを増やすべきである。また、図書館が著者を招いた講演会や読書会を開催することで、本との新たな出会いを提供できる。SNSで話題の本を紹介するなど、若者の興味を引く工夫も必要だ。
さらに、幼少期からの読書習慣形成が不可欠である。家庭や保育園、幼稚園で絵本の読み聞かせを積極的に行い、本に親しむ環境を作ることが、生涯にわたる読書習慣の基盤となる。読書は知識を深め、想像力を育む貴重な活動である。施設整備だけでなく、利用促進と関心喚起を組み合わせた総合的な取り組みが求められる。(795字)
小論文の対策は、以下の無料メルマガでも実施中↓↓↓
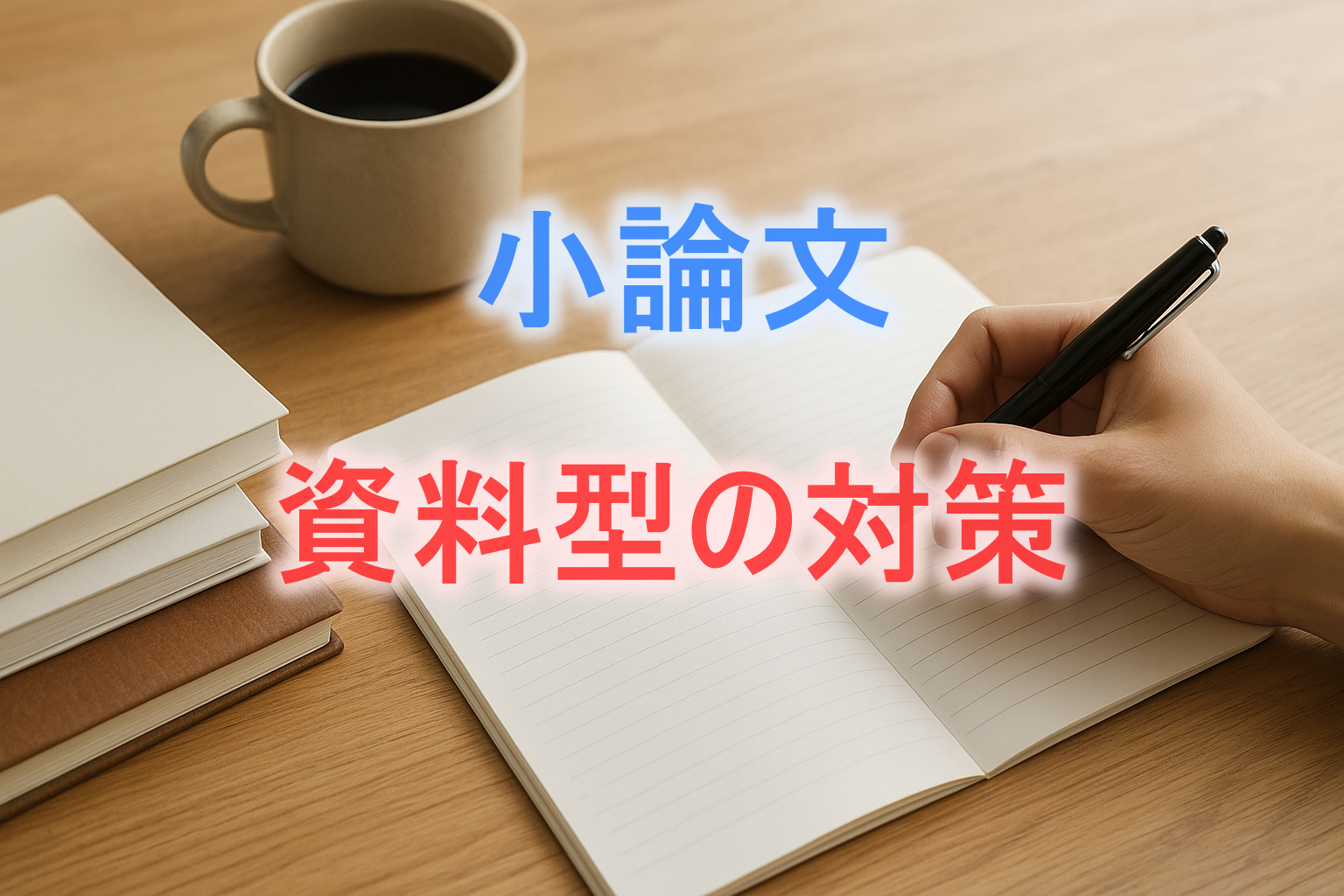
-500x336.png)

-500x336.png)

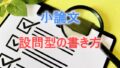
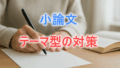
コメント