最近は原稿用紙をほとんど使わないで文章を書くため、いざ小論文の試験で原稿用紙を使って書かせられると戸惑ってしまいますよね。
ただ、大学入試や就職、昇進試験で小論文があり、手書きで書くことが求められる以上、原稿用紙を使った小論文の書き方を身に付けておく必要があります。
私が高校生のときも小論文の練習をするにあたって、渡された原稿用紙が「この用紙は縦書き横書きどっち?」と思っても、バカにされそうで先生に聞くことができませんでした。
ただこれは、用紙のある部分を見れば、見た目だけで、その原稿用紙が縦書きで書くべきか横書きで書くべきなのかを判断できます。
また特に小論文の横書きでの句読点の打つ位置など、恥ずかしくて今さら人には聞けない原稿用紙の使い方も見ていきますので、ご安心ください。
このように分かっているようで、分からない原稿用紙の使い方というものを縦書き横書き両方の形式で見ていきましょう。
今回学ぶこと
関連記事
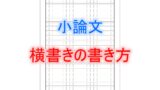
小論文の書き方での原稿用紙の使い方

小論文を書く際の原稿用紙の使い方は、合否を左右する重要なポイントです。
正しい書式や表記のルールを守ることで、内容だけでなく形式面でも評価を高めることができます。ここでは、原稿用紙の基本的な書き方や具体的な使い方のポイントを解説します。
原稿用紙の書き方の基本
原稿用紙の書き方には明確なルールがあります。
まず、指定字数の9割以上を書くことが基本です。
詳しくは以下をご覧ください。

受験生など書く側からすると面倒なのですが、こういう形式的なルールを守ることで余計な減点を防いで、採点者からの心証も良いものとなります。
原稿用紙の使い方
まずタイトルを書く場合、1行目の行頭から3マス空けて書き始めます。指示で「タイトルも書きなさい」などの指示がない場合は、タイトルは書きません。
受験番号と氏名は2行目に記入し、姓名の間は1マス空けるのが基本です。本文は1マス空けて書き始め、段落を変える際も同様に1マス空けます。
学校名は正式名称で記載し、公立高校なら「○○県立△△高等学校」のように書きます。
【横書きの書き始め】

【縦書きの書き始め】

ただし題名、受験番号、氏名は、多くの場合、指定欄外に書かせることが多いので、「原稿用紙に書きなさい」といった指示がない場合は、原稿用紙には書かないので気をつけましょう。
句読点や符号は1マスとして数え、行頭には置かず、前行末に入れるか閉じかっこと句点を同じマスに書きます。縦書きでは漢数字を用い、「二〇二五年」のように表記します。
【縦書きの数字の書き方】

また原稿用紙を効果的に使うには、書く文字数の把握が不可欠です。
「○○字以内」「○○字程度」「〇〇字以上、〇〇字以下」にかかわらず、制限字数上限の9割以上10割以下で書きます。
制限字数の8割に届かない字数不足や制限文字数を1字でも超える超過は、採点対象外になる可能性もあるため、注意してください。
【字数制限の例: 400字の場合】
適切な文字数:360字(9割)〜400字(10割)
不足とみなされる字数:320字未満(8割未満)
超過:401字以上(1字でも超えると減点対象)
また、促音「っ」や拗音「ゃ」「ゅ」「ょ」も1マスに1文字書きます。これらは行頭に置くことが可能ですが、句読点や閉じかっこは行頭に置いてはいけません。
繰り返し符号「々」も行頭には置けないため、その場合は漢字で書き直します。


数字やアルファベットの書き方は縦書きと横書きで異なりますので、試験形式に合わせて適切に対応しましょう。
【縦書き】
![]()
【横書き】

小論文での表記上の注意点
小論文では適切な表記を用いることが重要です。
まず、文体は常体(「だ・である」調)を使用し、敬体(「です・ます」調)は避けます。
また、口語表現や省略表現は使わず、書き言葉で統一します。
「なので」ではなく「したがって」、「バイト」ではなく「アルバイト」のように正式な表現を用います。
片仮名語も日本語で表現できるものは避け、オノマトペ(擬音語・擬態語)や流行語、若者言葉も使用しません。
詳しくは以下をご覧ください。
同じ言葉の繰り返しや重複表現も避け、表現力の高さを示すことが大切です。また、「~と思う」という曖昧な表現よりも「~と考える」「~である」と断定的に書くほうが説得力が増します。
文字は下手でもよいので丁寧に書き、採点者が読みやすいように心がけましょう。
これらの注意点を守ることで、先ほどもお伝えしましたが内容面だけでなく形式面でも高評価を得られます。
小論文の原稿用紙は「縦書き・横書き」どっち?

小論文を書く際に悩みがちなのが、原稿用紙の書き方です。渡された原稿用紙が縦書きと横書きのどちらで書くべきなのかを迷うことがありますが、これはパッと見た目だけで判断できます。
そして各大学・学部によって異なる場合があるので、志望校の形式に合わせて普段から練習しておくことが重要です。
近年は横書きが多いが、一概には言えない
現在の小論文試験では横書きの出題形式が主流になっています。
特に理系学部や社会科学系の学部では横書きが一般的であり、全体的な傾向としても横書きが増えています。
しかし、文学部など一部の学部では依然として縦書きが採用されていることもあります。
また、同じ大学でも学部や年度によって形式が異なることがあるため、「必ず横書き」とは断言できません。
志望校の過去問や入試情報を確認し、その大学・学部の出題傾向を把握することが最も確実な方法です。横書きが多いとはいえ、受験年度によって縦書きの可能性もあるので、両方の書き方に慣れておくとよいでしょう。
原稿用紙を見て、「縦書き・横書き」の判断の仕方
配布された原稿用紙自体から縦書きか横書きかを判断することができます。
タテに長く伸びているのが横書きの原稿用紙
ヨコに長く伸びているのが縦書きの原稿用紙
少しややこしいのですが、原稿用紙がヨコ方向に長く伸びる長方形ならば縦書きの形式で、タテ方向に長く伸びるの長方形ならば横書きの形式だということです。


縦書き横書きの原稿用紙がそれぞれ、この形式になっているのは書きやすいし読みやすいからです。
また、問題用紙に書き方の指示が印刷されていることがあるので、それを確認しましょう。
中には罫線だけ引かれていてマス目がない場合もありますが、その場合は問題文の指示を確認するか、紙の向き(タテに長く伸びているか、ヨコに長く伸びているか)で判断します。
また罫線の向き(タテ方向に引かれていれば縦書き、ヨコ方向に引かれていれば横書き)でも判断できます。
原稿用紙の使い方の基本(一マスに一文字、句読点も一マスに一字など)は縦書き・横書きどちらでも共通していますが、数字や英語の記入方法には若干の違いがあるので注意しましょう(下記参照)
問題文の形式で決まる
小論文の書き方は、基本的に問題文の形式に合わせられています。
問題文が縦書きで提示されている場合は縦書きで、横書きで提示されている場合は横書きで書かせることが多くなっています。
これは単なる形式ではなく、採点者が読みやすいからです。
ほとんどありませんが、問題用紙と解答用紙の形式が異なる場合は、問題用紙に書く形式の指示が書かれているはずなので、問題用紙の説明をよく読みましょう。
事前の説明、問題用紙の説明を読んでも分からない場合は、試験開始前に監督者に質問するのが最善です。
基本的には「問題文の縦・横書きの形式に合わせて、原稿用紙の形式も決まる」という基本を覚えておけば、ほぼ間違いありません。
小論文の横書きでの句読点の使い方

これまでみなさんは、作文などで縦書きの原稿用紙を使ってきており、縦書きの句読点の打ち方には慣れているでしょうが、横書きとなると「う~ん、どうだったっけ?」と戸惑うこともあるかもしれません。
そこで横書きでの句読点の打ち方を改めて確認しておきましょう。
原稿用紙マス目の左下に打つ
句読点は、縦書き原稿用紙ではマス目の右上に、横書き原稿用紙ではマス目の左下に打ちます。
詳しくは以下の内容もご覧ください。
↓ ↓ ↓ 小論文試験に必須の一冊 ↓ ↓ ↓
小論文の基本から、試験を想定した
実践練習まで、この一冊で身に付きます!
この一冊で小論文のお悩みすべて解決!
\ Amazonで400冊突破!/
行頭に打たない
これは縦書きも同じですが、横書きの原稿用紙でも行頭に句読点は打ちません。
カギかっこの受けなどの記号を含め、行頭に句読点を打つことは減点の対象になります。
以下で、横書き原稿用紙での句読点や記号などの書く位置を説明していますので、ご覧ください。
・小論文の横書きのルール
・マス目の端っこOKな記号、NGな記
・横書き原稿用紙での句読点やかっこの書き方
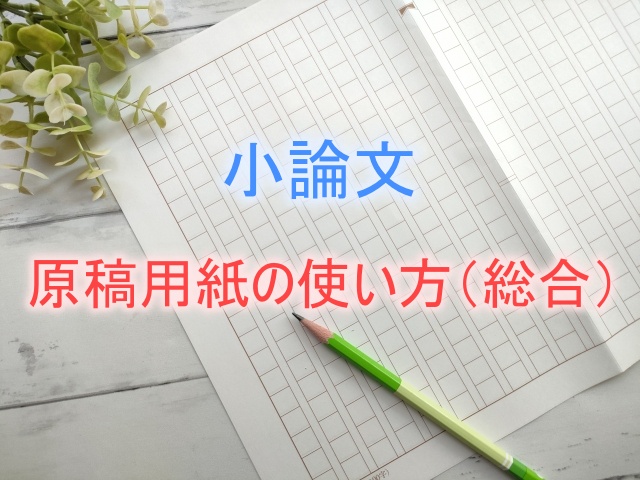
-500x336.png)




コメント