工学部の志望理由書の書き方で悩んでいる高校生の皆さん、「工学に興味がある」だけでは合格できる志望理由書は書けません。
工学部の志望理由書は、具体的な学習意欲と将来のビジョンを体系的に示すことで、説得力のある800字の文章が完成します。
本記事では、工学部志望理由書の書き方を4つのステップで解説し、入学後何を学びたいかの例文も豊富に紹介します。
これを読めば、あなたも必ず合格に近づく志望理由書が書けるようになります。
関連記事

大学の志望理由書(工学部)の書き方

工学部の志望理由書を効果的に書くためには、体系的なアプローチが重要です。単に「工学に興味がある」だけでは不十分で、具体的な学習意欲と将来のビジョンを明確に示す必要があります。
工学とは
工学とは、数学や物理学などの理論的知識を基盤として、実社会の課題解決に向けた技術開発を行う学問分野です。
純粋な学術研究とは異なり、人間の生活向上や社会発展に直結する実践的な価値創造を目指しています。
例えば、地震に強い建物の設計技術や、環境負荷を軽減する新エネルギーシステムの開発などが挙げられるでしょう。
工学者は常に「どうすれば技術で世界をより良くできるか」という視点で物事を捉え、創造的な解決策を生み出していく役割を担っているのです。
工学部で学べること
工学部では多様な専門分野を通じて、現代社会を支える技術の本質を学ぶことができます。
機械工学では、力学や材料科学を基礎とした機械システムの設計・製造技術を習得し、自動車産業やロボット開発に応用できる知識を身につけます。
電気工学では回路設計から電力システムまで幅広く学び、スマートフォンから発電所まで電気技術の全領域をカバーします。
建築学は構造力学と美的デザインを融合させ、安全で美しい建造物を創造する技術を探求する分野です。
情報工学ではプログラミングやAI技術を学び、デジタル社会の基盤となるシステム開発力を培います。
化学工学は化学反応を工業規模で制御し、新素材や医薬品製造に不可欠な技術を学べるでしょう。
エネルギー工学では再生可能エネルギーや省エネ技術を研究し、持続可能な社会実現に貢献する専門性を身につけることが可能です。
次に、以下の4つのステップを順番に進めることで、説得力のある志望理由書を完成させることができます。
① 学ぶきっかけ
志望理由書の冒頭では、なぜ工学部を目指すようになったのかという原点を明確に示します。
幼少期の体験や高校での学習、社会問題への関心など、具体的なエピソードから書き始めることが効果的です。
たとえば「高校の物理の授業で回路実験を行った際、LEDが光る瞬間に感動し、電気工学への興味が芽生えた」のような具体的な体験を挙げましょう。
重要なのは、そのきっかけがどのように現在の学習意欲につながっているかを論理的に説明することです。
単なる思い出話ではなく、工学への関心がどのように深まっていったかを順序立てて述べ、最終的に志望する分野への明確な動機として結論づけます。
このプロセスを通じて、読み手に対してあなたの工学への情熱が一時的なものではなく、継続的な関心に基づいていることを示せます。
志望理由書の基本は以下を参照。
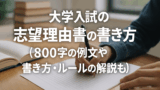
② 大学ホームページやパンフレットの読み込み
志望する大学の特色や強みを徹底的に調査することは、説得力のある志望理由を構築する上で不可欠です。
単に「有名だから」や「設備が良いから」といった表面的な理由ではなく、その大学が力を入れている研究分野や教育方針、独自のカリキュラムについて深く理解する必要があります。
特に注目すべきは、他の大学にはないユニークな取り組みや、志望する分野で特に優れた実績を持つ研究室の存在です。
大学の公式サイトでは、学科の教育目標や研究内容、教授陣の専門分野について詳細に調べましょう。
また、産学連携の実績や卒業生の進路データも重要な情報源となります。
これらの情報を基に、自分の学習目標と大学の教育方針がどのように合致するかを具体的に説明できるようになります。
その大学でしか学べない内容を見つけ出し、それがなぜ自分の将来の目標達成に必要なのかを論理的に結びつけることが求められます。
志望理由書を書く前の情報収集が大切だということですね。
③ アドミッションポリシーを読む
アドミッションポリシーは、その大学がどのような学生を求めているかを明文化した重要な指針です。
工学部では一般的に、論理的思考力、問題解決能力、そして社会貢献への意欲を持った学生を求めています。
このポリシーを詳細に分析し、自分の特性や経験がそれらの要求にどのように応えられるかを具体的に示すことが必要です。
たとえば「創造性豊かな技術者の育成」を掲げる大学であれば、自分がこれまでに取り組んだ創作活動や課題解決の経験を具体的に挙げ、その大学で学ぶことでさらにその能力を伸ばしたいという意欲を示しましょう。
また、国際的な視野を重視する大学なら、語学学習への取り組みや異文化理解の経験について言及することが効果的です。
アドミッションポリシーと自分の特性を照らし合わせることで、その大学に相応しい人材であることを説得力をもって伝えられます。
④ 今の自分と将来の自分とのギャップを埋める
現在の自分の知識やスキルレベルを客観的に把握し、将来の目標を達成するために何を学ぶ必要があるかを明確にすることが重要です。
将来の具体的な職業が決まっていなくても、工学の分野でどのような貢献をしたいかという方向性は持っておきましょう。
たとえば「環境問題の解決に貢献したい」「人々の生活を便利にする技術を開発したい」といった大きな目標で構いません。
その目標を達成するために、大学の4年間でどのような知識と技術を身につける必要があるかを具体的にリストアップします。
専門科目だけでなく、実験技術、コンピュータスキル、コミュニケーション能力なども含めて考えましょう。
そして、それらの学習計画が志望する大学のカリキュラムとどのように合致するかを説明することで、明確な学習ビジョンを持っていることをアピールできます。このギャップ分析により、大学進学の必然性と学習への強い動機を示すことができます。
工学部の入学後何を学びたいかの例文

入学後の学習計画を明確にするためには、自分の興味と大学の特色を照らし合わせることが重要です。以下の視点から例文をもとに考えてみましょう。
自分の学びたことと特色の合う大学を選ぶ
入学後何を学びたいかの基本は以下で参照してください。
学びたいことと大学の特色は、できるだけ具体的に書きましょう。
教授や研究室などの具体的な内容は、大学ホームページやパンフレット、アドミッションポリシーの読み込みが生きてきます。
オープンキャンパスなどにも参加すると、より具体的なことが書けるでしょう。
大学の特色から自分の学びたいことを考える
貴学の機械工学科で特に注目しているのは、ロボティクス分野への取り組みである。産業用ロボットから医療支援ロボットまで幅広い研究が行われており、これらの技術は高齢化社会の課題解決に直結すると感じている。また、3Dプリンターや最新の工作機械を使った実習環境も充実しており、理論だけでなく実際にものづくりを体験できる点に強く惹かれている。さらに、海外の提携大学との交換留学制度を活用し、グローバルな視点でエンジニアリングを学びたいと考えている。
これらの特色ある教育プログラムを通じて、次世代のロボット技術開発に携わる技術者を目指す。
自分の将来目標が決まっていない場合や、何を学びたいのかが具体的に決まっていない場合は、自分が興味のある大学の特色から考えてみることがオススメです。
そのさいも、自分の興味や関心を持った大学のホームページやパンフレット、アドミッションポリシーの読み込むことによって、学びたいことなどが具体的になっていくはずです。
将来の目標を考えてみる
将来は環境エネルギー分野のエンジニアとして、再生可能エネルギーの普及に貢献したいと考えている。特に太陽光発電システムの効率向上や蓄電池技術の開発に関心があり、貴学の電気電子工学科で基礎理論から応用技術まで幅広く学びたいと思う。また、学生時代には環境問題に取り組むサークル活動にも参加し、同じ志を持つ仲間たちと議論を深めていきたい。研究活動では国際会議での発表も経験し、世界レベルでの研究能力を身につけることを目標としている。
このような充実した学生生活を送ることで、持続可能な社会の実現に貢献できる技術者になりたいと考えている。
大学の志望理由書、工学部での800字例文

以下に工学部の志望理由書の具体的な例文を3つ示します。それぞれ異なる分野を志望する学生の視点で書かれており、ぜひ参考にしてみてください。
例文1
私は貴学の情報工学科への入学を強く希望する。高校で情報の授業を受ける中で、AIとプログラミングの分野に深い関心を抱くようになった。特に画像認識技術に触れた際、コンピュータが人間の視覚を模倣できることに感銘を受けた。この体験から、AI技術を活用して社会問題の解決に貢献したいと考えるようになった。
現在、医療分野では画像診断の精度向上が求められており、AIによる支援システムの開発が急務である。私は将来、医療画像解析の分野で活躍するエンジニアを目指している。そこで貴学を志望する理由は三つある。第一に、コンピュータビジョンの分野で著名な山田教授の研究室で学べることである。同教授の論文「深層学習による医用画像の自動診断システム」を読み、最先端の研究に深く感動した。第二に、貴学独自の産学連携プログラムが充実していることである。地元の総合病院と連携した実践的な研究に参加でき、実際の医療現場のニーズを理解しながら技術開発に取り組める。第三に、最新のGPUクラスターを備えた計算機環境が整っていることである。機械学習の研究には膨大な計算資源が必要であり、貴学の設備は研究活動に最適である。
入学後は、まず数学と統計学の基礎を固め、機械学習アルゴリズムの理論的背景を深く理解したい。その上で山田教授のゼミナールに所属し、医用画像解析に関する研究に従事したい。特に、CT画像からの早期がん検出システムの開発に挑戦し、診断精度の向上を目指す。
また、病院でのインターンシップにも積極的に参加し、医師や技師の方々との交流を通じて実用的な技術の開発を心がけたい。将来は医療AI技術者として、画像診断支援システムの開発に携わりたい。貴学での学びを通じて、医療の質向上と患者の負担軽減に貢献する技術者となることが私の目標である。(744字)
例文2
私は貴学の機械工学科への入学を心から希望している。幼少期からものづくりに興味があり、高校の技術の授業でロボット制作を体験した際、機械工学の奥深さに魅了された。特に、設計した機構が実際に動く瞬間の感動は忘れられない。この経験を通じて、人々の生活を豊かにする機械を開発したいという夢を抱くようになった。
現在の社会では高齢化が進み、介護分野でのロボット技術の需要が高まっている。私は将来、介護支援ロボットの開発に携わり、高齢者の自立した生活をサポートしたいと考えている。貴学を選択した理由は以下の通りである。第一に、ロボット工学分野で豊富な実績を持つ佐藤教授の研究室の存在である。同教授が開発した歩行支援ロボットの技術は素晴らしく、私もこの分野で研究を深めたい。第二に、貴学の実習設備が充実していることである。最新の3Dプリンターや精密加工機械を使用でき、アイデアを実際の形にする環境が整っている。第三に、医療機関との連携プロジェクトが活発であることである。実際の介護現場のニーズを理解しながら研究に取り組める点に強く惹かれている。
入学後は、機械力学と制御工学の基礎をしっかりと身につけたい。その後、佐藤教授のゼミナールに参加し、人間の動作解析と機械制御の融合について研究したい。具体的には、高齢者の歩行パターンを解析し、個人に最適化された歩行支援システムの開発に挑戦したい。
また、介護施設でのフィールドワークにも積極的に参加し、現場の声を製品開発に反映させることを重視したい。学外活動では、全日本学生フォーミュラ大会にも参加し、チームワークと実践的な技術力を磨きたい。将来は医療機器メーカーの開発エンジニアとして、高齢者の生活の質向上に貢献する製品を世に送り出したい。貴学での学びを基盤として、この目標を必ず実現させたいと考えている。(764字)
例文3
私は貴学の電気電子工学科への入学を強く志望する。高校時代に東日本大震災の報道を見て、電力インフラの重要性を痛感した。停電により多くの人々が困難な状況に置かれる様子を目の当たりにし、安定した電力供給システムの構築に貢献したいと考えるようになった。
将来は電力システム分野のエンジニアとして、持続可能なエネルギー社会の実現に寄与したいと思っている。そこで貴学への志望理由は三点ある。第一に、電力システム工学の権威である田中教授の指導を受けられることである。同教授の著書「スマートグリッドの基礎と応用」を読み、次世代電力網の可能性に深く感動した。第二に、貴学が推進している再生可能エネルギー研究プロジェクトの存在である。太陽光発電と風力発電の効率的な統合システムの研究は、まさに私が学びたい分野である。第三に、電力会社との共同研究が盛んであることである。実際の電力系統を扱う経験を積めることは、将来の仕事に直結する貴重な機会である。
入学後は、電気回路や電磁気学などの基礎科目を徹底的に学習したい。その上で、電力系統工学や制御理論の専門知識を身につけ、田中教授の研究室でスマートグリッドの研究に参加したい。特に、再生可能エネルギーの出力変動を補償する蓄電システムの最適制御について研究したい。また、電力会社でのインターンシップに参加し、実際の電力系統運用の現場を体験したいと考えている。
課外活動では、環境問題を考えるサークルに参加し、エネルギー問題について多角的に議論したい。将来は技術者として、次世代電力システムの開発に従事したい。再生可能エネルギーと既存の電力システムを効率的に統合し、環境負荷の少ない電力供給体制の構築に貢献することが私の目標である。貴学での充実した学びを通じて、この目標を達成したいと強く願っている。(757字)
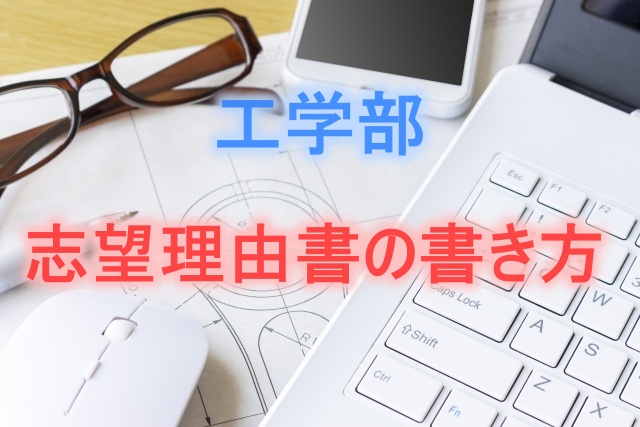
-500x336.png)

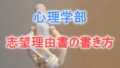
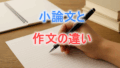
コメント