「設問型の小論文の書き方が分からない」「指示に正確に答えられているか不安」そんな悩みを抱えていませんか?
設問型の小論文には明確な攻略法があり、適切な手順を踏めば確実に得点できる答案が書けるようになります。
重要なのは設問文を正確に読み取り、問われたことすべてに漏れなく答えることで、自由記述型と指示詳細型それぞれに対応した具体的な書き方を身につけることが合格への鍵となります。
本記事では、設問型の小論文の基本から種類別の対策、書き漏れを防ぐテクニック、そして実際の例題と解答例まで、設問型小論文で高評価を得るための方法を詳しく解説しています。
関連記事
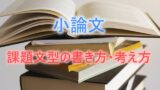
小論文の基本おさらい

設問型の小論文を書く前に、まずは小論文の基本を確認しておきましょう。
小論文と作文の違い、基本構成、そして論理的に書くためのポイントを理解することで、どんな形式の問題にも対応できる土台が築けます。
小論文の基本
まず小論文は、作文とは異なります。以下で小論文の基本について改めて確認しておきましょう。

書くルール
小論文の内容は良くても、書くルールを踏まえていないと減点され、最悪0点ということもあるので、以下で書くルールを確認しておきましょう。

原稿用紙の使い方
形式的なことですが、原稿用紙の使い方も小論文では採点対象になります。以下で原稿用紙の使い方についても改めて確認しておきましょう。
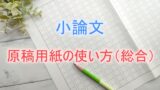
設問型の小論文の書き方

設問型の小論文には、自由に論じるタイプと詳細な指示があるタイプがあり、それぞれに適した対応が必要です。
ここでは設問型の特徴や種類を理解し、問われたことに確実に答えるための具体的な方法を解説します。
設問型とは
例題:科学を学ぶ意義とは何か、あなたの考えを述べなさい。
解答を書く条件が、短い指示文によって示される問題
設問型とは、短い指示文によって論じるべき内容が示される小論文の出題形式です。
例えば「科学を学ぶ意義とは何か、あなたの考えを述べなさい」のように、テーマと解答の条件が設問文で提示されます。
課題文や資料が添付される場合もありますが、基本的には設問文が解答の指針となるのが特徴です。
他の例としては「SNSが若者に与える影響について論じなさい」「地球温暖化への対策を述べなさい」といった形式があります。
設問型では、与えられた問いに対して的確に応答することが最も重要であり、設問文から外れた内容を書いてしまうと評価の対象外となってしまいます。
そのため、まずは設問文を正確に読み取り、何を答えるべきかを明確にすることから始める必要があります。
他の小論文の指導では、この設問型と「人口減少社会」「分断」など一言の問題から書かせるテーマ型を混同して紹介していることが多いですが、設問に解答するための条件が指示として書かれているものは設問型と定義して、対策を行っていきましょう。
テーマ型の問題は、また対策の方法が違ってきます。
↓ ↓ ↓ 小論文試験に必須の一冊 ↓ ↓ ↓
小論文の基本から、試験を想定した
実践練習まで、この一冊で身に付きます!
この一冊で小論文のお悩みすべて解決!
\ Amazonで400冊突破!/
設問型の種類
自由記述型 例題:科学を学ぶ意義は何か、あなたの考えを述べなさい。
指示詳細型 例題:日本には死刑制度が存在しているが、死刑制度を維持すべきか廃止すべきかについて議論がある。死刑制度を維持すべきか廃止すべきかについて、それぞれの論拠を示しつつ、あなたの意見を1000字以内で述べなさい。
設問型は大きく分けて「自由記述型」と「指示詳細型」の2種類があります。
自由記述型は「科学を学ぶ意義とは何か、あなたの考えを述べなさい」のように、テーマだけが示され、論じる角度や内容を自分で決める形式です。
自由度が高い反面、問題提起の仕方によって論点がぼやけたり、そもそもの書く方向性も自分で決める難しさがあります。
一方、指示詳細型は「日本には死刑制度が存在しているが、死刑制度を維持すべきか廃止すべきかについて議論がある。死刑制度を維持すべきか廃止すべきかについて、それぞれの論拠を示しつつ、あなたの意見を1000字以内で述べなさい」(2021年新潟大学文系後期試験)のように、論じる内容や手順まで細かく指定される形式です。
指示詳細型では、すべての指示に従って答えることが必須となる反面、その指示に従って書けば、書く方向性に悩むことなく書けます。
聞かれたことにはすべて答える
設問型の小論文で最も重要なのは、設問で聞かれたことにすべて答えることです。
どれほど優れた内容を書いても、問われていないことを論じたり、一部の問いに答え漏れがあったりすれば、大幅な減点となります。
例えば「賛成か反対か」を問われているのに意義を述べたり、「両方の論拠を示しつつ」という指示があるのに自分の立場しか述べなかったりするのは致命的です。
「そんなこと分かっているよ!」と思うかもしれませんが、実際に練習でも解答を書いてみると分かるように、書いていくうちに設問の書く条件を忘れてしまいがちです。
これはその人の記憶力にかかわらず、人の記憶力はかなりあいまいなので、まずは設問の書く条件は「忘れやすいものだ」ということを自覚しておきましょう。
そのため、解答を書き始める前に設問文に印をつけながら読み、「何を」「どのように」答えるべきかを箇条書きにすることをおすすめします。
特に複数の要求が含まれる設問では、一つひとつの指示を確認しながら書き進めましょう。
すべての問いに答えることが、合格答案への第一歩となります。
書き漏らさない答え方
実際に書き洩らしのない答え方として、設問に直接線を引いて番号をつけて答えていきます。
例えば問題として「科学を学ぶ意義は何か、あなたの考えを述べなさい」とあれば、以下の答え方でまずは答えます。

このように問題に下線を引き番号を書き込んだら、問題のすぐ下に、以下のようなメモ・テンプレートを作ります。
①
②(①をもとに)
上記のようにメモ・テンプレートを作成したら、メモ・テンプレートの番号と、問題に書き込んだ番号の箇所を見ながら、それぞれのテンプレートの箇所に30~40字以内で書いていきます。
これは設問の条件が多くなる指示詳細型でも同じです。
あとは以下のようにメモ・テンプレートで書いた答えをもとにアウトラインなどを書いて解答を書いていきます。(文字数が800字以下やそれ以上でも使えます)
このようにすることで、書き漏れがなく確実に設問の指示に沿った解答が書けるようになるでしょう。
> 小論文・完全ロードマップ解説の《無料メルマガ登録はコチラ》から
例題と解答例

ここでは、設問型の小論文の具体的な例題と解答例を3つ紹介します。
自由記述型と指示詳細型それぞれのパターンを確認し、実際の書き方をイメージしながら学んでいきましょう。
例題1(自由記述型:課題解決)
【問題】:「歩きスマホ」を減らすための方法について、あなたの考えを800字以内で述べなさい。
(解答例)
近年、スマートフォンを操作しながら歩く「歩きスマホ」が深刻な社会問題となっている。駅のホームからの転落事故や歩行者同士の衝突など、重大な事故も発生しており、早急な対策が必要だ。私は、歩きスマホを減らすために法的規制の導入と技術的対策の二つを提案する。
第一に、条例による法的規制を設けるべきである。現在、多くの自治体では歩きスマホに対する罰則がなく、注意喚起にとどまっている。しかし、危険性が高い駅のホームや横断歩道などの場所では、罰則付きの条例を制定することで抑止力が生まれる。実際、兵庫県では全国で初めて歩きスマホを禁止する条例が制定され、一定の効果を上げている。法的拘束力を持たせることで、人々の意識改革を促すことができるだろう。 ただし、どのような行為が「歩きスマホ」に当たるのかをきちんと定義して抑制的に運用しないといけない。
第二に、スマートフォン本体に技術的な対策を組み込むべきである。具体的には、歩行中であることを検知すると自動的に画面をロックする機能や、警告画面を表示する機能の搭載が考えられる。すでに一部のアプリではこうした機能が実装されているが、より多くの端末で標準装備とすることが望ましい。また、駅や交差点付近では位置情報と連動して警告を強化するなど、危険度の高い場所での使用を制限する仕組みも効果的だろう。技術の力を活用すれば、利用者の意識に関わらず物理的に歩きスマホを防ぐことが可能となる。
歩きスマホは個人のマナーの問題として片付けられがちだが、それだけでは解決は難しい。法的規制により社会全体のルールとして明確化し、同時に技術的対策で物理的に防止する。この二つのアプローチを組み合わせることで、初めて実効性のある対策となる。安全な歩行環境を実現するためには、社会全体で本腰を入れて取り組む必要がある。(762字)
例題2 (指示詳細型・賛否を問う)
【問題】:小学生がスマートフォンを利用することについて、賛成と反対それぞれの立場から考えられる根拠を示した上で、あなたの意見を800字以内で述べなさい。
(解答例)
近年、小学生のスマートフォン所持率が年々上昇しており、その是非について議論が分かれている。賛成派と反対派それぞれの主張を整理した上で、私の考えを述べたい。まず賛成派の立場からは、安全面と教育面での利点が挙げられる。共働き家庭の増加により、子どもが一人で過ごす時間が長くなった現代において、スマートフォンは保護者との連絡手段として重要な役割を果たす。
緊急時にすぐ連絡が取れることは、子どもの安全確保につながるだろう。また、学習ツールとしての活用も期待できる。教育アプリを使えば、算数や英語などを楽しみながら学ぶことができ、学習習慣の形成に役立つ。情報リテラシーを早期から身につけることも、これからの時代には必要だ。
一方、反対派の立場からは、健康面と教育面での悪影響が懸念される。長時間の使用により視力低下や睡眠不足を引き起こす可能性があり、成長期の子どもにとって深刻な問題となる。実際、スマートフォンのブルーライトが睡眠の質を下げることは科学的にも指摘されている。さらに、SNSやゲームへの依存により、学習時間が削られたり、友人との直接的なコミュニケーションが減少したりする恐れもある。対面での会話や外遊びといった、本来小学生に必要な経験が失われることは大きな損失だ。
これらを踏まえ、私は条件付きで賛成の立場を取る。スマートフォンは現代社会において不可欠なツールであり、完全に遠ざけるのは現実的ではない。ただし、使用時間の制限や利用できるアプリの管理など、保護者による適切なルール設定が不可欠である。例えば、一日一時間までと決めたり、食事中や就寝前は使用禁止にしたりするなど、明確な約束を設けるべきだ。子どもの安全と健全な成長の両立を目指すことが重要である。(726字)
例題3 (自由記述型・意義を問う)
【問題】:万博開催が日本にもたらす影響について、あなたの考えを800字以内で述べなさい。
(解答例)
万博は世界中から人々が集まる一大イベントであり、開催国に多大な影響を及ぼす。日本における万博開催は、経済面、社会面、そして国際的地位の面で重要な意味を持つと考える。 以下の三つ視点から考察していきたい。
第一に、経済への好影響が期待できる。万博開催に向けて会場建設やインフラ整備が進むことで、建設業や関連産業に大きな需要が生まれる。また、開催期間中は国内外から多数の来場者が訪れるため、観光業や飲食業、宿泊業などが活性化し、雇用創出にもつながる。例えば、過去の大阪万博では数千万人が来場し、関西経済に莫大な経済効果をもたらした。さらに、開催後も整備されたインフラや施設は地域の資産として活用され、長期的な経済効果が見込まれる。
第二に、社会の成熟を促す効果がある。万博では最先端の技術や多様な文化が紹介されるため、人々は新しい価値観や知識に触れる機会を得られる。特に若い世代にとって、世界の動向を肌で感じることは視野を広げる貴重な体験となるだろう。また、バリアフリー化やユニバーサルデザインの推進など、多様性を尊重する社会づくりのきっかけにもなる。会場整備を通じて実現されたこれらの取り組みは、万博終了後も社会全体に波及していく。
第三に、国際社会における日本の存在感を高める効果がある。万博の成功は日本の技術力や組織力を世界に示す絶好の機会であり、国際的な信頼を獲得できる。また、各国との交流を深めることで、外交関係の強化にも寄与するはずだ。グローバル化が進む現代において、こうした国際的なつながりは日本の将来にとって極めて重要である。 万博開催は一時的なイベントではなく、日本の未来を形作る重要な契機である。経済、社会、国際関係の各面で好影響をもたらし、国全体の発展に貢献すると確信する。(741字)
小論文の対策は、以下の無料メルマガでも実施中↓↓↓
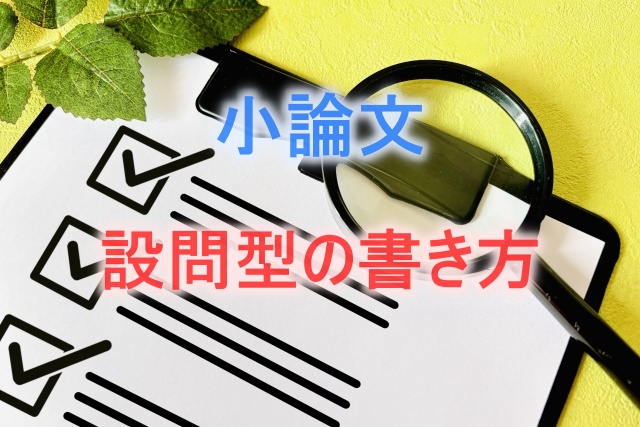
-500x336.png)


-500x336.png)
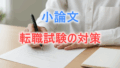
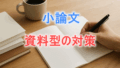
コメント