小論文のテーマがつまらない、難しいと感じて悩んでいませんか?
実は、魅力的な小論文を書くカギは「あなた自身の経験と思考」にあります。
本記事では、型にはまらない個性的な小論文の書き方と、自分の経験を効果的に活かす具体例をご紹介します。
誰でも実践できる方法で、採点者の心をつかむ小論文が書けるようになります。
あなたの小論文が「つまらない」から「印象に残る」ものに変わる秘訣を、ぜひ見つけてください。
関連記事
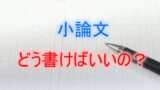
小論文のテーマで、つまらない文章を脱するには?

小論文が「つまらない」と感じられる主な原因は、考え方のパターン化や型にはめすぎることにあります。
採点者が読みたいのは、あなたの視点で書かれた文章です。
テーマに対して深く考え、自分なりの意見を述べることで、魅力的な小論文を書くことができます。以下では、つまらない小論文から脱却するための具体的な方法を紹介します。
問題ごとに個別の対策を立てない
小論文のテーマごとに対策を立てるという方法は、実は危険です。
事前に予想したテーマが出題されなかった場合、頭が真っ白になってしまいます。
時事問題や専門分野に関する情報をすべて把握することは時間的に不可能であり、特定のテーマについて書いた文章を暗記することも効率的ではありません。
むしろ重要なのは、どんなテーマが出題されても論理的に考え、自分の意見を組み立てる力を身につけることです。
小論文試験は「正解」を求めているわけではなく、あなたの「考える力」や「思考プロセス」を見ています。
テーマ別の対策ではなく、論理的思考力や文章構成力を高める練習に時間を使いましょう。
テンプレなどのワンパターンで書かない
「確かに〇〇は重要です。しかし私は△△だと思います」というパターン化された書き方は、読み手にうんざりした印象を与えます。
このような定型文は多くの受験生が使うため、個性が失われ、文章が平凡になってしまいます。
もちろん「確かに、しかし」といったテンプレートが使える問題もあるので、テンプレートの書き方が絶対にダメということではありません。
問題の前提や条件をもとに、書く構成を決めるということです。
そして小論文の冒頭部分は特に重要で、読み手の関心を引き付ける必要があります。
以下、テンプレートを使わない問題提起の仕方をご覧ください。
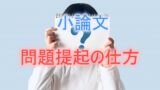
ただし、小論文の書き方の基本が分からないという人は、「だろうか・た・し・な・よ」のようなテンプレートに沿ってまずは書く練習をすると良いでしょう。
少し書き慣れてきたら、問題に沿ってテンプレートを脱した書き方で書いてみましょう。
考え方の基本を身に付けて書く練習をする
小論文で重要なのは「正解」ではなく「考える力」です。
特に医療や教育など正解のない分野では、その時々の状況に応じて最善を考える力が求められます。そのためには、考え方の基本を身につけることが大切です。
まず、テーマに対して多角的な視点から考えてみましょう。
賛成・反対だけでなく、様々な立場や状況を想定します。
次に、自分の主張とその根拠を明確にし、具体例を用いて説明します。
また、想定される反論にも触れ、それに対する答えを用意しておくと説得力が増します。
こうした思考の枠組みを繰り返し練習することで、どんなテーマにも対応できる基礎力が身につきます。
日頃からニュースや社会問題について考える習慣をつけることも、小論文力向上に役立ちます。
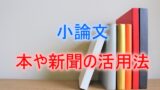
自分なりに考えるを繰り返す
小論文の採点者が最も求めているのは、あなたらしさが表れた文章です。
テンプレート通りの解答や、本やネットからの引用で構成された文章は、一目で見抜かれてしまいます。
それは「手作りの料理を期待していたのに、テイクアウトの食事を出された」ような失望を生み出します。
自分なりに考えるためには、まず与えられたテーマについて深く掘り下げましょう。「なぜそう思うのか」「それによってどのような影響があるか」などと自問自答します。
この繰り返しが、あなたの個性が光る説得力のある小論文につながるのです。そして、この一見地味な作業の繰り返しがあなたの独自性を生みます。
型にはまらず、しかし変に独自性を意識しないあなたの文章を目指しましょう。
小論文のテーマが難しい場合

小論文で難解なテーマに出会ったとき、多くの受験生は「何を書けばいいのか分からない」と頭を抱えてしまいます。
例えば「あなたが人との関わりを通して改めて見えた自分について」といった抽象的な問いには、どう取り組めばよいのでしょうか。
難しいテーマでも段階的なアプローチで整理すれば、自分の考えを論理的に表現できます。以下では具体的な取り組み方を紹介します。
まず問題の内容を理解する
難しいテーマに直面したときは、まず問題文を複数回読み、何が問われているのかを正確に把握することが重要です。
問題文のキーワードに注目し、それらが指し示す内容や意図を考えます。
例えば「人との関わりを通して見えた自分」というテーマであれば、「人との関わり」「見えた」「自分」という要素に分解できます。
これは「他者とのコミュニケーションや交流を通じて気づいた自分自身の特性や価値観」について問うています。
問題の本質を理解せずに書き始めると、的外れな内容になりがちです。
また制限字数も確認し、どの程度の分量になるか見当をつけましょう。
理解が曖昧なまま書き始めるのではなく、しっかりと問題文と向き合うことで、明確な方向性が見えてきます。
問題文を分解してみる
複雑なテーマは、いくつかの要素に分解すると取り組みやすくなります。各要素について個別に考えることで、全体像が見えてきます。
例えば先ほどの問題を「人との関わり」と「見えた自分」に分けて考えてみましょう。
「人との関わり」では、家族、友人、先生、見知らぬ人など様々な相手との具体的なエピソードを思い出します。
「見えた自分」については、その関わりを通じて気づいた自分の性格、価値観、強み、弱みなどを考えます。
さらに問題に含まれる時間軸(過去の経験か、現在の考えか)や、求められている視点(客観的分析か、主観的感想か)も意識しましょう。
問題を構成要素に分解し、それぞれについて考えることで、何を書くべきかが明確になり、論点がぶれない文章を作成できます。
問題の内容に個別に答える
分解した問題の各要素に対して、具体的に答えていきます。抽象的な表現だけでなく、具体例を交えることで説得力のある文章になります。
「人との関わり」については、印象に残っている具体的なエピソードを挙げましょう。例えば「部活動で意見の衝突があった場面」や「初対面の人と深い会話ができた経験」など、あなたの人間関係における転機となった出来事を選びます。
「見えた自分」については、その経験から気づいた自己の特性を明確に述べます。「自分は調整役に回りがちだ」「実は人の話をじっくり聞く忍耐力がある」など、具体的な気づきを表現しましょう。
このとき、単なる体験談で終わらせず、その経験からどのような考えや価値観が形成されたのかまでに言及することで、問題の核心に迫る内容になります。具体例と抽象的な考察のバランスが重要です。
自分の考えをまとめる
最後に、これまでの要素を統合して自分の考えをまとめます。
単なる体験の羅列ではなく、そこから導き出された自分自身についての洞察や今後の展望を含めることが重要です。
例えば「人との関わりを通して、自分は表面的には社交的でありながらも、内面では他者の評価を気にしすぎる傾向があることに気づいた」といった気づきから、「この自己認識を踏まえ、今後は他者の目を過度に意識せず、自分の考えをより素直に表現していきたい」といった展望へとつなげます。
小論文の締めくくりでは、テーマに対する自分の考えを再確認しつつも、新たな視点や気づきを加えることで、読み手に「考えが深まった」という印象を与えられます。
自分の言葉で誠実に書くことで、ありきたりな結論でも独自性のある文章になります。難しいテーマこそ、あなたの思考力を示すチャンスなのです。
小論文での自分の経験の入れ方(例文付き)

小論文において自分の経験を効果的に取り入れることは、説得力を高め、独自性のある文章を作るための重要な要素です。
多くの採点者は、一般論だけでなく、受験生自身の視点や体験が反映された文章を高く評価します。
しかし、単に体験談を羅列するだけでは不十分です。ここでは、自分の経験を小論文に取り入れる際のポイントと具体例を紹介します。
問題に沿って入れる
自分の経験を小論文に取り入れる際は、必ず問題のテーマに関連した経験を選ぶことが重要です。
いくら印象的な体験でも、テーマから外れていては評価につながりません。
まず、出題テーマを分析し、それに関連する自分の体験を思い出します。
例えば「環境問題」がテーマなら、地域の清掃活動への参加経験や、家庭でのエコ活動の実践などが関連します。
体験を選ぶ際は、問題文に含まれるキーワードとの接点を意識しましょう。
また、体験を語る際は冗長にならないよう、テーマとの関連性を明確にして簡潔に述べることが大切です。
「この経験から、テーマについてこう考えるようになった」という流れを意識すると、体験とテーマを自然につなげることができます。
問題に沿った経験を効果的に用いることで、採点者に「この受験生はテーマを理解している」という印象を与えられます。
問題が求めていなければ、必ずしも入れる必要はない
小論文で、自分の経験を入れることが常に必要というわけではありません。
問題の性質によっては、客観的な分析や論理的思考を重視すべき場合もあります。
例えば、「現代社会における〇〇の問題点と解決策を述べよ」という問題では、社会的な視点からの分析が求められており、必ずしも個人的体験は必要ありません。
一方、「あなたが考える〇〇とは何か」という問いには、自分の経験に基づいた独自の視点が求められています。
問題文の中に「あなたの考え」「あなたの経験から」といった表現があれば、積極的に自分の体験を取り入れるべきですが、そうでない場合は、客観的な分析を主軸に据え、必要に応じて経験を補助的に使うと良いでしょう。
無理に体験談を入れようとして論点がぶれるより、問題の意図に沿って解答することが評価につながります。
体験談の具体例を挙げる
効果的な体験談を書くためには、3つの要素を意識しましょう。
まず「自分の体験と照らし合わせる」ことから始めます。
自分独自の視点は採点基準でも重視される「意見の独自性」につながります。直接体験が最も価値がありますが、特別な実績がなくても「人との関わり」を中心に考えれば、誰でも体験を見つけられます。
次に「具体例を挙げる」ことが重要です。体験は具体的であるほど説得力が増します。
ただし、細かい状況説明よりも、エピソードの本質を簡潔にまとめ、テーマに素早くつなげることを意識しましょう。
不必要な情報が多いと、論点がぼやけてしまいます。
最後に「課題の問題点を自分なりに考える」ことで体験を深化させます。単なる体験談で終わらせず、そこから見えてきた問題の本質や原因を分析し、結論部分の解決策につなげることが重要です。
自分の意見に対する反論も想定しておくと、より論理的な文章になります。
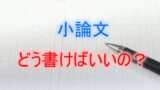
例文(悪い例)
テーマ:ボランティア活動から学んだこと
私は去年の夏休みに、友達に誘われて地域の高齢者施設でボランティア活動をした。最初は夏休みの課題のためだけに行ったのだが、思ったより楽しかった。高齢者の方々はみんな優しくて、いろいろな話をしてくれた。
活動内容は主に話し相手になることや、レクリエーションの手伝いだった。私は歌を歌ったり、トランプをしたりした。おじいちゃんやおばあちゃんたちはとても喜んでくれて、「また来てね」と言ってくれた。
この活動を通じて、ボランティアは大切だなと思った。高齢者の方々は話し相手が少なくて寂しい思いをしていることが分かった。若い人が訪問すると本当に嬉しそうだった。将来は福祉関係の仕事に就きたいと思うようになった。
ボランティア活動は自分のためにもなると思う。人の役に立つことができて、自分も成長できるからだ。これからも時間があれば参加したいと思う。
体験が羅列されているでだけで、個人的な感想に終わっています。
なぜ「ボランティア活動が自分のためになるのか」という具体的な理由がなく、「なぜ人の役に立つ」のか、「自分も成長できるのか」説得力に乏しい文章となっています。
例文(良い例)
テーマ:ボランティア活動から学んだこと
私は高校1年生の時から地域の児童養護施設で学習支援ボランティアを続けている。当初は単に進学実績に役立てたいという打算的な動機だったが、ある出来事を境に私の考えは一変した。
半年ほど経った頃、週に一度教えていた小学4年生の男の子が「先生、僕、今週テストで90点取れたんだ!」と満面の笑みで駆け寄ってきたのだ。彼は学習障害があり、それまで60点を超えることはほとんどなかった。私たちが毎週繰り返し練習した漢字と計算が、ようやく実を結んだ瞬間だった。彼の笑顔を見た時、私は「教える」という行為の本質的な意味を初めて理解した。
この経験から、ボランティアとは単なる「善行」ではなく、相互成長の機会であると気づいた。確かに私は知識を提供していたが、同時に子どもたちから忍耐や共感、そして小さな進歩を喜ぶ心を学んでいた。「教える側」と「教わる側」という一方的な関係ではなく、互いに影響し合う対等な関係こそが、真のボランティア精神なのではないだろうか。
社会には「ボランティアは余裕がある人がするもの」という見方もある。しかし、私は反対に「余裕がないからこそ、互いに助け合う関係が必要」だと考える。自分の限られた時間や能力でも、他者と共有することで新たな価値が生まれる。私のささやかな関わりが子どもたちの未来に影響を与え、彼らとの出会いが私の人生観を豊かにしている。この循環こそ、ボランティアの本質的価値ではないだろうか。
体験の具体例を挙げており、そこから何を考えたのかが明確に示されています。
その中で「余裕がないからこそ、互いに助け合う関係が必要」な理由が、「確かに私は知識を提供していたが、同時に子どもたちから忍耐や共感、そして小さな進歩を喜ぶ心を学んでいた」という具体例が示されています。
そしてボランティアの本質についての自分の考えを示されており小論文として良い解答だと評価できます。
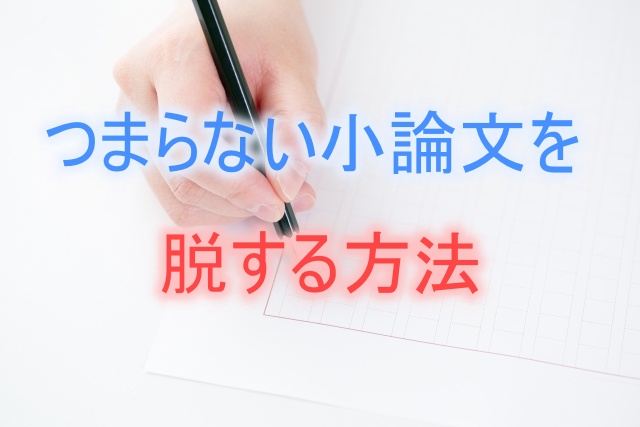
-500x336.png)



コメント