「大学入試での小論文の書き方が分からない」という高校生の皆さん、どこから手をつければいいか迷っていませんか?
小論文は作文とは異なり、論理的な構成と説得力のある根拠が求められるため、高校生にとって書き方の習得が重要な課題となります。
とくに書き出しは、読み手の関心を引く重要な部分であり、具体例を交えた効果的なパターンを身につけることで、合格に近づく小論文が書けるようになります。
本記事では、高校生向けの小論文の書き方から書き出しのコツまで、出題パターン別の具体例とともに詳しく解説します。
これを読めば、小論文の基本が理解でき、自信を持って大学入試に臨めるようになるはずです。
関連記事

高校生の小論文の書き方

小論文を書く前に、まずは小論文がどのような文章で、どの入試形式で使われるのかを理解することが重要です。正しい理解があってこそ、効果的な対策を始められます。
小論文とは何か?
小論文とは、出題されたテーマについて自分の意見を理由をもとに説明し、説得力のある文章を書く試験です。
作文とは異なり、感覚的な感想を述べるのではなく、「なぜそう考えるのか」を明確にして論理的に構成する必要があります。
小論文試験は一般選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜などで実施され、読解力・思考力・論述力を総合的に評価します。
特に総合型選抜では配点が大きく、合格を左右する重要な要素となっています。
一般選抜でも小論文を課す大学が増えているため、多くの受験生にとって対策が必要な試験と言えるでしょう。
大学は研究機関としての性質を持つため、レポートや論文の作成、また将来研究活動に必要な論理的思考力と表現力を小論文で測定しているのです。
小論文の評価基準
小論文の試験を合格するには、「どういう視点で評価されるのか?」をあらかじめ知っておくことが重要です。以下で小論文の評価基準を見ておきましょう。
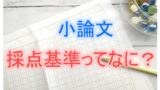
対策はいつから?
小論文の対策は、できるだけ早めに行う必要がありますが、最低限必要な期間というものがあります。
あくまで最低限必要であり、その期間練習すれば全て完ぺきというわけではないですが、「対策が間に合わなかった」ということにならないように、以下で見ておきましょう。
小論文の基本
小論文の基本的な構成は、「序論・本論・結論」であり作文の起承転結とは異なりますそのほかの小論文の書き方やルールについて、以下で確認しておきましょう。


書き出しのコツ

小論文で最も重要な部分が書き出しです。読み手の関心を引き、論文全体の方向性を決める重要な役割を担います。
ここでは出題パターンの理解から実際の書き方まで詳しく解説します。
出題パターンを知る
小論文の出題形式は大きく4つのパターンに分類されます。
設問指示型は、「首都機能の賛否についてメリットとデメリットを踏まえて、あなたの考えを述べなさい」などのように、具体的な設問の指示に従って解答する形式です。

課題文型は提示された文章を読んで、その内容について意見を求められる最も一般的な形式です。
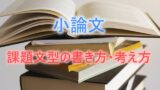
資料型(図表型)はグラフや統計データを分析して考察する問題で、データの読解能力が重要になります。

テーマ型は「『生きる』とはどのようなことか、あなたの考えを論じなさい」などの短い問いや写真や絵だけが与えられて自分の意見を述べる形式で、志望理由や社会問題について論じます。
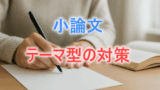
志望大学の過去問を確認して出題傾向を把握することが対策の第一歩となります。
大学・学部によって例年同じタイプを出題する傾向があるため、自分が受験する入試でどのパターンが出やすいかを事前に調べておくことで、効率的な準備ができるでしょう。
ただ、少数ですが大学・学部によっては、毎年違う形式の問題を出すところもあるので、過去問で把握しておきましょう。
それでも、上記に挙げた4つの形式のどれかに必ず当てはまるので、しっかり対策を行えば前年と問題形式が変わっても、きちんと対応することは可能です。
出題パターンごとの考え方、書き方
テーマ型では「環境問題について述べよ」のような設問に対し、「地球温暖化は喫緊の課題であり、個人レベルでの取り組みが重要である」のように明確な立場を示します。
自分の知識と経験を総動員して論理的に構成することが求められます。
課題文型では提示された文章の論点を正確に把握した上で、「筆者は○○と主張しているが、私は△△の観点から異なる見解を持つ」のように課題文の内容を踏まえて自分の意見を展開します。
筆者の主張を要約してから自分の考えを述べる流れが一般的です。
資料型では「このグラフから読み取れる傾向として、若年層の投票率が年々低下している点が挙げられる」のようにデータの客観的分析から始めて、その原因や対策について考察を深めていきます。
数値の正確な読み取りと分析力が評価のポイントになります。
問題の指示はスルーしない
小論文の解答を書く上で、問題の指示には必ず答えるようにしましょう。
問題の一部あるいは全部を見落としたりスルーして書くことは大幅な減点ですので、以下で答え方を見ておきましょう。
結論を先に考える
問題から解答を書くときには、まず結論から考えるようにしましょう。以下で考え方を示しています。

書き出し5パターン
効果的な書き出しには決まったパターンがあります。
効果的な書き出し5パターン
① ○○が問題になっている・それに対して○○だと考える
② ○○に対して○○だと考える
③ 私は○○に賛成である。その理由は2つある・一つ目は○○・・・
④ 私は○○について△△と××の観点から述べる
⑤ 課題文では○○と述べられている・資料から○○が読み取れる
①問題:近年の少子高齢化について、その問題点を明らかにしたうえであなたの考えを述べなさい。
書き出し:「近年、少子高齢化は限界集落という村や集落の維持が困難な地域が多発するなど深刻な問題となっている。それに対して私は地域コミュニティの再構築が必要だと考える」のように社会問題を提示してから自分の見解を示す方法。
②問題:AIの発達は私たち人間にどのようなことをもたらすのか、あなたの考えを述べなさい。
書き出し:「AIの発達に対して、私は人間の創造性を補完する有益なツールだと考える」のように直接的に意見を述べる方法。
③問題:死刑制度について賛否を示したうえで、あなたの考えを述べなさい。
書き出し:「私は死刑制度に反対である。その理由は2つある。一つ目は誤判の可能性、二つ目は教育的効果の欠如である」のように賛否を明確にして理由を整理する方法。
④問題:「教育格差の問題点について2つ以上の観点から考え、その是正方法を書きなさい」
書き出し:「教育格差について、経済的要因と地域格差の観点から述べる」のように複数の視点を示す方法。
⑤問題:課題文や資料から読み取れることをもとに、あなたの考えを書きなさい
書き出し:「課題文では技術革新の重要性が述べられている。資料からも研究開発投資の増加が読み取れる」のように課題文や資料の内容を踏まえる方法があります。
これらのパターンを使い分けることで、読み手に分かりやすい導入ができるでしょう。
小論文の構成

小論文の構成や解答を書くまでの手順、実際の試験で求められる時間管理について説明します。
質の高い小論文を完成させるためには、これらの要素も欠かせません。
基本構成
まず、以下で小論文の基本的な構成を見ていきましょう。
アウトラインを書く
次に、実際の小論文の試験では、問題を読んでいきなり解答を書き始めてはいけません。
まず解答の枠組みとなるアウトラインを以下をもとに書いていきます。(800字以下、800字以上でも使えます)
解答を書く
小論文の上達には「書くこと」と「添削してもらうこと」が必須であり、繰り返し練習することで書き方のコツを身につけられます。
まず自分で書いた解答を客観的に見直し、論理の飛躍や根拠不足がないかチェックしましょう。誤字脱字や文法ミスの確認も忘れてはいけません。
学校の先生や予備校講師に添削してもらうことで、自分では気づけない課題や弱点が明らかになります。
添削では論理的な構成、根拠の妥当性、表現の適切さなどが評価されるため、指摘を受けた部分は必ず改善して再度提出しましょう。
フィードバックをもとに文章を書き直し、再度添削してもらうプロセスを繰り返すことが実力向上につながります。
客観的な視点からの指導を受けることで、説得力のある小論文が書けるようになるでしょう。
練習の段階では実際に書くことよりも、書いた後に添削を受け、それを次の解答に生かすことが最重要事項です。
また分からない知識は積極的に調べ、書くさいのネタを増やすようにしましょう。
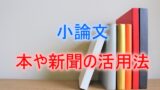
制限時間を意識して書く
小論文試験では開始後5~10分の構想時間が合否の90%を決めるといわれるほど重要です。
試験開始と同時に書き始めるのではなく、まず制限時間と文字数を確認し、出題パターンを判断してから解答の設計図となるアウトラインを作成しましょう。
規定の文字数で書くことはもちろん、実際の試験時間に合わせて時間内で書く練習が重要です。
800字や1000字の文章を原稿用紙に書くのにどの程度時間がかかるかを体感で理解しておくことで、本番で慌てることがなくなります。
一般的な時間配分は、構想に5~10分、見直しに5~10分で、その残り時間を解答を書く時間に使う方法が効果的です。
過去問を使って実際の試験時間で練習し、自分なりの時間配分パターンを確立しておきましょう。
↓ ↓ ↓ 小論文試験に必須の一冊 ↓ ↓ ↓
小論文の基本から、試験を想定した
実践練習まで、この一冊で身に付きます!
この一冊で小論文のお悩みすべて解決!
\ Amazonで400冊突破!/
原稿用紙の使い方

小論文は手書きで書くので、原稿用紙を適切に使うことができているかも評価の対象になります。
書く内容が良くても、原稿用紙の使い方を誤ると大幅に減点されることもあり、そのような形式的なところでの原点は非常にもったいないので、原稿用紙の適切な使い方についても改めて確認しておきましょう。
タテ書き・ヨコ書きの書き方
原稿用紙のタテ書き・ヨコ書きの書き方はそれぞれ異なる点があるので、以下で確認しておきましょう。
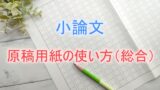
数字の使い方
数字の使い方についても知らないと本番で誤った書き方をして減点の対象になるので、以下できちんと見ておきましょう。
例題と解答例

実際の試験を想定した小論文の問題と解答例を以下に示しています。
制限字数では傾向の多い600~800字で解答例を作成しました。ぜひ書くさいの参考にしてみてください。
例題1(600字の解答例)
問題:SNSが高校生に与える影響について、あなたの意見を600字以内で述べなさい。
(解答例)
現代の高校生にとってSNSは日常生活に欠かせないツールとなっている。私はSNSが高校生に与える影響について利点と課題の両面を理解した上で適切に活用することが重要だと考える。まず、SNSの利点として、コミュニケーションの拡大が挙げられる。地理的な制約を超えて友人関係を維持できるため、転校や進学で離れた友人とも継続的に交流が可能である。また、学校という限られた環境では得られない多様な価値観に触れることができる。さらに、情報収集の手段としても有効で、進路に関する情報や社会問題についての知識を効率的に得られる点も評価できる。
一方で、SNSの負の側面も無視できない。最も深刻なのは、対面でのコミュニケーション能力の低下である。画面越しのやり取りに慣れすぎると、相手の表情や声のトーンから感情を読み取る力が衰える可能性がある。そして、他者との比較による精神的な負担も問題である。友人の投稿を見て自分の生活と比較し、劣等感を抱いたり、承認欲求が過度に強くなったりするケースが少なくない。さらに、依存性の高さも懸念される。常にスマートフォンを確認する習慣により、勉強や睡眠に支障をきたす高校生も多い。
これらの現状を踏まえ、SNSとの適切な関わり方を身につけることが必要である。利用時間を制限し、直接的な人間関係を大切にするバランス感覚を養うことで、SNSを有益なツールとして活用できるだろう。(579字)
例題2(600字の解答例)
問題:地球温暖化対策として個人ができることについて、あなたの考えを600字以内で述べなさい。
(解答例)
地球温暖化は人類共通の課題であり、国家レベルの政策と並んで個人の日常的な取り組みが不可欠である。私は省エネルギー行動と消費行動の見直しにより、個人でも温暖化対策に大きく貢献できると考える。まず、家庭での省エネルギー対策が効果的である。照明をLED電球に交換することで、従来の白熱電球と比べて約80パーセントの消費電力削減が可能だ。また、エアコンの設定温度を夏は28℃、冬は20℃に調整するだけで、年間の電力消費量を大幅に減らせる。使用していない電化製品のコンセントを抜く習慣により、待機電力による無駄なエネルギー消費も防げる。
次に、交通手段の選択も重要である。自家用車の利用を控え、電車やバスなどの公共交通機関を積極的に利用することで、二酸化炭素の排出量を大幅に削減できる。徒歩や自転車での移動も健康増進と環境保護の両面で効果的だ
さらに、日常の消費行動を見直すことも大切である。食品ロスを減らすため、必要な分だけを購入し、残り物を有効活用する工夫が求められる。マイバッグやマイボトルの使用により、プラスチック製品の消費を抑制できる。リサイクル可能な製品を選択し、適切な分別回収に協力することで、資源の循環利用も促進される。これらの個人レベルでの取り組みは小さく見えるかもしれないが、多くの人が実践することで社会全体の大きな流れとなり、地球温暖化の進行緩和に貢献するだろう。(581字)
例題3(800字の解答例)
問題:AI技術の発達が将来の雇用に与える影響について、あなたの見解を800字以内で論じなさい。
(解答例)
AI技術の急速な発達により、従来の雇用形態に大きな変化が生じている。私は短期的には特定分野での雇用減少が懸念されるものの、長期的には新たな職業の創出により、雇用全体にとって積極的な影響をもたらすと考える。ただし、この変化に対応するための教育制度の改革が不可欠である。
まず、AI導入による雇用への負の影響について考察する。製造業や事務作業において自動化が進み、単純作業や定型業務の需要は確実に減少している。銀行の窓口業務やレジ業務などが既に機械に置き換わりつつある現状がその証拠である。特に中程度の技能を要する職業において、この傾向は顕著に現れると予想される。こうした変化は、該当分野で働く労働者にとって深刻な問題となり、社会的な格差拡大の要因ともなりうる。また、AI技術の発達速度が人間の適応能力を上回る可能性もあり、短期的には失業率の増加が懸念される。
しかし、歴史を振り返ると、技術革新は常に新たな雇用機会を生み出してきた。産業革命時にも同様の懸念が生じたが、結果的に全体の雇用は増加した。AI分野においても、データサイエンティストやAIエンジニアなどの専門職需要は急激に拡大している。また、AIシステムの運用・保守を行う技術者や、AI倫理の専門家といった新たな職種も登場している。さらに、人間の創造性や共感力を要する分野では、むしろ雇用機会が拡大する傾向にある。介護、教育、芸術分野などでは、人間にしかできない価値の提供が求められるからである。
結論として、AI技術の発達は雇用に短期的な混乱をもたらす可能性があるものの、適切な対策を講じることで人類の労働をより豊かで創造的なものへと発展させる機会となる。重要なのは、技術の進歩を恐れるのではなく、それに適応し活用する能力を社会全体で培うことである。(743字)
例題4(800字の解答例)
問題:少子高齢化社会における若者世代の役割について、あなたの考えを800字以内で述べなさい。
(解答例)
日本は世界有数の少子高齢化社会となり、2025年には高齢化率が30パーセントを超える見込みである。この状況下で若者世代は社会の持続可能性を担う重要な役割を果たすべきだと考える。私は経済活動の活性化と世代間の理解促進により、少子高齢化社会の課題解決に若者が中心的な役割を担うべきであると考える。
第一に、労働力不足を補うための生産性向上が若者世代の重要な役割である。現在、労働人口の減少により多くの業界で人手不足が深刻化している。この問題に対し、若者世代はIT技術やデジタル技術を積極的に活用し、従来の働き方を改革する必要がある。例えば、AI技術を導入した業務効率化や、テレワークによる柔軟な勤務形態の普及により、少ない人数でより大きな価値を生み出すことが可能である。また、新たなビジネスモデルの創出により、これまでにない産業分野を開拓することも期待される。若者の柔軟な発想力と技術への適応力を活かし、日本経済の競争力を維持することが重要だ。
第二に、社会保障制度の維持においても若者世代の負担は重い。年金や医療費などの社会保障費は年々増加しており、若い世代がより多くの高齢者を支える構造となっている。この社会保障は、高度経済成長期を前提としており、今の少子高齢化にある社会に適応せず改革期に来ているだろう。年金保険料の積み立て制への移行など、社会に合わせた持続可能な制度改革に若い世代の知恵が必要である。
そして高齢者の豊富な経験と知識を活かす仕組みづくりにより、社会全体の知的資源を有効活用できる。例えば、高齢者が持つ技術や知恵を若者に伝承する制度を充実させることで、人材育成の効率化が図れる。こうして若者から高齢者までその人に合わせた社会参加を促すことにより、すべての人が生きやすい社会環境をつくること。この社会環境を将来世代に渡す責任として、若者世代の果たす役割は大きいと考える。(784字)
小論文の対策は、下の無料メルマガでも実施中↓↓↓
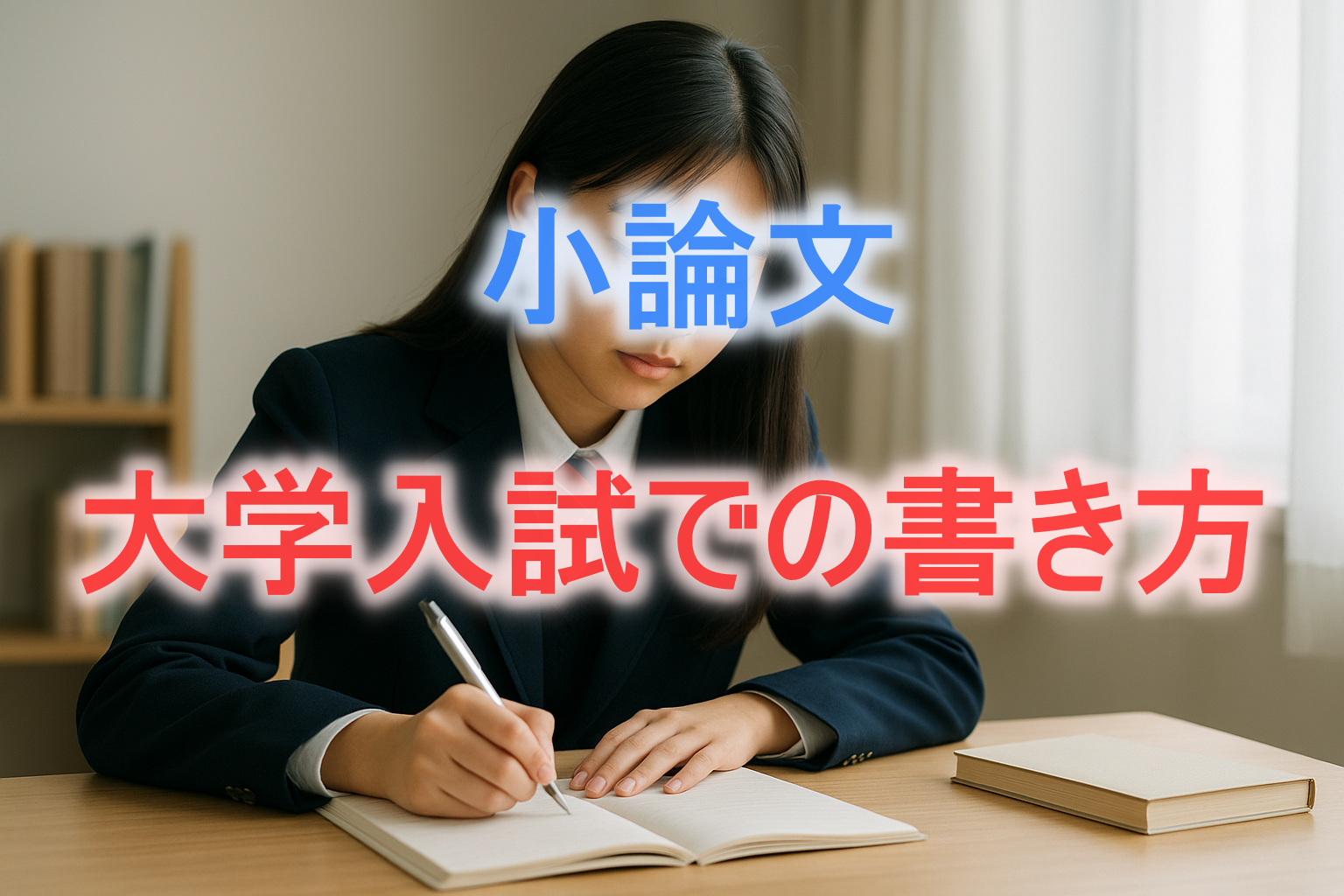
-500x336.png)



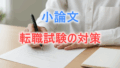
コメント