「賛成・反対の一方の立場で答えなさい」
小論文は、2択で答えさせる問題もよくあります。
ぶっちゃけどうでもいいわ! となりがちですよね。
ところが小論文で、こんなことを答えれば0点です。
また同じテーマでも、2つ以上のことが聞かれたり、複数の課題文が出されたりと頭が混乱するのも無理はありません。
しかし、どの問題形式や聞き方でも、ポイントを押さえれば無理なく答えることができます。
今回学ぶこと
関連記事

小論文の2択で「どちらでもいい」はダメ

よく賛成か反対かで、どっちつかずの答えや中間をとるような答え方をする受験生がいますが、それでは0点または評価はかなり低くなります。また小論文の問いは大きく3パターンに分かれます。
これら3パターンのどれであっても、ハッキリと自分の立場をとることが高評価の前提です。その詳細を見ていきましょう。
小論文の問題3パターン
➀ 「~について賛成か、反対かあなたの意見を書きなさい」(意見対立型の2択)
② 「○○の問題を改善するにはどうすればよいか、あなたの考えを書きなさい」(問題解決型)
③ 「~についてあなたの考えを述べなさい」(意見提案型)
小論文の問題の聞き方は、大きく分けるとこの3つのパターンとなります。
それぞれ以下で答え方について見ていきます。
意見対立型の答え方
「〇〇について賛成か反対か、その理由を踏まえたうえで書きなさい」
このような2択の問題では、必ず一方の立場で答えます。
賛成・反対どちらにすると有利、不利ということはありません。
それぞれ賛成・反対のメリット・デメリットを考え、それぞれ一文を30~40字以内のメモにして書きます。
書いたメモから賛成・反対から自分の立場を決め、メモ書きしたメリット・デメリットから自分の意見の根拠を考えてアウトラインを書きます。
そしてアウトラインをもとに解答を書いていきましょう。
あわせて読みたい

問題解決型の答え方
まず「何が問題なのか?」「なぜ問題なのか?」「その問題を放置するとどうなるのか?」をメモ書きしてみましょう。
そのメモ内容から、どのようにすれば問題が解決するのかを考えてみます。
このとき問題が100パーセント解決する方法などないので、問題が改善に向かっていくことを考えましょう。
またその解決策が現実的かどうか、きちんとした裏づけがあるのかどうかも考えて解決策を考えます。
メモ書きが済んだら、アウトラインを作成して解答を書いていきます。

意見提案型の答え方
「〇〇について、あなたの考えを書きなさい」
この意見提案型には隠された問いがあります。
それは上の意見対立型か、問題解決型のどちらか2つの問いが隠されています。
この問題の場合、小学生にスマートフォンを持たせることに(賛成か反対か)という問いが隠されています。
この問題の場合は、少子高齢化の現状と(その解決策または改善策)という問題解決策の問いが隠されています。
それぞれ上の意見対立型、問題解決型の書き方に戻って書いてみましょう。
小論文の1つの問いで2つ以上のことが聞かれる場合

1つの問いで複数のことが聞かれる問題について見ていきます。いろいろと聞かれて混乱しそうですが、問われていることはシンプルなので、落ち着いて見ていきましょう。
問われていることは1つのテーマ
例題
現在、多くの民間企業で定年制が採用され、そこで働く従業員は一定の年齢に達すると退職することとされている。もし仮に、法律により全ての民間企業に対して定年制の廃止を義務付けることが提案された場合、あなたはどのように考えるか。このような提案のメリット・デメリットを踏まえた上で、賛否とその理由も含め、あなたの考えを論じなさい。なお、賛否を示すときは理由だけでなく、その背景または補足を必ず入れること。
何だかいろいろ聞いていて、何が聞きたいのか分かりにくいですが、聞いていることは1つです。
「全ての民間企業へ定年制廃止を義務づける提案があった場合、あなたは賛成か反対か?」
この大元の答えるために、いろいろの答える条件が付いています。
聞かれていることには、それぞれ答える
問題が複数のことを聞いている場合、聞かれていることには全て答えます。
どれか一つでも答え損ねたり、無視して書くと減点になります。
面倒でも聞かれていることには全て答えるということを意識して書きましょう。
聞かれていることを分割する
例題
現在、多くの民間企業で定年制が採用され、そこで働く従業員は一定の年齢に達すると退職することとされている。もし仮に、法律により全ての民間企業に対して定年制の廃止を義務付けることが提案された場合、あなたはどのように考えるか。このような提案のメリット・デメリットを踏まえた上で、賛否とその理由も含め、あなたの考えを論じなさい。なお、賛否を示すときは理由だけでなく、その背景または補足を必ず入れること。
いきなり原稿用紙に書こうとして全て答えるつもりでいると、混乱したり、聞かれていることを書き漏らしたりということがあるので、聞かれていることをそれぞれ分割して考えてみます。
| 現在、多くの民間企業で定年制が採用され、そこで働く従業員は一定の年齢に達すると退職することとされている。もし仮に、法律により全ての民間企業に対して定年制の廃止を義務付けることが提案された場合、あなたはどのように考えるか。(問題に答える前提条件) |
| このような提案のメリット・デメリットを踏まえた上で(これを挙げる) |
| 賛否とその理由も含め(賛成か反対か理由を挙げて書く) |
| あなたの考えを論じなさい。(賛成か反対かを述べて自分の考えを書く) |
| その背景または補足を必ず入れる(定年制廃止を提案する社会的背景や補足を入れる) |
このように聞かれていることをそれぞれ分割して答えると、全て書き漏らさずに答えることができます。
聞かれたことに全て答えたら、まとめる
聞かれたことに全て答えたら、あなたの考えでまとめましょう。
上記の例題ならば、下記が解答例のまとめです。
小論文の複数課題文の答え方

複数の課題文がある問題の答え方について見ていきます。
結局基本今までの問題と同じなので、慌てず見ていきましょう。
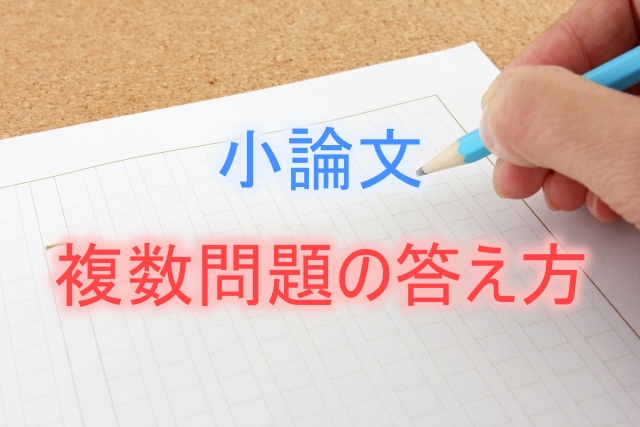
-500x336.png)

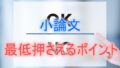
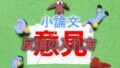
コメント