「工学部の小論文の書き方が分からない」「どんなテーマが出るのか不安」そんな悩みを抱えていませんか?
工学部の小論文にも、他の小論文同様に明確な評価ポイントがあり、適切な書き方を身につければ合格への道筋が見えてきます。
論理的思考力と技術的視点からの分析が重要で、過去問を通じて出題傾向を理解することが合格の鍵となります。
本記事では、工学部の小論文の書き方から頻出テーマの対策、実際の過去問分析、実際の試験を想定した解答例まで、工学部の小論文で高得点を得るための情報を詳しく解説しています。
関連記事
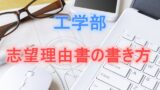
工学部での小論文の書き方

工学部の小論文では、技術的な知識と論理的思考力の両方が求められます。
ここでは、工学部で特に重視される能力と、出題される問題の特徴について詳しく見ていきましょう。
小論文の基本
工学部の小論文の書き方を見ていく前に、以下で小論文の基本を改めて確認しておきましょう。


工学部で求められること
工学部では論理的思考力と問題解決能力が最も重要視されます。
これは単に知識を暗記するだけでなく、与えられた課題に対して筋道立てて考え、実現可能な解決策を導き出す力のことです。
例えば、環境問題について論じる際には、現状を正確に把握し、技術的な観点から具体的な改善案を提示することが期待されます。
また、工学部では技術が社会に与える影響を多角的に評価する視点も求められます。
AI技術を例に取ると、その利便性だけでなく、雇用への影響や倫理的な課題についても考察する必要があるのです。
さらに、専門用語を正確に理解し、それを一般の人にも分かりやすく説明できる表現力も重要な要素となります。
これらの能力を総合的に示すことで、工学部にふさわしい人材であることをアピールできるでしょう。
工学部でよく出される問題形式
工学部の小論文では、最新技術の社会的影響を問う問題が最も頻繁に出題されます。
人工知能、ビッグデータ、IoT、5G技術など、現代社会を変えつつある技術について、そのメリットとデメリットを分析し、自分の見解を述べる形式が一般的です。
これらの問題では、技術的な理解だけでなく、社会への影響を総合的に判断する力が試されています。
もう一つの頻出パターンは、環境問題とエンジニアリングの役割に関する問題です。
地球温暖化、再生可能エネルギー、持続可能な開発といったテーマについて、工学的なアプローチでどのような解決策が可能かを論じることが求められます。
また、「○○技術の課題と解決策について述べなさい」という形式も多く見られ、この場合は問題点を明確に指摘した上で、実現可能な改善案を提示する必要があります。
これらの問題形式に慣れ親しんでおくことで、本番でも落ち着いて対応できるようになります。
そして問題形式は、「○○技術の課題と解決策について述べなさい」といった短い指示文から答える設問型、課題文を読ませてから指示に従って答えさせる課題文型、教授があるテーマについての講義をしてから問題に答えさせる講義型などが工学部で出される問題形式となっています。
↓ ↓ ↓ 小論文対策に必須の一冊 ↓ ↓ ↓
小論文の基本から、試験を想定した
実践練習まで、この一冊で身に付きます!
この一冊で小論文のお悩みすべて解決!
\ Amazonで400冊突破!/
工学部の小論文頻出テーマ

工学部の入試で出題される小論文には、明確な傾向があります。現代社会の技術的課題から環境問題まで、幅広い分野が扱われますが、特に重要な10のテーマについて理解を深めましょう。
頻出10テーマ
- 生物多様性と環境保護
- 感染症と科学技術の役割
- 自然災害対策と都市設計
- 医療、福祉の高度化と人工知能
- 脱炭素社会と再生可能エネルギー
- 環境問題とエンジニアリングの役割
- 最新技術の社会への影響
- エネルギー資源の未来
- ロボティクスと人間の協働
- データサイエンスの進展と個人情報保護
工学部の小論文では、生物多様性と環境保護が最も重要なテーマの一つです。
現在、地球上では年間数十種の生物が絶滅しており、この問題に対する工学的なアプローチが求められています。
具体例として、野生動物の移動ルートを確保するエコブリッジの建設や、生態系モニタリングシステムの開発などが挙げられます。
また、都市開発と自然保護のバランスを取るための技術的解決策についても考察が必要です。
感染症と科学技術の役割も頻出テーマとなっています。新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、医療技術や感染拡大防止技術の重要性が再認識されました。
mRNAワクチンの開発、PCR検査技術の普及、遠隔医療システムの導入など、科学技術が果たした役割は計り知れません。
自然災害対策と都市設計については、日本が地震や台風などの自然災害が多い国であることから、特に重要視されています。免震技術、津波避難ビル、スマートシティ構想など、災害に強い都市づくりの技術的側面が論じられます。
医療・福祉の高度化と人工知能では、診断支援システムや介護ロボットの活用が焦点となります。
脱炭素社会と再生可能エネルギーは、気候変動対策の観点から必須のテーマです。
これらの分野について深く理解するためにも、まずはニュースや新聞などで現状を把握して、技術的な視点から論理的に議論できる準備をすることが重要です。
> 小論文・完全ロードマップ解説の《無料メルマガ登録はコチラ》から
テーマの対策方法
頻出テーマの対策には、体系的なアプローチが効果的です。
まず、各テーマに関する基本的な知識を整理し、関連する技術やキーワードを覚えることから始めましょう。
例えば、環境問題であれば「カーボンニュートラル」「持続可能性」「生態系サービス」といった専門用語を正確に理解する必要があります。
次に重要なのは、具体的な事例や最新の技術動向を収集することです。
新聞の科学技術欄、学術論文の要約、政府の政策資料などから情報を得て、自分なりのデータベースを構築しましょう。
また、それぞれのテーマについて、メリットとデメリット、現在の課題と将来の展望を整理しておくと、論述の際に役立ちます。
実際の対策では、模擬問題を使った練習が欠かせません。
制限時間内に論理的で説得力のある文章を書くためには、アウトラインの作成から解答を書くまで、一連の流れを繰り返し練習する必要があります。
さらに、書いた文章を客観的に見直し、論理の飛躍がないか、具体例が適切かどうかを確認する習慣をつけることで、確実に合格レベルの小論文が書けるようになるでしょう。
難しいように見えますが、この繰り返しが試験での小論文を書く力を着実につけ、周りの受験生と大きな差をつけます。

過去問例
実際に工学部で出題された過去問例を2題ほど見ておきましょう。
次の3つの課題から1つを選択して解答すること。(400字以上500字以内で解答する)
(1) 半導体産業では、過去半世紀以上に渡る微細化技術の発展により、集積回
路上のトランジスタが高密度化し、半導体デバイスの処理速度の向上を果
たしてきた。今後の半導体産業では、微細化に加えどのような技術が求め
られるか、SDGs(持続可能な開発目標)と関連付けてあなたの考えを論述
しなさい。(2) 都市を支えるインフラストラクチャー(社会基盤を支える構造物)は、私
たちの快適な生活や産業活動のために必要不可欠な構造物である。近年,
これらの構造物の老朽化が大きな問題になっており、効率的な点検・補修・
維持管理・更新が求められている。工学の技術を用いた老朽化対策につい
て具体的な事例を挙げ、あなたの考えを論述しなさい。(3) 日本の農業は、国土の特性上、農地の規模が小さく大規模な生産を広範囲
で展開することが難しい。ロボット・AI・IoT などの先端技術を活用した
「スマート農業」において、生産効率を向上させるにはどのようにすべき
であろうか。あなたの考えを論述しなさい。(名古屋工業大学 工学部 2024年 一般選抜・前期日程)
近年、自然災害についてニュースなどでよく見聞きする機会が増えてきています。自然災害に対する工学技術の役割について、あなたの志望するコースに関連する技術がどのような役割を果たせるか、1つ以上例を挙げ、その利点と欠点を600字以上800字以内で述べなさい。
(富山大学 工学部・工学科 2024年 一般選抜・後期日程)
例題と解答例

実際の工学部の入試問題を想定した例題と解答例を示します。文字数や構成の参考にしてみてください。
例題1
【問題】人工知能(AI)技術の発展が労働市場に与える影響について、あなたの考えを800字以内で論じなさい。
(解答例)
私はAI技術の発展が労働市場に与える影響について、短期的には課題があるものの、長期的には社会全体に大きな利益をもたらすと考える。AI技術の導入により、確実に労働環境は変化している。製造業では既に多くの工場でロボットが組み立て作業を担当し、人間は品質管理や機械のメンテナンスといった、より高度な判断を要する業務に集中できるようになった。また、データ分析や会計処理などの事務作業においても、AIが定型業務を処理することで、従業員は戦略立案や顧客対応など創造的な仕事に時間を割けるようになっている。
しかし、この変化には課題も存在する。単純作業に従事していた労働者の中には、新しいスキルを習得することが困難な人もいるからだ。例えば、工場の流れ作業員がいきなりロボットの操作や保守管理を任されても、適応するのは容易ではない。このような労働者の再教育や職業転換支援が不十分であれば、失業率の増加や社会格差の拡大といった問題が生じる恐れがある。
この課題を解決するためには、企業と政府が連携した包括的な対策が必要である。企業は従業員のスキルアップ研修を積極的に実施し、政府は職業訓練制度の充実や転職支援サービスの強化を図るべきだ。例えばデンマークでは、技術革新による雇用変化に対応するため、国が主導して労働者の再教育プログラムを提供し、高い雇用率を維持している。
AI技術は人間を労働から解放するのではなく、より価値の高い仕事に従事できる機会を創出する。また人にしかできない仕事を再認識することにもつながる。AIに仕事を奪われるという発想ではなく、あくまでAIは価値の高い仕事への転換を労働市場に促す好機と捉えるべきである。そこで適切な教育と支援体制があれば、AI技術の発展は労働市場の質的向上に寄与するだろう。(740字)
例題2
【問題】IoT(モノのインターネット)技術の発展がスマートシティ構想に与える影響について、800字以内で論じなさい。
(解答例)
IoT技術の発展は、スマートシティ構想の実現において中核的な役割を果たしており、都市機能の効率化と市民生活の質向上に大きく貢献している。IoTセンサーの普及により、都市のあらゆる要素をデータ化し、リアルタイムで監視・管理することが可能になった。交通システムでは、道路に設置されたセンサーが車両の流量や速度を常時監視し、信号機の制御を最適化している。これにより渋滞の緩和と排気ガスの削減が同時に実現され、環境負荷の軽減につながっている。シンガポールでは、全市に設置されたIoTセンサーネットワークが交通量を予測し、動的な料金設定により交通流を制御している。
エネルギー管理においても、IoT技術は大きな変革をもたらしている。建物に設置されたスマートメーターが電力使用量をリアルタイムで把握し、需要予測に基づいた効率的な電力供給が可能になった。さらに、太陽光発電パネルや蓄電池と連携することで、地域レベルでのエネルギー自給自足システムの構築も進んでいる。
しかし、IoT技術の普及には課題も存在する。最大の問題はサイバーセキュリティである。数億台のデバイスがネットワークに接続されることで、サイバー攻撃の対象となるリスクが大幅に増加する。都市インフラがハッキングされれば、交通システムの麻痺や電力供給の停止など、市民生活に深刻な影響を与える可能性がある。
また、個人情報保護の問題も重要だ。IoTデバイスは市民の行動パターンや位置情報を常時収集するため、プライバシーの侵害につながる恐れがある。この問題を解決するには、データの匿名化技術や暗号化技術の向上が必要である。これらの課題を克服することで、IoT技術はスマートシティ構想の実現に不可欠な基盤技術として、持続可能で住みやすい都市環境の創出に貢献していくだろう。(739字)
上記の例題と解答例を参考に、まずは志望先の過去問題を入手して書く練習をしていきましょう。
小論文の対策は、以下の無料メルマガでも実施中↓↓↓

-500x336.png)


-500x336.png)


コメント