「段落分けって、どのタイミングでするの?」「そもそも書く字数が少ない場合は、段落分けしなくてもいいの?」
段落分けって意外と難しいですよね。
そこで今回は小論文の段落分けを、書く文字数としてよく設定される400字と800字の場合で見ていきます。
この2つ以外の書く文字数でも、基準が分かれば段落分けは簡単になるので、ぜひご覧ください。
今回この記事で学ぶこと
関連記事

小論文で200字以下の場合は、段落分けをしないのが基本

段落分けの本格的な内容に入る前に、書く文字数が少ない場合はやたらと段落分けをしないことについて見ていきます。
この段落分けをする・しないの基準を知っておくと、より段落分けがしやすくなるのでしっかりと見ていきましょう。
改行を1段落とする
まず問題に段落分けしなくてもよい、最初の改行もしなくても良いことが書かれている場合は、段落分けも最初の改行も行いません。
段落分けしなくても良い、最初の改行をしなくても良いと書かれていない場合は、最初の1文字目は1行下げます。
そして200字以下の文字数が指定されている場合は、途中での改行は不要です。
要約が400字近くになる場合は、段落分けをする
要約が400字になる場合で、改行不要の指示がない限りは200字あたりで改行して2段落とするのが良いでしょう。
要約も採点者の読みやすさを基本に、改行するのか・しないのかということを考えて行います。
とくに要約と意見論述をつなげて書く問題もあるので、このような場合は要約でもきちんと段落分けすることを意識しましょう。
以下の例題と解答例で見ていきます。(記事作成上、改行の1字下げはしていません)
例題:次の文章は、国際人権問題への日本の対応について記したものである。著者の議論を400 字程度でまとめた上で、それに対するあなたの考えを、具体例に触れつつ論じなさい。(合計1000字以内)
(課題文省略)
【解答例】
日本の国際人権への対応は、欧米に比べて自己抑制的であることが多い。この要因は、日本人の「訴訟嫌い」や、「話し合いによる穏健な解決を好む」非法的・調和優先的な文化と、「人権」という価値を他の国や社会へも宣布するという発想の弱い、非宣教主義的な文化によるものである。さらに、第二次大戦における日本の敗北や、戦争責任の未決という「すねに傷持つ身」の自覚からもきていると筆者は指摘する。
こうした特徴は、諸外国での人権侵害に対する独善的態度の抑制につながり、ときに日和見主義的な対応と見なされることがある。しかし一方で、このような日本の非独善的な対応は、米国型の宣教主義的・独善的な「人権外交」や、NGOの国際活動を是正・補完しうる。それは欧米中心の人権観から、他の文明の視点も考慮した文際的な人権観に基づく、国際人権政策の基礎づくりに貢献する可能性をも有している、と筆者は主張する。(ここまでが400字以内の要約)
近年のシリア紛争への介入に際して、現地市民に対する虐殺が行われている場合、米国型の干渉主義的な人権対応は、即効的で抑止力があるかもしれない。しかし、他国を軍事攻撃したり、経済援助の中断という制裁外交は、社会的な弱者や大量の難民を生み出す恐れがある。
一方、日本は人権侵害を行う国家・政権に対して、あえて強行的に対処せず、当該国の政治、経済、治安の混乱などを回避してきた。それは、日本が紛争に直接介入するのではなく、食糧や水、インフラ設備の修復など、緊急的に必要な支援を実施し、中長期的な開発支援を進めてきた。「マズローの欲求5段階説」にあるように、人は水や食料など生理的欲求を満たされて、はじめて社会的欲求に向かう。まず当該国の人の生活が安定してこそ、その国の未来を考えることができる。そして当該国のあり方を考えるのは、日本ではなく、当該国に暮らす人だという立場を取る。
このように日本の人道支援は、「安全に暮らす権利」など、欧米が見落としがちな社会権にも向いている。こうした日本の人権対応は、自由権を普遍的なものとする欧米の人権観を克服し、非欧米圏の意識や思考法をも考慮した、多角的な人権観の構築につながりうる。だからこそ筆者の言うように、日本の人権対応が文際的正統性をもつ、国際人権政策の基礎づくりに貢献する可能性をも有するのである。(合計952字)
上の解答例の要約は、もし改行しなければ全体として読みにくい文章となってしまいます。
要約も、改行不要の指示がない場合は、読みやすいかどうかということを第一に考えて改行するのか・しないのかの判断をしましょう。
小論文の400字での段落分け

小論文の論述での最小単位である400字での段落の取り方を見ていきます。
400字ピッタリではなく、300字~500字など、この前後の文字数での段落の取り方でも参考になるので、ぜひ見ていきましょう。
400字で小論文を書かせる目的
まず、なぜ400字で書かせるのでしょうか。
実際に小論文を400字で書いてみると分かりますが、意外とあっという間に埋まってしまいます。
余計なことを書くほどの文字数はありません。
つまり、「自分の意見を端的に書けるか」がポイントになります。
大学入試や採用試験でも、自分の意見を分かりやすくまとめて相手に伝えられる力があるのかどうかを見ています。
なぜ段落を分けるのか?
上でも少し書きましたが、なぜ「段落を分けるのか?」受験生のみなさんは考えたことがありますか。
「自分が書きやすいから」
たしかに、書きやすさから段落を分けるということもあります。
しかし一番は、読む方つまり採点者にとって「読みやすいから段落を分ける必要がある」ということです。
採点者の評価が、小論文の試験の合否を決めるのだから当然ですよね。
つねに他人から見て「読みやすいのかどうか?」を意識しながら段落分けを行いましょう。
最低2つ、多くて3つの段落分けをする
前置きが長くなりましたが、400字で段落分けをする場合、最低2つ、多くても3つの段落分けをします。
1つの話題を1つの段落として、多すぎず少なすぎずで段落分けを行います。
段落の分け方は、必ずしも3部構成ではない
そして段落の分け方で、「序論・本論・結論の3部構成で段落分けをするとよい」という指導がよくなされます。
たしかに400字ならば、小論文の基本構成で3段落がちょうど取れるので、分かりやすいですし、間違いではありません。
ただ、この3部構成が400字での段落の取り方の絶対ではありません。
1つの話のまとまりを基本にして、2つ~3つに段落を分けるということなので、話のまとまりで段落を分けることを基本にして2つ~3つの段落分けを行いましょう。
小論文の800字での段落分け

ここでは、小論文の試験で設定される文字数として頻度が多い800字での段落分けの方法を見ていきます。これから原稿用紙に書く練習をする人も、今まさに書く練習をしている人も、ぜひ参考にしてみてください。
4段落が基本
まず800字を書く場合、4段落に分けることが基本です。
理由は単純に「見た目のバランスが取れて読みやすいから」です。
実際に自分の書いた答案を採点者の視点で見てみると分かりますが、3段落では少ない印象を受け、5段落では少し多い印象を受けます。
あわせて読みたい

200字を一つのまとまりにする
800字の文字数で書く場合、4段落が基本と言いましたが、この場合200字を一つのまとまりにして段落分けすることが基本となります。
ただ、書いていると必ずしも200字ピッタリで段落分けできるわけではないので、1つの話のまとまりを基準として、大体200字あたりで段落分けをするというふうに考えておきましょう。
反対に1つの話のまとまりは、200字前後に収めることを意識して書いていきます。
1つの段落が1行など、極端に少ないとまとまりのない印象を受けるので、やはり200字を1つの話の基準として段落分けを行いましょう。
段落ごとに目的を持たせる
段落ごとに何を話すのか目的を決めて書きましょう。
書き慣れないうちは、あらかじめ4段落と決めておいて、それぞれ何について書くのか箇条書きで書いてから原稿用紙に書くと、段落ごとにまとまった文章が書けます。
例題
現在、多くの民間企業で定年制が採用され、そこで働く従業員は一定の年齢に達すると退職することとされている。もし仮に、法律により全ての民間企業に対して定年制の廃止を義務付けることが提案された場合、あなたはどのように考えるか。このような提案のメリット・デメリットを踏まえた上で、賛否とその理由も含め、あなたの考えを論じなさい。なお、賛否を示すときは理由だけでなく、その背景または補足を必ず入れること。〔大学入試 800字以内〕
【段落ごとに大まかな内容を箇条書きにする】
段落1:定年制廃止が導入された場合のメリット
段落2:定年制廃止が導入された場合のデメリット
段落3:定年制廃止が進む背景
段落4:定年制廃止に対する自分の意見
【解答例】
まず、民間企業の定年制廃止が導入された場合のメリットは、少子高齢化における人手不足の緩和や、それに伴う新規採用コストの削減、勤続年数の長い熟練社員による若手社員へのノウハウ継承など、膨大なコストをかけずに企業の事業継承が行いやすくなることである。
一方、定年制廃止のデメリットは、従来の定年退職者を雇用延長することにより、 企業内での世代交代が進みにくくなること。これにより新たな考えやテクノロジーの導入が行われにくくなり、企業体質が新たな時代への対応を困難にすることが考えられる。また日本では、多くの企業で年功序列という賃金体系をとっているため、高齢社員の雇用を延長すれば人件費の総和が増加し、業種によっては通勤や勤務中の病気や事故のリスクなど、企業のコストが増すことが挙げられる。
定年制廃止の動きが進む背景には、少子高齢化による人手不足を緩和することや、健康で意欲のある高齢者に働いてもらうことで、年金支給の後ろ倒しなど、増大する社会保障費を抑制することにある。このように見ると、定年制廃止は現在の社会的要請に沿ったものに見える。
しかし、私は定年制廃止を法律で義務付けることには賛成しかねる。それは定年制廃止を全ての民間企業に義務付けることは、例えば長距離バスの運転手など、高齢者が行うには困難な業種があるためである。たしかに、少子高齢化の人手不足から、高齢者でも長く勤務してもらえることは企業にとって財産であり、長距離運転など直接の業務が困難ならば、若手への運転技術の指導や、事務など他の業務に就くことも考えられる。ただ、それでも定年制廃止に伴うすべての高齢社員がこのような業務に就くことは、中小企業の多い日本では、抱える従業員数の限界から困難だろう。その代りに、定年制は維持した上で、社員の希望、能力あるいは健康状態を考慮した上での「選択的雇用延長」の広い導入が求められている。(791字)
あわせて読みたい
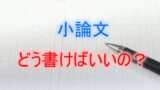
字数稼ぎの段落分けは減点
原稿用紙の書く文字数を稼ごうと、まだ話の途中なのに改行することは減点の対象となります。
これは採点者から見ると「ああ、こいつは文字数を稼ごうとしているな!」とすぐにバレてしまいます。
段落数が極端に少ないことも減点の対象ですが、反対に段落が無駄に多いことも減点の対象となるので気をつけましょう。
段落が多すぎると読みにくくなり、何が言いたいのか分かりにくい文章となります。
要約だろうと400字、800字の論述であろうと、採点者から見て読みやすいということを意識して段落分けを行っていきましょう。

-500x336.png)

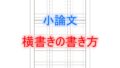

コメント