「試験まで1週間前だけど、小論文の対策を全然していない!」
「小論文の対策って、一週間で間に合うの?」
まず、ハッキリ言って1週間前から対策をしても、不十分だということはお伝えしておきます。
ただ、1週間前でもできることはあり、短期間でも対策することで合格できる可能性は十分あります。
そして何かしら毎日書くということを意識して行いましょう。
今回学ぶこと
関連記事

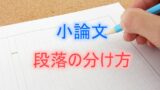
1週間前の小論文対策

1週間前の具体的な対策の前に、しっかりお伝えすることを見ておきます。ここで1週間前という短期間の心がまえを知って具体的な対策に移っていきましょう。
ハッキリ言って、1週間では不十分
冒頭でも言いましたが、1週間前での対策では不十分です。
小論文の学習には、できれば半年、最低でも3か月を確保した上で対策するというのが基本です。
基本を習得して正しい練習法で練習をすれば、義務教育を終えた人ならば誰でも書けるようになりますが、基本を習得したからといって、一朝一夕に小論文が書けるようになるわけではありません。
無責任な指導者や参考書では、「1週間前からでも対策は十分!」とうたうものがありますが、そんなことはなく、1週間では不十分だということを頭に入れておきましょう。
ただ完全に手遅れではなく、ノー勉強はもったいない
「じゃあ、もう手遅れ?今から対策してもムダなの?」かと言えば、そうではありません。
1週間前からできることはありますし、全く勉強をしないで試験本番に挑むというのは、とくに小論文ではもったいないです。
1週間前であろうと、きちんと対策を取って練習をすれば、やればやっただけの成果は出ます。
そしてきちんと対策を取って練習することで、合格圏内も狙えます。
下の対策で、1週間前の今からでもきちんと対策をしていきましょう。
ノー勉強できた場合の小論文、一週間前の対策

ここでは、今まで全く小論文の対策をしてこなかった人向けに、試験直前である1週間前からの具体的な対策方法について見ていきます。
過去問の把握
まず、大学入試、就職試験、昇進試験にかかわらず志望先の過去問を把握しましょう。
大学入試ならば赤本で、就職試験ならば志望企業のホームページの過去問などを見る、昇進試験ならば社内で同じ試験を過去に受けた人に聞いてみるなどします。
いずれでも分からない場合は、大学のパンフレットを見てそのビジョンや課題を把握する、就職試験ならば同業他社で公開されている過去問を見てみる、昇進試験ならば仕事上の経験であったり、昇進先や会社の問題や課題などを把握してノートなどにまとめてみます。
こういう作業をする中で、出そうな問題を予想してみましょう。
過去問のキーワードをもとにニュースや新聞をチェックする
把握した過去問や予想される問題をもとに、キーワードを設定して、そのキーワードに関連するニュースや新聞記事をチェックしてみましょう。
実際に書くネタになりそうなことはメモをしておきます。
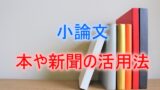
1~2日目、時間を計って模範解答を丸写しする
いきなりですが、模範解答を丸写しする際は、コピーでもよいので原稿用紙を用意して時間を計って写していきましょう。
これは小論文の書き方を習得すること、試験本番で想定される原稿用紙の形式に慣れること、時間内に書くことを意識するためのものです。
書き写す際は丁寧な字で書きましょう。
それと原稿用紙のタテ書き、ヨコ書きの形式は、過去問の問題文がタテ書きならばタテ書き形式の原稿用紙が多く、過去問の問題文がヨコ書きならば原稿用紙もヨコの形式が多いです。
ただし、入試の年度によって原稿用紙の書く形式は変わる場合があるので、タテ・ヨコ書き両方の形式で書き慣れておきましょう。
3~4日目、メモしたネタをもとに過去問などで書いてみる
ニュースや新聞記事を見てメモしたネタをもとに、過去問などで書いてみます。
できれば模範解答を写していない問題が望ましいですが、模範解答を丸写しした過去問でも、違う観点から書いてみるということもできるので、この段階では時間を意識しないで、とにかく指定文字数を書ききることを意識して練習しましょう。
あわせて読みたい
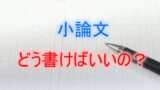
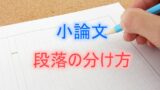
5~6日目、時間を計って練習問題で書いてみる
試験通りの制限時間と文字数で実際に書いてみます。
今までやってきたことを踏まえて、書いてみましょう。
あわせて読みたい

7日目、関連の問題で時間を計って書く、メモしたネタをもとに出そうな問題を予想する
試験直前の最終日は、過去問の形式や今まで集めたネタをもとに自分で問題を作成して、実際の試験時間や文字数を設定して書いてみましょう。
またメモしたネタをもとに、出そうな問題を予想しておきます。
そして、たとえ予想したものと異なる問題が出ても、今までの練習を信じ、軽く深呼吸するなど落ち着いて試験に挑みましょう。
とにかく小論文を毎日書く

1週間前という短期間で、決して欠かしてはダメなことについて見ていきます。短期間の対策でも合格を勝ち取りたいのならば、しっかり見ていきましょう。
書かない日を作ってはダメ
まず、これまで全く対策をしてこないで1週間前から練習し始めた人は、書かない日を作ってはダメだということです。
何か月も前から対策や書く練習をしてきた人はともかく、1週間前からの練習は不十分だということを自覚して、模範解答の丸写しでもよいので何かしら書く練習を毎日しましょう。
この直前期からの練習で、1~2日空けるだけで書く感覚は大きく鈍ってしまいます。
少し大変ですが「7日間、毎日書くなんて大したことない!」という気持ちで書く練習を怠らないようにしましょう。
書いたら必ず信頼できる大人の添削を受ける
そして、これが一番大切ですが、書いたら毎回必ず信頼できる大人の添削を受けてください。
学校の先生や身近な大人の人に頼んで、添削を受けましょう。
この直前期は、無料アプリ添削や他の添削サービスは使わずに、すぐフィードバックが返ってくる身近な人に頼んで、良かった点、改善点などを聞いて、次の答案に活かすことを繰り返してください。
小論文の基本も押さえておこう!
小論文の対策をこれまでしてこなかった人は、基本を押さえて書く練習をしていきましょう。
いくら書く練習をしても、基本が身についていないと内容以外で減点されてしまい非常にもったいないので、併せて押さえてくことをオススメします。

そして、たとえ直前期でもあきらめることなく練習を重ねて、「短いながらきちんと対策してきた!」という自信を持って試験本番に挑みましょう。
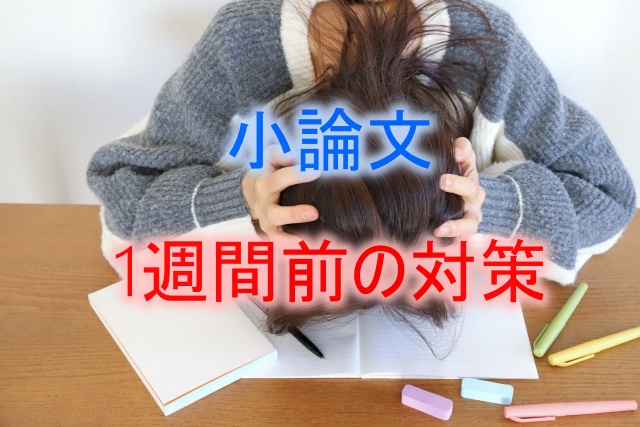
-500x336.png)

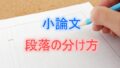

コメント