「テーマ型の小論文って何を書けばいいの?」「自由度が高すぎて逆に困る」そんな悩みを抱えていませんか?
テーマ型の小論文には明確な攻略法があり、与えられたキーワードから社会問題を見つけ出す手順を身につければ、どんなテーマでも自信を持って書けるようになります。
重要なのはテーマの意味を正確に把握し、出題者の意図を汲み取ることで、それを論理的に展開する力が合格への鍵となります。
本記事では、テーマ型の小論文の基本から具体的な書き方の手順、そして実際の例題と解答例まで、テーマ型小論文で高評価を得るための方法を詳しく解説しています。
関連記事
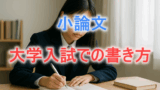
小論文の基本おさらい

設問型の小論文を書く前に、まずは小論文の基本を確認しておきましょう。
小論文と作文の違い、基本構成、そして論理的に書くためのポイントを理解することで、どんな形式の問題にも対応できる土台が築けます。
小論文の基本
まず小論文は、作文とは異なります。以下で小論文の基本について改めて確認しておきましょう。

書くルール
小論文の内容は良くても、書くルールを踏まえていないと減点され、最悪0点ということもあるので、以下で書くルールを確認しておきましょう。

原稿用紙の使い方
形式的なことですが、原稿用紙の使い方も小論文では採点対象になります。以下で原稿用紙の使い方についても改めて確認しておきましょう。
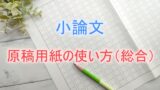
↓ ↓ ↓ 小論文試験に必須の一冊 ↓ ↓ ↓
小論文の基本から、試験を想定した
実践練習まで、この一冊で身に付きます!
この一冊で小論文のお悩みすべて解決!
\ Amazonで400冊突破!/
テーマ型の小論文の書き方
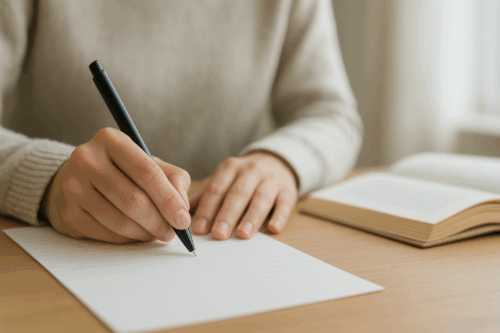
テーマ型小論文を攻略するには、まず問題の特徴を正しく理解することが大切です。
ここでは、テーマ型とはどんな問題なのか、テーマから何を読み取るべきか、そして具体的な書き方の手順について解説します。基本を押さえれば、どんなテーマが出題されても自信を持って書けるようになるでしょう。
テーマ型とは、どんな問題か
テーマ型小論文とは、短いキーワードや題材をもとに、自分の考えを論じる形式の問題です。
たとえば「空」「声」「食育」といった一つの言葉から論を展開させる問題や、「海・列車・感謝」のように三つのキーワードを組み合わせて書く三題噺(ばなし)型の問題があります。
また、写真や絵画が提示され、そこから読み取れることを論じるビジュアル型の問題も含まれるでしょう。
これらの問題は、課題文を読んで意見を述べる「課題文型」や、具体的な問いに答える「設問型」とは異なります。
テーマ型は自由度が高い反面、何を書けばいいのか迷いやすいのが特徴です。
- 設問型と混同されて指導されることもありますが、テーマ型では与えられた題材から自分で論点を見つけ出す力が求められます。
テーマは何か、何を求められているのか
テーマ型小論文で最も重要なのは、与えられたテーマが何を意味し、何を求められているのかを正確に把握することです。
たとえば「食育」というテーマなら、単に食事のマナーや栄養バランスについて書けばいいわけではありません。
現代社会における食の問題点や、教育としての食育の意義など、より深い視点が必要になるでしょう。
テーマを読み解く際は、そのキーワードから連想される社会的な課題や背景を考えます。
「なぜこのテーマが出題されたのか」「社会的にどんな問題と関連しているのか」という視点を持つことが大切です。
三題噺型の場合は、複数のキーワードに共通する社会的なテーマや、それらを結びつける論点を見つける必要があります。
出題者の意図を汲み取り、適切な方向性を定めることが合格への第一歩となります。
テーマ型の書き方
テーマ型小論文を書く際は、まずテーマから社会問題を考えることから始めましょう。
与えられたキーワードを手がかりに、それが現代社会のどんな課題と結びついているかを探ります。たとえば「声」というテーマなら、コミュニケーション不足や意見表明の重要性といった問題が見えてくるはずです。
次に「何が問題なのか」「なぜそれが問題なのか」を明確にします。
ここで注意したいのは、実際の現象と問題点を分けて考えることです。
例えば「SNSの普及」は現象であり、「対面コミュニケーションの減少による人間関係の希薄化」が問題点になります。現象をただ述べるだけでは小論文になりません。
問題点を特定したら、その原因や背景を掘り下げ、自分なりの解決策や意見を示します。
序論でテーマと問題点を提示し、本論で理由や具体例を展開、結論で自分の主張をまとめる三部構成で書けば、説得力のある小論文が完成するでしょう。
型にはめて書いてみる
実際に、以下のように小論文の書く型に当てはめて書いてみましょう。
はじめは型通りで構いませんが、問題に合わせて杓子定規に型を当てはめないで書くことがコツです。
その上で、以下のようにアウトラインを書いてから解答を書いていきます。(800字以下、800字以上を書くときでも使えます)
> 小論文・完全ロードマップ解説の《無料メルマガ登録はコチラ》から
例題と解答例

ここからは、テーマ型小論文の具体的な例題と解答例を見ていきましょう。
一つのキーワード型、三題噺型、絵の読解型という3つのパターンを取り上げます。それぞれの解答例を示しますので、構成や論の展開方法を参考にしてみてください。
例題1
問題:「空」というテーマについて、あなたの考えを800字以内で述べなさい。(新聞社 採用試験)
(解答例)
現代社会において、私たちは空を見上げる習慣を失いつつある。都市部では高層ビルが視界を遮り、多くの人がスマートフォンの画面に視線を落としたまま歩いている。この「空を見ない生活」は、現代人の心の余裕の喪失を象徴する深刻な問題だと考える。空を見上げる行為には、立ち止まって自分を見つめ直す意味がある。青く広がる空や流れる雲を眺めることで、思考の流れが変わり、新たな視点が生まれるのだ。
しかし現代社会では効率性が重視されるあまり、こうした一見無駄に見える時間が削られている。その結果、ストレスを抱え込みやすく、心の不調を訴える人が増加しているのが現状である。私自身、受験勉強に追われていた時期、空を見上げることで気持ちが落ち着いた経験がある。行き詰まったとき、ふと窓の外の空を眺めると、自分の悩みが小さく感じられた。空の広大さは、私たちに物事を俯瞰する視点を与えてくれるのだ。
この行為を持続させるには、意識的に空を見上げる習慣を取り入れることが有効である。たとえば通学路で信号待ちをする際、スマートフォンではなく空を見上げてみる。朝の空の色や雲の形を観察することで、季節の移ろいに気づき、自然とのつながりを実感できるだろう。学校でも、授業の合間に窓から空を眺める時間を意識的に設けることで、生徒たちの精神的なリフレッシュにつながるはずだ。
もちろんこの空を見上げる行為そのものが、すべて問題解決につながるわけではない。ただ空を見上げることは、単なる景色の鑑賞ではない。それは自分の内面と向き合い、心の平穏を取り戻すための大切な行為である。そのゆとりが問題解決の選択肢を広げ、解決の時間や方法などのヒントを与えてくれるだろう。忙しさに追われる現代人にこそ、立ち止まって空を見上げる時間が必要なのだ。(744字)
例題2
問題:「緑・朝・未来」という3つのキーワードをすべて用いて、あなたの考えを800字程度で述べなさい。(出版社 採用試験)
(解答例)
緑、朝、未来という3つの言葉には、希望と再生という共通のイメージがある。私はこれらのキーワードから、持続可能な社会の実現という現代的な課題を考えたい。現代社会では環境破壊が深刻化しており、特に森林の減少が問題となっている。緑は地球の肺とも呼ばれ、二酸化炭素を吸収し酸素を生み出す重要な役割を担っているのだ。しかし経済発展を優先するあまり、多くの緑が失われてきた。このままでは、未来の世代に豊かな自然環境を残すことができない。気候変動による異常気象も頻発しており、環境問題は待ったなしの状況である。
また朝という言葉は、一日の始まりであると同時に、新たな取り組みのスタートを象徴している。環境問題の解決には、今日という朝から行動を起こす必要がある。たとえば学校での植樹活動や、地域の緑化プロジェクトへの参加などが挙げられるだろう。小さな一歩でも、毎朝継続することで大きな変化につながるのだ。
私自身、地元の公園清掃ボランティアに参加した経験がある。朝早くから集まったメンバーと協力し、ゴミを拾いながら木々の手入れを行った。この活動を通じて、緑を守ることの意義を実感すると同時に、一人ひとりの行動が未来を変える力になると確信した。参加者の中には小学生もおり、若い世代が環境意識を持つことの重要性を感じた。
ただし、これらの活動は掛け声だけでやみくもに行えばよいわけではない。例えば緑を守るといっても、植樹でやたらに緑を増やせばよいものでもない。そこには適切な間引きやその地の環境に合わせた種類の植樹をする必要がある。そして緑を増やすなどの取り組みは地球のためではなく、人類にとっての環境を持続させる目的であることを忘れてはならない。そのうえで植樹や清掃といった身近な活動から、環境に配慮した消費行動まで、できることは数多くある。小さな努力の積み重ねこそが、持続可能な社会への道を開くのだ。(789字)
例題3
問題:下の絵を見て、そこから読み取れることについて、あなたの考えを800字で述べなさい。(大学入試)

(解答例)
この絵が描いているのは、現代社会におけるコミュニケーション不足の問題である。満員電車という密閉された空間で、人々は隣にいる人間ではなく、手元の画面に視線を注いでいる。物理的には近くにいながら、心理的には遠く離れている状況が表現されているのだ。スマートフォンの普及により、私たちは時間や場所を問わず情報にアクセスできるようになった。しかし、その便利さの裏で目の前の人との関わりが希薄になっている。電車内で偶然隣り合った人に関心を示すことはほとんどなく、誰もが自分の世界に閉じこもっているのが現状だ。
特に問題なのは、若い世代がデジタルコミュニケーションに依存しすぎている点である。SNSやメッセージアプリでのやり取りは増えているが、対面での会話が苦手になっている。相手の表情や声のトーンから気持ちを読み取る力が弱まり、その結果、誤解やトラブルが生じやすくなっているのだ。私自身も、友人との会話中にスマートフォンを見てしまい、相手を不快にさせた経験がある。
また、この絵からは孤独の問題も読み取れる。多くの人に囲まれているにもかかわらず、誰もが孤立している。現代人は人混みの中でも孤独を感じやすく、その孤独を紛らわすためにさらにスマートフォンに依存するという悪循環に陥っている。
この問題を改善するには、意識的にスマートフォンから離れる時間を作る必要がある。たとえば電車に乗っている間は画面を見ず、車窓の景色を眺めたり、周囲の人々を観察したりしてみる。そうすることで、リアルな世界への感受性が研ぎ澄まされていくだろう。学校でも、休み時間にスマートフォンを使わない日を設けるなど、対面コミュニケーションを促す取り組みが求められる。便利な道具に支配されるのではなく、道具を適切に使いこなす知恵が必要である。デジタルとリアルのバランスを保つことが、豊かな人間関係を築く鍵となるのだ。(781字)
小論文の対策は、以下の無料メルマガでも実施中↓↓↓

-500x336.png)


-500x336.png)
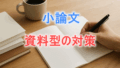
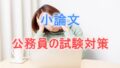
コメント