「小論文で論点がずれた…」と悩んでいませんか?
多くの受験生が直面するこの問題、実は解決法があります。
小論文の論点がずれる原因は、設問の誤解や知識不足、そして内容の広げすぎ・狭めすぎにあります。
本記事では「小論文の論点の見つけ方」を詳しく解説し、「小論文で論点がずれた」経験を持つあなたに具体的対策を提供します。
正しく論点を捉える方法を身につければ、設問の意図に沿った説得力のある小論文が書けるようになります。
論点がずれる失敗例や効果的な対処法を知って、小論文の苦手意識を克服しましょう。
今回学ぶこと
- 論点がずれる原因
- 正しい論点の見つけ方
関連記事
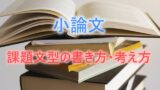
小論文の論点がずれたときの原因

小論文で論点がずれてしまう原因はいくつかあります。
多くの受験生が悩むこの問題は、正しく対処すれば必ず改善できます。
ここでは主な3つの原因と対策について詳しく解説します。適切な対策を理解して、説得力のある小論文を書けるようになりましょう。
設問を理解していない
小論文の論点がずれる最も基本的な原因は、設問そのものを正確に理解していないことです。
設問には「何について」「どのように」論じるべきかが明示されていますが、これを見誤ると的外れな解答になってしまいます。
例えば「インターネットをどのように利用すべきか」という問いに対して「インターネットを利用すべきかどうか」について論じるのは明らかなズレです。
設問を理解するポイントは、問われている内容を正確に把握することです。
「比較せよ」なら二つのものを対比し、「論じよ」なら自分の見解と根拠を示す必要があります。
問題文を何度も読み返し、キーワードに線を引いて問われていることを明確にしましょう。
設問の意図を正確に把握することが、論点がずれない小論文を書く第一歩となります。
設問の要求にこたえていない
問題の意図は理解していても、設問が求めている解答になっていないケースがよくあります。これは「何を答えるべきか」という設問の要求に応えていない状態です。
たとえば、「具体例を挙げて説明せよ」という指示があるのに、抽象的な説明だけで終わっていたり、「あなたの考えを述べよ」という問いに対して単なる一般論や事実の羅列だけになっていたりします。
設問の要求に応えるためには、問題文の指示語に注目することが大切です。
「どのように」「なぜ」「あなたの意見を」などの言葉が示す要求内容を明確にし、それに沿った回答を心がけましょう。
また、字数制限も重要な要求の一つです。設問が400字以内と指定している場合、その範囲内で核心をついた回答をすることが求められています。
設問をよく読み、何を問われているのかを正確に把握することが論点ずれを防ぐ鍵となります。
テーマや論点を正しく見つけられていない
小論文の題材となるテーマや本質的な論点を正しく見極められていないことも、論点ずれの大きな原因です。
例えば「情報社会における問題点とその対策」というテーマで、単にスマートフォンの便利さだけを述べるのは論点の取り違えです。
また、課題文がある場合、その中で本当に議論すべき中心的な問題点を見逃してしまうことも多いものです。
テーマや論点を正確に把握するには、問題文や課題文を読みながら問題の条件またはテーマと論点、結論の個所に線を引いたり、丸で囲み、読み返したときに一目で分かるようにすることです。
そして、「この問題は何について考えさせようとしているのか」という出題者の意図を想像することも大切です。
さらに、テーマについて異なる立場や視点からも考えてみることで、議論の核心に迫りやすくなります。論点を正しく見つけられれば、説得力のある一貫した小論文を書くことができるでしょう。
小論文の論点がずれる原因9事例

小論文で論点がずれる原因の典型的な9事例を見てみましょう。
| 番号 | 論点がずれる原因 |
|---|---|
| ① | 問題応答のズレ(問題を縮小してしまう) |
| ② | 論点のズレ(自分だけの経験を書く) |
| ③ | 論理のズレ(感想型) |
| ④ | 問題文の内容をムダに繰り返す |
| ⑤ | 事実を伝聞にしてしまう |
| ⑥ | 問題提起のズレ |
| ⑦ | 反論の再反論に根拠がない |
| ⑧ | ことわざ・格言は入れない |
| ⑨ | 熱意はいらない |
以下の問題と解答例を通して、どのような点に注意すべきかを考えていきます。失敗例を分析することで、自分が小論文を作成するときのミス防止にも役立ちます。
【問題】
環境問題への関心が世界的に高まる中、持続可能な社会の実現に向けて個人ができる取り組みが注目されています。一方で、個人の努力だけでは解決が難しい側面もあります。持続可能な社会を実現するために、私たちはどのような行動をとるべきでしょうか。あなたの考えを400字以内で述べなさい。
〔解答例〕
環境問題が深刻化していることは最近よく耳にするようになった。私は環境問題に取り組むべきだと思う。なぜなら地球環境を守ることは大切だからだ。
私は日頃からエコバッグを使っている。レジ袋をもらわないようにすることで、プラスチックごみを減らせるのではないか。また家族も同じようにエコバッグを使っている。
環境問題は個人で解決できるものではないのだろうか?いや、私は個人でも解決できると思う。確かに、大企業による環境破壊は問題だが、みんなが少しずつ努力すれば良くなるような気がする。「塵も積もれば山となる」ということわざがあるように。
私は将来、環境問題の研究者になりたいと考えている。そのために環境問題を学ぶカリキュラムが充実している貴学に入学して深く学び、社会に貢献したい。
① 問題応答のズレ(問題を縮小してしまう)
「私は環境問題に取り組むべきだと思う」という記述は、問題の本質を見誤っています。問題は「どのような行動をとるべきか」を問うているのに、「取り組むべきかどうか」という別の問いに答えています。このように問題の範囲を勝手に狭めると、的外れな回答になってしまいます。問われていることを正確に理解し、それに応える必要があります。
② 論点のズレ(自分だけの経験を書く)
「私は日頃からエコバッグを使っている」という個人的な体験のみに基づく説明は説得力に欠けます。小論文では、個人的な経験だけでなく、一般性のある事実や根拠を示すことが重要です。自分の経験を例として挙げるのは構いませんが、それがなぜ社会全体にとって意味があるのかを説明する必要があります。普遍的な視点からの議論を心がけましょう。
③ 論理のズレ(感想型)
「みんなが少しずつ努力すれば良くなるような気がする」という表現は単なる感想に過ぎません。「気がする」ではなく、なぜそう考えるのかの根拠を示すべきです。小論文では主観的な印象ではなく、論理的な思考過程と客観的な根拠が求められます。感想型の表現は説得力を大きく損ないます。
④ 問題文の内容をムダに繰り返す
「環境問題が深刻化していることは最近よく耳にするようになった」は問題文の内容を言い換えただけです。限られた字数の中で問題文の繰り返しは不要です。すでに共有されている前提を繰り返すのではなく、自分の主張とその根拠を述べることに紙幅を使うべきです。導入でも自分の立場を明確にすることから始めましょう。
⑤ 事実を伝聞にしてしまう
「環境問題が深刻化していることは最近よく耳にするようになった」という伝聞表現は小論文に適していません。小論文では「~らしい」「~と言われている」などの曖昧な表現ではなく、確かな事実として断定的に述べるべきです。伝聞表現は自分の主張に自信がないという印象を与えてしまいます。
⑥ 問題提起のズレ
「環境問題は個人で解決できるものではないのだろうか?」という問いかけは、元の問題設定にない論点です。問題は「どのような行動をとるべきか」を問うているのに、自分で異なる問題を設定しています。出題者が求めている問いに答えるべきであり、勝手に論点をずらすべきではありません。
⑦ 反論の再反論に根拠がない
「確かに、大企業による環境破壊は問題だが、みんなが少しずつ努力すれば良くなる」という部分は、反論に対する再反論が具体性を欠いています。なぜ個人の少しの努力が大企業の環境破壊に対抗できるのか、その仕組みや効果について具体的な説明がありません。反論を取り上げる場合は、それに対する再反論も説得力のあるものにする必要があります。
⑧ ことわざ・格言は入れない
「塵も積もれば山となる」ということわざを引用していますが、小論文では自分の言葉で論理的に説明することが求められます。ことわざや格言は自分の考えの代わりにはなりません。むしろ、安易に引用すると思考停止と見なされかねません。自分自身の言葉で論理的に説明する努力をしましょう。
⑨ 熱意はいらない
「私は将来、環境問題の研究者になりたいと考えている。そのために環境問題を学ぶカリキュラムが充実している貴学に入学して深く学び、社会に貢献したい。」という部分は志望理由書の内容です。小論文では設問に対する論理的な回答が求められており、受験意欲や将来の夢を述べる場ではありません。このような記述は論点ずれとなり、評価を下げる原因となります。
以上、論点がずれる原因の9事例でした。
「え~こんなも気をつけることがあるの?」と思うかもしれませが、どれも論点のズレの原因ですし、反対にこの9事例の失敗を踏まえておけば、論点を外さずに明確な小論文が書けるようになります。
その他、論点のずれに結びつく失敗

論点がずれる原因は他にもあります。
設問の要求を守らない以外にも、知識不足による誤解や思い込み、そして取り上げる内容の広げすぎや狭めすぎが論点のずれを引き起こします。
これらの失敗を防いで、的確な小論文を書いていきましょう。
知識不足による誤解や思い込み
知識不足は論点ずれの大きな原因です。
テーマに関する基礎知識がないまま執筆すると、誤った前提で議論を展開してしまいます。
例えば、環境問題について論じる際に「地球温暖化は科学的に証明されていない」という誤った認識から始めれば、その後の議論全体が説得力を失います。
また、用語の定義を誤解していることも致命的です。「少子高齢化」と「人口減少」を同一視したり、「グローバル化」を単なる「英語教育の強化」と考えたりすれば、議論の土台が崩れます。
さらに、時事問題について古い情報や一面的な理解しかないと、現状に即さない提案をしてしまいます。
こうした失敗を避けるには、日頃から多様な情報源に触れ、テーマについての基本的知識を整理しておくことが大切です。
特に受験では頻出テーマの基礎知識を押さえ、最新の動向も把握しておきましょう。
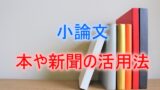
取り上げる内容の広げすぎ・狭めすぎ
論点をずらす別の失敗は、内容の範囲設定ミスです。
テーマを狭く捉えすぎると、本来必要な視点が欠け、一面的な議論になってしまいます。例えば「教育改革」というテーマで学校のICT環境整備だけを論じれば、教員の働き方や評価方法など他の重要な側面が抜け落ちます。
逆に広げすぎると、何について論じているのか焦点がぼやけ、深い考察ができなくなります。
また「食の安全」について書くつもりが、農業政策全般や世界の食糧問題まで広げてしまうと、本来のテーマに対する掘り下げが不十分になります。
適切な範囲設定のためには、与えられた字数制限を考慮し、テーマの中核となる要素を見極める必要があります。
まず序論で取り上げる範囲を明確にし、その枠組みの中で議論を展開することで、論点のずれを防ぐことができるでしょう。
小論文の論点の見つけ方

小論文を書く際に最も重要なのは、適切な論点を見つけることです。論点を正確に把握できなければ、いくら文章力があっても的外れな内容になってしまいます。
ここでは、さまざまな状況での論点の見つけ方について解説します。
問題文や設問の条件をよく読む
論点を見つける第一歩は、問題文と設問の条件を正確に理解することです。
多くの受験生が見落としがちなのが、設問に示された具体的な指示や条件です。
「〜の観点から論じなさい」「〜を踏まえて述べなさい」といった指示は、論点を絞り込む重要な手がかりとなります。
また、字数制限も内容の深さや広さに影響するため、800字なのか1200字なのかによって扱える論点の数や深さが変わってきます。
問題文を読む際は、キーワードに印をつけたり、設問の条件を書き出したりして、何について論じるべきかを明確にしましょう。設問の意図を正確に把握することで、採点者が求める内容に沿った小論文を書くことができます。
設問の読み取り方
課題文なしの場合
課題文がない場合は、与えられたテーマから自分で論点を設定する必要があります。
まず、テーマを複数の視点から考察し、問題の本質を見極めることが重要です。
例えば「環境問題」というテーマなら、経済的側面、社会的側面、技術的側面など様々な角度から検討します。
次に、現状分析を行い、そこから浮かび上がる課題や矛盾点を見つけましょう。この課題が論点となります。
さらに、自分の知識や経験を整理し、説得力のある具体例や根拠を準備します。
論点が定まったら「〜すべきか」「どのように〜すべきか」といった形で問いを立て、それに対する自分の立場を明確にします。
課題文なしの場合こそ、論点を絞り込み、深く掘り下げることが高評価につながります。
課題文ありの場合
課題文がある場合は、筆者の主張と論拠を正確に読み取ることから始めます。
課題文の構造を「問い」と「答え(結論)」に分解し、筆者がどのような問題提起をし、どのような結論に至ったのかを把握します。
次に、その主張を支える根拠や具体例に注目し、筆者の論理展開を追います。
この過程で、筆者が強調している部分や繰り返し言及している内容が論点のヒントになります。
また、接続詞(だが、でも、しかし、ただし、一方で、など)の前後も重要な論点が隠れていることが多いです。
筆者の主張に対して「賛成」か「反対」か、あるいは「部分的に賛成」なのかを決め、その立場から論を展開します。
また課題文の問題は、必ずしも賛否が示せるとは限らないので、課題文の内容を踏まえて書くようにしましょう。
そして課題文の内容を踏まえつつも、単なる要約にならないよう、自分の考えや新たな視点を加えることが大切です。
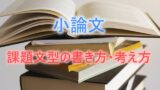
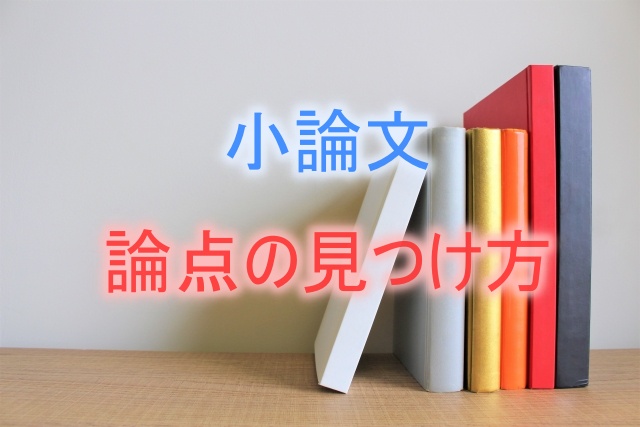
-500x336.png)

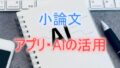

コメント