「小論文は『です・ます』と『だ・である』のどちらで書くべき?」と迷っていませんか?
実は小論文では、「です・ます」は基本使わず、「だ・である」調で統一するのが正解です。
丁寧に書こうとして「です・ます」を使ったり、謙虚さを表そうと「思う」という表現を入れたり、話し言葉の「だから」を使ったりすると、かえって説得力が弱まり減点の要因になります。
小論文は主張を強く伝える文章。断定的な「だ・である」調で書き、曖昧さを排除して言い切ることで文章に力が生まれます。
この記事では、小論文で使うべき表現と避けるべき表現を具体例とともに解説し、あなたの小論文の書く力を大きく向上させます。
今回学ぶこと
関連記事

小論文で、「です・ます」は基本使わない

他の文章で使えば、謙虚さや丁寧さを表せる敬体「です・ます」調は、小論文では基本的に使いません。
なぜ「です・ます」は使わないのかについて、詳しく見ていきましょう。
「です・ます」と「だ・である」の違い
まず文章の語尾が「です・ます」調は、敬体と言い丁寧な文末表現で文章を終えることができます。
例文
- 小論文は理由に基づいて、自分の考えを述べることが大切「です」。
- 率直な自分の考えを表現し「ます」。
一方、文章の語尾が「だ・である」調は、常体と言い断定的に物事を表現するときに使います。
例
- 小論文は理由に基づいて、自分の考えを述べることが大切「だ」。
- 率直な自分の考えを表現するべき「である」。
例外を除き「だ・である」で書く
小論文は、説得力が必要なので一部例外を除き「だ・である」調で書くことが基本です。
一部例外とは、問題文に「敬体で書きなさい」という指示があるときです。
また問題が作文を書かせる内容だあったり、「自分の両親に向けて手紙を書きなさい」など、明らかに「です・ます」の敬体で書いた方が良いときに限ります。
このような一部例外を除いては、「だ・である」調の常体文で書くようにしましょう。
ただ、作文の場合でも「両親に向けての手紙」といったもの以外は、常体文で書いても問題はないので、敬体で書く場合は超レアケースと考えても間違いありません。
「だ・である」を使う理由
「だ・である」調の常体を使うことは、説得力が必要な文章で力強さを表せることはもちろんですが、文字数の節約にもなります。
「です・ます」の敬体を使ってしまうと、使わなくても良いところに文字数を割いてしまい、自分の考えや具体例を書く文字数を少なくしてしまいます。
もっとも「です・ます」調で書いたから減点となるわけではありませんが、小論文では、デメリットの方が大きいです。
一見、「だ・である」調は丁寧な印象で使った方が良いと思われがちですが、小論文ではムダに文字数を使ってしまう、そのうえ使ったところで採点者の印象は何ら変わらない無益なものと覚えておきましょう。
そして文体は必ず統一させます。
「です・ます」調に「だ・である」調が混ざっていると、形式上的な部分で減点されます。
これはもったいないので、小論文では「だ・である」調で統一して書くことを徹底しましょう。
小論文で「思う」は使わない

「思う」という言葉も、文章で使うと一見「独善的でない自分の謙虚さ」を表すために使われがちですが、小論文では使うことを避けましょう。
その理由を以下で詳しく見ていきます。
「思う」を使わない理由
作文では自分の感情を表現するために「思う」という言葉を使っても良いですが、理由をもとに自分の意見を表現する小論文で使うと、その主張が弱くなってしまいます。
上の例でも、せっかく途中まで力強く自分の意見を言っているのに、最後の「思う」が曖昧さや主張の弱さにつながる残念な文章になっています。
自分では謙虚さで書いたつもりでも、採点者からすると「思う?あなたの感想?」と印象づけられてしまいます。
かえって印象をよくないものにするところで謙虚さは必要ありません。
「思う」は「~である」「~と考える」に言い換えます。
下の記事でも、小論文の評価基準をおさらいしておきましょう。
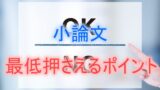
言い切る
上の「思う」という言葉に関連しますが、小論文では言い切るようにしましょう。
「思う」「感じる」「かもしれない」という言葉を使わずに、特に自分の意見や具体例を書くときは「だ・である」調で書いていきます。
自分の意見ではなく、予想される反論や他人の見解などを挙げるときは「~という見方がある」「~かもしれない」「~と思われる」と使っても良いですが、自分の意見やそれを裏づける具体例または理由などを挙げるときは、言い切るようにしましょう。
その他、使わない言葉
その他、使ってしまうと減点になる言葉は以下で押さえておきましょう。
小論文で「だから」も使わない

つい使ってしまいがちですが、小論文で「だから」などの話し言葉は使いません。話し言葉や流行語などは言い換えて使います。以下で詳しく見てきましょう。
NGワードは言い換える
「だから」「なので」というのは話し言葉で、小論文で使うと減点になります。
「したがって・よって・以上より・ゆえに・それゆえ」といった書き言葉に言い換えて使いましょう。
小論文で使える接続詞
使ってはいけない言葉を書いてきましたが、反対にこの言葉を使えると小論文の文章が引き締まり、印象が良くなる接続詞を以下で紹介します。
このようにNGワードを使ってしまうと小論文に締まりがなく印象が悪くなり、反対に適切な言葉を使うと文章に締まりが出て採点者の印象も良くなります。
したがって、受験生のみなさんも小論文で書く言葉を正しく使って好印象、合格できる小論文を目指しましょう。
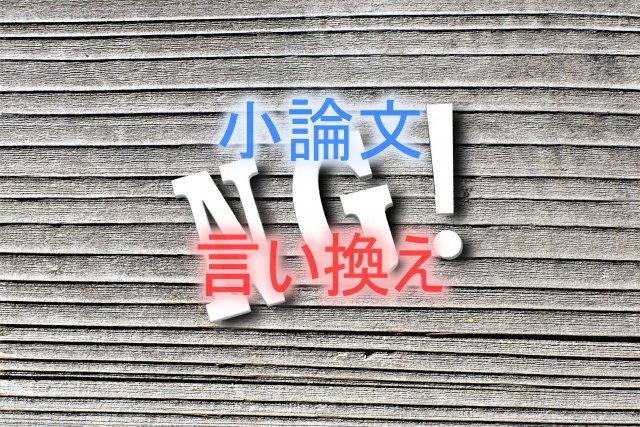
-500x336.png)

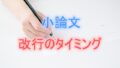

コメント