小論文試験で大阪万博がテーマに出題されたらどう書けばいいのか悩んでいませんか?
大阪万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、SDGsや持続可能な社会への問いかけを含む重要なテーマです。
今年(2025年)の4月から開催された大阪・関西万博も10月13日で閉幕します。
本記事では、大阪万博を題材にした小論文の書き方、予想されるテーマ、社会問題との関連性を徹底解説します。
環境問題から経済効果、文化的意義まで多角的な視点で考察し、志望分野別のアプローチ法も紹介。
大阪万博小論文の課題に立ち向かうための具体的なヒントが満載です。受験を控えた皆さんの不安を解消し、説得力ある小論文を書くためのポイントをお伝えします。
関連記事
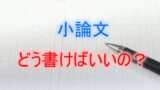
大阪万博を小論文の観点から見る

大阪万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をメインテーマに掲げ、SDGsの達成や持続可能な社会の実現に向けた様々な取り組みが計画されています。
小論文では、このテーマに関連した社会課題や未来展望について論じる問題が出題される可能性が高いでしょう。
以下では、受験生が押さえておくべき重要なポイントを解説します。
大阪・関西万博のテーマ
大阪・関西万博の「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマは、単なるキャッチフレーズではなく深い意味を持っています。
このテーマは、個人が自分らしい生き方を追求できる社会と、それを支える持続可能なシステムを国際社会が共に創造していくことを目指しています。
万博では「すべてのいのちが輝く未来」に向けて、世界中の人々が「幸せな生き方とは何か」を考え、アイディアを出し合う場が提供されるのです。
このテーマは現代社会が直面する多くの課題(格差、環境問題、テクノロジーの進化と人間性の共存)に対する解決策を模索するものであり、小論文ではこれらの視点から自分の考えを論理的に展開することが求められるでしょう。
SDGsの達成目標
大阪・関西万博は、SDGs(持続可能な開発目標)達成への重要な節目として位置づけられています。
万博開催から5年後の2030年がSDGsの達成目標年であることから、この国際イベントは持続可能な未来社会への具体的なアクションを促進する場となります。
万博では、環境保全、貧困撲滅、教育の質向上、ジェンダー平等など17の目標達成に向けて、世界中から集まる人々が新たなアイデアを交換し、革新的なソリューションを生み出すことが期待されています。
小論文では、特定のSDGs目標を取り上げ、大阪・関西万博がそれにどう貢献できるのか、またその目標達成のために私たち一人ひとりができることは何かについて論じる問題が予想されます。
大阪万博の課題を小論文で探る

大阪万博は単なるイベントではなく、社会的・文化的・経済的に多くの側面を持つテーマです。
小論文では、その多面性を捉えつつ、開催の意義から課題、将来への影響まで論理的に考察することが求められます。
以下では、小論文で取り上げるべき重要な観点を解説します。
開催の意義
大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、人間一人ひとりの可能性を最大限に発揮できる社会の実現を目指しています。
この万博は単なる展示会ではなく、SDGs達成に向けた国際的な取り組みの一環として位置づけられています。
2025年という開催年は、2030年のSDGs目標達成の5年前という重要な時期に当たり、世界の叡智を結集して持続可能な社会への道筋を示す機会となるでしょう。
また、1970年の大阪万博から約半世紀を経て再び関西で開催されることで、日本の技術力や文化を世界に発信する場としても大きな意義があります。
未来社会の実験場としての役割も期待されており、Society 5.0の実現に向けた具体的な取り組みが展開される予定です。
開催のメリット・デメリット
大阪・関西万博の開催には様々なメリットがあります。
まず、約3兆円の予算計上による経済効果が見込まれ、観光業の活性化や雇用創出につながるでしょう。
また、万博を契機としたインフラ整備が進み、大阪の都市機能が向上します。国際的な交流の場としても機能し、日本の存在感を高める効果も期待できます。
一方で無視できないデメリットも存在します。
開催地である夢洲は生物多様性のホットスポットとして認識されており、自然環境への影響が懸念されています。
市民団体の調査では希少種も発見されており、開発と環境保全のバランスが問われています。
また、巨額投資の費用対効果や、短期的な経済効果に終わらない持続的発展の実現も課題です。
さらに、埋立地という立地特性から、災害時の安全性についても慎重な検討が必要です。
そして、オリンピックや国民スポーツ大会などの大きなイベントが開催されるとき、よく「経済効果が〇億円」と言われますが、いったい誰にとっての経済効果なのか、開催地や開催国の国民にとって意義があるのかといったことも議論されるべきでしょう。
課題
大阪・関西万博の成功に向けては、いくつかの重要な課題があります。
第一に、環境アセスメントの適切な実施が挙げられます。開催地の夢洲は廃棄物処分場として埋め立てられた土地であり、環境への配慮が不可欠です。
市民団体からは「持続可能性評価」の導入が提案されていますが、現状では十分に反映されていない状況です。
第二に、SDGsの理念を実質化する運営方法の確立が求められます。
単にテーマとして掲げるだけでなく、万博自体の運営においても持続可能性を体現する必要があります。
第三に、多様なステークホルダーとの合意形成プロセスの構築も重要です。行政、企業、市民団体、地域住民など様々な立場の人々の意見を取り入れながら進めることで、真に社会に価値をもたらすイベントとなるでしょう。
| 課題 | 内容 | 背景・現状 | 求められる対応 |
|---|---|---|---|
| 環境アセスメントの適切な実施 | 開催地の夢洲は廃棄物処分場として埋め立てられた土地であり、環境への配慮が不可欠 | 市民団体からは「持続可能性評価」の導入が提案されているが、現状では十分に反映されていない | 環境影響評価の範囲拡大と、生物多様性保全への具体的取り組み |
| SDGsの理念の実質化 | 運営方法の確立が求められる | 単にテーマとして掲げるだけでは不十分 | 万博自体の運営においても持続可能性を体現する実践的アプローチ |
| 多様なステークホルダーとの合意形成 | 行政、企業、市民団体、地域住民など様々な立場の人々の意見を取り入れるプロセスの構築 | 現状では十分な合意形成プロセスが確立されていない | 多様な意見を取り入れる参加型の意思決定システムの導入 |
これらの課題解決は、万博の成否を左右する鍵となります。
開催後の影響
大阪・関西万博の開催後には様々な影響が予想されます。
最も重要なのは「レガシー」と呼ばれる万博の遺産をいかに活用するかという点です。過去の万博では、会場跡地が有効活用されず放置されるケースもありました。
大阪・関西万博では、開催前から「ポスト万博」を見据えた計画が必要です。
具体的には、会場となる夢洲の継続的な利用方法、展示された技術やアイデアの社会実装、国際的なネットワークの維持発展などが課題となるでしょう。
万博の象徴である周囲2kmの大屋根リングは北東200mを残して解体され、その200mのリングの一部は展望台としての活用が検討されています。しかし保存費に10年間で約55億円かかると試算され、入場料の徴取やクラウドファンディングなどの活用が挙げられています。
また、万博を通じて醸成された「いのち輝く未来社会」への意識や取り組みを一過性のものとせず、社会全体に定着させることも重要です。
SDGsの達成年である2030年に向けたマイルストーンとして、万博での成果を次の行動につなげる仕組みづくりも求められます。
大阪・関西万博が単なるイベントではなく、持続可能な社会への転換点となるかどうかは、この「開催後」をどう設計するかにかかっています。
大阪万博での小論文の予想テーマ

大阪万博をテーマにした小論文では、様々な角度からの問いが想定されます。
持続可能性、国際交流、科学技術の発展など、万博が包含する多様な側面から出題されるでしょう。
ここでは、頻出しそうなテーマや具体的な予想問題、志望分野別のアプローチを紹介します。
テーマ一覧
大阪・関西万博に関連する小論文のテーマは多岐にわたります。
メインテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を軸に、持続可能な開発目標(SDGs)の達成や未来社会のあり方について問われる可能性が高いでしょう。
具体的には、環境問題と経済発展の両立、先端技術と人間性の共存、グローバル化と地域アイデンティティの調和などが挙げられます。
また、1970年の大阪万博との比較から見る日本社会の変化や、ポストコロナ時代における国際イベントの意義についても注目されます。
さらに、万博の開催による地域活性化や社会インフラの整備、文化・観光資源としての価値など、地域社会への影響も重要なテーマとなるでしょう。
これらのテーマに対して、多角的な視点からの考察と、自分なりの問題意識を反映させた論述が求められます。
予想問題
【例題1】大阪・関西万博の開催は、持続可能な未来社会の実現にどのように貢献できるか、具体例を挙げて論じなさい。
【例題2】大阪・関西万博が地域経済にもたらす効果と課題について、あなたの考えを述べなさい。
【例題3】大阪・関西万博を通じた国際交流は、日本社会にどのような変化をもたらすと考えるのかを述べなさい。
【例題4】伝統と革新のバランスを考慮しながら、大阪・関西万博で日本の文化をどのように発信すべきか論じなさい。
これらの問題では、万博の社会的・経済的・文化的側面に着目し、自分なりの視点で論理的に展開することが重要です。
単なる一般論ではなく、具体的な事例や数値を用いながら、説得力のある論述を心がけましょう。
また、問題提起から解決策の提案まで含めることで、思考の深さと広さを示すことができます。
志望学部や志望企業の業種の観点から考える
志望する学部や業種によって、大阪万博をテーマにした小論文の切り口は変わってきます。
経済学部志望者なら、万博の経済効果分析や観光産業への影響、投資対効果の観点から論じると良いでしょう。
3兆円を超える予算の使途や、イベント後の経済的レガシーについての考察も効果的です。
工学部や情報系学部志望者は、万博で展示される先端技術や、Society 5.0の実現に向けた取り組みに焦点を当てると良いでしょう。
AIやロボット技術、スマートシティ構想などと万博の関連性を論じることができます。
環境系や社会学系の学部志望者は、開発と環境保全のバランスや、持続可能な社会づくりへの提言が適しています。
特に夢洲の生物多様性保全と開発のジレンマについて掘り下げると独自性が出せるでしょう。
企業志望者も業種に応じたアプローチが効果的です。
観光・サービス業なら来場者体験の向上策、メーカーなら出展技術の社会実装、建設業なら環境配慮型インフラの提案など、専門性を活かした論述が評価されます。
大阪万博から見る社会問題を小論文で考える

大阪万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」には、現代社会が抱える様々な課題への問いかけが含まれています。
小論文では、このテーマを深く掘り下げることで、独自性のある論述が可能になります。
ここでは、万博から社会問題を考える際の具体的なアプローチ方法を解説します。
考え方の手順
大阪万博から社会問題を考える際は、まず多角的な視点で捉えることが重要です。
はじめに万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」が内包する意味を分解してみましょう。
「いのち」は人間だけでなく動植物や生態系全体を、「輝く」は幸福や可能性の発揮を、「未来社会」は持続可能な次世代の生活様式を指しています。
次に、このテーマに関連する具体的な社会課題を洗い出します。
環境問題(気候変動、生物多様性)、格差問題(経済的・教育的格差)、テクノロジーの進化に伴う課題(AI倫理、プライバシー)などが挙げられるでしょう。
これらの課題について、現状分析→原因究明→解決策提案という流れで整理します。
特に大阪万博が掲げるSDGsとの関連性に着目すると、国際的な文脈の中で論じることができます。
最後に、万博というイベントがこれらの課題解決にどう貢献できるかという視点で考えをまとめると、説得力のある小論文になるでしょう。
当事者意識を持つ
大阪万博をテーマにした小論文では、単なる第三者的な分析ではなく、当事者意識を持った論述が評価されます。
万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」は、その「デザイン」という言葉が示すように、私たちが主体的に創り上げていくものだからです。
例えば、環境問題を取り上げる場合、夢洲の生物多様性ホットスポットとしての価値と開発のバランスについて、自分がその決断に関わるとしたらどう判断するかという視点で考えてみましょう。
また、万博で議論される「幸せな生き方」について、自分自身の価値観や生活スタイルと照らし合わせて考察することも重要です。
さらに、万博後のレガシー活用や地域への影響についても、将来その地域で暮らす可能性のある一人として意見を述べることで、説得力が増します。
小論文では「〜べきである」という一般論よりも、「私は〜と考える」という主体的な意見表明のほうが読み手に強い印象を与えます。
万博というグローバルなテーマを自分事として捉える姿勢が、小論文の質を高める重要な要素となるでしょう。
自分の普段の生活にどう関わるのかを考えてみる
大阪万博のテーマを自分の日常生活と結びつけて考えることで、小論文に具体性と説得力を持たせることができます。
万博が掲げる「いのち輝く未来社会」は遠い理想ではなく、私たちの日々の選択や行動の積み重ねから実現されるものだからです。
例えば、SDGsの達成を目指す万博の理念は、私たちの消費行動や資源利用と直結しています。
毎日使うプラスチック製品の選択、食品ロスへの対応、エネルギー使用の工夫など、身近な行動がどう未来社会につながるかを考察してみましょう。
また、万博で紹介される先端技術が、将来の働き方や学び方をどう変えるかも、自分の将来設計と関連づけて論じることができます。
さらに、万博への参加方法を考えることも有効です。
単なる見学者ではなく、ボランティアや情報発信者として関わる可能性、あるいはアイデアコンテストなどを通じて自分の考えを提案する機会などを想像してみましょう。
こうした具体的なつながりを意識することで、万博と自分を隔てる心理的距離が縮まり、より生き生きとした小論文を書くことができるでしょう。
とはいえ、万博の開催と自分の普段の生活とを結びつけるのは難しいですよね。
まずはインターネット上でもよいので万博関連のニュースを見る、大阪府など公的機関が発信している万博のSNS情報などを見ることから始めて、少しでも普段の生活と関りのありそうなことを探してみるとよいでしょう。

-500x336.png)



コメント