「課題文型の小論文の書き方って何から始めればいいの?」
「踏まえ方って、どうすること?」と悩んでいませんか?
課題文型小論文の書き方は実にシンプルです。
まず課題文を踏まえるとは、課題文の内容を理解し自分の意見の出発点にすること。
小論文の課題文型での書き出しでは、まず筆者の主張に触れ、それに対する自分の立場を示すのがポイントです。
本記事では、課題文型小論文の書き方として、要約がある場合とない場合の対応法、800字の効果的な構成法など、実践的なテクニックを解説します。
採点者に「この受験生は課題文をしっかり理解している」と思わせる方法を身につけましょう。
今回学ぶこと
関連記事

小論文の課題文型での踏まえ方

課題文がある小論文の場合、その課題文の主張や論点を理解し、自分の意見の出発点として活用することが求められます。
単に与えられたテーマについて自由に論じるのではなく、課題文との関連性を明確に示しながら書いていく必要があります。
| 項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 課題文を踏まえる基本 | 課題文の内容を自分の論の出発点とする | • 課題文の主張を正確に理解する
• 自分の立場(賛成・反対・一部同意など)を明確にする • 踏まえ方の例:「筆者の〇〇という主張から、私は△△と考える」 |
| 課題文理解の示し方 | 課題文の理解度をアピールする効果的な方法 | • 重要な論点や主張を自分の言葉で要約する
• 重要なキーワードを適切に使用する • 課題文の主張に対する評価を加える • 論理展開や事例にも触れる |
| 要約がある場合の対応 | 問題に要約がある場合の活用法 | • 要約を活用して論を展開する
• 文章全体の把握 → 本文の詳細理解の順で読む • 要約と本文の両方を参照しながら論を展開する |
| 要約がない場合の対応 | 自分で課題文の核心を見極める方法 | • 筆者の主張や中心的論点を特定する
• 主張を支える根拠や例示を把握する • 冒頭と結論部分に特に注目する |
| 書き出しの方法 | 効果的な小論文の書き出し方 | • 要約が求められる場合:中心的論点を簡潔にまとめる
• 要約がない場合:課題文の主張に触れてから自分の意見へ |
| 避けるべきこと | 減点につながる可能性がある行為 | • 課題文の内容を完全に無視する
• 単なる引用や丸写しに終始する • 課題文との関連性を示さない |
上記をもとに、効果的な課題文の踏まえ方について詳しく解説します。
課題文の踏まえ方
課題文を踏まえるとは、その内容を自分の論の出発点とすることです。
もっと簡単に言うと「課題文の内容をしっかり理解しているよ」と採点者に示すことです。
まず課題文の主張を正確に理解し、それに対する自分の立場(賛成・反対・一部同意など)を明確にします。
例えば「〇〇との筆者の主張から、私は△△と考える」というように、課題文との関係性を示すことが重要です。
課題文の内容を完全に無視して自分の意見だけを述べるのは避けましょう。
答案の冒頭部分で課題文の主張や課題文の内容に触れ、それを受けて自分の意見を展開すると、課題文を踏まえていることが明確になります。
課題文を踏まえることで、論点がぶれず、採点者に「問題の意図を理解している」という印象を与えることができます。
↓ ↓ ↓ 小論文試験に必須の一冊 ↓ ↓ ↓
小論文の基本から、試験を想定した
実践練習まで、この一冊で身に付きます!
この一冊で小論文のお悩みすべて解決!
\ Amazonで400冊突破!/
課題文を理解していることを示す
課題文を理解していることを示すには、いくつかの効果的な方法があります。最も基本的なのは、課題文の重要な論点や主張を自分の言葉で簡潔に要約することです。
ただし、単なる引用や丸写しは避け、自分の理解として表現しましょう。
また、課題文で使われている重要なキーワードを適切に用いることも効果的です。
さらに、課題文の主張に対する自分の立場を明確にし、「筆者の〇〇という考えは、△△の点で重要である」など、評価を加えることも理解を示す方法です。
課題文の論理展開や事例についても触れると、より深い理解を示すことができます。これらの工夫により、採点者に「課題文をしっかり読み込んでいる」という印象を与えることができるでしょう。
要約がある場合
課題文の要約が問題にある場合は、その要約を活用して論を展開することが効率的です。
要約をすることで課題文の内容が凝縮されるため、論点を把握しやすく、自分の意見の基盤として利用できます。
要約をする場合の課題文の読み方は、まず文章の全体像を把握し、次に本文を詳細に読んで理解を深めることです。
その上で、「筆者は〇〇と主張しており、本文では△△という事例で説明している」というように、要約と本文の両方を参照しながら自分の論を展開すると、課題文を十分に理解していることをアピールできます。
要約の方法については以下の記事もご覧ください。

要約がない場合
要約がない場合は、自分で課題文の核心をみる必要があります。
まず課題文を読み、筆者の主張や中心的な論点を特定しましょう。重要なポイントには印をつけたり、メモを取ったりすると良いでしょう。
次に、その主張を支える根拠や例示も把握します。そして、課題文の冒頭と結論部分に特に注目し、筆者の意図を正確に理解することが大切です。
自分の答案では、「本文では〇〇という問題提起がされており、筆者は△△と主張している」というように要点を整理して示すと効果的です。
このプロセスを通じて、課題文の論点を的確に把握し、それを踏まえた論述ができれば、要約がなくても十分に課題文を活用した小論文を書くことができるでしょう。
小論文の課題文型での書き出し

課題文型小論文の書き出し方は、合格への重要なポイントです。適切な書き出しは、あなたが課題文を理解していることを示すだけでなく、論理的思考力も伝えることができます。
課題文の内容や設問の形式によって書き出し方が変わることもあるため、状況に応じた効果的な導入方法を身につけましょう。
要約が求められている場合
要約が求められている場合は、まず課題文の中心的な論点を簡潔にまとめることから始めましょう。
重要なのは、筆者の主張を自分の言葉で的確に捉えることです。例えば「課題文では、少子高齢化の原因として女性の社会進出や医療の進歩による寿命の延長が挙げられている」のように、キーワードを用いながら要点を示します。
ただし、単なる言い換えや引用の羅列にならないよう注意が必要です。
要約部分は、指定文字数にしたがって全体の1/4程度に収め、残りのスペースで自分の意見を展開できるようにしましょう。
要約と自分の意見の区別が明確になるよう、「筆者は〇〇と主張している。これに対して私は…」といった接続表現を使うと効果的です。

要約がない場合
要約が求められていない場合でも、最初に課題文の主張に触れることで、課題文を理解していることを示しましょう。
「本文で述べられているように、現代社会では〇〇という問題が深刻化している」といった書き出しを、一文でもよいので書くと、スムーズに自分の意見へと移行できます。
ただし、課題文の全内容を細かく説明する必要はありません。(下記も参照)
筆者の中心的な主張や、自分の意見と関連する部分に絞って言及するのが効果的です。
例えば「筆者は環境問題について〇〇と指摘しているが、私はこの視点に加えて△△という観点も重要だと考える」のように、課題文への理解を示しつつ、自分の論点を提示することで読み手の関心を引きつけることができます。
字数が800字のときの書き始め
800字という限られた字数の小論文では、冒頭の書き出しを簡潔にまとめることが重要です。
導入部分は全体の約1/4以下(200字以下)に収め、残りを自分の意見の展開と結論に充てるバランスが適切です。
効果的な書き始めとしては、「本文では〇〇という問題について△△という見解が示されている。この主張は□□の点で重要だと考える」のように、課題文の要点と、それに対する自分の立場を明確に示す方法があります。
書き出しが長すぎると、自分の意見を十分に展開できなくなるため注意が必要です。
また、段落構成は、「導入(課題文の理解)→自分の意見の提示→具体例や根拠の説明→結論」という4段落構成が800字の小論文では読みやすく、分かりやすい印象を与えることができるでしょう。
課題文型小論文の書き方、考え方

課題文型小論文は、与えられた文章を読解し、それに対する自分の意見や考えを述べることがポイントです。
合格点を得るためには文章の正確な理解と論理的な意見の展開が求められます。以下では、課題文型小論文を効果的に書くための重要なポイントを解説していきます。
まず出題の意図を読み取る
課題文型の小論文で合格点を得るための第一歩は、出題の意図を正確に把握することです。出題者は何について書かせたいのか、どのような力を測っているのを読み取る必要があります。
まず設問文をよく読み、求められている論点や文字数を確認しましょう。
課題文を読む前に設問を確認することで、重要な箇所に注意を向けながら効率的に読み進めることができます。
また、下線部がある場合はその前後の文脈を特に注意深く読み、出題者が焦点を当てている論点を見逃さないようにしましょう。出題の意図を正確に理解することで、的外れな内容を書いてしまう失敗を防ぐことができます。
次に筆者の主張を踏まえる
課題文の筆者が何を主張しているのかを正確に理解することは小論文作成の基礎となります。
筆者の主張は通常、序論や結論部分に明示されていることが多いですが、文章全体を通して展開されている場合もあります。
キーワードや繰り返し登場する概念に注目し、筆者の価値観や立場を把握しましょう。
また、筆者が用いる具体例や論拠にも注目すると、主張の本質がより明確になります。
筆者の主張を正確に理解したら、それを自分の言葉で簡潔にまとめる練習をしましょう。まずは過去問の出典文章や新聞記事の内容を要約するなどして、自分の意見を書いてみます。
この練習を通じて、課題文の本質を捉え、それに対する自分の意見を構築するための土台を作ることができます。
筆者の主張に対する自分の意見を述べる書き方
筆者の主張を理解した後は、それに対する自分の意見を論理的に展開します。
まず結論として自分の立場を明確に示し、次にその理由を述べます。「私は筆者の〇〇という主張に賛成/反対である。なぜなら…」という形で書き始めるとよいでしょう。
理由の説明では、課題文に書かれていない具体的な事例や経験、統計データなどを用いて説得力を高めることが重要です。
単なる感想や印象ではなく、論理的な根拠に基づいた意見を展開しましょう。
また課題文の内容に賛成や反対で答えられない場合もあるので、注意してください。
最後に再度自分の結論を述べて締めくくりますが、単に冒頭の表現を繰り返すのではなく、議論を通じて深まった理解を反映させた表現にすると効果的です。
> 小論文・完全ロードマップ解説の《無料メルマガ登録はコチラ》から
課題文を参考にしながら自分の意見を述べる書き方
課題文は単なる読解対象ではなく、自分の意見を展開するための有益な材料です。
課題文から得た知識や視点を活用しながら、自分の考えを発展させましょう。
「課題文では〇〇と述べられているが、この点について私は…」というように、課題文の内容を参照しながら論を進めると読み手に伝わりやすくなります。
また、課題文の中の例示や論点を発展させて、現代社会の問題や自分の経験と関連付けることも効果的です。
ただし、課題文の内容を単に要約するだけにならないよう注意し、必ず自分独自の視点を加えましょう。
自分独自の視点というのは、課題文の内容に関連して課題文に書かれていないあなたの知っていること経験したことをもとに考えることです。
こうして課題文の内容と自分の意見をバランスよく反映させることで、読み手に「課題文をしっかり理解した上で、独自の思考を展開できる能力がある」ことを示せます。
課題文の内容を否定しない
これは独自の視点を持つとついやってしまいがちですが、課題文の内容を全面的に否定することは避けるべきです。
課題文は厳選された文章であり、何らかの価値や意義があると判断されているためです。
たとえ筆者の主張に同意できない部分があっても、まずはその価値を認めた上で、自分の異なる視点を提示するようにしましょう。
「筆者の〇〇という指摘は重要だが、さらに考慮すべき点として…」というように、課題文の内容を理解する姿勢を示しながら議論を展開します。
また、課題文の一部に同意し、別の部分については異なる見解を示すというバランスの取れた書き方も効果的です。課題文の内容に理解を示しつつ、自分の考えを述べることで、批判的思考力と柔軟な思考態度の両方を示すことができます。
「課題文を踏まえる」といった小難しい言葉を使われると、「よく分からん難しいことだ」と思いがちですが、実際に課題文の内容を理解して小論文を書くことは全く難しいことではありません。
この記事を読んでいるみなさんも、過去問などの課題文を読んで、どんどん小論文の練習をしていきましょう。
小論文の対策は、以下の無料メルマガでも実施中↓↓↓
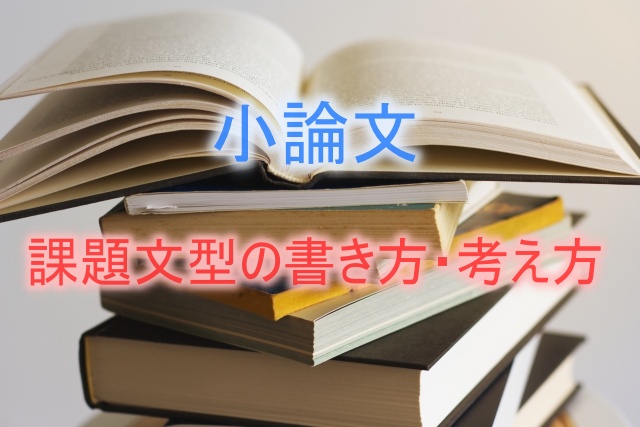
-500x336.png)


-500x336.png)
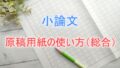

コメント