文学部の志望理由書の書き方が分からず悩んでいませんか?
「800字も何を書けばいいか分からない」「どう書けば合格できるのか不安」そんな悩みを抱える高校生も多いでしょう。
この記事では、志望理由書の書き方の基本から、大学・文学部の800字での志望理由書 の書き方を例文つきで詳しく解説します。
さらに、志望理由書 合格例を分析して分かった成功のポイントも紹介。本記事の方法で志望理由書を作成すれば、合格への道筋がはっきり見えるはずです!
関連記事

大学入試の志望理由書の書き方(基本)

志望理由書は大学入試における重要書類の一つで、総合型選抜や学校推薦型選抜では、ほぼ全ての大学で提出が求められます。
この書類は一次選考の書類審査で合否を左右するだけでなく、面接試験でも活用されるため、入試全体の結果に大きな影響を与えます。
志望理由書の書き方の基本
志望理由書では、「なぜその大学・学部を選んだのか」という具体的な理由、「なぜその学問分野を志望するのか」を自身の体験や価値観と結びつけた説明、「入学後の学生生活と卒業後の将来ビジョン」という3つの要素を明確に示す必要があります。
これらを一貫性を持って組み立てることで、説得力のある志望理由書が完成するでしょう。
大学側は志望理由書を通じて、受験生の過去の実績、入学後の明確な目標、そして卒業後の進路と社会貢献への意欲を評価しています。
単に「興味があるから」といった抽象的な表現ではなく、その大学の特色やカリキュラム、教授陣の研究内容などを踏まえた具体的で説得力のある動機を述べることが合格への鍵となります。
書き方の基本については、以下も参照。
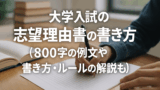
大学の志望理由書、文学部での800字例文

文学部の志望理由書では、単に「本が好きだから」という理由だけでは不十分です。
なぜその大学の文学部で学ぶ必要があるのか、文学研究を通してどのような社会貢献を目指すのかを具体的に示すことが重要になります。
なぜ、その大学の文学部で学びたいのか?
志望する文学部を選ぶ際は、その大学独自の特色や教育内容を具体的に示すことが不可欠です。他の大学でも通用する曖昧な理由では、志望動機の説得力が失われてしまいます。
重要なのは、カリキュラムの特徴、教授陣の専門分野、研究設備などを詳しく調べることです。
例えば「○○教授の近世文学ゼミで江戸時代の庶民文学を研究したい」「貴学の古典籍デジタルアーカイブを活用して原典研究を行いたい」といった具合に、固有名詞を用いて具体性を高めましょう。
また、その大学でしか学べない特別なプログラムや他学部との連携制度があれば、それらも志望理由として活用できます。
このような具体的な学習計画を示すことで、真剣にその大学で学びたいという気持ちが伝わります。
いくら熱意を示しても、相手に伝わる熱意でなければ意味がありませんよね。
> 小論文・完全ロードマップ解説の《無料メルマガ登録はコチラ》から
きっかけは何か?
文学部を志望するきっかけは、読書体験や高校での授業、日常生活での出来事など様々な形で生まれます。重要なのは、そのきっかけを単なる思い出話で終わらせないことです。
例えば、特定の作品との出会いが志望のきっかけになった場合、その作品のどこに感銘を受けたのか、なぜ自分の価値観に影響を与えたのかを具体的に説明しましょう。
「夏目漱石の『こころ』を読んで人間の心の複雑さに興味を持った」ではなく、「主人公の心理変化の描写に感動し、文学が人の内面を描く力について深く研究したいと考えるようになった」といった具合です。
また、そのきっかけから現在の志望に至るまでの思考プロセスも重要で、どのような経験を積み重ねて志望が固まったかを論理的に説明することが求められます。
文学を通して、どう社会貢献したいのか?
文学部志望者にとって最も重要なのは、文学研究をどのように社会に還元するかという視点です。
単に「文学が好きだから研究したい」では不十分で、具体的な社会貢献の方向性を示すことが求められます。
現代社会では、文学の役割が多様化しています。教育現場での国語教育改善、文学療法による心理的支援、地域文化の保存と継承、国際文化交流の促進など、様々な分野で文学の知識が活用できます。
例えば「古典文学の研究を通じて日本文化の海外発信に貢献したい」「現代文学の分析により若者の心理的課題解決に取り組みたい」といった具合に、自分の研究分野と社会課題を結びつけることが大切です。
また、将来の職業イメージも含めて、研究者、教員、編集者、文化行政など具体的な進路と関連付けて説明すると説得力が増します。
文学部というと、とかく文学作品や感性の方向ばかりに目が行きがちですが、大学の文学部という高等教育の機関である以上、その研究が社会貢献に役立つものであるという視点は大切ですよね。
800字の志望理由書の例文
以下、文学部を想定した800字の志望理由書です。文学部志望の受験生は参考にしてみてください。
私は貴学文学部日本文学科への入学を強く希望する。高校時代に宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を読み、文学が持つ人の心を癒やし、希望を与える力に深く感銘を受けた。この体験から、文学研究を通じて現代社会の様々な問題に向き合い、人々の心の支えとなる作品を生み出したいと考えるようになった。
文学への関心が高まったのは、祖母の介護を手伝った経験がきっかけである。認知症が進行する中で、昔の童謡を歌うと表情が明るくなる祖母の姿を見て、言葉や物語が人の心に与える影響の大きさを実感した。この時、文学作品が時代を超えて人々の心に寄り添い続ける意味について深く考えるようになった。特に近代文学における人間描写の繊細さと、読者の心に響く表現技法について研究を深めたいと思うようになった。
そこで貴学を志望する理由は三つある。第一に、近代文学を専門とする田中教授のゼミナールで学べることである。同教授の著書「近代文学における心理描写の変遷」を読み、文学作品の表現技法の発展について深い感銘を受けた。第二に、貴学独自の文学療法研究プログラムが充実していることである。文学と心理学を融合した学際的アプローチにより、文学の社会的意義について多角的に学べると考える。第三に、古典籍研究センターの豊富な資料を活用できることである。原典に直接触れながら研究を進めることで、より深い理解を得られると期待している。
入学後は、近代文学の基礎理論をしっかりと身につけるとともに、心理学や社会学の知識も習得したい。特に文学作品が読者の心理に与える影響について研究を進め、卒業論文では「近代小説における心理療法的効果」をテーマに取り組む予定である。また、地域の読書会や朗読ボランティアにも参加し、実際に文学作品が人々に与える影響を体験的に学びたい。そして将来は文学研究者として大学に残り、文学の社会的意義について研究を続けたいと考えている。(792字)
志望理由書の合格例を参考にみる

合格した志望理由書には共通する特徴があります。
大学の求める人材像を把握し、自分の経験と志望動機を論理的に結び付けて、将来への明確なビジョンまで示している点です。
合格例から見えること
合格者の志望理由書を分析すると、徹底した大学研究が行われていることが分かります。
単にパンフレットを読むだけでなく、アドミッションポリシー(入学者受け入れ方針)を詳しく研究し、大学が求める人材像を正確に把握しているのです。
早稲田大学の合格一例では「コスモポリタニズム」「グローバル・ガバナンス」といった大学パンフレットで重要視されていた専門用語を効果的に使用しています。
これは偶然ではなく、志望校の教育理念や特色を深く理解した結果です。
また、自分の経験をこれらの理念と結び付けることで、「なぜこの大学でなければならないのか」という問いに対する説得力のある回答を提供しています。
合格者は自分の体験と大学の方針を見事に一致させることで、入学後の成長可能性を具体的に示すことに成功しているのです。
失敗例と同じ過ちを繰り返さない
志望理由書でよく見られる失敗パターンを理解することで、同じ過ちを避けることができます。
最も多い失敗は「なんとなく興味がある」「幅広く学びたい」といった抽象的な表現を使うことです。
失敗例では、どの大学にも当てはまる汎用的な内容になってしまいがちです。
「様々な分野を学びたい」「多くの人と交流したい」といった曖昧な表現は、志望動機の本気度を疑われる原因となります。
また、大学の特色を調べずに書いた志望理由書は、その大学でなければならない理由が不明確になります。
さらに、過去の体験を単なる思い出話として終わらせてしまい、そこから得た学びや気づきを志望動機に結び付けられないケースも多く見られます。
これらの失敗を避けるためには、具体的な体験と明確な学習目標、そしてその大学独自の特色を論理的に結び付けることが重要です。
志望理由書を書いたあとの小論文対策はコチラ↓↓↓
↓ ↓ ↓ 小論文試験に必須の一冊 ↓ ↓ ↓
小論文の基本から、試験を想定した
実践練習まで、この一冊で身に付きます!
この一冊で小論文のお悩みすべて解決!
\ Amazonで400冊突破!/
自分の志望理由が将来のことまで一直線になるように考える
優秀な志望理由書では、過去の体験から現在の志望動機、そして将来の目標まで一貫したストーリーが展開されています。この一貫性こそが、志望理由書に説得力を与える最も重要な要素です。
合格例を見ると、例えば海外生活体験 → 国際政治への関心 → 大学での学習計画 → 国際公務員という将来目標まで、全てが論理的につながっています。
単に「国際関係に興味があるから政治経済学部を志望する」ではなく、なぜその分野に関心を持ったのか、大学で何を学び、それを将来どう活かすのかまで明確に示されているのです。
また、在学中の具体的な行動計画(留学、研究活動など)も含めることで、志望の本気度を証明しています。
このように、過去・現在・未来を一本の線でつなぐことで、読み手である大学側に「この学生なら入学後も目標に向かって努力し続けるだろう」という確信を与えることができるのです。
そこで大切なことは何を経験したかではなく、その経験が志望する大学・学部での学びにどう活かせるのか、将来に活かせるのかということですね。
どの学部でも、まして文学部でもこれは同じであり、志望理由書の採点担当の教授が見ている視点です。
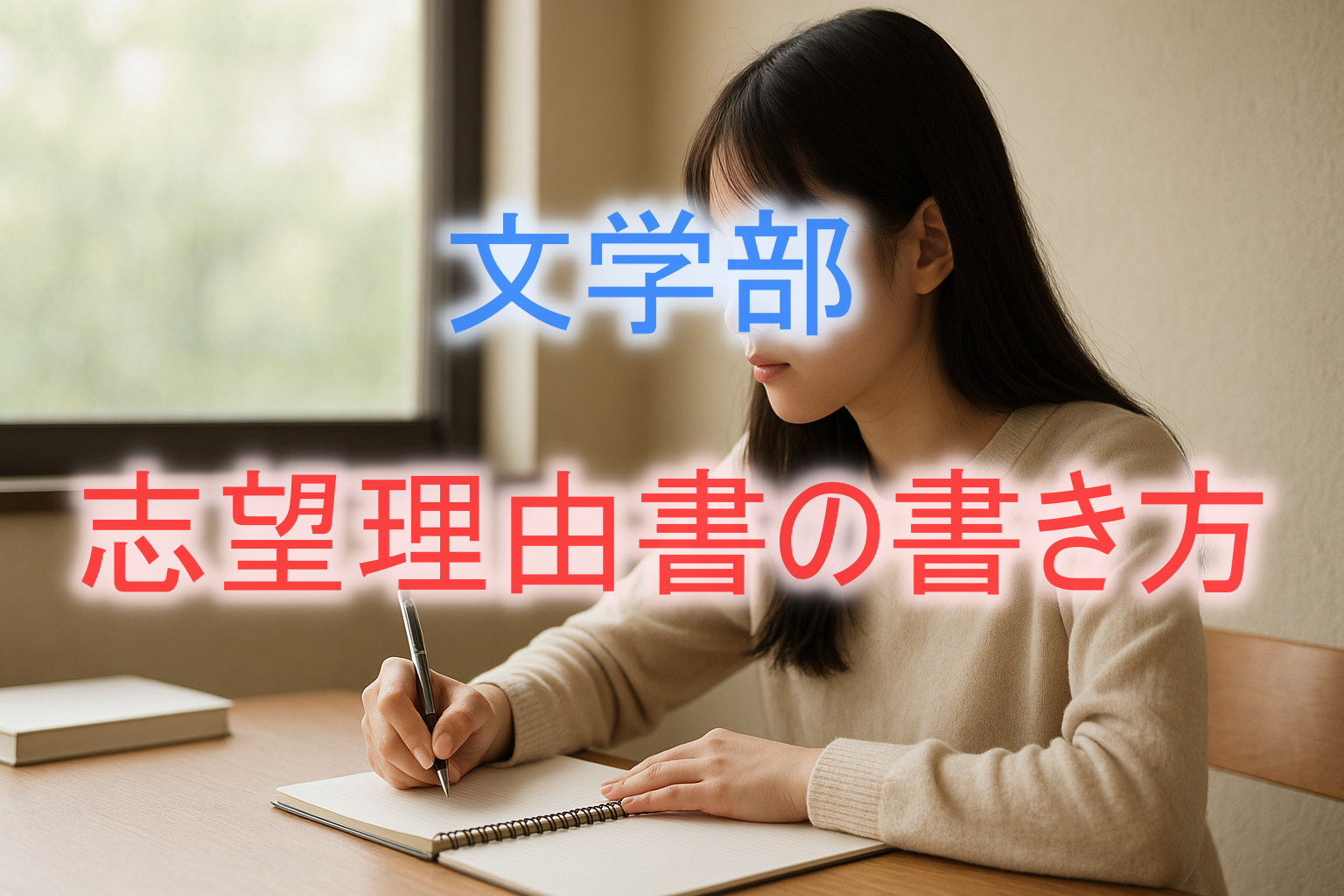
-500x336.png)

-500x336.png)

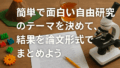
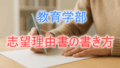
コメント