「小論文が半分しか書けなかった」「小論文が全く書けなかった」と感じて、合否が心配になっていませんか?
時間が足りなくて途中で終わってしまった、頭が真っ白になって何も書けなかった、こんな経験をした受験生は決して少なくないでしょう。
でも実は、自分では「書けなかった」と思っても合格の可能性が残されているケースが多いのです。
また就活の小論文が書けなかった場合も同様で、白紙でなければチャンスはあります。
この記事では、小論文が書けなかった状況別の合否判断や採点者の視点について詳しく解説します。あきらめる前に、まずは現実を正しく把握してみましょう。
- 書けなかった状況の把握
- 採点基準の確認
- 「書けなかった」と思っても、あきらめない姿勢
関連記事のURLを貼る
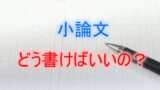
小論文が半分しか書けなかったら合否は?

ここでは小論文が半分くらいしか書けなかった場合の合否について見ていきます。
採点基準の確認
小論文の試験は、字数オーバーのような即0点になる場合を除いては採点者が複数人で読んだ上で減点方式の評価を行うので、半分しか書けなかった場合でも評価の対象になります。
以下の記事で確認しましょう。
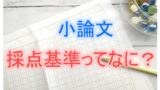
結論から言えば厳しい
半分くらいしか書けていない場合、結論を言うと合格は厳しいです。
指定文字数の最低8割以上を書けていることが基準なので、難しいと考えるべきです。
指定文字数については以下で確認しましょう。
ただし、あきらめる必要はない
ただ、文字数の不足だけで即不合格というわけではなく、採点者は内容もしっかりと見ているので、合格は厳しいですが自分でダメだと思った内容が採点者に評価されて、総合的な評価に反映されることもあるので、あきらめる必要はありません。
以下の記事も参考にしてみてください。
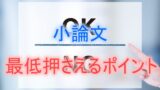
小論文が全く書けなかった場合は?

小論文が全くかけなかった場合の合否は、どうなるのかについて見ていきます。
本当に全く書けなかったのか、自分の中で書けなかったと思っているだけのどちらかということもあるので、詳しく見ていきましょう。
こちらも厳しい
まず、本当に全く書けていない場合、合格は厳しいと考えてください。
評価基準に沿っても書けていない場合は、当然評価は低くなり合格に満たない可能性が高いので、その時の試験の教訓を次の小論文の試験に活かしましょう。
評価基準のおさらい
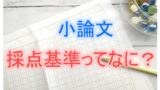
自分が書けなかったと思う=不合格とは限らない
ただし自分の中で「全く書けなかった」「手応えがなかった」という場合、小論文の書くルールを守っている、文字数もある程度満たしている、採点者から見て内容も悪くないと判断されれば合格できる可能性は十分あります。
反対に自分の中で手ごたえがあったとしても、評価基準を満たしていなければ不合格になる場合もあります。
小論文の基本を押さえておく
試験本番で「全く書けなかった」「手応えがなかった」となることのないように、練習のときから以下で小論文の基本やルール、考え方について踏まえておきましょう。



就活の小論文が書けなかった合否は?

就活の小論文で「書けなかった」と感じる状況も様々です。
完全に白紙だったのか、途中まで書いたのか、自分なりに完成させたが満足できなかったのかによって、合否への影響は大きく変わってきます。
本当に書けなかったのかどうか
「書けなかった」という状況を正確に把握することが重要です。
完全に何も書けずに白紙で提出した場合は、企業側に意欲や基礎的な文章力を疑われる可能性が高くなります。
一方で、時間内に完成できなかったものの途中まで書けている場合や、自分では不満足だが一通り書き上げた場合は状況が異なります。
企業の採用担当者は、限られた時間内での思考プロセスや表現力を評価しており、完璧でなくても受験者の人柄や考え方が伝わる内容であれば、選考通過の可能性は十分残されています。
自分が「書けなかった」と感じても、実際には評価に値する内容が含まれているケースも少なくありません。
就活での小論文の書き方は、以下を参照。
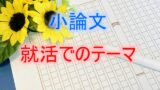
白紙は問題外だが、書いていれば分からない
白紙での提出は確実に不合格につながりますが、何かしら文章を書いていれば合否は予測できません。
企業の採用担当者は、完璧な小論文よりも受験者の人間性や思考力、将来性を重視する傾向があります。
文字数が規定に満たなくても、自分の考えが明確に表現されていれば評価される可能性があるでしょう。
また、独自の視点や体験談が含まれていれば、他の応募者との差別化につながることもあります。
採用担当者は数多くの小論文を読んでいるため、型にはまった完璧な文章よりも、個性が感じられる内容に注目する場合があります。
重要なのは、限られた時間内で自分なりに真摯に取り組んだ姿勢が伝わるかどうかです。
「文は人なり」と言われるように、大学入試でも就職試験でも、小論文の文章を読めば「この受験生はよく考えているな!」「コイツはいい加減だな」と分かるもので、普段の練習もそうですが、試験本番でも率直な考えを書くということが評価されるということを覚えておきましょう。
選考を通過させて面接に呼んでみたいかどうか
最終的な判断基準は「この人と直接話してみたい」と採用担当者に思わせられるかどうかです。
小論文は面接前のスクリーニング(選別)の役割を果たしており、完璧な文章力よりも人物像が見えることが重要になります。
たとえ文章が未完成でも、誠実な人柄や熱意、自分の経験や価値観が伝わる内容であれば、面接で詳しく話を聞いてみたいと判断される可能性があります。
企業側も限られた情報の中で判断しているため、小論文だけで全てを決めるわけではありません。
むしろ、書かれた内容から受験者の潜在能力や成長可能性を見出そうとしています。
同程度の能力を持つ候補者が複数いる場合、小論文の完成度が決め手となることもありますが、それ以上に「会ってみたい」と思わせる魅力があるかどうかが重要な要素となるでしょう。
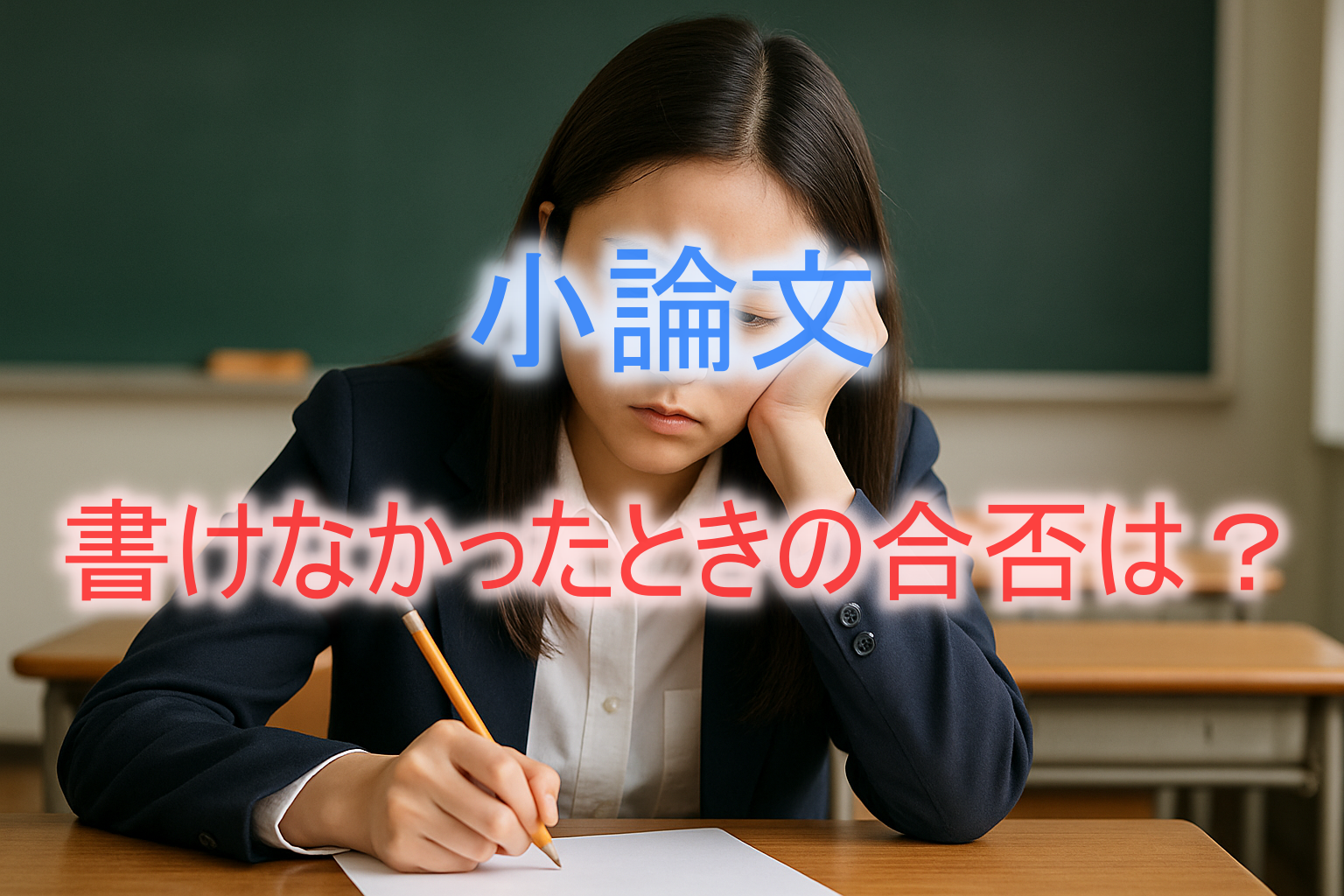
-500x336.png)


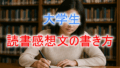
コメント