「小論文であなたの考えを述べよ」という問題に直面し、何から手をつければいいのか途方に暮れていませんか?
多くの受験生が悩むこの課題は、実は型や構成を理解すれば効果的に取り組めます。
本記事では、「あなたの考えを述べなさい」の書き出しのコツや、設問・資料・テーマ別の効果的な構成法を徹底解説。
さらに様々なテーマの解答例も紹介し、あなたの小論文の書く力を向上させます。
読めば書き方の基本が身につき、本番で焦ることなく自信を持って取り組めるようになるでしょう。
関連記事
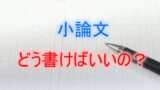
小論文の「あなたの考えを述べよ」というときの構成

大学入試の小論文で「あなたの考えを述べよ」という問題に直面すると、何をどう書けばいいのか悩んでしまう方は多いでしょう。
この記事では、効果的な構成や書き方のポイントを解説します。
まず問題から書くべきことをつかむ
出題形式によって、書くべき内容は異なります。まずは問題文をよく読み、何を求められているのかを正確に把握しましょう。
「あなたの考えを述べよ」という指示は、大きく分けて「賛否を問う」「解決策の提案を求める」「テーマの深掘りを求める」のいずれかを意図しています。
設問型の場合
特定の質問に答える形式の問題では、設問の意図を正確に理解することが重要です。
例えば「18歳選挙権についてあなたの考えを述べなさい」」という設問なら、賛成か反対かの立場を明確にてから理由を説明する構成が適切です。
まず第一段落で自分の立場を示し、第二段落で根拠を述べ、第三段落で具体例を挙げ、最後に結論をまとめるという流れがわかりやすいでしょう。
【800字前後、4段落で書く場合】
第1段落:賛成か反対か(その理由)
第2段落:賛成・反対の根拠
第3段落:具体例を挙げる(予想される異論・反論に対処)
第4段落:自分の意見のまとめ
上記の構成が必ずしも万能ではないのですが、基本として覚えておくと応用ができます。
課題文型の場合
与えられた文章を読み、それに対する意見を述べる形式では、課題文の正確な理解が評価のポイントになります。
まず課題文の主張をしっかり要約し、それに対する自分の立場を明確にしましょう。
課題文型では、筆者の主張を簡潔にまとめてから、それに対する自分の意見と理由、具体例、そして結論という構成が効果的です。
【800字前後、4段落で書く場合】
第1段落:課題文のまとめ(要約の指示がない場合は一文で触れる程度でもよい)自分の意見
第2段落:理由
第3段落:具体例(予想される異論・反論に対処)
第4段落:結論
↓ ↓ ↓ 小論文対策に必須の一冊 ↓ ↓ ↓
小論文の基本から、試験を想定した
実践練習まで、この一冊で身に付きます!
この一冊で小論文のお悩みすべて解決!
\ Amazonで400冊突破!/
資料型の場合
グラフや統計データなどの資料が提示される形式では、資料の読み取りと分析が重要です。
資料から読み取れる事実を客観的に述べてから、それに対する自分の解釈や意見を展開していく構成が適切です。
【800字前後、4段落で書く場合】
第1段落:資料の事実把握・分析
第2段落:自分の意見や見解
第3段落:異なる視点の見方や異論・反論への対処
第4段落:結論
テーマ型の場合
「環境問題について自由に論じなさい」のように大きなテーマだけが与えられる場合は、まず自分が取り上げる具体的な課題を明確にしましょう。
例えば環境問題なら「自然エネルギーの活用不足」など特定の課題に絞り、その原因と解決策を論じる構成が効果的です。
第一段落で課題を提示し、第二段落で原因分析、第三段落で解決策、第四段落で結論という流れで書くと、論理的でわかりやすい文章になります。
小論文では、自分だけの独創的な意見より、筋の通った論理展開が重視されます。基本的な構成を踏まえたうえで、自分の言葉で率直に考えを述べることが高評価につながるでしょう。
【800字前後、4段落で書く場合】
第1段落:問題提起
第2段落:原因分析
第3段落:解決策(あるいは改善方法の提示)
第4段落:結論
これら問題形式ごとの構成は、書き慣れないと難しく感じるかもしれませんが、上記の構成を基本にして書く練習を行い、この基本を応用して説得力のある文章を作成していきましょう。
初めから完璧を目指す必要はないので、どんどん書いて文章の構成を身に付けていってください。
小論文 あなたの考えを述べなさい 書き出し

「あなたの考えを述べなさい」と言われて、まず書き出しをどう書いてよいのか分からず固まってしまう場合が少なくありません。
まず書き出しが決まらないと、その後の文章も書けないので、それぞれの問題形式で見ていきましょう。
設問型の場合
設問型の課題では、問いかけに対して明確な立場を示すことから始めます。
効果的な書き出し例
- 「〜という問題は現代社会において重要な課題だ。私はこの問題について、〜と考える」
- 「〜については他に○○の見解があるが、私は〜の理由から〜という立場をとる」
- 「〜という問いに対して、私は〜という観点から考察したい」
ポイント:
- 問題の本質を簡潔に捉える
- 自分の立場を明示する
- 問題の背景や社会的文脈に簡潔に触れる
- 主張と理由の概略を示す
課題文型の場合
課題文型での書き出しは、課題文の内容を踏まえることから始めます。
踏まえるとは「課題文の内容を理解しているよ」ということを示して書くということです。
以下の課題文を要約しないで踏まえるときの書き方を示します。
課題文
あなたは「葬式」という言葉を聞いたとき、どのような光景を思い浮かべるだろう。亡くなった人を偲び、悲しみの涙が見られ、生老病死の中でもっとも悲しく、否定的なものと見られることが多い。ところが、アフリカのある民族では、色とりどりの棺に亡くなった人を入れ、そのまわりで人々が踊り、祭りでも行うかのように楽しく笑って死者を送るのだそうだ。それは、あの世でも故人が楽しく暮らせるように、現世の最期に笑って死者を送り出すという考え方からきている。日本では到底考えられないことだが、世界にはそういう考え方をする民族もいるのだそうだ。
要約がある場合は以下の記事を参考にしてみてください。

効果的な書き出し例
- 「〇〇から~のように」
- 「〇〇という内容を踏まえて、私は〇〇だと考える。なぜなら○○」
- 「〇〇といわれるように私たちは○○しがちだ。しかし○○である」
ポイント:
- 課題文で筆者の言いたいこと(主張・論点・結論)を的確につかむ
- 課題文の切り貼りはしないこと
- 課題文の内容を踏まえて、課題文では触れられていない内容や軽くしか触れられてない内容を深堀して書く
資料型の場合
資料型の課題では、提示された資料の要点を的確に把握し、その分析から始めます。
効果的な書き出し例:
- 「提示された資料によると、〜という傾向が読み取れる。この傾向から私は〜と考える」
- 「〇〇から○○にかけての〜の変化は、〜を示唆している。このデータを踏まえると〜」
- 「グラフAとグラフBを比較すると、〜という相関関係が見られる。この事実は〜を意味していると考えられる」
ポイント:
- 資料の単なる描写ではなく、分析的視点を示す
- 数値の変化や対比に注目する
- 資料から読み取れる意味や示唆を述べる
- 客観的な分析を心がける
テーマ型の場合
テーマ型の課題では、与えられたテーマの重要性や現代的意義を述べることから始めます。
効果的な書き出し例:
- 「〜というテーマは、現代社会において〜という点で重要な意味を持っている」
- 「〜は近年、〜という社会変化によって注目されるようになった。私はこのテーマについて〜」
- 「〜という問題は、〜と〜の側面から考察する必要がある。特に私は〜の観点から〜」
ポイント:
- テーマの重要性や現代的意義を述べる
- テーマのどの側面に焦点を当てるかを明確にする
- テーマに関する一般的な認識や社会背景に簡潔に触れる
- 独自の視点を加える
書き出しは、ワンパターンにしないこと
書き出しをワンパターンにすると、没個性的な印象を与えます。
多様な書き出しパターン:
- 問いかけ型:「〜ではないだろうか」「〜とは何か」
- 対比型:「〜という見方がある一方で、〜という側面も重要である」
- 定義型:「〜とは、〜を意味する。この観点から考えると〜」
- 引用型:「〜という言葉があるように、〜」
- 現状分析型:「現在、〜という状況が広がっている。この背景には〜」
ポイント:
- 課題の性質に合わせて適切な書き出しを選ぶ
- 奇をてらった表現や複雑な修辞は避ける
- 読み手にとって理解しやすい自然な文体を心がける
- 書き出しと本論、結論の調和を意識する
書き出しも、構成と同じく書いて慣れるしかないので、どんどん書いて自分なりの書き方を見つけていきましょう。
結論の書き方
結論部分では、それまでの論述を踏まえて自分の考えを明確に再提示します。
効果的な結論例:
- 「以上の理由から、私は〜と考える」
- 「これらの観点を総合すると、〜という結論に至る」
- 「〜と〜の両面から検討した結果、私は〜という立場をとる」
ポイント:
- 本論で述べた根拠と結びつけた形で結論を述べる
- 単なる繰り返しではなく、思考の発展を示す
- 問題提起に対する応答、将来展望、提言などを加える
- 確信を持った表現を用いる(「〜である」「〜といえる」など)
あわせて読みたい

とくに結論は文章の締めとして最重要で、この結論の出来が小論文の文章としての良し悪しを決めてしまうので、気を抜かずに書き切りましょう。
> 小論文・完全ロードマップ解説の《無料メルマガ登録はコチラ》から
小論文テーマ別の解答例

ここでは小論文のテーマ別の解答例を示します。
以下では、社会的なテーマについて解答例を作成しました。各テーマに対して、高得点を狙う小論文に必須の分かりやすさを意識した構成で書いています。
死刑制度に対するあなたの考えを述べなさい
【解答例】
死刑制度は慎重な運用を前提に維持すべきだと考える。凶悪犯罪に対する抑止力として機能するとともに、被害者や遺族の感情に配慮する側面もあるからだ。
しかし死刑の執行には取り返しのつかない問題もある。冤罪の可能性は完全に排除できず、一度執行すれば誤判が判明しても取り返しがつかない。また、死刑囚の精神的苦痛や刑務官への心理的負担など、制度を支える人々への影響も看過できない。
諸外国では死刑を廃止する流れがある一方、日本では国民の多くが死刑制度を支持している。この背景には犯罪被害者への共感や社会正義の実現という価値観があるからだ。
死刑制度は単なる応報ではなく、社会の安全と正義のバランスを保つための最終手段として位置づけるべきであり、そのため自白偏重に陥らない取り調べの可視化や何重にも及ぶ証拠のチェックなど、えん罪で死刑が確定することのないように、より慎重な運用と十分な情報公開が必要である。
長時間労働の是正には、どのような施策が必要かを述べなさい
【解答例】
長時間労働の是正には、法的規制と企業文化の変革を両輪とした包括的な視点が必要だ。過労死や心身の健康被害、ワークライフバランスの崩壊など、長時間労働がもたらす弊害は無視できないためだ。
まず法的規制としては、労働時間に対する上限規制の厳格化と違反企業への罰則強化が求められる。同時に、生産性や成果を重視する評価制度への転換も重要で、「時間」ではなく「成果」で評価する仕組みへの移行が必要だ。
具体的な取り組みとしては、デジタル技術を活用した業務効率化やテレワークの推進がある。あるIT企業では、リモートワークと集中業務時間の設定により、残業時間が40%減少した事例もある。
長時間労働の是正は単なる労働時間の短縮ではなく、働き方そのものを見直す社会変革だと位置付けられる。個人の健康と幸福を守りながら、企業の生産性も高める「働きがい改革」として推進すべきである。
真に「学ぶ」とは、どのようなことかあなたの考えを述べなさい
【解答例】
真に「学ぶ」とは、知識を受動的に受け取るだけでなく、自ら考え、実践し、変容することだと考える。学びとは本質的に、自己変革のプロセスだからだ。
学ぶには三つの段階がある。まず「知る」段階では情報を取り入れるが、これだけでは表面的な理解にとどまる。次に「考える」段階では、得た知識を批判的に検討し、自分の文脈に位置づける。最後に「変わる」段階では、学んだことを基に行動や思考パターンを変化させていく。
例えば外国語を学ぶ場合、単語や文法を暗記するだけでは真の学びとは言えない。その言語が話される文化的背景を理解し、実際にコミュニケーションを取る中で自分の視野が広がり、異文化への理解が深まってこそ、真の学びとなる。
真の学びとは、知識の蓄積ではなく、知を通じた自己の変容と成長である。「わかった」と思う瞬間よりも、「わからない」ことに気づき、新たな探求を始める姿勢こそが、学びの本質だといえるだろう。
以上、3つの解答例を紹介しました。
これらの答えが唯一の正解ではなく、基本構成に沿って意見・その理由・具体例が簡潔にまとめられている文章が小論文では高得点を得られる文章なので、みなさんもどんどん書いて、合格点を得られる小論文に仕上げていきましょう。
小論文の対策は、以下の無料メルマガでも実施中↓↓↓

-500x336.png)



-500x336.png)

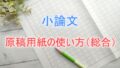
コメント