「小論文、最後まで書き終わらなかったけど、合格した」というのは、ときどき受験生から聞かれます。
よく「小論文が7割しか書けなかったので、不合格ですか?」という質問も受けますが、必ずしも不合格と決まるわけではありません。
「じゃあ、どうして書き終わらなかった答案で合格できたの?」となりますよね。
それは小論文の基本を、しっかりと踏まえている答案だからです。
「その基本ってなに?」
それを知りたいですよね。
そこで今回は多少の不備があっても合格できる、落としてはいけない小論文の基本について見ていきます。
関連記事
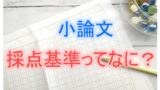
小論文ができなかったけど受かった仕組み

ここでは多少の不備があっても評価される採点の仕組みについて見ていきます。
採点基準の仕組み
まず小論文の採点は、複数の人の評価の平均で決まります。これは一人の評価によって評価基準が偏らないようにするためです。
採点基準については以下の記事もご覧ください。
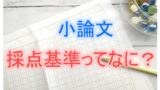
基本を押さえていれば、多少不備があっても評価される
ここを落とすと大幅減点されるという基本を落とさなければ、「7割しか書けなかった」「書き終わらなかった」という不備があっても、小論文では合格する可能性はあります。
反対に、「9割以上書けている」「書き終わって完成している」という答案でも、基本を落としていると不合格になる可能性が高くなります。
では、落としてはいけない「小論文の基本は何か?」を以下で見ていきましょう。
> 小論文・完全ロードマップ解説の《無料メルマガ登録はコチラ》から
小論文が「書き終わらなかった」のに、なぜ合格したのか?

ここでは小論文が「書き終わらなかった」のに合格できた、そのポイントについて見ていきます。
以下のポイントをきちんと踏まえておけば、多少不備があっても合格する可能が高くなるので、合格の最低ラインとして踏まえておきましょう。
合格のための4つの基本ポイント
| ポイント | 内容 | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 1. 問題の解答 | 問題で聞かれていることにすべて答える | • 最も減点されるポイント
• 複数の質問がある場合は特に注意が必要 |
| 2. 論理的な構成 | 自分の意見とその理由をセットで示す | • 多少の不備があっても高評価
• 「何を考えるか」と「なぜそう考えるか」の両方が必要 |
| 3. 適切な言葉遣い | • 主語は「私」
• 書き言葉を使用 • 流行語・省略語を避ける • 「い抜き言葉」「ら抜き言葉」に注意 |
• 不適切な言葉遣いの積み重ねは、大きな減点につながる
• 学術的文章としての体裁を保つ |
| 4. 読みやすい字 | 丁寧な字で書く | • 読みにくいと評価対象にならないリスク
• 日頃から手書き練習が重要 |
1.聞いていることに答えている
まず問題が聞いていることには、すべて答えます。
「当たり前じゃん!」と思うかもしれませんが、多くの受験生ができていません。
とくに問題が複数のことを聞いている場合、見落としたり書いていくうちに忘れたりすることはよくあります。
聞いていることに答えないというのは、最も減点されるポイントなので、「問題で聞かれていることには、すべて答える」ということを徹底しましょう。
聞かれていることにきちんと答える方法は、以下の記事でも紹介しています。
2.自分の意見とその理由が、きちんとセットになっている
問題の聞いていることに答えた上で、「自分はどう考えるのか?」「なぜそう考えるのか?」という意見とその理由がきちんとセットになっている答案は、多少不備があっても高く評価されます。
自分の意見やその理由を考える方法は、以下の記事を参考にしてください。

3.適切な言葉づかい
小論文を書くときの主語は「私」、「書き言葉」になっている、「エビデンス」「サステナブル」「時短」などの流行語や省略語を使わないなど、適切な言葉づかいで書くことも大きなポイントです。
また「い抜き言葉」や「ら抜き言葉」を使うことも、積み重なるとかなり大きな減点となるので気をつけましょう。
4.読みやすい字で書かれている
まず、小論文は読みやすい字で書かれていないと、最悪読まれず評価の対象にならないので、ヘタでもよいので丁寧な字で書きましょう。
アウトラインやメモなど、原稿用紙の指定枠以外に書くものは自分が判読できれば走り書きなどでもよいですが、原稿用紙に書く本文は採点者の人が読みやすい丁寧な字を書きます。
普段から手書きで丁寧な字で書く練習をしておきましょう。
よく合格の体験談で、「書き終わらなかったけど合格できた」「そんなに練習しなくても合格できる」というコメントがありますが、それらの受験生だった人によくよく聞いてみると、この4つの基本をしっかり学習していた、正しい方法で練習していたことが分かります。
| ポイント | 内容 | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 1. 問題の解答 | 問題で聞かれていることにすべて答える | • 最も減点されるポイント
• 複数の質問がある場合は特に注意が必要 |
| 2. 論理的な構成 | 自分の意見とその理由をセットで示す | • 多少の不備があっても高評価
• 「何を考えるか」と「なぜそう考えるか」の両方が必要 |
| 3. 適切な言葉遣い | • 主語は「私」
• 書き言葉を使用 • 流行語・省略語を避ける • 「い抜き言葉」「ら抜き言葉」に注意 |
• 不適切な言葉遣いの積み重ねは、大きな減点につながる
• 学術的文章としての体裁を保つ |
| 4. 読みやすい字 | 丁寧な字で書く | • 読みにくいと評価対象にならないリスク
• 日頃から手書き練習が重要 |
基本を踏まえて正しい練習方法で練習をしておけば、受験生本人が「書き終わらなかった」と思っていても、きちんと評価されることがあるということを覚えておきましょう。
小論文は「7割しか書けなかった」から即不合格でもない

たとえ7割しか書けなくても、小論文はそれだけで即不合格にはなりません。
とはいえ、試験後にこんなことで焦って、他の教科の対策がおろそかにならないように、形式的な部分もきちんと見ておきましょう。
書き終わらない or 内容が薄い・設問に答えないどっちがダメ?
よく受験生からこういった質問がありますが、結論から言えば「書き終わっていない、完成していない答案」の方が評価が低くなります。
まず、指定の文字数の9割、最低でも8割を満たしていない答案は、読む前に一覧すれば分かるので、大学入試や就職試験、昇進試験にかかわらず「書く意欲がない」とみなされてしまいます。
これはいくら内容がよくても、指定字数を満たしていない答案は採点すらされない可能性があり、非常にもったいないことですよね。
とはいえ、指定字数を満たしていれば内容が薄い、設問に答なくても良いということにはならないので注意しましょう。
指定字数を満たして、完成した答案だけが評価の対象になるということです。
基本を踏まえていれば、多少文字数が少なくても合格する可能性はある
ただ、上記で見てきた基本を踏まえていれば、多少文字数が少なくても合格できる可能性は十分あります。
とはいえ、文字数も最低基準を満たしていなければ「読まない」という採点者もいますし、試験後このようなつまらないことで焦らないためにも、日頃からまず書く文字数の最低基準を満たすように練習をしていきましょう。
文字数の理想は9割以上、最低8割
大学での採点担当の教授や、企業の担当者の多くが「9割以上は書いて欲しい」というように、小論文の書く文字数の理想は9割以上です。
ただし、指定の文字数を1字でも超えたら0点もしくは大幅減点となるので気をつけましょう。
そして9割以上も書けないという場合もあるので、最低8割は必ず書くようにしてください。
これは「〇〇字以内」「〇〇字程度」「〇〇字以上〇〇字以下」などのすべての指定文字数の上限にあてはまると考えて練習しましょう。
あわせて読みたい
時間を計って、アウトラインの作成や本文の書く練習をする
「本番で書き終わらなかった」「7割しか書けなかった」というのは、時間を計って書く練習というのが足りない結果なので、試験前から時間を計ってアウトラインの作成や本文の書く練習を繰り返し行います。
こうすることで自分の書ける速さや時間配分を把握して、本番でも焦ることなく書くことができます。
あわせて読みたい

今回見てきたポイントというのは、あくまで合格できる最低ラインのポイントなので、試験後に「書けなかった」と焦ることのないよう、余裕を持って合格できるように日頃から練習を重ねていきましょう。
小論文の対策は、以下の無料メルマガでも実施中↓↓↓
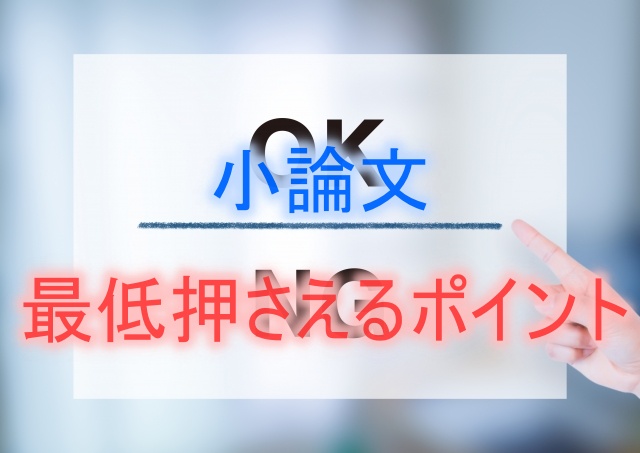
-500x336.png)

-500x336.png)

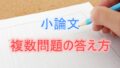
コメント