「どう書き始めればいいの…」と小論文の書き出しに頭を抱えていませんか?
多くの受験生が悩むこの問題を解決します。
本記事では、採点者に好印象を与える「小論文の書き出し例」を3つのパターンで紹介し、効果的な書き方のポイントを解説します。
また「小論文の書き出し例文」も掲載しているので、実際の問題にも応用できます。
明確な型を身につければ、小論文の書き出しはもう怖くありません。今すぐ実践できる書き方を学び、受験の不安を解消しましょう。
今回学ぶこと
関連記事

小論文の書き出し例・3パターン

小論文の書き出しには効果的な型があります。
ここでは、受験生が実践しやすい3つの書き出しパターンを紹介します。
どのパターンも結論を先に述べる形になっていますが、問題の性質や自分のスタイルに合わせて最適なものを選びましょう。
これらを使いこなせば、採点者に好印象を与える明快な文章が書けるようになります。
パターン1:自分の主張や考えから書く
「〜について私は○○だと考える。なぜなら~」
小論文で最も基本的な書き出しは、自分の考えを最初に明示する方法です。
「〜について私は○○だと考える」という形で始めることで、読み手は文章の方向性をすぐに把握できます。
例えば「環境問題への取り組みについて、私は個人の意識改革が最も重要だと考える」といった書き出しです。
この方法の利点は、主張が明確になり論点がぶれにくくなることです。
ただし、単に主張を述べるだけでなく、その後に「なぜなら~」と続け、簡潔に理由の概要を示すと説得力が増します。
主張が先にあることで、採点者は残りの文章をその視点から読むことができ、一貫性のある印象を与えられます。
自分の考えを整理しやすい問題や、意見を求められる問題に特に有効なアプローチです。
後半では具体例や詳細な説明を加え、最後に主張を別の言葉で再確認すると効果的です。
パターン2:賛否の立場から書く
「〜について、私は賛成(または反対)である。その理由としては~」
問題が特定の事柄に対する賛否を問うている場合、「〜について、私は賛成(または反対)である」という書き出しが適しています。
例えば「高校での制服廃止について、私は条件付きで賛成である」といった形です。
このパターンでは、自分の立場を明確にした後、「その理由としては~」と続けると自然です。
賛否を述べる際には極端な表現を避け、条件や範囲を限定すると論理的に見えます。
例えば「すべての場面で反対」ではなく「現状では反対」など、状況を考慮した表現を心がけましょう。
後半では自分の立場を支える具体的な根拠を示し、結びでは初めの立場を再確認しつつ、より広い視点からの意義を述べると説得力が増します。
パターン3:理由や解決策の個数を示してから書く
「〜の理由(または解決策)は○つあると考える。1つ目は~、2つ目は~」
問題分析や解決策の提示を求められる場合、「〜の理由(または解決策)は○つあると考える」という書き出しが効果的です。
例えば「若者の投票率低下の要因は主に2つあると考える」といった形式です。
この書き出しの強みは、読み手に文章の構成が予め伝わることで理解しやすくなる点です。
数を示した後には「1つ目は~」と続け、各理由や解決策を段落を分けて説明していきます。この形式は特に、社会問題の分析や政策提言を求める問題に適しています。
ただし、示した数と実際に書く内容の数が一致するよう注意が必要です。
また、単なる羅列にならないよう、理由同士の関連性や優先順位にも触れると論理性が高まります。
結びでは各要素をまとめ、総合的な視点から問題の本質や解決の方向性を再確認すると印象に残る文章になります。
以下、書き出し後の定型フレーズも紹介しているので参考にしてください。
| パターン | 基本形式 | 例文 | 特徴・メリット | 注意点 | 適した問題タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| パターン1:自分の主張や考えから書く | 「〜について私は○○だと考える」 | 「環境問題への取り組みについて、私は個人の意識改革が最も重要だと考える」 | ・主張が明確になる
・論点がぶれにくい ・一貫性のある印象を与えられる |
・主張だけでなく「なぜなら〜」と理由の概要も示す
・最後に主張を別の言葉で再確認する |
・自分の考えを整理しやすい問題
・意見を求められる問題 |
| パターン2:賛否の立場から書く | 「〜について、私は賛成(または反対)である」 | 「高校での制服廃止について、私は条件付きで賛成である」 | ・立場が明確になる
・論点が絞られる |
・極端な表現を避ける
・条件や範囲を限定すると論理的になる ・「その理由としては〜」と続けると自然 |
・賛否を問う問題
・立場表明を求める問題 |
| パターン3:理由や解決策の個数を示してから書く | 「〜の理由(または解決策)は○つあると考える」 | 「若者の投票率低下の要因は主に3つあると考える」 | ・文章構成が予め伝わる
・読み手が理解しやすい |
・示した数と実際の内容数を一致させる
・理由同士の関連性や優先順位に触れると良い ・「1つ目は〜」と続け、段落分けする |
・社会問題の分析を求める問題
・政策提言を求める問題 |
最初はフレーズを覚えるためにも、問題に合わせてこのまま使ってみることをオススメします。
まずは型を覚えることで、書き慣れた時に応用が利くようになりますよ。
小論文の書き出し例での注意点

小論文の書き出しは全体の印象を左右する重要な部分です。
効果的な書き出しにするためには、いくつかの注意点を押さえる必要があります。
ここでは書き出しで避けるべき点や、効果的な書き方のポイントについて解説します。適切な書き出しは、採点者に好印象を与え、論理的な文章展開の土台となります。
書き出しに個性や日記的記述は不要
小論文の書き出しでは、自分の体験談や感想から入りたくなる誘惑があります。
しかし「先日テレビで見た番組がきっかけで~」や「私は幼い頃から~に興味があり」といった日記的な書き出しは避けるべきです。
このような個人的なエピソードは論点をぼやけさせ、採点者に「作文」と誤解される恐れがあります。
小論文は客観的な視点と論理性が求められる文章形式です。
書き出しでは、テーマに対する自分の立場や考えを端的に示し、読み手が文章の方向性をすぐに理解できるようにすることが大切です。
個性的な表現よりも、明確さと簡潔さを優先させましょう。
特に入試では限られた時間内で採点されるため、冒頭から要点を押さえた文章構成が高評価につながります。
書き出しは、結論を先に書くとは限らない
小論文では「結論から先に書く」と教わることが多いですが、これは絶対のルールではありません。
問題の性質や文字数制限によっては、異なるアプローチが効果的な場合もあります。
例えば、複雑な社会問題を扱う場合は、「~という観点から考えてみたい」など、まず問題の背景や現状を簡潔に説明してから自分の見解を述べる方が理解されやすいことがあります。
また、対立する二つの意見を比較検討する問題では、両論を簡潔に示してから自分の立場を明らかにする書き出しも有効です。
重要なのは、読み手を混乱させない論理的な流れを作ることです。
ただし、どのような書き出しを選んでも、序論の終わりには必ず自分の立場や主張を明確にしておくことが大切です。
書き出しのスタイルは内容に合わせて柔軟に選びましょう。
問題に合わせて書き出しを書く
小論文の書き出しは、出題された問題の性質や求められている解答形式に合わせる必要があります。
例えば、「〜についてあなたの考えを述べなさい」という問題には主張から入る書き出しが適していますが、「〜の問題点とその解決策を論じなさい」という問題では、まず問題の本質を簡潔に示してから解決の方向性を提示するほうが適切です。
また、資料や図表の分析を求める問題では、そのデータから読み取れる重要な傾向や特徴を書き出しで示すと良いでしょう。
書き出しパターンをいくつか用意しておいて、問題に応じて使い分けられるようにしましょう。
どの問題が出ても、杓子定規に「この書き出しパターンしか使わない!」となると、問題に合わない恐れがあるばかりか、採点者をウンザリさせるという悪印象にもなるので、問題に合わせて書き出しパターンを使いこなす柔軟さも身に付けてください。
小論文の書き出しでの4例文

小論文の書き出しを具体的にイメージできるよう、実際の例文を紹介します。
これらの例は、現代社会の重要テーマを扱った小論文の書き出し部分です。
パターンごとの特徴を活かした書き出しをぜひ参考にして、自分の小論文作成に役立ててください。様々なテーマに対応できるよう、複数のアプローチを身につけましょう。
例文1
地球温暖化対策として、プラスチック製レジ袋の有料化は効果的な政策だと考える。この政策は消費者の環境意識を高め、使い捨てプラスチックの削減につながるからだ。
日本では2020年7月から全国的に実施され、それまで年間約300億枚消費されていたレジ袋の使用量が大幅に減少した。実際、環境省の調査によれば、政策導入後1年間でレジ袋辞退率は約75%に達し、約13万トンのCO2排出削減効果があったとされる。
例文2
高齢化社会における介護ロボットの導入について、私は積極的に推進すべきだと考える。なぜなら、深刻化する介護人材不足を補い、介護者の身体的負担を軽減できるからだ。
厚生労働省の推計によれば、2025年には約37万人の介護人材が不足するとされている。この状況下で、持ち上げ支援や見守りなどを行う介護ロボットは、人手不足を補う有効な手段となる。
例文3
日本の教育現場における英語教育改革については、小学校低学年からの導入に反対の立場をとる。確かにグローバル化に対応するため早期英語教育の必要性を主張する声は多いが、発達段階を考慮すれば母語の習得を優先すべきだからだ。
言語学者の研究によれば、母語の基礎が確立していない段階での第二言語学習は、両言語の発達に悪影響を及ぼす可能性がある。
例文4
高校でのスマートフォン使用については、学習への集中力低下を理由に禁止すべきという意見と、緊急時の連絡手段として許可すべきという意見が対立している。
両者の主張にはそれぞれ妥当性があるが、私は一定のルール設定を条件に許可すべきだと考える。なぜなら、適切な管理下での使用は教育的価値と安全確保の両立が可能だからである。
これらの例文はあくまで参考例で、私の個人的な見解ではありませんし、ほんの一例にすぎませんが、この例文を受験生のみなさんならどう書き換えるも考えながら、他の問題でも書くときの参考にしてみてください。
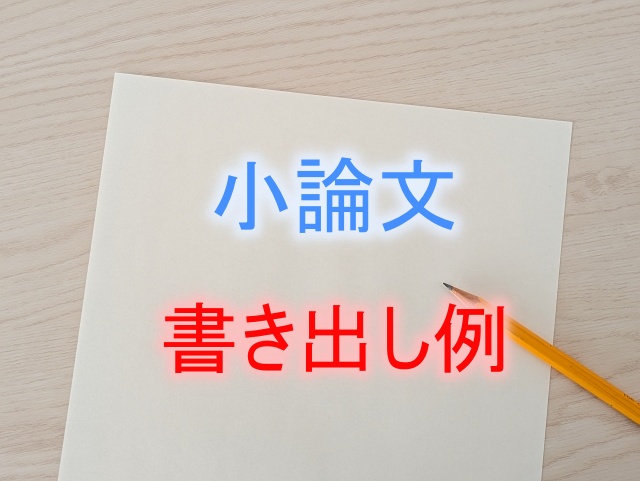
-500x336.png)


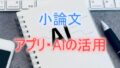
コメント