「指定校推薦ってなに?」「対策はどうすればいいの?」そんな疑問や不安を抱えていませんか?
実は、指定校推薦には明確な仕組みがあり、適切な対策を行えば合格への道筋が見えてきます。
評定平均の維持から小論文・面接対策まで、成功のポイントを正しく理解することが重要です。
また、よく言われる「指定校推薦はやめた方がいい」は本当なのか?どんなデメリットがあるのか。
本記事では、指定校推薦の基本的な仕組みから具体的な選考スケジュール、校内選考を勝ち抜くための対策方法、さらに小論文や面接の準備まで、あなたが指定校推薦で志望校合格を掴むために必要な全ての情報を詳しく解説しています。
関連記事
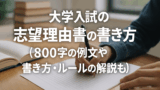
指定校推薦のしくみ

指定校推薦を検討している高校生にとって、まずはその仕組みを正しく理解することが重要です。制度の概要から具体的な選考プロセスまで、指定校推薦の全体像を詳しく解説していきます。
指定校推薦とは
指定校推薦は、高校が特定の大学から推薦枠を与えられ、その枠に対して校内選考を経て選ばれた生徒を大学に推薦する制度です。
これは、まさにオリンピックや世界大会で国を代表するアスリートが選ばれるのと同じような感覚といえるでしょう。
高校という「チーム」から選抜された代表として、大学に送り出される特別な制度なのです。
大学側は長年の信頼関係を築いている高校からの推薦を重視し、高校側は優秀な生徒を責任をもって推薦します。この信頼関係こそが指定校推薦の基盤となっています。
スポーツでのオリンピックや世界大会と違う点は、指定校推薦が決まるとほぼその大学への合格が保証されるという特徴です。
指定校推薦のスケジュール
8月:高校で生徒に対して推薦枠の情報公開
9~10月:校内選考の実施、推薦者の決定
11月:大学への出願
12~1月:小論文、面接試験の実施
1~2月:合格発表
指定校推薦のスケジュールは、毎年夏頃から動き始めます。
6月から7月にかけて各大学から高校に推薦枠が通知され、8月頃に学校側が生徒に対して推薦枠の情報を公開するのが一般的です。
9月から10月にかけて校内選考が実施され、推薦者が決定されます。
その後、11月に大学への出願、12月から1月にかけて面接や小論文などの選考が行われ、1月下旬から2月上旬には合否が発表されることが多いです。
一般入試よりも2〜3ヶ月早く進路が確定するため、受験生にとって精神的な負担軽減につながります。
上のスケジュールはあくまで一般的なものなので、詳細については志望校の募集要項などで確認してください。
指定校推薦の候補者になるポイント
・欠席や遅刻をしないなど評定平均を4.0以上に保つ
・部活動や生徒会をはじめ、課外活動に積極的に関わる
指定校推薦の候補者として選ばれるには、まず評定平均の高さが最重要ポイントです。大学が設定する基準(多くの場合4.0以上)をクリアすることが前提条件となります。
ただ、高校のレベルや指定校推薦先の大学の難易度によっても評定平均の基準値は異なりますので、志望する大学が自分の出身校の生徒に求める評定平均がどのくらいか募集要項などで確かめておきましょう。
次に出席状況や生活態度が重視され、欠席や遅刻の回数が少ないことが求められます。
さらに部活動や生徒会活動、委員会活動での実績も大きな評価材料になるでしょう。
校内選考では志望理由書の提出、面接、小論文などが課されることもあります。
これらの選考を通じて、学力だけでなく人間性や意欲も総合的に判断されるため、日頃の学校生活全般にわたって真摯に取り組む姿勢が重要です。
校内選考に選ばれるためにやるべきこと
・定期テストでの好成績を維持する
・部活動や課外活動にも積極的に参加する
・英検などの資格取得を計画的に行う
・先生や同級生との良好な関係を築く
校内選考に選ばれるためには、まず基本的な出席管理から始めましょう。
欠席・遅刻・早退を可能な限り避け、規則正しい学校生活を送ることが大切です。
評定平均については、定期テスト対策をしっかり行い、全教科でバランスよく成績を向上させる必要があります。
また、部活動や課外活動にも積極的に参加し、リーダーシップや協調性をアピールできる実績を積むことが重要です。
英検などの資格取得も条件となる大学が増えているため、計画的に取得しておきましょう。
さらに、先生方や同級生などとの良好な関係を築き、普段から誠実な態度で学校生活を送ることで、推薦を受ける際の信頼度を高めることができます。
ただし、指定校推薦の基準には1,2年次の評定平均も含まれているので、こういったことを3年生から意識して始めても遅いかもしれません。
しかし、1,2年生までの評定平均などが基準値を大幅に下回っていなければ、挽回できるチャンスもあるので、指定校推薦を目指す人は、あきらめずに取り組んでみましょう。
そして、まだ1,2年生で指定校推薦を目指す人は、上に挙げたポイントを今から意識して高校生活を送るようにしましょう。
指定校推薦のメリット・デメリット
メリット
・合格率が非常に高い
・学力試験では届かない大学に入るチャンスがある
・早期に進路が決定して、高校生活最後の後半は余裕をもって過ごせる
・受験校が1校に限られるので、経済的な負担が軽減される
デメリット
・他大学との併願は不可
・指定校推薦枠がなければ受験は不可
・入学後、周囲との学力差を感じてしまう場合もある
・ミスマッチが起こりやすい
指定校推薦の最大のメリットは、合格率が非常に高く、早期に進路が決定することです。
受験勉強から解放されるため、高校生活最後の後半を余裕をもって過ごすことができ、将来に向けた準備に時間を使えるでしょう。
また、学力試験の成績では届かない大学に合格するチャンスがあることも大きな魅力です。経済的負担も軽減され、一つの大学のみの受験で済むため受験料も抑えられます。
一方でデメリットとしては、専願制のため他大学との併願ができないことが挙げられます。
合格後に「やっぱり別の大学を受験したい」と思っても、原則として辞退はできません。
また、学部・学科の内容が想像と違っていた場合のミスマッチが起こりやすいことも注意点です。
指定校推薦を利用する前には、大学・学部が自分の将来の目標や興味関心に適しているかをしっかりと調べることが不可欠です。
指定校推薦はやめた方がいいのか?
結論から言えば、ただ「受験勉強をしなくていい」「楽して大学に入れる」という考えならばやめた方がいいです。
先ほどのメリット・デメリットで触れたように、「学習についていけない」「思っていたのと違う!」というミスマッチが起こりやすくなるからです。
そして指定校推薦で入学した生徒には、大学側も入学後の成績、態度などの追跡調査を行います。
その状況によって翌年以降の出身校の指定校推薦の枠をどうするのかに反映されます。
もしあなたが何となく指定校推薦を利用して大学に入り、「思っていたのと違う!」となって成績や態度が芳しくないと、その影響は翌年以降の後輩の受験機会にも及ぶのです。
したがって、単純に「受験勉強なしで大学に入りたい」「早く受験を終えて安心したい」という安易な考えならば、自分のためにも出身高校やその後輩のためにもならないので、指定校推薦は受けるべきではありません。
ただ指定校推薦の枠がある大学のことをよく調べて、自分の学びたいことや興味関心と一致しているのであれば、積極的に活用してみましょう。
実際にある調査で指定校推薦を利用して大学受験に合格した本人または保護者100人を対象に、「指定校推薦にしたことを後悔したことはあるか?」とのアンケートを取ったところ、じつに84%の人が「後悔したことはない」と答えています。
このように自分の進路をきちんと考えて利用した人にとっては、指定校推薦というのは良い入試制度であることが分かります。
指定校推薦の落ちる確率はどのくらい?

指定校推薦でよく「100%落ちることはない。指定校推薦が決まると絶対に合格する」といわれますが、実際のところはどうなのかについて見ていきます。
99%落ちることはない
指定校推薦で不合格になる確率は、実質的にほぼ0%に近いといえます。
これは指定校推薦が大学と高校の信頼関係に基づく制度であり、大学側が高校の推薦を尊重するためです。
校内選考を通過した時点で、すでに大学が求める基準をクリアした生徒として認められているからです。
また、大学側も合格ラインを比較的低く設定しており、よほど問題のある態度や著しく不適切な対応をしない限り、不合格にすることはありません。
つまり、校内選考を勝ち抜いた時点で、合格はほぼ確実と考えて良いでしょう。この高い合格率こそが指定校推薦の最大の魅力といえます。
ただし、100%合格するわけではない
指定校推薦でも稀に不合格となるケースが存在するため、完全に油断してはいけません。
小論文の出来が著しく悪い場合や、面接での態度が極めて不適切な場合には、大学側が「合格させるに相応しくない」と判断することがあります。
特に私立医学部や一部の理系大学では競争が激しく、面接や小論文の評価が内申点と同じレベルで重視されるためです。
これらの大学では、指定校推薦といえども他の受験生と同様の厳しい選考が行われます。そのため、指定校推薦だから安心と考えず、小論文対策や面接練習をしっかりと行うことが重要です。
準備を怠らない姿勢こそが確実な合格への道筋となります。
翌年の指定校推薦にも影響する
指定校推薦で万が一不合格になった場合、その影響は翌年以降の後輩にも及ぶ可能性があります。
たとえ試験の成績が悪いなかで合格したとしても、大学側が「この高校からの推薦生は期待に応えられない」と判断すれば、翌年の指定校推薦枠が削減されたり、完全に取り消されたりすることがあるのです。
実際に、私の高校時代も前年まであった、ある大学の指定校推薦枠が私の受験年度で取り消しになっていたので、前年に不合格か、合格しても試験の成績が著しく悪かったということなのでしょう。
私自身は、高校時代の定期テストなどの成績があまり良くなかったので、指定校推薦を利用する発想はありませんでしたが、私の同級生で利用したいと考えていた人の受験機会が先輩によって奪われてしまったのかもしれません。
このように、たとえ合格したとしても、入学試験の成績や入学後の成績、態度が著しく悪ければ、同様に後輩の受験機会を奪うことになりかねません。
指定校推薦は個人の問題にとどまらず、学校全体の信頼に関わる制度だということを理解し、責任をもって臨むことが大切です。
指定校推薦の小論文の対策は、いつから始めるの?

指定校推薦における小論文対策のタイミングは、校内選考の有無や個人の状況によって異なります。最適な開始時期を把握して、効率的な準備を進めましょう。
指定校推薦が決まってから
基本的に指定校推薦の小論文対策は、推薦が決まってからの7月頃から本格的に始めるのが一般的です。
この時期であれば、志望大学の出題傾向や求められる内容を具体的に把握した上で、集中的に対策を行うことができます。
ただし、校内選考で志望理由書や小論文、面接が課される場合は話が別です。
校内選考の準備として行った小論文対策は、そのまま本番の指定校推薦でも活用できるため、一石二鳥の効果が期待できるでしょう。
校内選考に小論文がある学校では、5月から6月頃には準備を開始し、選考を通過した後も継続して対策を続けることが重要になります。
小論文の対策自体は早めに行う
小論文のスキル向上という観点では、指定校推薦に関係なく早めに対策を始めることをおすすめします。
高校2年生の後半から3年生の春頃に基礎的な文章構成や論理的思考力を身につけておけば、様々な場面で応用が利くからです。
万が一指定校推薦で不合格になった場合や、途中で第一志望を変更することになった場合でも、すでに培った小論文のスキルは一般入試での小論文対策にそのまま活用できます。
また、総合型選抜(旧AO入試)を併願する際にも役立つでしょう。早期に対策を始めることで、様々な入試形態に柔軟に対応できる基盤を作ることができるのです。
指定校推薦の小論文例文

指定校推薦の小論文の対策を見ていきましょう。
他の大学入試よりも対策は少なめですが、やはり実際に書く練習をしていかなければ上達はしないですし、当日の成績が悪いと万が一にも不合格になったり、たとえ合格しても翌年の指定校推薦枠が取り消されるなど、後輩に迷惑をかけてしまう場合があります。
学校の代表として下手な成績をとらないためにも、小論文の試験に向けてしっかり書く練習を行いましょう。
過去問の入手法、例題と解答例、評価例など
過去問の入手方法や実際の例題と解答例、評価例などは、総合型選抜の小論文と共通する点が多いので、以下を参照してください。
志望理由書の書き方や面接について

指定校推薦では志望理由書の提出や面接が課されることが多く、これらの対策も合格への重要な要素となります。
適切な準備と練習で自信を持って臨めるよう準備しましょう。
志望理由書の書くコツ
志望理由書の書くコツは、徹底的に具体的に書くことです。志望理由書の書き方は以下を参照してください。
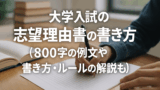
面接の練習をする
指定校推薦の面接では、志望動機や将来の目標について明確に答えられることが重要です。練習を通じて、自分の考えを論理的かつ簡潔に伝える力を身につけましょう。
まず、よく聞かれる質問パターンを整理し、それぞれに対する回答を準備することから始めます。
「なぜこの大学を選んだのか」「大学で何を学びたいか」「将来どのような職業に就きたいか」といった基本的な質問に対して、具体的なエピソードを交えながら答えられるよう練習が必要です。
とくに志望理由書で書いた内容については必ず聞かれるので、志望理由書のコピーをとっておき、内容について受け答えできるようにしておきましょう。
また、面接官との自然な会話を意識し、一方的に話すのではなく相手の反応を見ながら対応する柔軟性も大切になります。
家族や先生に協力してもらい、実際の面接を想定した練習を重ねることで本番での緊張を軽減できるでしょう。
面接については以下も参考にしてみましょう。(教育学部の面接についての内容ですが、面接全般に共通する内容なので参考になるかと思います)
校内選考に通らなかった、指定校推薦に落ちたときの対処法
校内選考で選ばれなかった場合や指定校推薦で不合格になった場合でも、他の入試制度を活用して志望校合格を目指すことは十分可能です。
まず検討すべきは公募推薦で、これは指定校推薦と異なり全国の高校生が応募できる制度です。評定平均や活動実績が重視される点は指定校推薦と共通しているため、これまでの努力を活かすことができます。
次に総合型選抜(旧AO入試)も有力な選択肢となるでしょう。学習意欲や将来への展望を重視する選考方式のため、志望理由が明確な受験生には適しています。
最終的には一般入試という選択肢もあり、学力試験で勝負することになりますが、これまでの推薦対策で身につけた文章力や面接スキルは決して無駄になりません。
指定校推薦は、高校入学時からの生活態度や定期テストの成績など学校生活全般での総合的な評価を含めた厳しい校内選考で選ばれるために、3年生から目指しても遅いですし、校内選考の候補にすらならない場合があります。
しかし反対に定期テストや課外活動などで、よい高校生活を送ってきた人にとっては、受験機会が増える選択肢として指定校推薦というものが用意されています。
そして1,2年次の評定平均などが基準値を大幅に下回っていなければ、3年次からの挽回のチャンスもあります。
大学入学後に何をしたいのか、あるいは現在のあなたと将来の目標とのギャップを埋めるために何を学ぶべきなのかが明確で、志望先に指定校推薦の枠と受験基準を満たしているのであれば、受験機会を増やすという点で指定校推薦の制度も積極的に活用してみましょう。
まとめ
指定校推薦は、よくやめた方がよいといわれますが、これはたんに「受験勉強をしなくていい」「楽して大学に入れる」という安易な考えならば、ミスマッチが起こりやすくなるからやめた方がよいということです。
指定校推薦の特性を理解して、自分の目標や興味関心が一致しており、評定平均などの基準を満たしていれば、8割が「指定校推薦にしたことを後悔していない」という先輩のアンケート結果からわかるように、指定校推薦は積極的に活用するべき入試制度だといえます。
その中でも、後の大学でのレポートや論文を書く基礎としても重要であり、その先の就職試験の対策にもなる小論文の対策も、ぜひ今のうちから行いましょう。
小論文の対策については、下の無料メルマガでも実施中↓↓↓
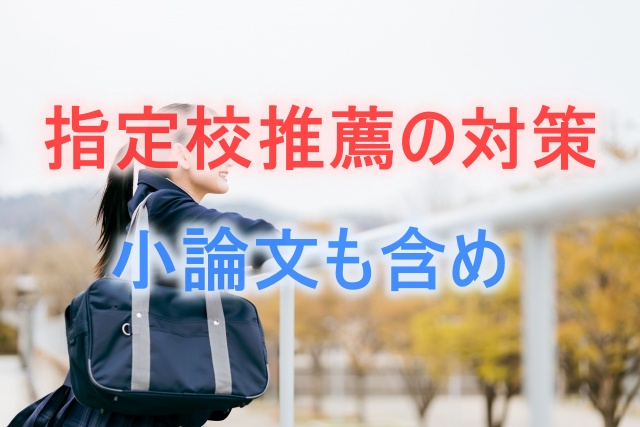
-500x336.png)

-500x336.png)


コメント