教育学部の志望理由書の書き方が分からず悩んでいませんか?
「800字も何を書けばいいか分からない」「どう構成すれば合格できるのか不安」そんな悩みを抱える高校生も多いでしょう。
この記事では、大学・教育学部800字での志望理由書の構成から例文、さらに教育学部の面接対策まで詳しく解説します。
本記事の方法で志望理由書を作成すれば、合格への道筋がはっきり見えるはずです!
関連記事

大学入試の志望理由書の構成

志望理由書を効果的に書くためには、自分の過去・現在・未来を整理し、それらを論理的に結びつけることが重要です。
ここでは、合格につながる志望理由書の構成について、3つのステップで解説します。
志望理由書の基本
志望理由書では、「なぜその大学・学部を選んだのか」という具体的な理由、「なぜその学問分野を志望するのか」を自身の体験や価値観と結びつけた説明、「入学後の学生生活と卒業後の将来ビジョン」という3つの要素を明確に示す必要があります。
これらを一貫性を持って組み立てることで、説得力のある志望理由書が完成するでしょう。
大学側は志望理由書を通じて、受験生の過去の実績、入学後の明確な目標、そして卒業後の進路と社会貢献への意欲を評価しています。
単に「興味があるから」といった抽象的な表現ではなく、その大学の特色やカリキュラム、教授陣の研究内容などを踏まえた具体的で説得力のある動機を述べることが合格への鍵となります。
書き方の基本については、以下も参照。
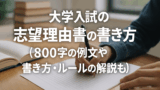
① まず今までやってきたことを考える
志望理由書の土台となるのは、これまでの経験や活動の振り返りです。高校生活で取り組んできた学習活動、部活動、ボランティア、課外活動など、あらゆる体験を洗い出してみましょう。
ただし、単なる活動の羅列ではなく、その活動を通じて何を学び、どのような能力を身につけたかを明確にすることが大切です。
例えば、生徒会活動に参加した場合、「生徒会長を務めた」という事実だけでなく、「学校行事の企画運営を通じて、多様な意見をまとめる調整力と、課題解決に向けた実行力を身につけた」といった具体的な学びを整理します。
活動の規模や結果の大小は問題ではありません。重要なのは、その経験から何を得たかという「プロセス」と「学び」です。
この段階では、将来の目標とは切り離して考え、純粋に自分の経験を客観視することから始めましょう。そうすることで、自分では気づいていなかった強みや関心分野が見えてくるはずです。
純粋に自分がこれまで何をどのように行ってきたのかを考えてみましょう。
② 次に将来像を考える
過去の経験を整理した後は、将来どのような人物になりたいかを具体的に描きます。
「教師になりたい」という漠然とした目標ではなく、「小学校教師として、一人ひとりの個性を大切にした学習指導により、子どもたちの学ぶ意欲を引き出す教育者になりたい」といった具体性が求められます。
将来像を考える際は、志望する大学や学部が育成を目指す人材像との整合性も意識しましょう。
教育学部であれば、単に「子どもが好き」というだけでなく、教育現場の課題を理解し、それに対してどのようなアプローチで貢献したいかまで踏み込んで考える必要があります。
また、将来像は現実離れした夢物語ではなく、努力によって実現可能な目標として設定することが重要です。
自分の適性や興味、社会のニーズなどを総合的に考慮し、説得力のある将来像を描きましょう。この将来像が志望理由書全体の方向性を決める重要な要素となります。
志望理由書を書いたあとの小論文対策はコチラ↓↓↓
↓ ↓ ↓ 小論文試験に必須の一冊 ↓ ↓ ↓
小論文の基本から、試験を想定した
実践練習まで、この一冊で身に付きます!
この一冊で小論文のお悩みすべて解決!
\ Amazonで400冊突破!/
③ ①と②のギャップを埋めるために学びたいことを考える
現在の自分と理想の将来像との間には必ずギャップが存在します。
このギャップこそが、大学で学ぶべき内容を明確にする鍵となります。
「今の自分には何が不足しているのか」「その不足を補うために、なぜその大学・学部でなければならないのか」を論理的に説明できれば、説得力のある志望理由が完成します。
例えば、「地域の教育格差解消に貢献する教師」を目指す場合、現在の自分には教育学の専門知識や、多様な学習ニーズに対応する指導技術が不足していると分析できます。
そのギャップを埋めるために、「貴大学教育学部の〇〇研究室で学習心理学を学び、△△教授のゼミで実践的な指導法を身につけたい」という具体的な学習計画を示すのです。
重要なのは、そのギャップが志望校でしか埋められない理由を明確にすることです。その大学・学部の特色ある教育プログラム、研究領域、教授陣の専門性などを具体的に調査し、自分の学習ニーズとの適合性を論理的に説明しましょう。
入りたい大学に合わせるのではなく、「自分の将来像に合う大学」「現在の自分と将来像のギャップを埋めてくれるために学べる大学・学部」という発想を持って志望先を選び書いてみましょう。
そのほうが嘘偽りのない志望理由書が書けますよ。
志望理由書の構成要素
① 今までやってきたこと
② 将来像
③ ①と②のギャップを埋めるために志望先で学ぶこと
大学・教育学部800字での志望理由書の例文

教育学部の志望理由書では、将来の教育観と具体的な実践方法を明確に示すことが重要です。
以下では、効果的な志望理由書を書くためのポイントと実際の例文を紹介します。
フワッとした目標ではなく具体的に書く
教育学部の志望理由書で最も重要なのは、将来の教育目標を具体的に描くことです。
「子どもが好きだから教師になりたい」「人に教えることが得意だから」といった抽象的な表現では、採点者の心に響きません。
代わりに、「どのような教育課題に取り組みたいか」「どのような授業を通じて子どもたちに何を伝えたいか」を明確に示しましょう。
例えば、「ICTを活用した個別最適化学習により、学習困難を抱える児童一人ひとりの可能性を最大限引き出す小学校教師」のように、具体的な教育手法と対象、目指す成果まで含めた目標設定が効果的です。
また、現代の教育現場が直面している問題意識を示し、それに対する自分なりの解決策を提示することで、教育への深い理解と熱意をアピールできます。
このような具体性は、あなたが教育について真剣に考え、将来への明確なビジョンを持っていることを証明し、採点者に強い印象を残すことができるでしょう。
面接で何を聞かれてもいいくらい掘り下げる
志望理由書に記載した内容は、面接において必ず深掘りされると考えておく必要があります。
書面では表面的に書いていても、面接では「なぜそう考えるようになったのか」「具体的にどのような取り組みをしてきたのか」といった詳細な質問が飛んできます。
そのため、志望理由書に書く内容は、すべて自分の体験や考察に基づいた本物でなければなりません。
例えば、「教育格差の解消」を目標として掲げる場合、実際に学習支援ボランティアに参加した体験や、地域の子どもたちとの関わりから得た気づき、関連書籍の読書体験などの具体的な根拠が必要です。
また、その体験から何を学び、どのような課題意識を持つようになったかまで整理しておきましょう。
面接官が「それについてもう少し詳しく教えてください」と質問したときに、エピソードを交えながら生き生きと語れる内容だけを志望理由書に記載することで、一貫性のある説得力のある志望動機を構築できます。
教育学部での800字の例文
私は将来、地域の教育格差解消に貢献する小学校教師として、すべての子どもたちが等しく学習機会を得られる社会の実現を目指している。現在の日本では、家庭環境や経済状況により子どもたちの学力に格差が生じており、この課題解決には教師一人ひとりの意識改革と実践的な指導力向上が不可欠である。私は貴大学教育学部で学習心理学と教育方法学を深く学び、多様な学習ニーズに対応できる教育者になりたい。
この目標を抱くようになったきっかけは、高校2年時に参加した学習支援ボランティアでの経験である。経済的困窮により塾に通えない中学生たちに勉強を教える中で、彼らが本来持っている学習意欲と潜在能力の高さに驚かされた。それは家庭の経済的な状況と学習意欲は必ずしも相関関係にないことを示している。
そして同時に、適切な学習環境と指導方法が提供されれば、どの子も大きく成長できることを実感した。この体験から、教育の機会均等の重要性を深く理解し、すべての子どもたちの可能性を引き出せる教師になりたいと強く願うようになった。しかし、どのようにしたらすべての子供たちの学習意欲と潜在能力を引き出せるのかという具体策が今の私にはない。
したがって現在の私には、教育現場で実際に格差を解消するための専門知識と実践的指導技術が不足していると痛感する。そこで貴学の教育学部で○○教授が研究されている「個別最適化学習理論」や、△△研究室で行われているICT活用教育の実践研究は、まさに私が目指す教育の実現に直結する学問分野である。また、貴学の教育学部の充実した教育実習プログラムを通じて、理論と実践を結びつけた深い学びを得たい。4年間の学びを通じて、教育格差という社会課題に真正面から取り組める教育者として成長していく決意である。(735字)
志望理由書をもとにした教育学部の面接

教育学部の面接では、提出した志望理由書を基に深い質問が投げかけられます。面接官は志望動機の本気度と具体性を確認したいと考えているため、適切な準備が合格の鍵となります。
書いた志望理由書はコピーを取っておく
志望理由書を提出した後は、必ず手元にコピーを残しておくことが重要です。
面接までには数週間から数か月の期間があるため、自分が何を書いたかを正確に覚えていない可能性があります。
面接官は志望理由書の内容を詳細に把握した状態で質問してくるため、書いた内容と異なる回答をしてしまうと一貫性に欠けると判断される恐れがあります。
コピーを保管する際は、単に手元に置くだけでなく、定期的に読み返すことが大切です。特に面接が近づいてきたら、志望理由書の内容を完全に把握するまで繰り返し確認しましょう。
また、書いた当時の心境や、なぜその表現を選んだのかという背景も思い出しておくと、面接で詳細を聞かれた際に自然に答えることができます。
デジタルデータとして保存する場合は、印刷版も用意しておくことをお勧めします。紙で読む方が内容を把握しやすく、重要な箇所にマーカーを引くなどの準備も効率的に行えるからです。
書いた時の初心を思い出しながら面接まで内容を把握しておきましょう。
志望理由書に書いたことは、すべて聞かれるつもりで準備をする
面接官は志望理由書の一文一文に注目し、そこから深掘りできる質問を用意しています。そのため、志望理由書に記載したすべての内容について、詳細に説明できるよう準備する必要があります。
特に、具体的な体験談や将来の目標については、「なぜそう思ったのか」「どのような変化があったのか」といった背景まで整理しておきましょう。
例えば、「学習支援ボランティアに参加した」と書いた場合、活動期間、対象者、具体的な指導内容、困難だった場面、その解決方法、得た学びなど、あらゆる角度からの質問を想定してください。
また、「教育格差の解消」を目標に掲げた場合は、その社会問題についての基本的な知識や、なぜ自分がその課題に取り組みたいと考えるのかという根本的な動機まで説明できるよう準備しましょう。
さらに、志望理由書に書いた内容と関連する時事問題や教育理論についても基本的な知識を身につけておくと、より説得力のある回答ができるようになります。
結論 → 理由で簡潔に答える
面接では限られた時間の中で自分の考えを正確に伝える必要があるため、回答は簡潔かつ論理的に構成することが重要です。
最も効果的な答え方は、まず結論を明確に述べ、その後に理由や根拠を簡潔に説明する構成です。この方法により、面接官は回答の要点を即座に理解でき、好印象を持ってもらえます。
具体的には、質問に対して30秒程度で結論を述べ、残りの30秒で具体例や理由を説明するのが理想的です。
例えば、「なぜ教師を目指すのか」という質問には、「子どもたち一人ひとりの可能性を最大限引き出したいからです。学習支援ボランティアで、適切な指導により学習困難を抱える生徒が大きく成長する姿を見て、教育の持つ力を実感しました」といった構成で答えます。
長々と話してしまうと要点が伝わりにくくなるだけでなく、面接官に「論理的思考力が不足している」と判断される可能性もあります。事前に主要な質問に対する回答を1分以内にまとめ、実際に声に出して練習しておきましょう。
面接の練習をする
面接本番で緊張せずに実力を発揮するためには、事前の練習が不可欠です。
一人で練習することも重要ですが、可能な限り他者に面接官役を依頼し、実際の面接に近い環境で練習することをお勧めします。
学校の先生などに協力してもらい、様々なパターンの質問を投げかけてもらいましょう。
練習の際は、単に回答内容を確認するだけでなく、声の大きさ、話すスピード、表情、姿勢などの非言語コミュニケーションにも注意を払ってください。
教育学部の面接では、将来教壇に立つ人物としての資質も評価されるため、人に物事を伝える能力が重要視されます。明るく自信を持った話し方ができるよう、繰り返し練習しましょう。
また、想定外の質問をされた場合の対応も練習しておく必要があります。
知らない内容について質問された際は、素直に「勉強不足で申し訳ありません」と答えた上で、関連する知識や自分なりの考えを述べる練習をしておくと、本番での対応力が向上します。
教育学部は、志望理由書と面接が他学部よりも連動しているので、志望理由書を書くときは面接を意識して書き、志望理由書と面接でワンセットの試験だと考えておきましょう。
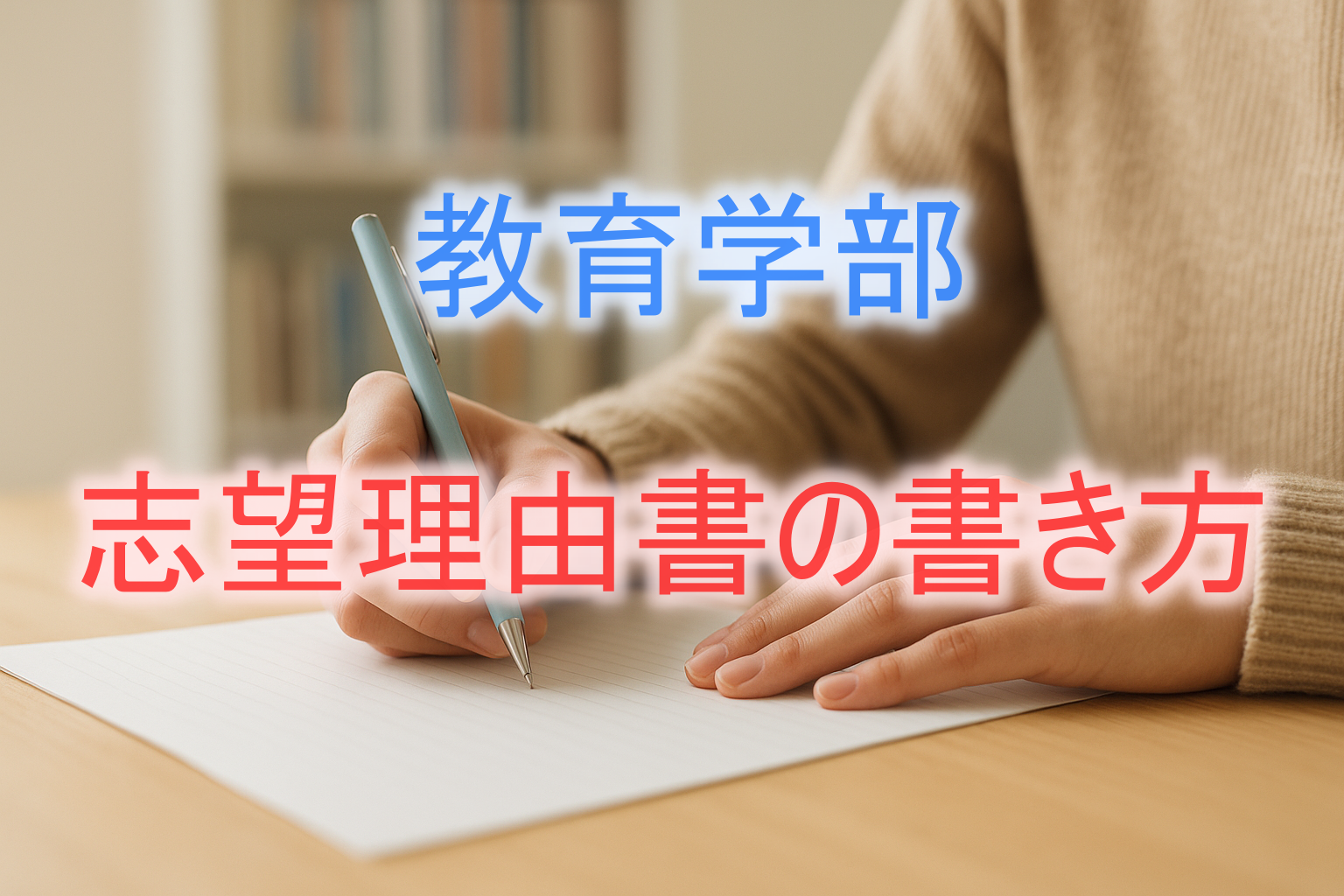
-500x336.png)


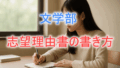

コメント