「法学部の志望理由書の書き方が分からない」「将来の夢がないのに志望理由なんて書けない」そんな悩みを抱えていませんか?
法学部の志望理由書は、社会課題を法的視点で解決したいという意欲を示せば、説得力のある志望理由書が完成します。
本記事では、「夢ない」状態からでも書ける志望理由の見つけ方から、憲法や人権への理解の示し方、大学選択理由の書き方、800字での具体的な例文まで、あなたが「書けない」から「書ける」に変わる法学部志望理由書作成法を詳しく解説します。
関連記事

大学の志望理由書(法学部)の 書き方

法学部の志望理由書を書く上で重要な4つのポイントについて詳しく解説します。これらの視点を理解することで、合格に近づく志望理由書を作成できるでしょう。
① 法の観点から社会課題を解決する
法学部の志望理由書では、社会にある様々な問題を法律という手段で解決したいという姿勢を示すことが重要です。
現代社会には格差問題、環境問題、人権侵害など多くの課題が存在しており、これらに対して法的なアプローチで向き合う意欲を表現しましょう。
具体的には、自分が関心を持つ社会課題を一つ選び、それがなぜ重要なのかを説明します。
たとえば、労働問題に興味がある場合は「働き方改革関連法案の意義」について触れたり、環境問題であれば「環境法の役割」について言及することで、法律への理解を深めたい理由が明確になります。
単に「社会貢献したい」というだけではなく、具体的にどのような課題に、どのような法的手段でアプローチしたいかを示すことで、説得力のある志望理由となります。
志望理由書の基本的な書き方は、以下を参照
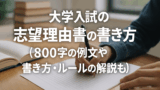
② 憲法や人権の考え方は必須
憲法は法学部で学ぶ基礎的な分野であり、志望理由書でも憲法や人権への理解を示すことは欠かせません。
憲法は国家権力を制限し、国民の基本的人権を保障する最高法規であり、法学を学ぶ上での土台となる重要な科目です。
志望理由書では、憲法第13条の個人の尊重、第14条の法の下の平等、第25条の生存権など、具体的な条文に触れながら自分の関心を表現するとよいでしょう。
ただやみくもにこれらを書くのではなく、自分の志望理由や学びたいことに合わせて書くようにしましょう。
また、現在進行中の憲法に関する議論や判例についても言及できれば、時事問題への関心の高さもアピールできます。
ただし、憲法改正などの政治的な問題については、偏った立場を取らず、学問的な視点から客観的に捉える姿勢を示すことが大切です。
人権問題についても同様に、理論的かつ冷静な分析力があることを伝えましょう。
③ 憲法と法律の違い
法学部志望者として、憲法と一般的な法律の違いを正しく理解していることを示すのも重要なポイントです。
憲法は国家の基本的な統治構造を定め、国民の権利を保障する最高法規である一方、法律は憲法の範囲内で国会が制定する具体的なルールです。
平たくいうと、法律は国家権力による強制力で国民を拘束するルールであり、憲法はその国家権力を拘束して国民の人権を守るための最高法規です。
かつての治安維持法のような「(思想的に)あいつが気にくわないから逮捕できる」法律を仮に国が制定しても、現行の日本国憲法の基本的人権に反するため、その効力は無効となります。
このように不当な国家権力の行使から、国民の身体や生命、財産などを守る最高法規が憲法という位置づけです。
したがって憲法の下に法律があり、憲法の内容に反する法律は無効となります。厳密にはその法律を無効とするためには違憲審査を経なければいけませんが。
この違いを理解していることで、法学への基本的な知識があることをアピールできます。
たとえば「憲法で保障された表現の自由が、具体的にはどのような法律で実現されているのか学びたい」といった表現を使うことで、憲法の理念が個別の法律にどう反映されているかという法体系全体への関心を示せます。
また、憲法違反の疑いがある法律について憲法裁判所(日本では最高裁判所)が判断を下すという司法制度についても触れられれば、より深い理解を持っていることが伝わります。
④ 社会的な出来事に関心をもつ
法学部で学ぶ内容は常に社会情勢と密接に関わっているため、時事問題への関心を示すことも志望理由書では重要です。
最近のニュースや社会的な動きに対して、法的な観点からどのような疑問や関心を持っているかを具体的に書きましょう。
たとえば、SNSでの誹謗中傷問題に関連して「表現の自由と人格権のバランス」について考えたことや、コロナ禍での緊急事態宣言を通じて「行政権の行使と国民の権利制限」について疑問を持ったことなど、身近な出来事と法学の結びつきを示すことができます。
ただし、時事問題を取り上げる際は、一方的な意見を述べるのではなく「この問題について法学の観点から深く学んでみたい」という学習意欲を中心に据えることが大切です。
また、古い事例ではなく比較的新しい社会問題を選ぶことで、現在進行形で社会に関心を持っていることもアピールできます。
「将来の夢ないし」法学部の志望理由が思いつかない

法学部への進学を考えているものの、将来の夢がはっきりしない高校生は少なくありません。しかし、明確な将来像がなくても効果的な志望理由書は作成できます。
法学部で学べること
法学部では幅広い法分野を体系的に学ぶことができ、これらの知識が将来の進路選択の指針となります。
民事法では契約や不法行為など私人間の法律関係を、刑事法では犯罪と刑罰について学習します。憲法は国家権力の制限と基本的人権の保障を扱い、国際法は国家間の関係を規律する法律です。
国際人権法は近年注目が高まっている分野で、世界各国における人権保護の仕組みを研究します。
これらの分野は相互に関連しており、例えば憲法で保障された人権が民事法でどう実現されるか、刑事法における被疑者の権利はどう守られるかなど、法律全体を俯瞰的に理解できるのが法学部の特色です。
将来の具体的な目標が決まっていなくても、まずはこれらの法分野に触れることで自分の関心のある領域を見つけることができます。
【法学部で学べること】
刑事法:犯罪と刑罰についての学習
憲法:国家権力の制限と基本的人権の保障
国際法:国家間の関係を規律する法律
国際人権法:人権に関する条約や宣言、これらを実施する制度や手続き
「何を学びたいのか、なぜ学びたのか」が重要
法学部の志望理由書では将来の夢よりも「何を学びたいのか」という学習意欲の方が重要視されます。
法学部への関心を持ったきっかけとして、ニュースで見た社会問題、家族や友人との議論、高校の授業での気づきなど、身近な体験から法律への興味を見つけることができます。
たとえば「SNSでの誹謗中傷問題を見て、表現の自由と人格権のバランスについて深く考えたい」「コロナ禍での緊急事態宣言を通じて、国家権力と個人の自由の関係を学びたい」といった具体的な関心を示すことが効果的です。
重要なのは「なぜその問題に関心を持ったのか」「どのような観点から学びたいのか」を明確にすることです。
将来の職業は決まっていなくても、法学への知的好奇心があることを伝えれば十分に説得力のある志望理由となります。
法学の分野で将来この仕事に就きたいなど、はっきりした目標のある高校生はあまりいませんよね。
ですから何を学びたいのかが重要になってきます。
その大学の法学部を選んだ理由
志望校選択の理由は、他大学との差別化を図る重要な要素です。
各大学の法学部には独自の特色があり、カリキュラム、教授陣、ゼミの内容、司法試験対策などを具体的に調べて比較することが必要です。
例えば「A大学には企業法務に強い教授陣が揃っている」「B大学では1年次から少人数のゼミが設置されている」「C大学は国際法分野での研究実績が豊富」といった特徴を見つけることができます。
大学のウェブサイトやパンフレットを詳しく調べ、オープンキャンパスに参加して実際の雰囲気を確認することも大切です。
また、その大学でしか学べない特別な授業や、興味のある教授の存在、充実した図書館などの学習環境についても具体的に触れることで、真剣に大学研究を行ったことが伝わり、志望度の高さをアピールできます。
将来「こんな感じになりたい」くらいは書く
具体的な職業が決まっていなくても、大まかな方向性は示すことができます。
法学部志望者は一般的に「正義と平等への関心を持つ人」「社会問題の解決に貢献したい人」「法の専門家として活躍したい人」「個人の権利保護について学びたい人」「法律の枠組みを理解したい人」に分類されます。
法学部というと弁護士や検察官、裁判官といった法曹三者が思い浮かびますが、実際の進路はもっと多様です。
法律実務家として企業の法務部門で働く道、法学研究者として大学で教鞭を取る道、国家公務員や地方公務員として行政に携わる道などがあります。
「将来は法的な知識を活かして社会貢献したい」「公正な社会の実現に向けて働きたい」といった抽象的な表現でも構いません。
大切なのは法学を学ぶことで自分がどのような人間に成長したいのかという意欲を示すことです。
法学部志望の場合は、学べることや学校・学部などの特色から志望理由や将来の目標を設定してみるという、他の学部とは逆向きに考えてみるとよいかもしれませんね。
その他、夢がない時の対処法
夢がないことを過度に悩む必要はありません。多くの経験や出会いの中で夢は自然と見つかるものであり、現在の状況は一時的なものと考えることができます。
まず大切なのは、自分の現在の関心事や好奇心を振り返ることです。完璧な夢でなくても、少しでも興味を持てる分野があれば、それが出発点となります。
次に、小さな目標を設定することが効果的です。
将来の大きな夢ではなく、今できることや近い将来に達成したいことから始めてみましょう。
例えば「人とのコミュニケーションを深めたい」「社会の仕組みを理解したい」といった身近な関心も、立派な動機になります。
また、様々な経験を積むことで新たな発見が生まれる可能性があるため、積極的に行動することも重要です。
夢は無理に作り出すものではなく、生活の中で自然に育まれていくものであることを理解し、焦らずに自分のペースで見つけていけばよいのです。
大学の志望理由書、法学部での800字例文

実際の志望理由書例文を通して、効果的な書き方のポイントを具体的に理解しましょう。失敗例とOK例の比較で基本を押さえ、3つの進路別例文で応用を学べます。
失敗例文
法学部の志望理由書でよく見られる失敗パターンの例文です。抽象的な表現が多く、具体性に欠けているため説得力がありません。また、その大学を選んだ明確な理由が書かれていない点も問題です。
この例文の問題点は「法律は重要」「正義感が強い」といった抽象的な表現に終始していることです。また、なぜその大学の法学部なのかという理由が全く示されていません。
OK例文
具体的な体験や関心を示し、その大学を選んだ明確な理由が書かれているため説得力があります。自分の問題意識と学習目標が明確に表現されています。
この例文は具体的な体験、明確な学習目標、その大学を選んだ理由が適切に盛り込まれています。
800字の例文
(弁護士志望の例)
私は貴学法学部で法律を学び、将来は弁護士として社会正義の実現に貢献したいと考えている。この志望を抱くきっかけとなったのは、高校1年生の時に参加した模擬裁判である。被告人の立場に立って弁論を行う中で、適切な法的主張の重要性を痛感した。また、SNSでの誹謗中傷問題が社会問題化する中、被害者の人権を守りつつ表現の自由とのバランスを取る難しさを実感し、法律の専門知識の必要性を強く感じるようになった。特に印象的だったのは、ある有名人がSNSで受けた中傷により精神的苦痛を訴えた裁判を目にした時である。名誉毀損と表現の自由の境界線がどこにあるのか、法的根拠に基づいた判断の重要性を深く理解した。
貴学法学部を志望する理由は、実務に直結した教育体制が整っていることである。特に山田教授の「民事訴訟実務」のゼミでは、実際の判例を用いた模擬法廷が開催されており、実践的なスキルを身につけることができる。また、田中教授の「企業法務研究」では、現役弁護士を招いた講義が定期的に開催され、実際の法律事務所での業務内容を詳しく学ぶことが可能である。さらに、貴学は司法試験合格者数で全国上位の実績を誇り、充実した司法試験対策講座が用意されている点も大きな魅力である。
入学後は憲法、民法、刑法の基礎をしっかりと学んだ上で、民事法分野を中心に専門知識を深めたい。特に契約法や不法行為法について詳しく研究し、企業法務にも対応できる幅広い知識を習得したいと考えている。現代社会では企業活動が複雑化しており、コンプライアンス体制の構築や国際取引に関する法的問題など、多様な分野での専門性が求められているからである。
また、民事調停や家事調停などの裁判外紛争解決手続きについても学び、依頼者にとって最も適切な解決方法を提案できる能力を身につけたい。将来は依頼者の立場に立って最善の解決策を提案できる弁護士となり、法の力で社会に貢献していきたい。(798字)
(法の研究者志望の例)
私は貴学法学部で憲法学を学び、将来は法学研究者として学術分野で貢献したいと考えている。この志望を持つようになったのは、高校の現代社会の授業で日本国憲法第9条について学んだことがきっかけである。平和主義の理念と自衛隊の存在という現実の間にある複雑な問題について考える中で、憲法解釈の奥深さに魅力を感じるようになった。特に集団的自衛権の行使容認をめぐる議論では、憲法第9条の文言と政府解釈の変遷について詳しく調べ、憲法学における解釈論の重要性を実感した。
また、コロナ禍における緊急事態宣言の発令により、国民の行動制限と憲法が保障する自由権の関係について深く考察するようになった。営業の自由や移動の自由といった経済的自由権が公衆衛生という公共の利益のためにどこまで制限されうるのか、比較衡量論の観点から研究したいと思うようになった。
貴学法学部を志望する理由は、憲法学分野での研究実績が豊富であることである。特に佐藤教授の人権論ゼミでは、最新の判例分析を通じて憲法解釈の現代的課題に取り組むことができる。また、田村教授の統治機構論では、三権分立の現代的意義について比較憲法学の視点から学ぶことが可能である。さらに、貴学の法学部には充実した法学図書館があり、国内外の法学文献を幅広く収集している環境も研究を志す私には理想的である。ドイツ語やフランス語の憲法学文献も豊富に所蔵されており、比較憲法研究に必要な資料を十分に活用できる。
入学後は憲法の基本原理を学んだ上で、特に基本的人権の現代的展開について研究したい。新しい人権概念の理論構築や、デジタル社会におけるプライバシー権の在り方、AI技術の発展が人権保障に与える影響などを中心に学術論文の執筆にも挑戦したい。将来は大学院に進学し、博士号取得後は大学教員として後進の指導にあたりながら、憲法学の発展に寄与していきたい。(779字)
(国際機関で勤務志望の例)
私は貴学法学部で国際法を学び、将来は国際機関で働きながら世界の平和と発展に貢献したいと考えている。この目標を抱くようになったのは、高校2年生の時に国連の活動について調べる機会があったことがきっかけである。特に国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の活動を知り、法的手段を通じて難民の権利保護に取り組む意義を深く感じた。また、近年のウクライナ情勢やミャンマー問題を見る中で、国際法の重要性と限界について考えるようになった。ロシアによるウクライナ侵攻では国際法違反が明白であるにもかかわらず、国連安保理が機能不全に陥る現実を目の当たりにし、国際法の実効性確保という課題に強い関心を抱いた。
貴学法学部を志望する理由は、国際法分野での教育が充実していることである。特に田中教授の国際人権法ゼミでは、実際の国際裁判所の判例を用いた研究が行われており、理論と実務の両面から学ぶことができる。山本教授の国際機構法では、国連システムの構造的問題について批判的に検討する授業が展開されており、国際法の限界と可能性を深く学べる点に魅力を感じている。
また、貴学では毎年国際模擬裁判大会に参加しており、実践的な国際法の知識を身につけることが可能である。昨年度は国際司法裁判所模擬法廷で優秀な成績を収めた実績もあり、高いレベルでの学習環境が整っている。さらに、英語での法学論文執筆指導も行われているため、国際的な場で活躍するために必要なスキルを習得できる。
入学後は国際法の基礎から応用まで体系的に学び、特に国際人権法と国際人道法について専門知識を深めたい。武力紛争下での文民保護や、国際刑事法における個人責任の追及メカニズムについても研究したいと考えている。また、国連やその他の国際機関でインターンシップに参加し、実務経験も積みたい。将来は国際公務員として、法の力で国際社会の課題解決に取り組んでいきたい。(786字)
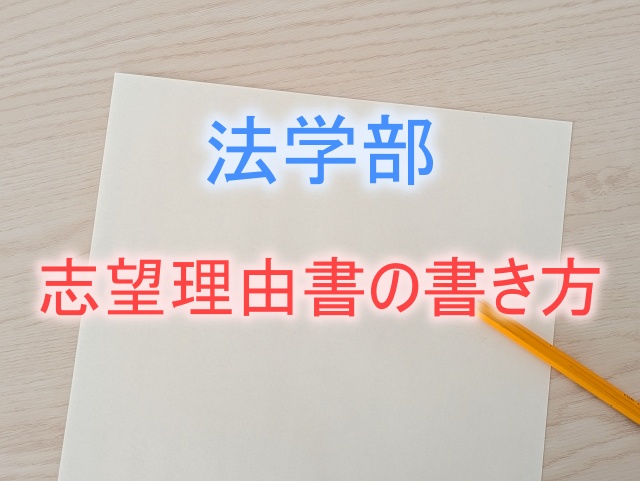
-500x336.png)


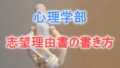
コメント