「小論文を書いたけど、添削を誰に頼めばいいの?」「親や学校の先生だと恥ずかしいし、何かいろいろ言われそうで怖いわ!」
確かに、自分の書いた小論文の内容をいろいろ言われたり、ともすると否定されるようなことは怖いですよね。
ただ、他者の視点で添削を受けないと小論文は上達しないので、やはり添削を受けるということは、どうしても必要です。
特に人の評価が「何言われるか分かんなくて怖い、嫌だわ!」という人は、まず無料の添削アプリなどを使って、ある程度評価されることに慣れてきたら、人の添削や評価を受けるという段階を踏むことがオススメです。
ここでは、小論文を書いた後の添削を受ける手順を紹介します。
あわせて、他では紹介されない裏ワザの添削方法も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
今回学ぶこと
- 小論文の添削方法
- 添削してくれる人がいないときの見つけ方
- 添削の裏ワザ法
関連記事
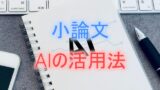
小論文の添削を受けるのは怖い?

「小論文を書いたけど、人に見せたくないな」「学校の先生や自分の親だと何言われるか分からないから嫌だな!」
その気持ちはよく分かります。
人に読まれるような文章を書くようになった私も、今でもそういう気持ちはあります。
これは小論文に限らず、他のジャンルの文章を書く際にもそういう抵抗があり、どんな著名人と言われる人でも持っている気持ちなのでしょう。
ですから、あなたが「自分の書いた小論文を人に見せるのは嫌だな」という気持ちは自然なことです。
しかし、その気持ちにこだわりすぎて添削や評価を受けないと、いつまでたっても合格できる小論文が書けるようにはなりません。
「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」という言葉があるように、上達するためには初めに多少の恥をかいても、後で小論文が書けるようになって帳消しにしてしまいましょう。
小論文の添削アプリ

とはいえ、人の添削を受けるのにまだ抵抗があるという人は、初めは無料の文章添削アプリやチャットGPTなどを使ってみましょう。
添削で使える無料アプリには、「PRUV 」「Grammarly」「Hemingway Editor」などがありますが、言語が英語で手続きが少し面倒なことや、数万円分の広告を決められた日数以内に掲載して実質無料といったリスクがあります。
そこで、本当に無料で気軽に使える添削アプリは「チャットGPT」です。
誤字脱字だけではなく、内容自体の修正案や評価を下してくれます。
私もチャットGPTでの添削を試したところ、修正後の解答例によっては「なるほど、いい感じの文章だね」というものもありました。
ただ修正の解答例によっては、むしろ表現が冗長になったり、不必要な言い回しがあったりと小論文の解答例としてはイマイチなものもあります。
そして添削の無料アプリやチャットGPTなどは、ある程度の添削をしてくれますが、その模範解答だけでは不十分なので、やはり最終的には身近な信頼できる大人に添削してもらうことが一番です。
それに小論文の試験は手書きで書くので、やはり手書きで書いたものを字が読みやすいかどうかも含め、練習で添削してもらうと良いでしょう。
添削方法の裏ワザ

これは他でなかなか紹介されず裏ワザの方法ですが、新聞の読者投稿に小論文の書き方を意識した文章を投稿して掲載されるというものです。
これはある程度の文章が書けないと、そもそも掲載されないので、ある程度小論文が書けるようになってからですが、誰でも無料でリスクなく投稿できます。
そして掲載されると多少文章が修正されることが多いので、自分の書いた原稿と掲載された内容を見比べて、どこが修正されたのかを確認するといいでしょう。
これは新聞記者という文章を書くプロから添削を受けたことになります。
しかも私の地元の地方新聞では、1回掲載されるごとに1,000円分ほどの図書カード1枚がもらえるので教材費に充てることもできます。
独学で小論文を学習するには添削が欠かせない

とくに独学で小論文の学習を進める場合には、書いた答案の添削を受けて、修正を反映し、再び書いてまた添削を受けるというプロセスは欠かせません。
↓ ↓ ↓ もっと詳しく学びたい人はコチラ ↓ ↓ ↓
小論文の基本から、試験を想定した
実践練習まで、この一冊で身に付きます!
この一冊で小論文のお悩みすべて解決!
\ Amazonで400冊突破! /
また上記で紹介した無料添削アプリや裏ワザ法は、あくまで身近な信頼できる大人の添削を受ける補助的な役割に過ぎず、必ず人の添削を受けることと組み合わせて使うことが望ましいです。
そして最終的な練習は、やはり手書きで小論文を書いて、字が読みやすいかどうかも含め信頼できる身近な大人の人に添削をしてもらうと良いでしょう。
模試ならば、多少読みにくく汚い字でも頑張って読んでくれますが、大学入試や就職試験での読みにくい字の答案は、それだけでまず読んでもらえません。
つまり、どれだけ内容が良くても小論文では不合格扱いをされてしまいます。
したがって、小論文の解答は基本的に原稿用紙の形式に手書きで書いて、信頼できる身近な大人の人の添削を受けるようにしましょう。
その補助的な役割として無料添削アプリや新聞への投稿などの方法も活用してみてください。
小論文を添削してくれる人がいない

身近に小論文を添削してくれる人がいない場合、多くの受験生が不安を感じています。
自己添削では気づけない問題点や改善点を見つけることは難しく、効率的に実力を伸ばすためには第三者からの客観的な評価が欠かせません。
ここでは、添削者がいない状況でも対策できる方法を紹介します。
添削先をどこにするか?
自分の書いた小論文の添削をどこに見てもらうか分からないという人は、有料ツールを利用する前に以下の無料アプリを活用してみてください。
上記はすべて無料の方法で添削が行えます。
有料の添削サービス
プロの指導を受けるなら、有料の添削サービスが最も確実な選択肢です。
オンラインの添削サービスは、場所や時間を選ばずに利用できる大きなメリットがあります。
代表的なサービスとして「小論文添削ドットコム」は入会金不要で、1200字あたり3000円程度から利用可能です。文字数に応じた料金体系なので、必要な文章だけを選んで依頼できる柔軟性が魅力です。
教育大手のベネッセが提供する「小論文特講」は、学部系統別の対策ができる総合的なサービスです。WEB講義や動画コンテンツで基礎から学べるほか、7回分の添削が含まれています。16,500円の買い切り型なので、計画的に利用したい方におすすめです。
個人間でのやり取りを望む場合は、スキルマーケット「ココナラ」も選択肢の一つです。志望校の合格者や現役の教育関係者に直接添削を依頼できるため、より具体的なアドバイスが得られる可能性があります。1回あたり1,000円~3,000円程度で利用でき、添削者の評価を確認してから依頼できる安心感もあります。
サービス選びでは、志望校の合格実績や添削者の経歴、料金体系、対応の速さなどを総合的に比較検討することが大切です。最初は1回だけ試してみて、相性が良ければ継続利用するという方法もおすすめです。
添削サービス比較表
| サービス名 | 特徴 | 料金体系 | おすすめポイント |
|---|---|---|---|
| 小論文添削ドットコム | ・入会金不要 ・文字数に応じた料金体系 ・必要な文章だけ依頼可能 |
1200字あたり3000円程度~ | 柔軟性が高く、必要なときだけ利用したい方に |
| ベネッセ「小論文特講」 | ・学部系統別の対策可能 ・WEB講義や動画コンテンツ提供 ・7回分の添削付き |
16,500円(買い切り型) | 基礎から学びたい方、計画的に利用したい方に |
| ココナラ | ・個人間でのやり取り ・志望校合格者や教育関係者に依頼可能 ・添削者の評価確認可能 |
1回あたり1,000円~3,000円程度 | 志望校に特化したアドバイスが欲しい方に |
・小論文添削ドットコム
・ベネッセ「小論文特講」
・ココナラ小論文添削
サービス選びのポイント
- 志望校の合格実績
- 添削者の経歴
- 料金体系
- 対応の速さ
※最初は1回だけ試して、相性が良ければ継続利用するのがオススメ。
信頼できる大人を見つける
身近な環境で添削してくれる人を探すことも有効な方法です。
まず候補となるのは学校の先生、特に国語科の教員ですが、必ずしも国語の先生が小論文の適切な指導ができるとは限らないことも覚えておきましょう。
学校によっては社会科など、他の教科の先生できちんとした添削ができる人もいます。
添削をお願いするときは、授業後や放課後の時間を活用して相談してみましょう。進路指導室の先生も小論文指導の経験がある場合が多いので、積極的に声をかけてみることをおすすめします。
また地域の図書館や公民館で開催される学習支援イベントも活用できます。
どのような方法でも、添削を依頼する際は礼儀正しく、相手の時間を尊重する姿勢が大切です。また、一度限りではなく継続的に指導を受けられる関係を築くことで、より効果的な学習が可能になります。
小論文添削でのAIのレベル

ここでは実際に無料の有効なツールと言われているAI(チャットGPT、Claude)を使って添削した結果を紹介します。
AIに添削してもらう場合の参考にしてみてください。
チャットGPTによる添削
「以下の小論文の添削をして」と入力しました。
例題2:科学を学ぶ意義は何か、あなたの考えを論じなさい。〔大学入試〕
〔解答〕
科学を学ぶ意義とは、未だ解明されていない自然法則を理解し、それを技術に反映させ、人の生活を豊かにしようとするものである。さらに、放射線の原理など自然の法則を理解することで、危機に際して自らの身を守ることにつながり、ひいては人権を守ることにもつながる。したがって私は、すべての人に科学を学ぶ意義があると考える。なぜなら、科学とは上記のように、私たちの日常生活にも直結するものであり、人が生活していく上で、これら科学を学ぶ意義と無関係な人はいないからである。
確かに、科学は万能ではないし、使い方を誤れば福島原発事故のように、私たちの生活を破壊し、古里を追われ、人によっては一生癒えることのない心の傷を負わされることもある。しかし、未だ解明できない自然の法則があることが判明するのも科学を学ぶ意義であり、また過去の誤った科学の利用を検証し、未来の科学の学びに生かし、私たちの生活にも反映させることが大切である。したがって、すべての人に科学を学ぶ意義があると考える。
添削結果
【論理構成の観点】
主張が明確に示されている点は良いですが、「科学を学ぶ意義」と「科学のリスク」に触れる部分のバランスが少し曖昧です。リスクを指摘する部分が中途半端に終わっており、科学を学ぶ意義への肯定的な論点が弱まっているように感じます。この点を補強し、リスクをどう活用するべきか具体的に言及することで、全体の説得力が高まります。
【誤字脱字の観点】
「人が生活していく上で、これら科学を学ぶ意義と無関係な人はいないからである。」
→ 「これら科学を学ぶ意義」を「科学を学ぶ意義」に簡潔化すると良いです。
【表現方法の観点】
いくつか冗長な表現や不自然な部分を修正します。
原文:「未だ解明されていない自然法則を理解し、それを技術に反映させ、人の生活を豊かにしようとするものである。」
→ 修正案:「未解明の自然法則を理解し、それを技術に応用して人々の生活を豊かにすることだ。」
冗長表現を削除し、簡潔にしました。
原文:「したがって私は、すべての人に科学を学ぶ意義があると考える。」
→ 修正案:「そのため、すべての人に科学を学ぶ意義があると私は考える。」
言葉の流れを整え、より自然にしました。
チャットGPTによる模範解答
科学を学ぶ意義とは、未解明の自然法則を理解し、それを技術に応用して人々の生活を豊かにすることだ。また、放射線の原理のような自然法則を理解することで、危機的状況において自らの身を守る力を養うことにもつながる。ひいては、これが人権を守る手段にもなるため、私は科学を学ぶ意義をすべての人に共有すべきだと考える。
確かに科学は万能ではなく、使い方を誤れば福島原発事故のように、人々の生活を破壊し、ふるさとを失う人々を生み出す悲劇にもつながる。しかし、これも科学を学ぶ意義の一つである。なぜなら、科学を学ぶことで過去の誤りを検証し、未来の科学技術の発展に生かすことができるからだ。科学をただ否定的に捉えるのではなく、その可能性と限界を認識しながら学び続けることが重要である。
さらに、科学は日常生活にも密接に関係している。スマートフォンやインターネットといった現代社会を支える技術は、科学の成果そのものであり、それらを活用する上でも科学的知識が必要不可欠である。科学を学ぶことで、私たちはただ技術を使うだけでなく、その背景や仕組みを理解し、よりよく活用する力を得ることができる。
このように、科学を学ぶ意義は多岐にわたる。自然の法則を理解すること、危機に対応する力を養うこと、技術を活用する能力を高めることのすべてが含まれる。科学の発展が人々の生活を豊かにする一方で、そのリスクも理解し、過去の教訓を未来に生かすことが必要だ。科学を学ぶ意義は、すべての人の生活に関わるものであり、現代社会で生きる私たち全員にとって重要である。(794字)
文章が少し唐突であったり、「現代社会で生きる私たち全員にとって重要である」と違和感のある部分があるものの、なかなかの模範解答を書いてくれます。
添削ポイント
冒頭の明確化
「目指す教師像」を簡潔に述べ、その具体的な内容を補足しました。具体例の活用と洗練
元の例文にあった具体例を活かしつつ、説明を整理し、説得力を高めました。生徒への助言の意図をより分かりやすく表現しました。経験の関連性を強調
自身の経験をより深く掘り下げ、目指す教師像との関連性を明確に示しました。結論の力強さ
教師としての使命感や決意を明確に述べ、教育理念を基盤にした論旨の一貫性を高めました。
他の解答でも、小論文としてどんなに良い文章を書いても「良い点」と併せて改善点やアドバイスをくれるので、「なんだよ、イチャモンつけるのかよ!」と思わずに参考にしてみましょう。
Claudeによる添削
【例題】:あなたの目指す教師像とは、どのようなものか、本県の教育理念を踏まえた上で述べなさい。
「一人ひとりの子どもたちに向き合う教育」という本県の教育理念を踏まえて、私の目指す教 師像は、生徒一人ひとりをきちんと見て、日々の学習と結び付け、その可能性を引き出してあげることだ。これは、たんに教科の学習を行うことではなく、学習以外でも、その子の優れていること、得意なこと、可能性のあることを見極め、その可能性を日々の学習と結び付けて、引き上げていくこと だ。
私は小学校の教員を志望しているが、例えば、ある生徒が教科学習は苦手だが、走ることが得意なら、「○○君は走るのが速いね。算数や国語も、もう少しできるようになると、走るペース配分も 考えられるし、完走後のインタビューにきちんと答えられて、カッコよく見えるよ」と生徒自ら「そうか、やってみよう」と思える助言を与えてあげることだ。
私がこう考えるようになったのは、小学校3年生のときの担任の先生が、「○○さんは勉強がで きるだけでなく、人に教えるのも上手だよね」と言ってくれたことだ。それまで私は、自分はただ学 校の勉強ができるだけで、他に何も取り柄などないと思っていたのだ。しかし、その先生の言葉をき っかけに、教科学習で同級生に教えるようになり、「○○さんの説明は、わかりやすくて助かる。あ りがとう」と感謝され、人に説明できるよう学習に努めることで、さらに自らの学習にもつながって いった。そこから自分の可能性を発見し、教師の道を目指すようになった。
したがって、日々の学習も大切だが、その子の得意なこと、優れていることなど、生徒一人ひと りの可能性と結び付けて、それぞれの教科学習が、その可能性にどのように役立つのかを伝えれば、 学習にも意欲がわき、同時にその子自身も伸ばせる。そこで身についた努力する大切さや自信が、生 徒一人ひとりの、今後の人生における糧となるはずだ。このように、生徒一人ひとりの可能性を見極 め、その可能性を引き上げる教師を目指したい。(791字)
「上の問題で書いた下の解答の評価と添削をして」とお願いしました。
評価と添削
総合評価
この解答は「一人ひとりの子どもたちに向き合う教育」という県の教育理念を踏まえた教師像を述べており、基本的な構成と内容は良好です。特に個人的な経験を交えながら具体例を示している点は高く評価できます。ただし、改善すべき点もいくつかあります。
良い点
- 県の教育理念を明確に冒頭で示している
- 個人の経験を基に教師像を具体的に説明している
- 目指す教師像が「生徒一人ひとりの可能性を見極め、引き上げる教師」と明確
- 学習と生徒の得意分野を結びつける具体例を挙げている
- 字数制限内に収めている
改善点
構成面
- 段落分けが不明確で、一つの段落が長すぎる箇所がある
- 論理展開をより明確にするための接続詞や段落の整理が必要
内容面
- 「本県の教育理念」についての言及が簡潔すぎる
- 教師としての専門性や授業力についての言及が少ない
- 学習指導要領や現代的な教育課題への言及がない
添削例
「一人ひとりの子どもたちに向き合う教育」という本県の教育理念は、児童生徒の個性や特性を尊重し、それぞれの可能性を最大限に引き出すことを目指すものである。この理念を踏まえ、私の目指す教師像は、「児童一人ひとりの可能性を見極め、その成長を支援できる教師」である。
この教師像を実現するためには、まず児童一人ひとりをよく観察し、教科学習だけでなく、その子の優れた点や得意分野、可能性を見出すことが重要である。そして、その可能性を日々の学習活動と関連づけながら、児童の成長を促していきたい。
私が小学校教員を志望するのは、児童期が自己の可能性を発見する重要な時期だと考えるからである。例えば、ある児童が教科学習は苦手でも運動が得意な場合、「走るのが速いね。算数や国語ももう少しできるようになると、走るペース配分も考えられるし、インタビューにも自信を持って答えられるよ」と、児童が自ら「やってみよう」と思える助言ができる教師でありたい。
私がこのような教師像を抱くようになったのは、小学校3年生の担任教師の影響が大きい。「勉強ができるだけでなく、人に教えるのも上手だね」という言葉をきっかけに、私は自分の新たな可能性を発見した。クラスメイトに学習内容を説明する中で感謝される喜びを知り、より分かりやすく教えるために自分自身も学習を深めた。この経験から、教師という職業に憧れるようになった。
教師の専門性として、確かな教科指導力と児童理解に基づく生徒指導力は不可欠である。しかし、それに加えて、一人ひとりの児童の個性や特性を生かした指導ができることが、本県の教育理念を具現化する上で重要だと考える。教科の学習内容が児童のどのような可能性に結びつくのか具体的に示すことで、学習意欲を高め、児童の自己肯定感を育むことができる。
このような指導を通して身につけた努力する態度や自信は、児童の生涯にわたる学びの基盤となる。社会が急速に変化する現代において、自己の可能性を信じ、主体的に学び続ける力を育成することは特に重要である。
以上のように、本県の教育理念に基づき、児童一人ひとりの可能性を見極め、その可能性を引き出し、伸ばすことのできる教師を目指したい。(796字)
アドバイス
- 「本県の教育理念」についてもう少し深く言及すると良い(理念の背景や意義など)
- 現代の教育課題(ICT活用、主体的・対話的で深い学び、多様性への対応など)と関連づけると説得力が増す
- 教師としての資質・能力をより具体的に示す(授業力、学級経営力、コミュニケーション能力など)
- 段落構成を「導入→自身の考え→具体例→自身の経験→教育的意義→結論」と整理すると読みやすくなる
この修正例では、原文の良い点は残しつつ、より教育的な視点を加え、構成を整理しました。採用試験では「教育に関する専門的知識」と「教師としての資質」の両面が評価されますので、バランスよく表現することが重要です。
「小論文の添削をして」と入力しなかったので、模範解答が少し作文的な文章になっていますが、そこそこの解答例を出してくれます。
さらに添削のポイントやアドバイスまでくれるのはありがたいですよね。これがチャットGPT、Claudeのどちらも無料で利用できます。
AO入試など個別の対策が必要な小論文でも、志望校のアドミッションポリシーなどを読み込ませた上で小論文の添削をしてもらうというのも一つの手かもしれません。これは私もまだ行っていないので、AIがしっかりとした添削ができるのか保証はできませんが。
いずれにせよ、AIによる添削はあくまで参考例として、やはり信頼できる大人に添削をしてもらいましょう。
小論文の添削まとめ

小論文を上達させるには自分の文章を客観的に評価してもらうことが不可欠です。しかし、どこに添削を依頼すればよいのか迷う方も多いでしょう。
ここでは、無料ツールの活用から有料サービスまで、小論文添削の方法を段階的にご紹介します。状況や予算に合わせて、最適な添削方法を選びましょう。
まずAIなどの無料ツールを利用する
繰り返し言いますが、最初の一歩として無料のAI添削ツールを活用することがおすすめです。チャットGPTやClaude、GeminiなどのAIツールは、文法ミスの指摘や文章構成のアドバイスを無料で受けられます。
入力した小論文に対して、論理展開の問題点や表現の不自然さをすぐに指摘してくれるため、初稿の改善に役立ちます。
特に文章添削に特化したAIサービスでは、「説得力」「論理性」「表現力」など多角的な観点から評価を受けられます。
また、オンラインの無料添削コミュニティやSNSグループでは、同じ志望校を目指す仲間から意見をもらえることもあります。
これらのツールは24時間いつでも利用できる便利さがありますが、志望校特有の出題傾向や採点基準に合わせた専門的なアドバイスは限定的です。
あくまで基礎的な文章力向上や初期段階での改善に活用し、より専門的な添削へステップアップする土台として活用しましょう。
信頼できる大人に見てもらう
AIツールで基本的な問題点を修正した後は、実際の人からのフィードバックを得ることが重要です。
まずは学校の先生など身近に信頼できる大人に相談してみましょう。多忙な場合もありますが、放課後や昼休みなど時間に余裕がある時を見計らって依頼するとよいでしょう。
相談する際は、「何を伝えたいのか」「どのような点を重点的に見てほしいか」など、具体的な要望を伝えることが効果的です。
ただし、アドバイスの質は人によって大きく異なるため、複数の意見を比較検討することをおすすめします。
専門的な知識がない場合は一般的な感想にとどまることもあるので、その点は理解した上で活用しましょう。
無料ツールが利用できない場合に、有料サービスの利用
AIや身近な人からの添削で十分な成果が得られない場合は、専門の有料サービスを検討しましょう。
「小論文添削ドットコム」のようなオンラインサービスでは、1200字あたり3000円程度で専門家による添削が受けられます。ベネッセの「小論文特講」は16,500円で7回分の添削が含まれた総合的なパッケージを提供しています。
予算に余裕があれば、総合型選抜専門塾のような対面指導がおすすめです。
直接講師と対話しながら添削を受けられるため、理解度が格段に向上します。「クイックチェック」のようなスピード添削サービス(12,000円程度)も、試験直前の最終チェックとして有効です。
有料サービスを選ぶ際は、志望校の出題形式に対応しているか、継続的な指導が受けられるか、添削のスピードはどうかなどを確認しましょう。
| サービス名 | 形態 | 料金 | 特徴 | おすすめシーン |
|---|---|---|---|---|
| 小論文添削ドットコム | オンライン | 1200字あたり3000円程度 | 専門家による添削 | 必要な時だけ利用したい場合 |
| ベネッセ「小論文特講」 | オンライン | 16,500円 | 7回分の添削が含まれた総合パッケージ | 計画的に学習を進めたい場合 |
| 総合型選抜専門塾 | 対面 | 高額(要確認) | 直接講師と対話しながら添削 | 予算に余裕があり、高い理解度を目指す場合 |
| クイックチェック | オンライン | 12,000円程度 | スピード添削 | 試験直前の最終チェック |
・小論文添削ドットコム
・ベネッセ「小論文特講」
・クイックチェック
費用対効果を考慮すると、初期段階では無料ツールを活用し、本格的な対策が必要になった時点で有料サービスに移行するという段階的なアプローチが有効です。
専門家の目を通すことで、自分では気づけない問題点が明らかになり、合格への近道となるでしょう。
このように小論文の添削ツールというのは、有料のものだと手が出しにくいですが、無料のものも含め、現在の自分の学習状況や試験までの時間に応じて上手く使い分ければ、これ以上ない強力な味方になるので、今回挙げた添削ツールをぜひ有効活用してみてください。
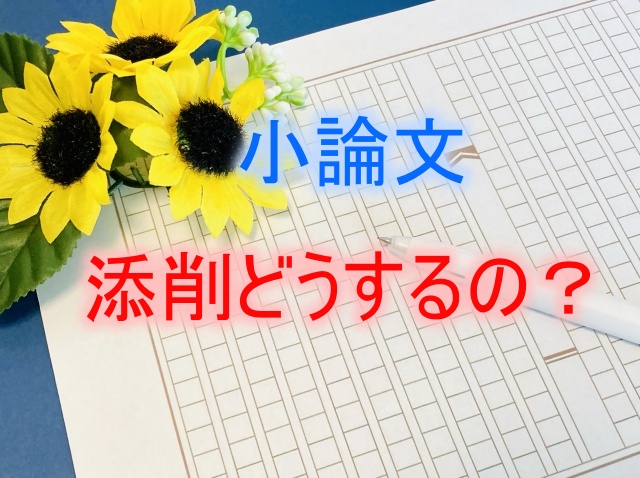
-500x336.png)




コメント