「教育学部の小論文ってどう書けばいいの?」「一般的な小論文と何が違うの?」そんな疑問や不安を抱えていませんか?
実は、教育学部の小論文には明確な特徴があり、適切な書き方を身につければ合格への道筋が見えてきます。
オリジナリティよりも現実性を重視し、教育現場で実践可能な提案をすることが重要です。
また、「いじめ問題」「ICT教育」「特別支援教育」などの頻出テーマへの対策も欠かせません。
本記事では、教育学部での小論文の書き方から具体的なテーマ分析、実際の教育学部を想定した小論文の解答例まで、志望校合格をつかむために必要な情報を詳しく解説していきます。
関連記事
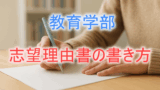
教育学部の小論文の書き方

教育学部の小論文では、一般的な小論文とは異なる特別な視点が求められます。
教育現場で実際に指導する立場を想定し、現実的で実践可能な提案を心がけることが重要です。以下で詳しく見ていきましょう。
小論文の基本
教育学部の小論文を書いていく前に、まずは小論文の基本について、以下で改めて確認しておきましょう。


↓ ↓ ↓ 小論文試験に必須の一冊 ↓ ↓ ↓
小論文の基本から、試験を想定した
実践練習まで、この一冊で身に付きます!
この一冊で小論文のお悩みすべて解決!
\ Amazonで400冊突破!/
オリジナリティーより現実性
教育学部の小論文では、独創的なアイデアよりも実現可能な提案が評価されます。これは教育現場が法的な枠組みや組織運営の中で成り立っているためです。
まず文部科学省の最新学習指導要領を熟読し、その方針に沿った内容を書くことが基本となります。
教育基本法や憲法についても理解を深めておく必要があります。なぜなら、公立学校の教員は公務員として法令遵守が求められ、私立学校であっても教育の公共性から同様の責任を負うからです。
学校は組織として機能しており、個人の判断だけで教育方針を決めることはできません。
「学校に行かなくてもよい」といった極端な意見や、学校方針に従わない授業方法を提案することは避けるべきです。
教員として生徒にどう接するかを考える際は、組織の一員としての立場を忘れず、現実的で実践可能な指導方法を提案することが求められます。
このように教育者としての立場を踏まえたうえで、オリジナリティーを出したいということなら問題ありません。
現状に批判的であること
教育現場の課題を的確に把握し、建設的な改善策を提案する姿勢が重要です。
現代社会ではAI(人工知能)の発展やグローバル化といった急速な変化が起きており、教育もこれらに対応する必要があります。
学習指導要領で示された「生きる力」「主体性」「対話」といったキーワードの真の意味を深く理解し、これらの資質を育むための具体的なプログラムや授業内容を考えることが求められます。
しかし現実の教育現場では、教師が一方的に解説し生徒が受動的に聞く従来型の一斉授業が依然として主流です。
このような旧態依然とした教育手法では、変化する社会で求められる能力を育成することは困難でしょう。
こうした現状に対して批判的な視点を持ちながら、同時に実現可能な改善策を提示することが大切です。建設的な批判を通じて、より良い教育のあり方を模索する姿勢を示すことが評価につながります。
教育学部の小論文テーマ

教育学部の小論文では、出題パターンを理解して適切に対応することが重要です。主要な3つのパターンと頻出テーマを把握し、実践的な考え方を身につけましょう。
問題の3パターン
② 統計データや調査結果を読み取り、適切な対応策を提案する
③ 社会変化と教育の関りから、教育の将来の在り方を論じる
教育学部の小論文は大きく3つの出題パターンに分類できます。
第一は、学級崩壊や反抗期の生徒への対応など、特定の教育現場の事例について指導方針を考えるパターンです。
第二は、統計データや調査結果を読み取り、児童・生徒の傾向を分析して適切な対応策を提案するパターンです。
第三は、社会変化と教育の関わりを考察し、将来の教育のあり方を論じるパターンです。
いずれのパターンでも共通して求められるのは、受験生自身の経験を踏まえた視点です。
自分が子どもだった頃の体験や、周囲から見聞きした事例などを活用し、「教育現場の当事者として自分ならどう対応するか」という実践的な観点から論述することが重要です。
単なる知識としてではなく、現実的で実行可能な提案を心がけましょう。
最初は思いつかないかもしれませんが、知識をもとに考えていく中で過去の自分の体験や聞いた話も踏まえながら考えるとよいでしょう。
学校の先生というと、見えないところでどのような仕事をしているのか分からず「学校が長期休みの時は休みとれていいね」と小学生の私は思っていましたが、今から考えるとやることがたくさんあって大変な職業だと思います。
近年では教員の勤務実態も世の中に認知されてきて、教員のなり手が減少している中、それでもやはり子供の成長を見ていくやりがいと、その子供の成長を支えるために職場環境の改善を教員ひとり一人が考えていける志望者が教育現場に求められているといえるでしょう。
> 小論文・完全ロードマップ解説の《無料メルマガ登録はコチラ》から
教育学部の5テーマ
テーマ 1「教育の本質」
教育の本質を問うテーマでは、知識の伝達、人間形成、社会との関わりの3つの視点から考察することが求められます。単に知識を教えるだけでなく、個人の成長と社会全体の発展にどう貢献するかが論点となります。知識の体系的習得により論理的思考力を養い、多様な価値観を受け入れる人間性を育成し、最終的に社会に貢献できる人材を育てることが教育の目標です。
具体例として、学校行事での協力体験や異なる意見との対話経験などを挙げ、教育が単なる知識習得を超えて「生きる力」を育む場であることを論じます。また、現代社会でフェイクニュースが問題となる中、批判的思考力を身につける教育の重要性も指摘できるでしょう。教育は個人の可能性を広げ、公正で発展的な社会を築く基盤となることを強調することが大切です。
テーマ 2「いじめ問題」
いじめ問題は教育現場で最も深刻な課題の一つであり、多角的な対応策が求められます。いじめの早期発見と適切な対処、被害者への支援、加害者への指導、そして予防的な環境づくりが重要な要素となります。
教師として児童・生徒の変化に敏感になり、相談しやすい雰囲気を作ることが基本です。また、いじめが起きた際には、事実確認を慎重に行い、関係者全員に適切な対応を取る必要があります。
予防策として、日頃から学級内の人間関係を把握し、多様性を認め合う学級風土を育てることが効果的です。
道徳教育や人権教育を通じて、相手の気持ちを思いやる心を育み、コミュニケーション能力を向上させる取り組みも重要でしょう。
保護者や地域との連携も欠かせず、学校全体で一貫した方針のもと、組織的に取り組む姿勢を示すことが求められます。
テーマ 3「ICT教育」
ICT教育は現代教育における重要な課題として頻出します。
デジタル技術の急速な発展に伴い、情報活用能力の育成が急務となっています。タブレットやパソコンを効果的に活用した授業設計や、プログラミング的思考の育成、情報モラルの指導などが論点となります。
単に機器の使い方を教えるのではなく、情報を適切に収集・整理・発信する能力や、デジタル社会で責任を持って行動する態度を育てることが重要です。
一方で、デジタル格差の問題やスクリーンタイムの過多による健康への影響も考慮する必要があります。
ICT活用により個別最適化された学習環境を提供できる利点を活かしつつ、対話的で協働的な学びも大切にするバランスの取れた教育実践が求められます。教師自身のICTスキル向上と、従来の教育手法との適切な組み合わせを考えることが重要でしょう。
テーマ 4「特別支援教育」
特別支援教育は、障がいのある児童・生徒への適切な教育的対応を考えるテーマです。
インクルーシブ教育の理念のもと、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導や支援を行うことが求められます。
発達障がい、知的障がい、身体障がいなど、多様な特性を理解し、個別の教育支援計画を作成することが重要です。
また、通常の学級における特別な配慮を必要とする児童・生徒への対応も含まれます。
効果的な支援には、専門機関との連携や保護者との協力が不可欠です。学級全体で多様性を受け入れる環境づくりを進め、お互いを理解し支え合う関係を築くことも大切な視点です。
合理的配慮の提供により、すべての子どもが能力を最大限に発揮できる教育環境の実現を目指す姿勢を示すことが求められます。ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた授業づくりも重要な要素となるでしょう。
テーマ 5「キャリア教育」
キャリア教育は、児童・生徒が自らの将来を主体的に考え、社会で自立して生きる力を育成するテーマです。
職業体験や進路指導を通じて、働くことの意義や社会貢献の大切さを理解させることが重要です。
また、変化の激しい現代社会において、生涯にわたって学び続ける姿勢や、困難に立ち向かうレジリエンス(回復力)を育てることも求められます。
具体的には、地域の職業人との交流や実際の職場見学、起業家精神を育む活動などが効果的です。
小学校段階から発達段階に応じて、働く人への憧れを抱かせ、中学・高校では具体的な職業選択や進路決定に向けた支援を行います。
自己理解を深め、社会の一員としての自覚を持たせることで、将来への展望を明確にし、学習意欲の向上にもつなげることができるでしょう。
考え方
教育学部の小論文では、理論と実践を結びつけた論述が重要です。
まず問題の背景や現状を客観的に分析し、教育学的な観点から課題を整理します。その上で、学習指導要領や教育基本法などの法的根拠を踏まえながら、現実的で実行可能な解決策を提案することが求められます。
抽象的な理想論ではなく、教育現場で実際に取り組める具体的な方法を示すことが大切です。
自身の経験を効果的に活用し、教育者としての視点を明確にすることも重要な要素です。過去の学校生活や部活動での体験、ボランティア活動などから得た学びを踏まえ、「教師として生徒にどのように関わりたいか」という明確なビジョンを示しましょう。
また、現代社会の変化に対応できる柔軟性と、教育の不変の価値を大切にする姿勢の両方を併せ持つことが求められます。
教育学部の小論文の解答例

以下で実際の教育学部の小論文を想定した3つの問題と解答例を示しています。書くさいの参考にしてみましょう。
例題1
問題:現代の子どもたちにとって必要な教育とは何か。AI時代を見据えて、あなたの考えを800字で述べなさい。
【解答例】
現代の子どもたちに必要な教育は、AI時代においても人間らしさを失わない「共感力」と「創造力」を育むことである。技術の発達により、単純な計算や情報処理はAIが担うようになった。こうした変化の中で、教育が果たすべき役割は従来の知識詰め込み型から大きく転換する必要がある。AIには代替できない人間固有の能力を伸ばすことこそが、現代教育の最重要課題といえるだろう。
まず共感力について考えてみたい。私は中学時代、クラスの友人が家庭の事情で悩んでいた際、その気持ちに寄り添い話を聞いたことがある。その経験から、相手の立場に立って物事を考える力の大切さを実感した。AIは膨大なデータから最適解を導き出せるが、人間の複雑な感情や文脈を理解することは困難である。教師が一人ひとりの児童生徒と向き合い、心の通った対話を重視する教育によって、この能力を育成できる。
次に創造力である。AIは既存のパターンから新しい組み合わせを生み出すことはできるが、真に独創的な発想は人間の特権といえる。美術や音楽といった芸術活動はもちろん、理科の実験や社会科の調べ学習においても、子どもたち自身が疑問を持ち、試行錯誤する過程を大切にすべきである。失敗を恐れずチャレンジする姿勢を育むことで、未知の問題に対する柔軟な思考力が身につく。
また、協働する力も重要である。グループワークや討論を通じて、異なる意見を調整し合意形成を図る経験は、AI時代だからこそ価値を持つ。技術が進歩しても、人と人とのつながりは社会の基盤であり続ける。そして何よりも自分自身で考える力を養うことが必要である。そのために常に疑問を投げかけ、自問自答する力と疑問を調べ解決する力を育みたい。AI時代の教育は、技術と共存しながらも人間らしさを大切にする教育である。共感力と創造力を軸とした教育実践により、子どもたちの豊かな人生を支えたい。(776字)
例題2
問題:学級経営において最も重要なことは何か。具体的な取り組みとともにあなたの考えを800字程度で述べなさい。
【解答例】
学級経営において最も重要なことは、児童生徒一人ひとりが安心して学習に取り組める「心理的安全性」を確保することである。心理的安全性とは、失敗を恐れず自分の考えを表現できる環境のことを指す。この環境が整って初めて、子どもたちは主体的に学び、互いに支え合う関係を築くことができる。私自身、小学校時代に担任の先生が「間違いは学びのチャンス」と繰り返し伝えてくれたことで、積極的に発言できるようになった経験がある。
具体的な取り組みとして、まず学級のルール作りを子どもたちと一緒に行うことが効果的である。教師が一方的に決めるのではなく、なぜそのルールが必要なのかを話し合い、全員が納得した上で決定する。この過程で、子どもたちは学級の一員としての自覚を持ち、ルールを守ろうとする意識が高まる。そしてクラスのすべての子どもに自分で納得できる役割りを与えてあげることだ。学級運営を乱さない、他の子に迷惑をかけないことであれば、「先生○○やりたいです!」といったことはどんどん行わせてあげることだ。
また、日常的な声かけも重要である。できているところを具体的に褒め、困っている子には「どうしたの?」と声をかける姿勢を大切にしたい。小さな変化にも気づき、適切なタイミングで支援することで、子どもたちとの信頼関係が深まる。
さらに、多様性を認め合う学級風土の醸成も欠かせない。一人ひとりの個性や特性を理解し、それぞれの良さを学級全体で共有する時間を設ける。これにより、違いを否定するのではなく、お互いを認め合う関係が生まれる。問題が生じた際には、当事者だけでなく学級全体で解決策を考える機会を作る。責任を押し付けるのではなく、どうすればより良い学級にできるかを共に考えることが大切である。心理的安全性の確保により、子どもたちが持つ可能性を最大限に引き出す学級経営を目指したい。(774字)
例題3
【問題】:インクルーシブ教育の推進において、通常学級の担任教師はどのような配慮が必要か。あなたの考えを800字以内で述べなさい。
【解答例】
インクルーシブ教育の推進において、通常学級の担任教師には「個別最適化」と「集団への配慮」を両立させる視点が必要である。特別な支援を必要とする児童生徒も、そうでない児童生徒も、共に学び成長できる環境を作ることがインクルーシブ教育の目標である。しかし、多様なニーズに応えながら学級全体をまとめることは容易ではない。私は高校時代、聴覚障害のある同級生と共に学んだ経験から、適切な配慮の重要性を実感している。
まず、個別最適化の観点では、一人ひとりの特性を理解し、適切な合理的配慮を提供することが重要である。発達障害のある児童には、視覚的な手がかりを増やしたり、座席の位置を工夫したりする配慮が有効である。また、学習の進度や方法についても柔軟に対応し、その子が最も力を発揮できる方法を見つけることが大切だ。
同時に、学級全体への配慮も欠かせない。特別な支援が必要な児童生徒への配慮を「特別扱い」として捉えるのではなく、多様性を認め合う学級風土を育むことが重要である。友達同士が自然に助け合い、お互いの違いを理解し合える関係性を築くための指導が求められる。具体的には、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた授業づくりが効果的である。すべての児童生徒にとって分かりやすい板書や説明を心がけ、多様な学習スタイルに対応できる教材を準備する。これにより、特別な配慮を自然な形で提供できる。
また、専門機関や特別支援学校との連携も重要である。専門的な知識を学び、効果的な支援方法を身につけることで、より質の高い教育を提供できる。この過程で教師としての私の学びや改善にもつながり、それを学級運営に反映させればよりよい学びの場になるはずだ。このようにインクルーシブ教育は、すべての子どもの可能性を信じ、共に成長する教育である。多様性を力に変える学級経営を実践したい。(769字)
上に挙げた3つの解答例のように、教育者としての立場や現実性を踏まえながら、あなたならどのように考えるのかを意識しながら書く練習をしていきましょう。
小論文の対策は、以下の無料メルマガでも実施中↓↓↓

-500x336.png)


-500x336.png)

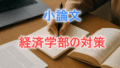
コメント