「勉強しなきゃ…」と思いつつ、小論文の練習方法に悩んでいませんか?
添削を誰に頼めばいいのか、どう練習すればいいのか分からず、不安を感じている受験生は多いものです。
本記事では、スマホ一つで手軽に始められる小論文練習アプリや、質の高い添削が受けられる練習サイトを紹介します。
さらに、課題文型の練習問題での効果的な取り組み方も解説。AIを活用した添削方法も含め、時間や場所を選ばず効率よく小論文力を磨く方法が分かります。
小論文対策に悩むあなたも、この記事を読めば今日から効果的な練習をスタートできるでしょう。
- 無料アプリやサイトの活用法
- 課題文型の小論文でのAI活用法
関連記事

小論文の練習アプリ

小論文対策に効果的なアプリやオンラインツールを活用することで、時間や場所を選ばず効率的に練習できます。また、プロの指導を受けるよりも費用を抑えながら、質の高い添削や情報収集が可能です。
以下では、特にオススメのアプリについて詳しく紹介します。
まず小論文の対策おさらい【4手順】
まず以下の4手順で、小論文を書くと上達していくので、それぞれおさらいしておきましょう。
② 実際に書く
③ 添削を受ける
④ 添削で受けた改善点をもとに、また書く
② 実際に書く



④ 添削で受けた改善点をもとに、また書く
添削で受けた改善点は修正し、「ここは良く書けている」と良い評価を受けたところは次に回答を書くときも活かしましょう。
書く際の知識の付け方はコチラ
オススメのアプリ
対策の手順を身に付けたら、実際に書いて添削を受けます。
添削の際に、最初から人に見てもらうのは「恥ずかしいし、何言われるか分からないから気が引ける」という人は、無料の添削アプリを利用してみましょう。
小論文練習に役立つアプリは数多く存在しています。
まず注目したいのは、文章添削に特化した「Grammarly」や「Hemingway Editor」です。これらは文法チェックだけでなく、文章の明瞭さや読みやすさまで指摘してくれるため、論理的な小論文作成に役立ちます。
ただ、これらは文法や誤字脱字のチェックが中心で、内容面まで完全に添削されるものではないことを覚えておきましょう。
また、情報収集には「スマートニュース」や「ヤフーニュース」「CNN.co.jp」がおすすめです。
時事問題は小論文のテーマになることが多く、日頃から多様な視点で社会を見る習慣をつけられます。
通学中など移動時間を有効活用したい方には、音声で情報を得られる「VOICY」も便利です。
ただこれらの内容は鵜呑みにせず、事実関係の確認や記事の見解などは自分で考えてみることをオススメします。
また、人による添削を希望する場合は「ココナラ」のようなスキルマーケットが活用できます。
自分の志望校や分野に詳しい講師を選んで、個別に添削を依頼できるのが魅力です。
無料で基本機能を使えるアプリも多いため、複数組み合わせることで効果的な小論文対策が可能になります。
オススメの小論文の練習サイト

ここでは小論文の練習をするにあたってのオススメのサイトを紹介します。
手前味噌だが、このサイト
自分で言うのもなんですが、小論文の基礎から実践練習まで体系的に学べ、考え方や添削の方法まで学べるこのサイトがオススメです。
無料ですべて見ることができ、練習や試験本番での書き方など、もれなく実戦的に使うことができます。
小論文の課題文型の練習問題でもAIを活用する

ここでは課題文型の練習問題で書いた解答を、ClaudeやチャットGPTといったAIに「添削と評価」をしてもらったサンプルを紹介します。
対象サンプル
【例題】:下の文章を読んで、あなたの考えを800字以内で書きなさい。
〔課題文〕
あなたは「葬式」という言葉を聞いたとき、どのような光景を思い浮かべるだろう。亡くなった人を偲び、悲しみの涙が見られ、生老病死の中でもっとも悲しく、否定的なものと見られることが多い。ところが、アフリカのある民族では、色とりどりの棺に亡くなった人を入れ、そのまわりで人々が踊り、祭りでも行うかのように楽しく笑って死者を送るのだそうだ。それは、あの世でも故人が楽しく暮らせるように、現世の最期に笑って死者を送り出すという考え方からきている。日本では到底考えられないことだが、世界にはそういう考え方をする民族もいるのだそうだ。
〔解答例〕
「葬式」において、笑って死者を送り出すというアフリカのある民族のように、私たちは違う考え方や価値観、さらにその背景を知ることで、自分たちの考えが相対的なものだと気づかされる。とくに海外留学の経験がある人は、そのことをよく実感できるだろう。しかし、海外留学の経験がなくても実感できる場面はある。
私は以前、コンビニのアルバイトで、アルバイトに入ったばかりのブラジル人留学生に、「店員の引き継ぎは夜の7時だから、その時間に来てね」と伝えた。ところがその留学生は、夜の7時40分になってコンビニに来た。私が怒って、「どうして夜の7時に来てと言ったのに、こんなに遅刻したの」と聞いたら、「ブラジルでは、夜の7時から7時59分までが夜の7時だから、遅刻はしていないよ」とのことだった。
このとき私は、日本とブラジルとでは時間の考え方が違うことに気づかされた。なるほど、日本とは時間の考え方が違うのならば、「日本では夜の7時というのは、7時ちょうどに間に合うまでという意味だから、遅くとも夜の6時55分までには到着してね」と伝えなければいけなかったのだ。 このように、相手の考え方や価値観の違い、その背景を理解しようとせずには物事はうまくいかない。自らの考え方や価値観を絶対的なものとみなし、違う考え方や価値観の相手を、相手の説明も詳しく聞かず、その背景も考えてみることなく排除しようとすれば、異文化交流はおろか、同じ日本人どうしでも物事はうまくいかないだろう。
私たちはつい、自分の考えや価値観、自国の文化や習慣を絶対的なものとみなし、異なる考えや価値観、他国の習慣を「おかしなもの」とみなしがちだ。しかし、異なる考えや価値観の背景を知り、理解しようと努力すること。その上でこちらの考えを相手に分かりやすく伝えることが、国際化が進む現代においては、ますます重要となってくる。(776字)
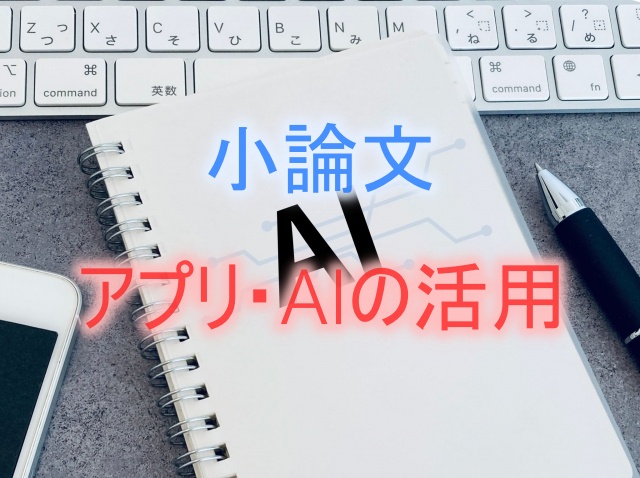
-500x336.png)




コメント