「経済学部の小論文の書き方が分からない」「どんな視点で書けば良いのか不安」そんな悩みを抱えていませんか?
経済学部の小論文にも、他の小論文同様に明確な評価ポイントがあり、適切な書き方を身につければ合格への道筋が見えてきます。
問題解決力と経済的視点からの分析が重要で、過去問を通じて出題傾向を理解することが合格の鍵となります。
本記事では、経済学部の小論文の書き方から頻出テーマの対策、実際の過去問分析、実際試験を想定した解答例まで、経済学部の小論文で高得点を得るための情報を詳しく解説しています。
関連記事

経済学部の小論文の書き方

経済学部の小論文では、現実の経済問題を理論的に分析し、論理的な解決策を提示する力が求められます。
ここでは、評価される具体的なポイントと頻出テーマの対策方法を詳しく解説していきます。
小論文の基本
経済学部の小論文の書き方を見ていく前に、まず小論文の基本について以下で改めて確認しておきましょう。


問題解決力が評価される
経済学部の小論文で最も重視されるのは、経済理論を現実の問題に適用する思考力です。
たとえば、インフレーション問題について論じる際、単に現状を説明するだけでなく、需要と供給の理論や金融政策の仕組みを用いて原因を分析する必要があります。
さらに重要なのは、複数の要因を関連づけて考察する能力で、物価上昇が消費者心理や企業の投資行動にどのような影響を与えるかまで検討することが求められます。
このような多角的な分析を通じて、経済学の基礎的な概念を実際の社会課題に応用できる能力を示すことで、高い評価を得られるでしょう。
経済的な視点から解決策を提案する
経済学部の小論文では、問題の分析だけでなく、実現可能で効果的な解決策の提案が不可欠です。
解決策を検討する際は、短期的効果と長期的影響の両方を考慮し、政策の副作用についても言及することが重要になります。
例えば、雇用問題に対して最低賃金の引き上げを提案する場合、労働者の所得向上というメリットと、企業の人件費負担増加による雇用減少リスクの両面を検討する姿勢が求められます。
また、提案する政策の実施主体(政府、企業、国際機関など)を明確にし、具体的な実施方法や期待される成果を数値的根拠とともに示すことで、説得力のある小論文に仕上がります。
経済学部の小論文を書くときは、社会課題の解決という視点を常に持つようにしましょう。
志望理由書の記事でも触れましたが、個人的にお金持ちになりたいとか、ある企業に就職したいという思いで経済学部を目指すとミスマッチが起こりやすくなります。
↓ ↓ ↓ 小論文対策に必須の一冊 ↓ ↓ ↓
小論文の基本から、試験を想定した
実践練習まで、この一冊で身に付きます!
この一冊で小論文のお悩みすべて解決!
\ Amazonで400冊突破!/
経済学部の頻出9テーマと考え方
② 環境経済学
③ 市場の失敗
④ 経済政策
⑤ 経済発展
⑥ 社会保障
⑦ 労働とグローバル化
⑧ 観光と地域経済
⑨ 制度と未来
① グローバル経済
グローバル経済のテーマでは、国際貿易や外国投資を通じた各国経済の相互依存関係を理解することが重要です。2025年にトランプ政権が実施した関税政策では、日本に対して15%の関税が課され、GDP成長率を0.4ポイント押し下げる影響が予測されています。このような具体的な時事問題を扱う際は、貿易収支の変化や為替レートへの影響、企業の価格転嫁行動など複数の視点から分析する必要があります。解答では、比較優位理論などの経済学の基本概念を用いながら、保護主義と自由貿易のバランスについて論じることが求められます。また、国際協調の重要性や各国が直面するジレンマについても考察し、現実的な政策提案を行うことで説得力のある小論文となるでしょう。
② 環境経済学
環境経済学では、経済活動が環境に与える影響と、環境保護と経済成長の両立という課題を扱います。工場からの廃水による水質汚染や温室効果ガスの排出など、企業活動による負の外部性が市場価格に反映されない問題を理解することが重要です。小論文では、ヨーロッパのグリーンニューディールや日本の環境政策など具体的な事例を取り上げ、カーボンプライシング(炭素税や排出量取引)といった政策手段の効果を分析しましょう。解答では、短期的なコスト増加と長期的な持続可能性のトレードオフを認識しつつ、再生可能エネルギーの導入や技術革新による環境と経済の両立策を提案することが求められます。多角的な視点から環境問題の経済的側面を論じることで高評価につながるでしょう。
③ 市場の失敗
市場の失敗とは、市場メカニズムだけでは資源配分が最適にならず、社会全体の福祉が損なわれる状況を指します。外部性、公共財、情報の非対称性という3つの主要因を理解することが重要です。たとえば環境汚染は負の外部性の典型例で、企業が汚染コストを負担しないため過剰生産が生じてしまいます。小論文では、具体的な市場の失敗事例を挙げ、なぜ市場が適切に機能しなかったのかを経済理論で説明する必要があります。解答では、ピグー税(汚染税)や補助金、規制といった政府介入の手段を検討し、それぞれの政策効果と限界について論じることが求められます。
④ 経済政策
経済政策のテーマでは、政府や中央銀行が経済を安定化させるための政策手段とその効果を理解することが重要です。2024年に日本銀行はマイナス金利政策を解除し、政策金利を0~0.1%に引き上げるなど、長期間続いた金融緩和からの正常化を進めています。小論文では、物価上昇が続く中での金融政策の転換について、インフレ抑制と経済成長のバランスという視点から分析する必要があります。財政政策(減税や公共投資)と金融政策(政策金利の調整)の違いを理解し、それぞれの効果と副作用を論じましょう。解答では、現実の経済データを踏まえながら、短期的な景気対策と長期的な経済の持続可能性の両面から政策を評価し、より効果的な政策の組み合わせを提案することが高評価につながります。
⑤ 経済発展
経済発展のテーマでは、国や地域が長期的に成長し豊かになるプロセスとその要因を理解することが重要です。技術革新、教育投資、インフラ整備、制度改革など、成長を促進する複数の要素を総合的に考察する必要があります。小論文では、特定の国の成功事例(東アジアの経済発展)や失敗事例(資源依存型経済の停滞)を取り上げ、その背景にある政策や社会的要因を分析しましょう。開発途上国が直面する課題として、貧困の罠、所得格差の拡大、環境破壊などを挙げ、それらに対する解決策を検討することが求められます。解答では、国際協力の役割や持続可能な開発目標(SDGs)との関連にも触れながら、包摂的な経済成長の実現に向けた具体的な戦略を提案することで説得力のある小論文となるでしょう。
⑥ 社会保障
社会保障のテーマでは、公的年金、医療制度、介護保険など、人々の生活を支える仕組みの持続可能性が問われます。少子高齢化が進む日本では、現役世代の負担増加と給付水準の維持という両立が困難な課題となっています。小論文では、社会保障制度の目的が単に弱者を守るだけでなく、社会全体の安定を保つ機能であることを理解し、世代間の公平性や財源確保の問題を論じる必要があります。ベーシックインカム(全国民への一定額給付)のような新しい制度についても、そのメリット・デメリットを検討しましょう。解答では、高齢者の就労支援、税制改革、若年層への投資など、現実的な改善策を複数の視点から提案することが重要です。理想論に終わらず、財政制約を踏まえた実行可能な政策を示すことで高評価が得られるでしょう。
⑦ 労働とグローバル化
労働とグローバル化のテーマでは、外国人労働者の受け入れ、働き方改革、雇用の多様化といった現代的課題を扱います。日本では労働力不足が深刻化する中、海外人材への依存が高まっていますが、言語や文化の違いへの対応が重要な課題となっています。小論文では、テレワークや副業の普及、AI・デジタル技術による働き方の変化についても考察する必要があります。企業の生産性向上だけでなく、働く人の幸福度やワークライフバランスの観点から論じることが重要です。解答では、外国人労働者が安心して働ける環境整備(教育支援、地域の受け入れ体制)や、柔軟な働き方を支える制度設計を提案しましょう。人を中心に据えた労働政策と経済発展の両立について、多様性と共生の視点から論じることで説得力のある小論文となります。
⑧ 観光と地域経済
観光と地域経済のテーマでは、観光産業が地域にもたらす経済効果と、オーバーツーリズムによる弊害のバランスを考察します。京都や沖縄などでは観光客の集中により、交通渋滞、騒音、ゴミ問題、住民生活への影響が深刻化しています。小論文では、観光収入による地域活性化と住民の生活環境保護という両面を理解し、持続可能な観光のあり方を論じる必要があります。解答では、観光地の分散化、公共交通の整備、マナー教育、入域制限といった具体的な対策を提案しましょう。また、観光収入が地域全体で分かち合われる仕組みや、地域文化・伝統の保護についても考察することが重要です。行政、住民、観光客、企業など関係者全員の利益を調整する視点を持ち、経済効果と文化保護の両立を目指す提案を行うことで高評価につながるでしょう。
⑨ 制度と未来
制度と未来のテーマでは、AI・デジタル技術の進歩による社会変化に対応した新しい制度設計を考察します。自動化により一部の仕事がなくなる可能性がある一方、リモートワークの普及で働き方の自由度は高まっています。小論文では、技術進歩がもたらす便利さとリスクの両面を捉え、税制、教育、雇用などの社会制度をどう再設計すべきか論じる必要があります。変化に適応できる人材育成のための教育改革や、デジタル格差の解消策についても検討しましょう。解答では、公平性、効率性、持続可能性といった複数の価値基準を考慮しながら、現実の課題(少子化、格差拡大、技術の不均衡)を踏まえた制度改革を提案することが重要です。実行可能で人々がよりよく生きるための具体的な制度設計を示すことで説得力のある小論文となるでしょう。
頻出テーマの具体例
・インバウンドによる国内消費
・グローバリゼーションへの対応
・格差社会とベーシックインカム
・暗号通貨、人工知能による経済効果
経済学部の小論文で頻出するテーマは多岐にわたりますが、現代の重要課題が中心となっています。
近年特に注目されているのは、AIの普及による労働市場への影響や、暗号通貨が既存の金融システムに与える変化です。
これらのテーマに対応するため、日頃から経済に関するニュースに敏感になり、新技術が経済に与える影響について理論的背景とともに考察する習慣を身につけましょう。
また、格差社会やベーシックインカム、環境問題と経済成長の両立といったテーマでは、多様なステークホルダーの立場を理解し、バランスの取れた視点で論じることが重要です。
各テーマの基本的な理論を押さえつつ、最新の事例や統計データを活用して具体性のある議論を展開することで、説得力のある小論文を書くことができます。
経済学部の小論文の過去問

書く手順として、実際の経済学部で出された過去問題から書き方を見ていきましょう。
出題傾向
経済学部の小論文では、課題文やグラフ、統計データ、新聞記事などの資料を読み取る問題が主流となっています。
受験生は単に自分の意見を述べるのではなく、提示された情報を正確に理解し、それを基に論理的な分析を行う必要があります。
特に多いのは、経済指標のグラフから傾向を読み取り、その背景にある経済現象を説明する問題や、複数の経済データを比較して課題を特定する問題です。
このような出題形式では、データの読み取り能力と経済学の基礎知識の両方が試されるため、日頃から経済白書や統計資料に触れる習慣を身につけることが重要になります。
資料を基にした論述では、客観的な事実と自分の考察を明確に区別して記述することが高評価につながるでしょう。
北九州市立大 経済学部 2024年の問題
北九州市立大学の小論文は出題テーマが具体的で、受験生にとって取り組みやすい入試として知られています。2024年度の経済学部では、現代社会の具体的な経済課題を扱った問題が出題される傾向が続いています。
過去の出題を見ると、地域経済の活性化や少子高齢化と経済政策、環境問題と経済発展の両立などが頻出テーマとなっており、受験生の身近な問題意識と経済学的な思考力の両方を評価する内容となっています。
解答では、問題の構造を整理し、複数の要因を関連付けて分析する能力が求められるでしょう。
また、解決策の提案においては実現可能性と効果の両面から検討し、具体的な政策手段を含めて論述することが重要です。
(課題文は省略)
設問1 下線部(1)の2つの分け方について、それぞれが企業のパフォーマンスに与える影響に言及しつつ200字以内で説明しなさい。
設問2 リーとカニングハムのメタ分析の研究結果で、国籍のダイバーシティーがチームのパフォーマンスを有意に下げる結果となったのはなぜか。本文の内容にもとづき400字以内で説明しなさい。
設問3 あなたの経験からダイバーシティーが組織・集団のパフォーマンスにプラスまたはマイナスの影響を与えた事例を挙げ、その原因と結果について、本文の内容を踏まえて500字以内で論じなさい。なお、ここでのパフォーマンスとは、目標の達成といった成果だけでなく、チームの団結度合いを表すような感情的・心理的成果も含むものとする。
東北学院大学 2024年 学校推薦型選抜・総合選抜型小論文
東北学院大学では過去3年間の試験問題が公開されており、著作権の都合上問題本文を省略しているものもあります。
2024年度の学校推薦型選抜・総合選抜型小論文では、現代社会の課題に対する多角的な視点での分析力が重視されています。
経済学部関連では、地域経済の振興策や働き方改革の経済効果、デジタル社会における経済活動の変化などが出題される可能性が高いでしょう。
これらの問題では、経済理論の知識だけでなく、社会情勢への理解と独自の視点での問題解決能力が評価されます。
受験生は日頃から経済ニュースに関心を持ち、理論と実践の両面から考察する習慣を身につけることが合格への近道となります。
解答では論理構成を明確にし、根拠に基づいた説得力のある議論を展開することが求められるでしょう。
【学校推薦型選抜・総合型選抜A日程第二次選抜】
(課題文は省略)
以下の文を読み、問いに答えなさい。
問1 文章の内容を100字以内に要約しなさい。
問2 あなたにとってよりよいコミュニケーションはどのようなもの
か、筆者の考えを踏まえながら700文字以内で述べなさい。【総合型選抜B日程第二次選抜・資格取得による推薦B日程】
(課題文は省略)
以下の文を読み、問いに答えなさい。
問1 文章の内容を100字以内に要約しなさい。
問2 「中国」「朝鮮」「日本」といった表記が自然で普遍的なもので
あると理解することに対して、問題文の内容を踏まえた上であ
なたの考えを700字以内でのべなさい
例題と解答例

経済学部の小論文対策では、実際の例題を通じて解答の構成や論述のポイントを理解することが重要です。
ここでは3つの典型的な出題パターンについて、600字以内の解答例を示しながら効果的な書き方を解説します。
例題1
【問題】日本の労働力不足問題について、その原因と経済への影響を分析し、効果的な解決策を800字以内で提案しなさい。
(解答例)
日本の労働力不足は深刻な経済課題となっている。この問題の主要因として、少子高齢化による生産年齢人口の減少と、働き方に対する価値観の変化が挙げられる。特に15歳から64歳の人口が継続的に減少しており、2050年には現在より約3000万人少なくなると予測されている。また、若年層の就労意識の変化により、従来型の長時間労働を避ける傾向も労働力不足に拍車をかけている。経済への影響は多方面に及んでいる。
まず生産性の低下により、GDP成長率の鈍化が深刻化している。さらに社会保障制度への負担増加により、現役世代一人当たりの負担が増大し、消費意欲の減退を招いている。企業レベルでは、人材確保コストの上昇と事業拡大の制約により、国際競争力の低下が懸念される。
これらの解決策として三つの提案を行う。第一に、AI・ロボット技術の積極的導入により、労働集約的産業の自動化を推進すべきである。第二に、見過ごされてきた就職氷河期世代の雇用安定化や拡大してきた非正規雇用の縮小と正規雇用との格差是正を行う必要がある。そのうえで、労働力不足が生じるのであれば外国人材の活用を、受け入れ先の地域住民の理解や文化的な差異に配慮したうえで受け入れる必要があるだろう。そして第三に、働き方改革を通じてワークライフバランスを改善し、女性や高齢者の労働参加を促進することが重要である。
ただし高齢者の雇用は、やはり年齢や健康などに配慮し、女性あるいは男性も子育て世代や生理的特徴に配慮しながら労働参加を促進していくべきだろう。要するに労働環境をある特定の人のみに配慮するのではなく残業や長時間労働の是正、非正規雇用の縮小と、どの世代にあっても働きやすい環境を作ることが積極的な労働参加を促し、その労働参加や集約産業を補うものとしてAIを活用する。これらの施策が人口減少の社会にあっても労働力不足問題の根本的解決につながると考える。(782字)
例題2
【問題】デジタル通貨(CBDC)の導入が日本経済に与える影響について、メリットとデメリットを整理し、あなたの見解を800字程度で述べなさい。
(解答例)
中央銀行デジタル通貨(CBDC)は、従来の金融システムに革命的変化をもたらす可能性を秘めている。日本におけるCBDC導入のメリットは複数存在する。まず決済の効率性向上により、取引コストの大幅削減が実現する。現金の製造・管理費用が年間約2兆円かかる中、デジタル化により大幅なコスト削減が期待できる。また金融包摂の促進により、銀行口座を持たない層も金融サービスにアクセス可能となり、経済活動への参加機会が拡大する。さらに金融政策の効果的実施が可能となり、マイナス金利政策などの直接的な実行により、景気調整能力が向上する。
一方でデメリットも無視できない。最大の懸念はプライバシー保護の問題である。政府による取引の完全な把握により、個人の経済活動が監視される恐れがある。また既存金融機関への影響も深刻で、民間銀行の預金業務縮小により金融システム全体の安定性が脅かされる可能性がある。さらにサイバーセキュリティリスクの増大により、システム障害や不正アクセスによる経済的損失が懸念される。
ただし、デメリットの方は事前の準備によって解消、あるいはそのリスクが減少するものが多い。例えばプライバシー保護の問題は、CBDCを政府から独立した機関の運営とし、取引履歴を直接の取引相手以外には非開示とすることで可能である。また民間銀行の預金業務縮小により安定性が損なわれるのであれば、段階的に様子を見ながら行えば金融システムの不安定化は最小限に抑えられるだろう。
以上を踏まえて、私はCBDC導入に賛成である。ただし段階的導入により、プライバシー保護機能の強化と既存金融機関との共存モデルの構築が不可欠である。具体的には、取引履歴の匿名化技術導入と、民間銀行の融資業務を強化する補完的制度設計が必要となる。適切な制度設計により、CBDCは日本経済の競争力向上に大きく貢献するものと考える。(767字)
例題3
【問題】グラフから読み取れる日本の貿易収支の変化について分析し、今後の対策について600字以上800字以内で論じなさい。※グラフ省略
(解答例)
提示されたグラフから、日本の貿易収支は2010年代以降大きく変化していることが読み取れる。2011年の東日本大震災以降、原発停止による燃料輸入増加により貿易赤字が続き、2014年には過去最大の赤字を記録した。その後徐々に改善したものの、2020年のコロナ禍で再び悪化し、近年は資源価格高騰の影響で不安定な状況が続いている。
この背景には構造的要因が存在する。第一に、エネルギー依存度の高さである。原油・天然ガスの輸入依存度が90%を超える中、国際価格変動の影響を直接受ける脆弱性が露呈している。第二に、製造業の国際競争力低下が挙げられる。特に電子機器分野では韓国・中国企業の台頭により、従来の輸出主力商品の優位性が失われつつある。第三に、円安進行による輸入コスト増加が貿易収支悪化を加速させている。
そこで今後の対策として三つの方向性を提案する。まずエネルギー安全保障の強化が急務である。再生可能エネルギーの導入拡大により、エネルギー自給率の向上を図るべきである。またEV(電気自動車)などの普及拡大を行い、原油依存を極力減らしていく必要があるだろう。次に製造業の高付加価値化を推進する必要がある。AI・バイオテクノロジー分野への集中投資により、新たな輸出競争力を構築すべきである。
原発停止による燃料輸入増加により貿易赤字が続き、原発再稼働というのも選択肢にあるかもしれない。しかし、東日本大震災の経験から過酷事故が起きれば土地を追われ復興までに膨大なコストがかかり、また平常運転でも核のゴミ処理の問題が不確定な中、持続可能な貿易収支の改善にはつながらない。その一方、サービス貿易の拡大による収支改善が重要となる。観光業の復活と金融・IT分野での国際展開強化により、貿易構造の多様化を図る必要がある。これらの施策を総合的に実施することで、持続可能な貿易収支の改善が実現できるものと考える。(776字)
上記を参考に、実際に書く練習をしてみましょう。
小論文の対策は、以下の無料メルマガでも実施中↓↓↓
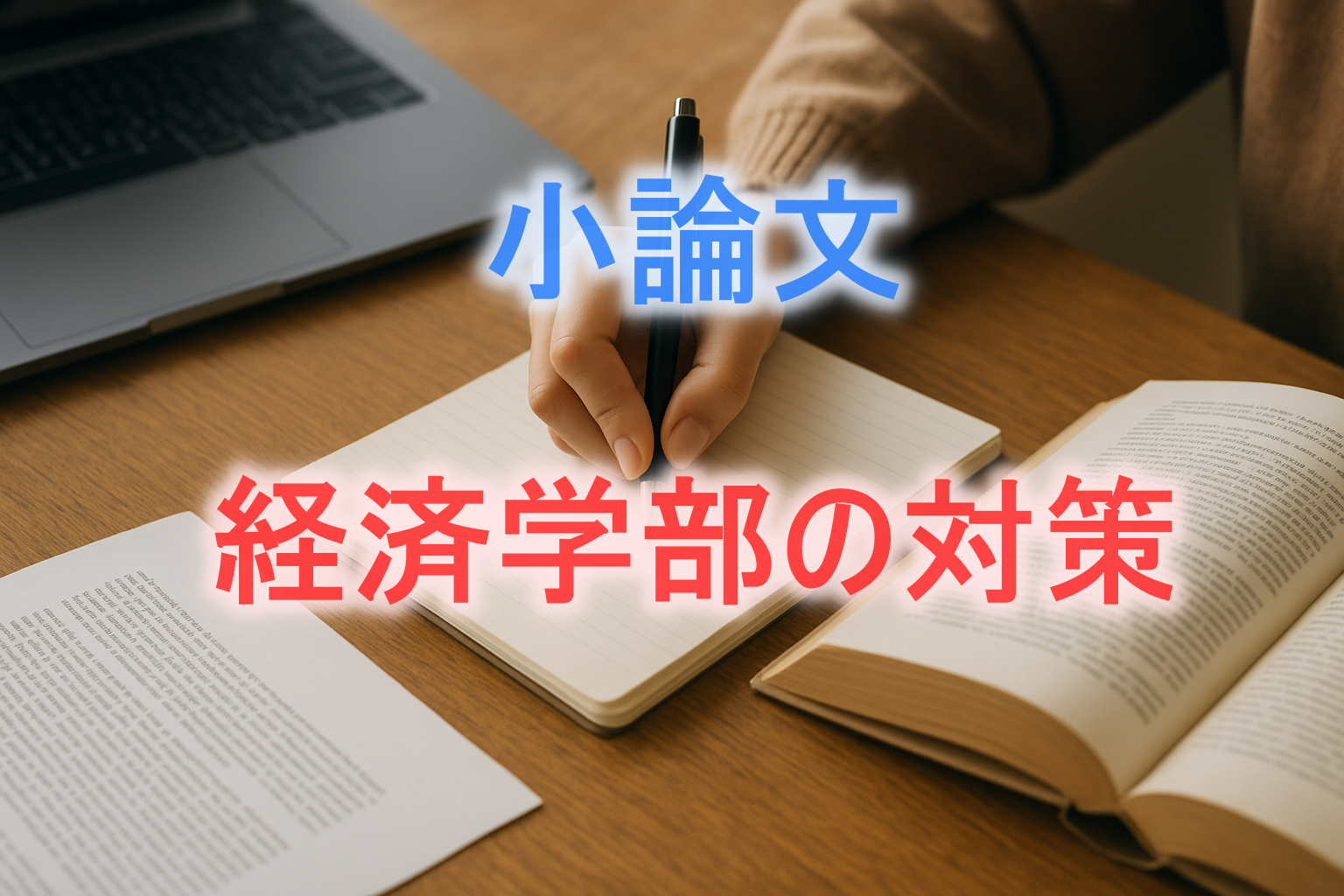
-500x336.png)




コメント